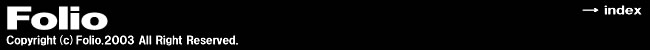|
白い太陽があった。その周りには青い空と小さい雲があって、その下で濃い緑の葉と優しい風が揺れていて、そしてそのさらに下の地面の上に、僕と僕の影があった。
電車を降りた僕は、赤い屋根の古びた駅舎に向かって歩き始めた。空気が美味しい。日本で迎える夏は六年ぶりだった。その間にアメリカでテロがあり、イラク戦争があり、人が沢山死んで、僕は二十歳になっていた。そんな年月の経過でさえ、この田舎町の風景を変えることはできなかったらしいなと、駅から見える田んぼを見ながら思った。
東京から電車を乗り継ぐこと五時間と三十分。僕はようやく故郷に帰ってきた。夏の真っ盛りの田舎には蝉の声しか聞こえてこない。青と白と緑。日が暮れれば赤や紫や黒。人工的なネオンも、摩天楼の灯もここには存在しない。
手紙は来る前に出しておいたから、駅舎をくぐれば、ひょっとしたら彼女が迎えに来てくれているかもしれない。それとも、六年間の音信不通は僕たちの仲を引き裂いているのかもしれない。どっちでもいいだなんて思わない。彼女が来てくれていれば、僕は嬉しい。
次の六年が過ぎても絶対に自動にはならないだろう改札を抜けて、木造の駅舎の中に入った。木の匂いがいっぱいで、六年前にはなかった冷房設備がついていた。涼しさに後ろ髪を引かれながら、僕は駅舎から外に出た。
暑かった。道は曲線を描きながら続いている。ところどころにある家屋や商店は、平屋と二階建てばかりだった。それ以外には、青い田んぼと、もこもこした森しか見当たらない。
僕は歩き出した。駅舎の出口付近に、日傘を指した女の人が立っていた。ジーパンに白いTシャツ。目にかかるくらいの前髪、黒い髪を背中に流して、傘をくるくる回していた。綺麗な人だなと思った。その横を通り過ぎようとしたとき、僕は何かにつまづいて、転びそうになっていた。
「いきなり無視はないんじゃないの?」
と彼女は言ったけど、僕は黙っていた。「こんなに簡単によろけちゃって、向こうの治安は相当良かったみたいね。一体ニューヨークまで行って何を学んできたの?」
ああ、と僕は声を上げた。
「驚いたな、気がつかなかった。こんなに美人になってるとは思わなかったよ」
「なるほど」 彼女は大げさに息を吐いた。「お世辞の言い方は学んだわけね」
「少なくとも、足払いのよけ方は教わらなかった」
僕は彼女の前に立ち、黒い目を覗き込んだ。黒い髪と黒い瞳を美しいと思うのは、六年のアメリカ暮らしを経た今も、僕が純粋な日本人である証拠なのかもしれない。
僕の目を見つめ返して、彼女は笑った。
「おかえり」 と彼女が言ったから、
「ただいま」と僕は答えた。
母親が死んで、ニューヨークにいる親戚の家に行ったのは、僕が十四歳のときだった。青春の真っ只中で、僕はこの村が好きだったけど、子供が一人で生きていくにはこの国は少しだけ不親切だった。
当時付き合っていた女の子を残して、僕はアメリカに渡った。彼女とは、二十歳を過ぎたら帰ってくると約束した。絵里は泣きながら「絶対だからね」と指きりを求め、僕は渋い顔で「絶対だ」と小指を差し出した。他愛無い、よくやる子供の約束だ。
その他愛無い子供の約束は守られた。僕らはこうして歩いている。田んぼの中の道をゆっくり歩いている。暑くて暑くて汗が流れて止まらなかったし、日本の夏はジメジメして不快だったけれど、どうやら約束だけは守られた。
「暑い」
畦道を歩きながらながら、僕は言った。この村には森と、森の中にある川と、壊れないのが不思議なくらいに古びた学校くらいしか見るべき場所がない。僕らはとりあえず森に向かっていた。
「男のくせに情けない」
「男だろうが女だろうが暑いものは暑い。暑さが平気なのは多分、蚊と延暦寺の坊主だけだ」
「なにそれ」
「心頭滅却すれば火もまた涼し」
「馬鹿なこと言ってないで歩きなさいよ。向こうに行ってヤワになったんじゃないの?」
「ニューヨークは灰色のビル街だ。視界が三百六十度開けていて、直射日光に当たりっぱなしなんて聞けば、大抵のニューヨーカーは気絶する。嘘じゃない。僕は頑丈な方だ。嘘じゃない」
当然、嘘だった。それは絵里も分かっているらしく、馬鹿じゃないの、とボヤいただけだった。僕は笑った。絵里も昔は暑さがダメで、いつも小川や学校のプールについて行かされたことを思い出したのだ。
森に着く前に絵里の家に寄り、彼女は日傘を置いて麦藁帽子を被り、僕は荷物を置いてスイカを持ってきた。絵里の家には誰もいなかった。僕と違って両親は健在なはずだから、田んぼの方へ仕事をしにいってるのだろうと思った。
「岬はどうしたのかな?」
森の中の小川につけてスイカを冷やしながら、僕は尋ねた。僕は川の近くにある石に腰掛けていて、絵里はスイカの隣に座り込んでいた。岬とは、絵里の妹の名前だった。
「男について出て行ったよ。まともな人だったから、親も許したみたい。もう、二年近く前になる」
絵里は、そのことが不満でたまらなかったらしい。彼女はすごく不機嫌そうな声でそう言って、それを聞いた僕はふうんと答えて立ち上がった。小川のせせらぎは、昔と同じく綺麗だった。靴を脱いでズボンを捲り上げた。川に足を入れると、ひんやりと冷たい感覚が足裏から脳髄を差した。六年間も忘れていた爽快感に、僕は少し嬉しくなった。絵里が僕に続いた。バシャリと、水が跳ねた。
「まだ小学生だったかなあ。三人でよくここに来たね」
絵里は僕だけじゃなく、岬も巻き添えにしてこの小川まで遊びに来ていたのだ。夏休みになると、僕らは三人で朝からここに来て、日が暮れるまで遊んでいた。ここは、僕らの秘密基地だった。三人で遊んだ思いでは、ここにしかない。
「岬が転んだのを助けようとして、ケイが逆に怪我しちゃったんだよね」
「あれは事故だ。僕のせいじゃない」
「そうだね。ケイの運動神経が鈍いのは、ケイのせいじゃない」
血を恨むんだねだなんて、さも面白そうに笑う絵里に向かって、僕は下唇を突き出した。僕は男の子だったから、女の子に怪我をさせちゃいけないと思ったんだ。結果、僕は足に大怪我を負ってしまって、その夏はずっと家で療養していた。岬と絵里は、そんな僕を見舞ってくれた。泣きながら僕に謝罪と感謝を繰り返す岬の姿は、正直辛かった。きっと、僕が何もしなくても岬は大した怪我もしなかったに違いないからだ。
僕が勝手に手を出して、勝手に怪我をしたに過ぎない。なのに岬を泣かしてしまった。子供心に思ったひどい罪悪感を覚えている。
岩の間を縫って流れてくる小さな川。きっとこの川の姿は変わっていないのだろうけど、それを見下ろす僕の視線はずいぶんと高くなった。六年は、短いようで長い。足元の水流を手ですくって口に運ぶ。味は変わっていなかった。
「おいしい」
絵里は何も言わなかった。ただ、あの夏からずっと残っている僕の足の傷跡を見ている。
降ってくる蝉の声が懐かしかった。木漏れ日の作る陽だまりの中で、僕は思い出す。あれも夏だった。十四歳の夏、母親が死んで僕がここを去ると決まったとき、僕と絵里はここで最初で最後のキスをした。それは、岬も知らない、二人だけの秘密だった。
絵里はその話をしようとはしなかった。恥ずかしかったのかもしれないし、気にしていないのかもしれない。僕だけが覚えているなんてことになったら恥ずかしいから、それは僕も口にしないことにした。
青い空は高く、森はいい匂いに満ちていた。
「この銅像、まだあったのか」
裏庭に二宮金次郎の像がある中学校なんて、もう日本には数えるほどしか残っていないんじゃないかと思っていたけど、そうでもないのかもしれない。
訪れた母校は、校舎の汚れがひどくなっていただけで、あまり変わっていなかった。隣接した校長先生の自宅は平屋のままだし、風が吹くたびに儚く鳴る風鈴も記憶と一緒だった。先生に挨拶しようと思って自宅に向かいかけた僕を、絵里が引きとめた。
「校長先生、しばらく留守にしてるの」
「そうなんだ。どこに行ってるの?」
「知らない」
二宮金次郎の持つ本に目をやった。当然だけど、僕が表紙にマジックで書いた『保健体育』という文字は消されていた。僕は銅像をポンポンと叩いた。あのときにそうしたように。
僕はここで絵里に告白した。七年前の夏だったから、僕と絵里は一年間も付き合っていたことになる。それが短いのか長いのか当時はわかっていなかったけれど、アメリカでのガールフレンドとの付き合いは最長でも九ヶ月だったのだから、僕の生涯最長記録になる。
この銅像相手に告白の練習をして、登校日の帰りに彼女に声をかけてここに呼び出した。呼び出す前から緊張しっぱなしで、ロクに相手の顔も見れなかった。彼女が来たことを確認して、僕は好きだと告げた。
言い切ってから、僕は顔を上げた。そのときに見た、顔を真っ赤に染めた絵里の顔を、僕は今でも鮮明に思い出せる。その時に感じた僕の、言葉では表せない不安と緊張と恐れは、それ以上にハッキリと覚えている。彼女が「わたしもケイちゃんが好き」と言ってくれたとき、僕の全身から汗が噴出した。終わったと思った。
絵里に微笑みかけて、僕はすぐに金次郎に向かって振り返った。それから、この銅像をポンポンと叩いて「内緒だぞ」と言った。絵里はそれを「僕と絵里が付き合いはじめたことを内緒にしよう」という意味に受け取ったようだった。
僕はそれを否定することもできないで、ただ金次郎を眺めていた。どちらでも良かった。金次郎に約束を守ってもらうために、保健体育の落書きは、いつか消してやらなければならないなと思った。
多分、あのことは今でも絵里は知らない。知らないでいいと僕は思っている。知らないでいてほしいと今でも思っている。もちろん、絵里が薄々それに気付いていたことも知っているし、そのためにあの怪我があったのかもしれないことも想像ができた。けれど、僕はそうは思いたくなかった。これ以上の罪悪感はまっぴらだった。僕は後ろめたい気持ちのまま、一年後アメリカへ旅立った。
「森に戻ろうか」 いたたまれなくなって、僕は思わず言っていた。
「どうして?」
「スイカを忘れてきた」
「もう少しあそこに置いておいてもいいじゃない」
「スイカを食べるのを忘れていたんだ」
都合よく、僕のお腹の虫が騒いだ。朝の電車のなかでお弁当を食べてから、僕は何も胃袋に入れてなった。時刻はそろそろ三時を回ろうとしている。
「僕はスイカが好きなんだ」
絵里はアメリカ人がするように肩をすくめて、ちょっと笑った。麦わら帽子からこぼれた黒い髪が太陽の中で光って、それを見た僕は、絵里はやっぱり美人になったと思った。
「じゃあ、わたしの分も食べていいよ」
「何で? 絵里もスイカが好きだったじゃないか」
「お腹が一杯なの」
「残念だな」
と僕は言った。「僕と会えて胸が一杯だとか言われたら、凄く嬉しかったのに」
「ケイと久しぶりに会えて、胸が一杯なの」
振り返る間際、涼しげに目元を細めて、絵里は微笑した。自分で言わせたくせに顔が赤くなっているのに気付いた僕は、照れ隠しで空を見上げた。
「アメリカ人はあれくらいで照れたりはしないんじゃなかったの?」
「今のは不意打ちの上に心が入りすぎてた。社交辞令には慣れてるんだけど、本気の告白は別だ」
あはは、と絵里は初めて声を上げて笑った。綺麗な笑い声だった。
「当然でしょ」 と彼女は言った。「六年も溜めてたんだから」
かなわないなと思った。
森へ帰る途中、絵里は急に走り出した。追いかけようと走っているうちに、汗がまた流れ出した。三時を回ると、村の人たちが田んぼの仕事から帰ってくる。視線から逃げるように、僕らは走った。
懐かしい顔をいくつも見かけた。本当はゆっくり挨拶したかったけれど、絵里を見失うとまずいし、前から「早くおいで」と急かされるから、会釈さえできなかった。
本当は、立ち止まろうと思えばできた。絵里もそれくらいは待ってくれるだろうと思ったし、先に行ってしまっても小川の位置くらいは覚えていたから、問題は何もなかった。
けれど、麦藁帽子を抑えて走る絵里の姿は、文句なしに美しかった。汗が細い顎から落ちる瞬間は、ほとんど幻想的でさえあった。畑仕事を終えた泥だらけの人たちの中にあって、絵里は一人だけ嘘みたいに綺麗だった。
だから、僕は立ち止まれなかった。絵里の姿を見ていたくて、他の人に挨拶なんてしている暇はなかった。森の入り口が見えてきてからも、僕らは変な追いかけっこを続けた。
森に入る直前、視界の隅に校長先生の姿が見えて、僕は会釈しようかどうか迷った。どうやら「しばらくの留守」から帰ってきたようだった。僕は校長先生ではなく、絵里をとった。
土と葉の匂いに満たされた森の中は涼しかった。小川の水で喉を潤してから、僕らは少しだけ森の中を歩き回った。蝉はどこに隠れたのかと不思議なるほど、木々のざわめき以外に、音はなかった。異様に静かな空間で、僕たちは思い出話に花を咲かせていた。
一本だけ、道に張り出した枝があって、それで僕は思い出した。けれども、絵里は何も気にしていなかったようだし、僕らにとってそれは思い出すべきではないことだったので、何も言わなかった。
不思議な違和感があった。それは六年という歳月だけでは説明できない何かだった。僕はそれに気付きそうになっていて、絵里はそれに気付きたくないようだった。
絵里が幽霊だなんて、そんな馬鹿な怪談めいた違和感じゃなかった。何かが少しづつズレているんだと思った。風が吹いて、汗に濡れた僕らの間を駆けていった。少し、肌寒かった。夏の太陽はまだ高かった。青空の中心に、まだ白い太陽がかかっていた。森の道端に、真っ赤な彼岸花が咲いていた。
僕らはまた川に戻り、スイカを割って食べた。絵里は本当に少しだけしか食べなかった。昔はあんなに美味しそうに僕と取り合っていたのに、今はすごく大人しく上品に食べていた。
「種はちゃんと出しなさいよ」
僕は種をプププと飛ばした。絵里に向かって飛んでいった種は一つも絵里には当たらなかった。「キャア」と短い悲鳴を上げて、絵里がよけたからだ。悲鳴は森に響き渡った。
「何するのよ!」
怒ってスイカを齧った絵里は、でもうまく種を飛ばせなかった。六年のブランクがある僕ができたのに、絵里にはもうそれができなかった。絵里は、女の人に成長していた。
絵里だけじゃない。六年が経って、僕らは大人になったのかもしれなかった。味覚も変わったのかもしれないし、記憶が薄れたのかもしれない。僕らはもともと、ただの友達くらいの関係でしかなくて、僕が思っているほど色の濃い思い出は、絵里の中にはないのかもしれなかった。そう思うと、少し寂しかった。
スイカの汁でベタベタになってしまった顔を、川につけて洗った。麦藁帽子を木の枝にひっかけて、絵里も僕の真似をした。僕らは前髪までびしょびしょに濡れて、笑いあった。絵里の笑顔だけは子供の頃と変わりなかった。
「ふう」
と息を漏らして、僕は前髪をかき上げた。毛の先から、雫がポタポタと落ちていった。絵里がそれを真似して前髪をかき上げようとしたとき、僕は心臓が止まるかと思った。
絵里の白くて小さい額が、陽だまりの中にあった。そこには何もなかった。すごく綺麗な、白い額だけが僕の瞳に写っていた。全てのズレが修正された一瞬だった。違和感は、どこかに吹き飛んでいった。
僕は笑い出した。六年は長かった。どうしようもなく長かった。だから僕は、こんな簡単なことにさえ気付けなかった。
「何を急に笑ってるのよ?」
綺麗な額を晒しながら、絵里は眉を寄せた。
「六年の長さを痛感してしまったのだ」
「どういうこと?」
「言葉通りの意味だよ」
と、僕は言った。「六年は長いから、アメリカでテロが起こったり、イラクで戦争があったり、僕らが二十歳になったり、姉が男と一緒に出て行ったり、妹が姉の代わりを演じたりしなきゃいけなくなって、僕がそんなことにも気付かなくなる」
彼女は目を見開いて、それから舌を出した。「バレちゃったんだ」
「バレちゃったね」 と、僕は微笑んでみせた。「ご苦労様、岬」
それが、彼女の本当の名前だった。僕の目の前にいるのは、絵里ではなく、岬だった。
絵里には、一卵性双生児の妹がいた。岬という名前の彼女は、絵里にそっくりで、絵里と違ってスイカがあまり好きじゃなくて、暑さに弱くなかった。
僕が「岬はどうした」と聞いたとき、彼女はとても不機嫌そうな声で「男と出て行った」と答えた。きっと、出て行ったのは岬ではなくて絵里の方だったのだろう。絵里の決断は正しかったと思う。僕だって、六年間ずっと絵里を思い続けてきたわけじゃない。アメリカで懇意になった女の子も何人かいた。絵里のことを責めるつもりはない。
けれども、岬は僕と絵里の約束を覚えていた。二十歳になって僕が帰ってくるという手紙が来たとき、優しい岬は絵里がもう他の男と一緒に出て行ったとは言えなかったに違いない。だから、岬は絵里を演じることにした。ずっと騙しきるつもりはなかっただろうけど、とにかく絵里と入れ替わってみせた。僕はまんまとそれに引っかかってしまった。
校長先生はきっとどこにも出かけていなかっただろうし、森に帰ってくるときに岬が急に走り出したのは、村のみんなの話からボロが出ないようにするためだったのだろう。僕が感じた違和感はそれだった。彼女は絵里ではなかった。
だから、二人だけの秘密の場所に来ても、岬は何の反応も示さなかった。僕が絵里に告白した場所に来ても、僕が絵里とキスしたことを思い出しても、彼女は何も特別なことを感じなかった。だって、彼女は岬だったのだから。
「よく分かったね」
「分かるさ」
岬は笑った。「今までずっと気付かなかったトーヘンボクがよく言うよ」
僕は少しだけ言葉に詰まってから、続けた。「絵里の額はそんなに綺麗じゃないんだよ」
岬の顔が絵里にダブった。顔面が、血で濡れているようだった。
「髪の生え際に一本、細い傷跡があるんだ。絵里が前髪を伸ばしてたのは、そのせいだと思う」
「よく覚えてるね、そんなの」 少し不服そうに、岬は言った。
「覚えてるさ」 僕は森の方を見た。「僕がつけた傷だからね」
道に張り出した枝に、血がついているように見えた。
「いくらトーヘンボクの僕だって、女の子の顔につけた傷のことを忘れるほど腐っちゃいない」
「女の子の顔を傷つけるだけで、十分に腐ってると思うけどね」
わざとおどけて言った岬の声は、けれど僕の心の刺さった。その通りだと思った。僕は腐ってる。
「向こうに行く前の春だったと思う。二人でここを散歩してたら、あんな感じで道に張り出した枝があった。僕がそれを手でよけたんだけど、途中で折れちゃったんだ。それが、絵里の額に刺さった」
今でもたまに夢に見ると言ったら、絵里や岬は笑うだろうか。笑ってくれるだろうか。
「血が沢山出たよ。けれど、絵里は僕が親に怒られるといけないからって、それを誰にも言わなかった。川で血を洗って、夜になって傷がかさぶたになってしまうまで、ずっとここにいた。上げていた前髪を下ろすようになったのは、あれからだったんだ」
絵里は何も言わなかった。時刻は大体午後の四時ごろになっていると思う。夏の太陽はまだまだ高くて、西の空を見ても、あの世界が燃えているように綺麗な夕焼けを見ることはできなかった。日本は、ニューヨークよりずっと暑かった。
「そんなことがあったんだ」 岬は頬を膨らませた。「損したな、じゃあ」
石に腰掛けた岬の、長い黒髪が靡いていた。黒い絹の糸みたいなそれは、記憶の中にある絵里のものよりもずっと艶やかに見えた。
「ケイが前髪を下ろした髪型が好きだから、お姉ちゃんもそうしてるんだと思ってた」
自分の前髪を触りながら、岬は目を細めた。そういえば、絵里が前髪を下ろし始めてすぐ、岬も髪型を変えた。さっきの口ぶりを思い出す限り、僕を待たないで消えていった絵里に対して、岬は必要以上の怒りを感じているようだった。今も昔も、岬の心は変わっていないようで、それは僕も同じだった。
「その髪型は、僕の責任?」
「そうなるね」
「じゃあ、安心していい。僕は今の岬の髪形も、今の岬自身も好きだから」
初めて、岬が赤面した。僕は岬の隣の石に座って、華奢な肩を抱いた。岬は抵抗しなかった。夏は暑くて、太陽がまだ高くて、森が静か過ぎたから、僕は岬にキスをした。
「さすがにアメリカンね」
「アメリカは関係ない」 僕は大真面目に言った。「七年も溜めてたんだ」
岬の髪の毛はいい匂いがした。僕は岬が好きだった。
「顔が一緒だから?」 と岬が問いかけ、
「中身が別だからさ」 と僕は答えた。
顔が一緒だから。懐かしい台詞だと思ったら、それは僕自身の台詞だった。ひどい台詞だと思った。二宮金次郎は、さぞかし怒っているだろう。
僕は岬が好きで、それは今始めて抱いた思いではなくて、七年越しの恋だった。あの夏、僕は絵里ではなく岬に恋をしていた。緊張でまともに顔を上げられなくて、呼び出す相手を間違えてしまったことに気付いたのは、告白を終えてようやく顔を上げられたときのことだった。
僕はひどく恐ろしい思いをしたけれど、あのときに「間違えた」だなんてことを言えるはずもなかった。僕は二宮金次郎に向かって、僕が岬に告白したかったことは内緒だぞと言った。その約束は、僕がアメリカに行っても、帰ってきてからもおそらくは守られた。あのとき、僕は絵里と付き合うことにした。絵里を好きになることにした。顔が一緒だからなんていう無理な理由で自分自身さえ誤魔化して。
絵里はそのことに気付いていて、それで僕の心を自分に向けようとしたんじゃないかと思う。もちろん、これが僕の邪推に過ぎなかったらそれが一番良い結末だ。けれども、僕はどうしても考えてしまうのだ。絵里はあのとき、わざと枝をよけなかったんじゃないかと。わざと額を傷つけてまで、僕の心に自分の居場所を作ろうとしたんじゃないかと。
いくら空想したところで、絵里はもう僕の目の前にはいない。絵里は僕以外の男を好きになったし、僕は絵里に対して最低な男のままだ。岬の髪に触れながら、ただ岬のことだけを思うことにした。僕に肩を抱かれて、岬はカチカチに緊張していた。
「汗臭い」 と岬が言った。
「あ、ごめん」 離れようとした僕の腕を、岬が掴んだ。
「別に、汗臭いのも嫌いじゃない」
アメリカで遊んでいた僕よりも、知らない男についていった絵里よりも、岬は純粋に恋をしていたんだと痛感した。岬をもっと強く抱き締めたいと思った。夏だった。もう少しだけこの季節が続けばいいのにと、高くなっていく自分の体温を感じながら、僕は願った。
|