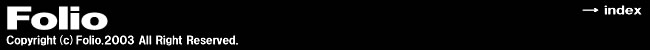|
随筆家で幻想小説家だった内田百間は偉いひとで、ドイツの翻訳童話集「王様の背中」の序文にこういうことを書いている。子供に向けた昭和初期の本である。
「このお話には何も教訓がありません。だから安心してお読みください」
こんな夢をみたことがある。
僕には恋人がいて、恋人は朝ごはんをつくってくれようとしている。
「何がいい」と聞くので、僕は「たまごやき」とこたえた。
恋人はそれを聞いて、なにかむすっとして不機嫌なようすだった。
「たまごやき?」
「たまごやきだよ。ふつうのたまごやき」
たまごは冷蔵庫にいくつかあったはずで、油は流しの下の扉の中にある。
塩とこしょうは、レンジの脇にいつも並べておいてある。
材料はそろっているはずだ。なにも問題はない。
恋人はなにか言いたそうな感じだったが、むすっとしたまま、台所のほうへ行ってしまった。引き戸がどしんと音をたてて閉まった。
たまごやきというのは、ふつうのスクランブルエッグのことだ。
フライパンを温めて、油をひいて、たまごを2個割ってフライパンに入れ、塩とこしょうを少し入れて(まあ、たくさんでもいいがね)、さいばしでごちゃごちゃっとかき混ぜ、半熟以上になったらできあがりだ。
うちの親は適当なのでだいたい固くてひとかたまりになったものを作る。
いもうとは甘いのが好きなので、砂糖を混ぜてかたまりになる前にひきあげる。
ぼくはそのときどきである。3分でできあがる。
台所のほうは、しばらくしーんとしていた。そのあとで、がしゃんとかごしゃんとかいう音がときどきしはじめた。いったい何をしているのだろう。
30分たっても、たまごやきはちっともできてきそうな感じがない。たまごやきには、たまごの焼けたにおいがつきものだが、ぜんぜんにおってこない。
心配になって、引き戸をあけてそっと台所をのぞいてみた。
恋人は流しの前で、背中をまるめていっしょうけんめい何かをかきまぜていた。
テーブルの上には何冊かの料理本が開きっぱなしになって散らばっている。「ミラノ風」とか「純和風だし」とかの大きな活字が見えた。その脇に、日清の小麦粉の黄色い袋が開いていて、中身の粉が青いテーブルクロスの上に少しこぼれていた。
ほかに、パセリやシナモンや黒こしょうのびんが並べておいてある。
テーブルを廻って脇に立つと、恋人は目に涙を浮かべて、小麦粉と卵を泡立て器でがちゃがちゃかき混ぜていた。
「見ないでよ!」
僕がいるのに気づいて、恋人はボウルを両手で抱えてかくしてしまった。
「見ないでって! ちゃんと作ったらそっちへ持っていくから」
「何作ってんだよ?」
「たまごやきよ!」
「なんでそんなにたいへんなんだよ」
「あなたが作ってくれって言ったから作ってるんじゃない!」
「そんな凝ったもんじゃなくていいよ」
「うちではこれがふつうなのよ!」
「そんなにすごいのかよ」
「すごいのよ!」
なんだか僕は、彼女のいきおいに圧倒されて居間に戻った。
爽やかな夏の朝は、のっけから不穏な雰囲気を帯びていた。テレビを点けると、めざましテレビで大塚アナが今年は冷夏になりそうで、冷夏になると米の出来が悪くなる上にビールなど関連商品の売れ行きがにぶって不況になる、と解説していた。
しばらくしたら、居間の引き戸がばーんと音をたてて開いた。
びっくりしてふりむくと、彼女が戸口に立っていた。手が真っ黄色だ。
「あたし、出て行くわ」
「へっ」
「さようなら」
「ちょっと待て、おい」
「あなたにはついていけないの」
「何言ってんだよ」
「なにか、わかったの。ついていけないってことが」
「言ってることがわからないよ」
「なんてもう! オーブンレンジの予熱がどうだっていうのよ!」
ほおの筋肉がせり上がって、片目だけほそくなっていた。
「オーブンレンジなんて使わなくていいじゃん」
「使わなきゃいけないの! うちはね、あなたのとこよりずっとすごいのよ」
「そりゃすごいなあ。うちは農家で悪かったなあ」
「すごいでしょ」
「農家で悪かったから、出て行くのだけはよしてくれ」
「もう決めたの。わかったの。オーヘントッシャンとか、セットプレイとか、どうだっていうのよ」
彼女は、ついに泣き出した。
「むつかしいこと言うなよ」
「むつかしいこと言ってるのはそっちじゃない! あたしはね、和民のほっけが好きなのよ。ずーっと好きだったのよ」
「俺も好きだよ」
「そういうことが何でわからないの!」
「和民のほっけで何をわかれって言うんだよ」
2人してにらみあった。
「台所へ行ってみようぜ」
「行ってみなさいよ」
台所へ行ってみた。台所は思ったより散らかっていなかった。洗い桶の中に、ボウルとさいばしと泡立て器がつっこんであった。
まな板の上に、こんがり黒焦げになった塊が乗っかっていた。大きなハンバーグのようだった。
「これがたまごやきか」
「違うわ」
「じゃあ何だよ」
「何か、何かよ」
とりあえず箸で割ってみた。中身は黄色くて、たまごやきのように見えた。
「なにすんのよ」
「食べてみるんだよ」
「やめてよ! やめてよやめてよ!」
彼女の攻撃をかわして口に入れたたまごやきは、小麦粉のダマが混じり、こしょうがきつかったが、たまごやきだった。
「たまごやきじゃないか」
「違うわ」
「違うって、たまごやきだぜ、これは」
「そうやってまた、ほめる余裕を見せてわたしを笑おうっていうんでしょ」
「笑ってないよ」
「そんなつまんないもの、どうして食べられるのよ」
「食べられるって、俺、しょっちゅうこれくらいの食べてるぞ」
「つまらないじゃない。どうしてつまらないって言えないの?」
「無理につまらないって言えるかよ」
「つまらないって言うのは、ありがとうって言うのと同じことよ!」
「めちゃくちゃなこと言うなよ」
「だからあなたはつまらないのよ!」
「そんなこと言ってもさあ」
「あなたみたいなつまらない人とは一緒にいられないの」
「えっ」
「あなたと一緒にいると、みんながどうしてつまらない人とつきあってるのって笑ってる気がするのよ。そういうことが分からない? あたしがどれだけたいへんだったか」
「どうしてそこへ行くんだ」
「あたし、つまらないのよ」
「俺はつまらなくないよ」
「どうしてあたしとつきあってるのよ」
「そりゃ、おととし公園で告白したしさあ。好きだしさあ。それから、なんというか」
「なによ」
「たまごやきみたいなもんさ」
「え」
「いちばんつまんないと思ってるものが、いちばんだいじなものなんじゃないかな」
|