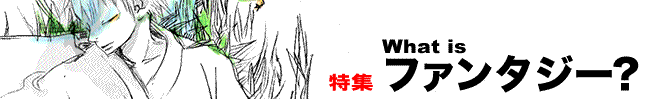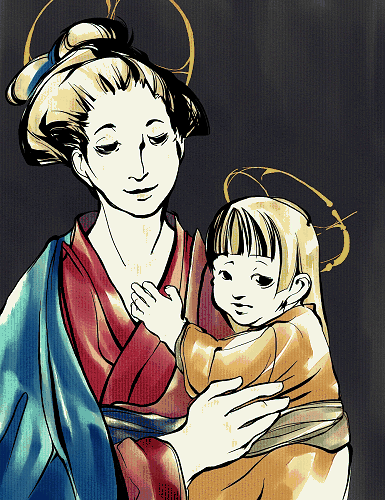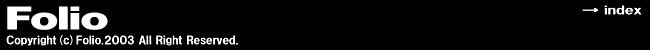「あなた。噂になっていますよ」
朝になって妻がいった。胎蔵の所に通うことが、だろう。もしくは長崎へ使いをやったことか、だろう。
私は歯楊枝を盥に汲んだ水で洗いながら、答えた。
「まあ、いいじゃないか」と引き続いて顔を洗う。
「嫌ですわ。人聞きの悪い」
私はトキの身体を引き寄せた。
「もう。濡れた手で触らないでください」と布巾を差しだす。
「済まぬ。今度着物を買ってやるから」
「関のお役目はきちんとしてくださいよ」
「分かってる」
とはいっても、今年はお上りが少ないのでただ関所の奥に座ってうとうととしているのだった。御番役の橋爪様はもうずっと来ない。旅人の相手は下の者達が行なう。私は鳶が松の枝に留るのを待ち、それが吉兆の印だと思ったりして時間を潰しているだけなのだ。
ならば、延々と孤独に石を積む胎蔵の何が悪いというのだ。私は胎蔵が描いた天狗のような異人の顔を思い浮かべた。憑き物のついた胎蔵は石垣と門を造り続けるだろう。彼の脳裏にはなにが浮かんでいるのだろう。背中に羽の生えた小さな天女の話など、誰が信じるものか。そして彼の言葉を思いだして私は段々と気分が悪くなってきた。ヤツの妄想に付きあってしまう己に腹が立った。
私は馬を用意させて、駆けた。山を駆けて隣の宿場に向かった。向かう途中で海沿いの祠を通り過ぎて、岬に辿り着いた。岩が海面から突きだしてその先端に注連縄が結ばれて岬の岩と繋がっている。
かつてこの岬から、僧侶と下女が補陀落へ向けて漕ぎだしたという謂れがあった。人々の噂ではもっぱら二人は通じ合っていたといい、現世では結ばれることを許されないので補陀落に賭けたという。または、飛び抜けて知力眼力のあったその詮海という僧侶は現世の矛盾に縛られてゆくのを肯んじえず、補陀落にやみつきになって、仕舞いには自らの身で確かめたくなったとも言われていた。
何故ここ、なのだ、という疑問が私の頭を充満した。岬は他にもあるのだ。私は詮海が創建した古寺に立ち寄った。
「おや、おや。古屋官兵衛様。何か御足用がおありですか」
出てきた俊景に私は詮海の蔵書を見せてくれと頼んだ。
「あれは門外不出となっております」
「では、なぜ補陀落へと参ったのだ?」
俊景は頭を振ってわかりませぬ。私どもに詮海様のお考えが分かるはずはありませぬ。さてはて、官兵衛殿は何故、そのことに御興味を持たれたのです? と訊く。私は逡巡したが、胎蔵の出来事の概略を話した。俊景にはひどく関心をひく逸話だったようで、そのような世迷い事を言いふらす輩が、古屋様の下男に居るのですね、と繰り返した。
「いや、大ぴらにはせぬようにと、わしが釘を刺している」
「ならば安心です」
俊景はその大きな目をくりくりとさせて答えた。
数ヶ月が経過して、私は僧侶達が屋敷に入ってきたという報告を受けて関から家に急いで戻ると、俊景たちが胎蔵を拘束して、連れ去ろうとしていた。
「待て」と割って入ると、俊景は私に「この男の城を見た。相当なものだ。ことによってはそちも加担しているのかも知れない。なにを考えているのか詮議するだけだ」と答えた。
「それは奉行所の役目ではないか」と声をあげると「これは拙僧たちの問題なのです」とにべもなく答えた。おまけに城ではない。加羅かどこかの街の石垣なのだ。
妻が私の袖を引っ張り押し止めた。私は胎蔵の犬のような目を見た。もうどこにも向かっていない、ただぼんやりと遠くを見詰めるような視線で地面の一点を凝視していた。悔しいだろうと思われた。私は、約束を違えた俊景を恨んだ。
「この男の話す話をそのまま放置しておくわけにはいかんのです」
俊景は法衣に指をかけて煽ぐような動作を見せた。そして、これはわしらの問題だ、と繰返した。そして背後の僧達に目配せをして胎蔵の縄を引っ張った。私は止めようとしたが、その時はじめて胎蔵は私を見付けたかのような顔をして、「官兵衛様。わしは大丈夫です」といった。妻は心配そうな顔で私を見た。私はじっとその場で立ち尽くすしかなかった。
そして「大丈夫」と妻に囁いて励ました。
当然、その日のうちに私は橋爪様から呼びだされて叱責を喰らった。私は心無い者に噂された。私は心細い気がしてじっと黙っていた。
長崎からの早馬が戻ってきたのはそれから二日程経った午後だった。
「古屋官兵衛はおらぬか」と関で呼びまわり、慌ててでた私を出迎えたのは、長崎所司代の役人、大元重光という者だった。その男の後ろに息をつかせた使いの者が恐縮している。
「お前は御禁制の品をいかようにして持ちえたのだ」と驚く私を尻目に大元は私が下人に持たせた胎蔵の描いた夢の刀剣の写しを指し開いた。
「いえいえ、これは」と私が説明しても一向に肯んじえず、大元は私を縛るように言いつけた。
「この絵を描いた者はどこだ」
大元重光は座敷の入り口で私を問い詰めた。俊景に捕らえられたと報告し、私は「それは、本当に南蛮に存在するのですか」と訊いた。
「知らぬとは言わせぬぞ」
「知らないのです」
私は断固として拒否した。私は何も知らないのだ。
「その男に問い質してみればよい」
大元重光は私の前から居なくなった。私は縄に縛られたまま、不条理に怒りを燃やしていた。その一方でなにもかも失ってしまったような気がして、古屋家の衰退を招くのは我が身だったのかと悔やんだ。
胎蔵を恨み。我が身を恨んだ。そして胎蔵の夢の中にでてくる様々な奇怪な生物や、その物語を恨んだ。
永劫なる時間に感じられた。私は精神が非常に衰弱してぐったりと畳に頭を付けてもう何もかも遠くなるように、盲漠とした意識に浸っていた。
きっと大元重光が戻ってきた時には、私は奇怪な形相になっていただろう。
怒りによって、憎しみによって、後悔によって。
「なるほど、お主の申すことは確かに正しいようだ」
寺から戻った大元は言った。
「あの下男は、憑き物がついているようだ。紙を渡すと数限りない禁制品の絵を描いてな。これだ」
彼は私の足下に紙を投げ、何枚もの紙がはらはらと揺れて落ちた。
そこには刀剣や天狗の絵や小人の絵が稚拙な筆致で描かれていて、揃いも揃って奇妙な衣服を着ていたり、中には守宮(やもり)の化け物の絵があった。
「所中で話題になってな。御禁制品の絵を誰が描いたのか、ということが」
縄を解かれながら私は訊いた。
「では実際にあるのですね」
「商館に問い質すと、本国にあるそうだ」
「まったく同じものが?」
「似ているものがあるそうだ。この異人達はあちらの神代の物語にでてくるもののようだ」
私は愕然とした。
「胎蔵にはそのような知識はない」
「もちろん、ヤツにはそのようなものを見たことも聞いたこともないだろう」
大元は四角い顎を撫でながらいった。
「厄介をかけたな。わしは証拠の絵を持って長崎に帰る。そのうちに正式の沙汰があるだろう」
あっさりと私は無罪放免となった。
どこからその話が漏れたのだろうか、翌日には胎蔵の石垣のまわりに人々は集まり、がやがやと騒ぎ始めていた。石垣は完成間近で、円弧の門は器用に均衡を保ち、図面の通りに完成していた。人々はそれを褒て囃した。
私が到着すると、人々は胎蔵に会わせろといって、私の周囲を取り囲んだが、なだめ倒して人々を下がらせ、門番を立たせてから胎蔵の家に入った。
「官兵衛様、申し訳ないことです」
彼は左足を誰かに潰されて臥せっていた。
「済まぬことをした」
私が謝ると、胎蔵は頭を畳に押し付けて平伏した。
「紙と硯を頂戴したいのです」
「なぜ」
「私の命は長くないのです。その前にこの脳にあるものを全て吐きだしたいのです」
尋問に気を弱くしたのだろうと私は思った。
「そのようなことを言うものではない」
「いいえ。急いで描かねばなりません。足がこのようになってしまったあと、私にはそうするしかないのです」
いつになく真剣な目だった。私は肯んじ、配下の者を呼んで、紙と硯を持ってこさせた。胎蔵は紙を見ると煎餅布団をはね上げて起き上がり筆を取った。
それからひとつきの間、彼はひたすら描き続けた。
紙が切れると床板を外して描き、壁に描き、樽桶にも描こうとした。私は狂気極まる彼の幻のような事物にほとほと感心し、言葉もなく見守り続けた。
ひとつき後、長崎からの使者が到着して、私に僅かな褒美を与え、胎蔵を連れてゆくことにしたと伝えた。
胎蔵は膨大な量の紙を私に預けて村を去っていった。
半年後、大元から胎蔵が長崎で死んだとの報が入った。商館の人々との付きあいに慣れたという話が伝わってきた直ぐ後だった。私の手元には胎蔵の絵だけが残った。
橋爪様が病に倒れたので私は関の見張り役になった。
これで古屋家は安泰だと安心したのと入れ違いに、ハルが消えた。
突然ハルは居なくなった。どこを探しても見つからず、泣き叫ぶことに疲れた妻は喉を突いて自害しようとしたのを、私は止めた。修羅場が何日も続き、やがてふたつきも経たぬ間に妻は臥せってしまった。は古屋家のハルは天狗が連れ去ったのだと人々は噂した。
私は今でも時々、胎蔵の石垣を眺めにゆく。
了
|