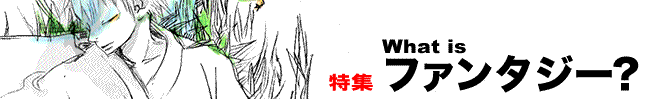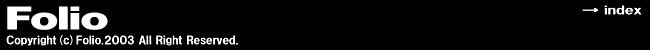|
彼女が魔女の末裔だと分かったのは僕らが七回目のセックスを終えた後で、僕はゴミに埋もれたゴミ箱を探すため、灯(ひ)を探っている最中だった。あー自分の生活はダラシガナイ。死にたい。僕がそんな事を呟いたあと、彼女は「死んじゃあ困る」と言い、指先一つで目の前にゴミ箱を出した。そして自分の身を打ち明けた。
僕は彼女のうなじに指を挿し入れながら、ダラシナイの「ダラシ」とはどういう意味かと彼女に問うた。彼女の答は「どうでも良くない?」だった。魔女は意外に無知なのだった。その晩以来、彼女の魔法を目にすることはなかった。
僕は彼女に夢中だった。どうせ一服盛られたに違いない。それでも僕は相変わらず僕で、彼女は美しく魅力的だった。
おそらく二百二十回目くらいのセックスのあと、僕らは別れた。出来た子供を生む生まない──そんなどこにでもある出来事によって入った亀裂を、最後まで修復できなかった。呪い殺される事まで覚悟したが、果たしてそうはならなかった。それどころか、彼女は僕の新しい恋の手助けまでした。知的で活動的で嘘つきで──別れた魔女とは全く逆のタイプだったが、まあ、惚れたものはしょうがないと思う。「今後私にどんな質問をしても、あなたは死ぬ」別れ間際に言った彼女のセリフが気に掛かるが、訊かねば良い話だ。そんな機会もないだろう。
一年後、彼女から暑中見舞が届いた。懐かしい字だった。今のあなたの恋人に宿っている心は私で、あなたが私だと思っている女は既に別人です──とある。へえ。
ああ、魔女は厄介だ。それとも魔女と思い込んでいるから、厄介なのか。あの夜の魔法は幻覚に過ぎないのではないか。真実を今の恋人に問い質したいが、怖くて訊けない。死にたくない。例えば同じに位置にあるホクロのこととか、小さなことが気になってしょうがない。それでも下らぬことに囚われていると、そう信じたい。ただ一つ、彼女に一生解けない魔法を掛けられたのには間違いない。
了
|