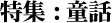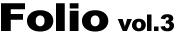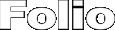「…でも、ジェイ。僕は無駄だとは思わないよ。童心っていうのは、ここに溜まっていく水のようなもので…子供のうちに貯えたものは、大人になっても決して枯れない」
アールは自分の胸を指さした。その泉は心の奥底で深い森に守られて、決して濁ることのない清水をたたえている。ときには、たとえば真冬の湖のように表面が凍りつくこともある。それでも魂が生きている限り、底にある水脈が尽きることはない。
「それは、本当に苦しいときに僕等を救ってくれる。砂漠で命を救う水のように」
アールの泉は深く豊かだった。そしてそれこそが今となっては、彼にとっての生きる原動力になっていた。だから、こんなときでも心のどこかで、懐かしい童話を信じている。ここがアヴィニョンの橋であってくれれば、全てが平等の自由郷であってくれればと思っている。
「そうすれば 僕とお前が争う必要もない。そうだろ、ジェイ」
ジェイは無言で振り返った。肩越しにアールの絶望的に澄んだ眼と、立てかけたライフルの先端が見えた。こいつは俺を撃ちたくないんだ、ジェイはぼんやりと思う。たとえ敵同士であっても、この橋の上にいる間は、その立場を忘れたいと思っている。
いつまでここにこうしていればいいのだろう。橋の両側には、アールとジェイがそれぞれ所属する部隊が睨み合い、膠着状態が続いていた。互いを攻撃しないのは、ふたりの命が惜しいからではない。ジェイは爆薬を持っている。闇雲に攻撃すれば爆発するかもしれない。橋が壊されれば、互いに活路が閉ざされる。それを恐れてどちらも手が出せずにいるのだ。
こんなときの対処のしかたが、訓練のプログラムに入っていただろうか。ジェイは必死で記憶をたどろうとするが、意識は散りぢりになってうまくいかない。
さっきの怪我で氷が割れたんだ、とジェイは思う。脳裏に浮かぶのはアールが語った夢の断片。それは氷の割目からにじみ出す甘い水のようで、身を浸していると、確かに慰められる心地がした。
モシモ マホウツカイガ イテクレタラ
なんの脈絡もなく、ジェイはぼんやりと思う。魔法の杖の一振りで、この橋を、アールの言うような休戦地帯に変えてくれたらいいのに。そうすれば二人とも無事に、この窮屈なあずまやから出て行ける。それよりも、この止まらない脇腹の出血をなんとかしてもらおうか。傷の痛みは既に鈍く拡散され、ただ掻きむしりたいような空虚感だけがあった。
ぐらりと身体が傾き、ジェイは横なりに倒れた。
「ジェイ」
異変に気づいてアールが振り返る。ジェイは眼を閉じて応えない。厚い衣服に溜まっていた血液がどろりと流れだし、石畳を汚す。アールは言葉もなくそれを見つめる。眼の中の絶望が濃度を増す。ジェイの呼吸は、次第に浅く遅くなっていく。
引き裂かれた世界をつなぐ橋の上、太陽はまだ高い。二人の若い兵士の上を斜めに通り過ぎ、彼らが見たことのない世界の裏側へと、やがて沈んでいく。
了
| Back | 3 / 3 |