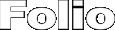その住宅地の真ん中にある小さな公園には幾人もの婦人が犬の散歩でやってきては、談笑をしていた。鎖で繋がれた犬達は互いにじゃれ合い、声を出し合い、手や足を絡めて転がり、追いかけっこをしながら、はしゃいでいる。
日が当たる穏やかな週日の午後、養殖されたキツツキが公園の緑の間をいったりきたりしていて、暢気な情景がそこにあった。婦人たちはあまり犬達が度を超さないように、時々目をやりながら家計のことや、近所のうわさ話に花を咲かせていた。
そんな様子を遠くから眺める、婦人と犬が公園の入り口でじっと彼らの様子を見ている。
「ね。トシちゃん。おいたしちゃだめよ。いい子だから」
犬は首をあげてママを見る。
「いよいよ、公園デビューだね」
「そうよ」
ママは着飾った衣装をもう一度整え、背筋を伸ばした。
「ちゃんとおしっこの時はママに言うんですよ」
「うん。大丈夫だって」
犬は手のない腕をまるで人間の時のように挙げてテレビで見た敬礼のまねをした。
「あんたをチャームしたのは遅かったけど、年長なんだから、しっかりやるのよ」
婦人はしゃがんでポーチからだした櫛で、犬の髪を整える。
「わかってるよ。ねえ、行こうよ、ママ」
「じゃあ、いくわよ」といい、婦人は犬の鎖を引いて歩き出した。犬はとことこと不器用に歩き出す。その姿は手首から先と膝から下を切り落とした少年だった。最近は「チャーム=愛玩」するということは、こういうことをいうのである。
子供はいい子であらねばならない。ママの言うとおりに従ういい子である。純真で適度に暴れん坊で、だからこそ手足なんていくらでも生やせるし、子供は親の庇護の下にいなければならないのだ。
これが、愛玩家の意見で、非愛玩家の家庭は時代に遅れていた。我々は子供の安全と教育のために子供を愛玩するのだ。これは子供の権利と親の権利を両立させるために必要な手術なのだと、テレビの広告はいう。だけど、学校のクラスからはぽつりぽつりと子供の姿が減っていき、ハナコは悲しかった。
ついに隣家のトシちゃんまでいなくなったのだと、しばらく悲しい気分で過ごし、時々トシちゃんの家に様子を見に行くのだが、トシちゃんのママは当然、時代遅れで貧しい家の子には会わせてはくれなかった。
ずっとトシちゃんとは子供の頃から一緒だった。
一緒に遊んで、一緒に育った。大きくなるとトシちゃんはいつからか塾に通いだした。そして毎晩遅く帰ってくるようになった。勉強しなきゃいけないのだと、やがてハナコからは離れていった。
だけど、どうした訳か、トシちゃんはすぐに塾を辞めたようだった。ハナコはそう聞いて、またトシちゃんと一緒に遊べるのかと思って嬉しかったが、そうはならなかった。トシちゃんは学校にも来なくなり、愛玩手術を受けたとママから知らされた。
ハナコの家では、パパとママはよく喧嘩をしていた。ハナコも愛玩すべきだ、というパパと、いいえ、どこにそんなお金があるの、というママである。パパはよく家にいて一人でお酒を飲んでいた。ママはよく泣いていた。ハナコは自分がチャームになった時のことを考えて、そうなれば、パパとママは優しくなるだろうかと考えた。でも怖かった。やはり今のままでいいと思っていた。しかしながら、どこか寂しかった。自分だけは特別に遅れているような気分がするのだ。勿論世間的には遅れた家の子だった。
みんなパパとママに愛されているのが、その身体が証明している。
チャーム手術は高額な金額がかかったからだ。パパもママも嫌いだ、と思った。
「勉強しなさい。勉強して、お金持ちに勝つのよ」とママはいう。ハナコは勉強は嫌いだった。
隣とうちを比べてみる。年々豪奢になってゆく隣の家と、ずっと寂れたままの小さなうち。ハナコは給食がないので、昼は学校の屋上で雲を眺めている。貧乏でイジメられたことも多々。汚い。臭い。意地悪がハナコの代名詞だった。
ある夜、ベッドに入っても寝付かれずに何もかも嫌になっていると、ふとトシちゃんの家の明かりが裏庭から漏れているのが見えた。
ハナコはこっそり家を抜け出した。
垣根の間をくぐり抜けて、裏庭に回ってガラス越しに覗いてみると、すっぱだかのトシちゃんはすっぱだかの綺麗なトシちゃんのママの足にしがみついていた。ママの足を舐めているようだった。トシちゃんのママはハナコのママのようにおでぶさんではなくて、お姫様のように綺麗な人だった。トシちゃんのママはハナコの学校の先生だった。ハナコはガラスを慎重に少し開けた。
「もっとちゃんとしてよ」
トシちゃんのママはトシちゃんを王女様のように叱っている。と、突然トシちゃんを蹴っとばして、泣き出したトシちゃんに向かって「いい子ね。いい子ね。だから、ママのいうこと聞いて」といって、またトシちゃんを殴りはじめたのだった。
ハナコはびっくりした。トシちゃんが蹴られるのと同時に身が竦む思いがして、心臓が跳ね上がるかと思われた。トシちゃんがかわいそうと思いながら、目が離せない。何故だろう。どきどきしながら、このどきどきは怖い、というのとは違っているのだ、と感じた。
声が家の中から聞こえた。
「ねえ。悪かったわ。だから、ママを癒してちょうだい」
甘ったれた声だった。これが国語のコイズミ先生の声だとは誰も思わないだろう。
ソファーにコイズミ先生が腰を下ろす。トシちゃんは、涙をしゃくりながらおそるおそるコイズミ先生に近付いて、その白くて細い足の間に頭を埋める。ハナコの動悸はいよいよ激しくなった。コイズミ先生は段々と声がゼリーのようにとろけだして、「ああ、そうよ。そうよ。ゆっくりゆっくりして」といい、柔らかな口調で「そう。上手になったわ」とトシちゃんの頭を撫でた。やがて猫のような声をだして、ぐったりとソファーに身体を寝転がして「トシちゃん。あなたはいい子だわ」と呟く。
トシちゃんは呆然とした顔で頭をゆらゆらさせている。恥ずかしそうにもじもじとしながら、ご褒美を待つ犬の顔で、じっと目を輝かせていた。
ハナコは愕然とした。こんなのトシちゃんじゃない、と思ったらママはゆっくりとソファーから起き出して、トシちゃんの身体をまさぐった。そしてトシちゃんの足の間に手を差し込む。トシちゃんは目をつむって天井を見上げて目を瞑った。恍惚とした表情だった。
ハナコは恐ろしくなった。
そして緊張して窓から離れる。
もう涼しい秋なのに、じっとりとした汗が噴き出していた。言葉もなかった。毎晩のようにそんなことが繰り返されているのだろうか。ハナコは悲しいのか怖いのか分からず、急いで家に戻り、布団に潜り込んで身を丸めたのだった。その夜は眠れなかった。
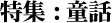
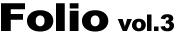
悲しい犬
サイキカツミ
 イラスト:ミンチ
イラスト:ミンチ
それからは、ハナコは学校でコイズミ先生の姿を見ると(幸いにしてハナコの担任ではなかったが)いつもあの白い足を思い出した。廊下ですれ違った時に、トシちゃんが嘗めていたコイズミ先生のあの真っ赤な場所を思い出して、頬が照りつけるような気分になった。自分にもあんな場所があるのかとこっそり鏡で見て見たが、恐ろしくなってやめた。綺麗な人には毒々しい、あのような場所があるのだ。醜いわたしにはないのだ、と思った。
コイズミ先生のスカートから伸びるすらっとした足。あんな風に綺麗になりたいのだ。そしてトシちゃんに、と思うと、もう駄目だった。胸がはち切れそうになって、自分が分からなくなった。
ある日、ハナコは風邪をひいた。学校を休んで寝ていると、隣の家の窓が開く音が聞こえた。トシちゃんが居るのかも知れないと思い、起きあがって窓から覗くと、果たしてそれはトシちゃんだった。手のない腕でガラスを無理矢理開けたのだろう。トシちゃんは窓から顔をだして首を桟の上に置いてじっと外を眺めていた。
ハナコは久々にトシちゃんを見て嬉しくなった。でも、その淋しそうな表情からは、外に出たいのかなと思った。ハナコの中で外に出してあげたいと気持ちが変わるのに、そう時間はかからなかった。
窓から手を振ると、トシちゃんは酷く嬉しそうな顔をしてハナコを見た。
手のない腕を振り返した。
「外に出たいの?」
「うん。でも、出ちゃだめって、ママが言ったんだ」
ハナコは頭がだるいなあ、と感じながら、家をでて垣根をくぐる。
庭に面した大きなガラス窓をトシちゃんは背を伸ばして開けようとするが、手がないのでなかなか開けることができなかった。
裏庭に回って、この前の夜に開いていた窓が開いていたらなあと期待してると、やはり開いていた。どうやらコイズミ先生はこの窓の戸締まりを忘れるようだ。ハナコは嬉しかった。ハナコは忍び込んだ。帰りは玄関でいいやと思い、靴も忘れない。
「ハナちゃん」
部屋に滑り込むと、トシちゃんが駆け寄ってきた。ハナコは嬉しかった。が、トシちゃんはすっぱだかだった。びっくりして声をあげるとトシちゃんはソファーの影に隠れた。
「ごめんよ。ごめんよ。でもママが服、隠しちゃったんだ」
「大丈夫よ」と言いながら、トシちゃんの足の間に小さく見えるものから目が離せなかった。
ハナコはこんなに間近で男の子のおちんちんを見るのは初めてだったので、照れながら、でもトシちゃんのはこの前こっそり見てるのだし、好奇心は抑えられなかった。
「ううん。いいよ。そのままで」
「ごめん」といいつつトシちゃんはソファーの陰から出てきたのだが、やはり恥ずかしいようで、四這いになったまま、うつむいていた。
「久しぶりだね」
「うん」
「元気?」
「うん。でも、今日は風邪で休んでるの」
「大丈夫?」
「大丈夫よ」と言いながら、やっぱり頭痛がするのだった。ふと、トシちゃんの身体に幾つも傷や痣があるのに気がついた。
「それは?」と駆け寄ったハナコが聞くと、ママが、と答えた。
「僕はママを上手にしてあげれなくて、いい子じゃないから、ママが叱るんだ」
ハナコはその言葉を聞くと、どきりとした。トシちゃんを殴るコイズミ先生の姿が浮かんだ。トシちゃんが悪い訳じゃないのに、と思ったし、その言葉が示すことが、とてもイケナイコトを表わしているような気がしたのだ。トシちゃんがそのような生活をおくっているのかと思うと悲しくなった。
「ねえ、チャームされて、楽しい?」
「うん」そう小さな声で頷くトシちゃんの頭を、恐る恐るハナコは撫でた。
「うちもね、トシちゃんみたいになるかも。ママとパパが話し合ってる」
「じゃあ、また一緒に遊べるね」
ハナコはトシちゃんの笑顔を見ていると、本当に跳ね上がるかと思えるほど嬉しそうで、それでいて、チャーミングになったトシちゃんはどこか頼りなさそうな印象を受けた。以前、遊んでいた時のトシちゃんとは何かが違っていた。トシちゃんの身体に手を触れた。肌が冷たい、と思った。
居間のテレビがずっと喋ったままのおじさんの様子を映している。自宅学習児のための教育番組のようだ。なにやら難しそうな、ハナコには到底分からない奇妙な図を、指揮者のような棒で差し示していた。トシちゃんは毎日あんなので勉強してるんだ、とハナコが溜息を吐いたとき、トシちゃんは顔をあげた。
「うんち」
「え?」
トシちゃんは慌てて、部屋の奥からバスルームにある砂箱に身を隠した。ハナコは呆然と部屋の中を見た。以前、まだトシちゃんに手足があった頃、積み木や車のおもちゃがあった。でも今はもう、ない。ヘッドホン型の記憶インプット機器や、テレビ教科書がそのかわりに仕付けられていた。そして砂箱。トシちゃんの生活はもう以前とは随分変わってしまったのだ。たぶんそれらの調度は高価なものだろう。決してハナコの家では買えない機器も含まれているに違いなかった。
ハナコはそのときはじめて、なんか別世界だ、と思った。
バスルームから声が聞こえた。ハナコは心配しつつバスルームに駆け込む。
「うんちついちゃった。ママに叱られるんだ。どうしよう」
トシちゃんは今にも冷や汗をかかんとするように焦っていた。
ハナコは考えて、「じゃあ」バスルームを指さして、「あっち」と言った。タイルに座らせてシャワーをひねる。温かい湯気がふっと充満した。
トシちゃんの身体に湯を当てると、きゃっきゃとトシちゃんはくすぐったそうにして、身を捩らせた。
「お尻向けてよ」と苛立ってハナコがいうと、殊勝にトシちゃんはお尻を向けた。
シャワーをあてがうと、トシちゃんは気持ちよさそうな顔をした。うまく洗い流せただろうかと思っていると「ねえ。ママがしてくれるようにして」と、トシちゃんはハナコの側に起きあがって寄り添うように座った。なに? と思う瞬間、おちんちんが目に入って、それはさっきまでぷらぷら揺れていた小さなものとはちがって棒のようになっていた。ハナコは慌ててシャワーを落とした。パジャマにお湯がかかって身体があったかくなってくる。
「さわって」
「いやよ」
いいから、お願い。とトシちゃんは勧めたが、ハナコはそれは悪いことだと思った。ハナコは顔を逸らした。パジャマが身体にべっとりとまとわりついて、奇妙な感じがした。トシちゃんが迫ってくるので、慌てて逃げようとすると急に顔が近付いた。
「やめて」というのより早くトシちゃんはハナコの身体の上にのしかかってくる。
「ねえ。ハナちゃん。僕のこと嫌い?嫌い?」
トシちゃんはハナコの頬をぺろぺろと、まるで犬そのもののように嘗めた。突き出たそれをハナコのお腹に押しつけるようにした。
「ママはね、これをゆっくり手で触ってくれるんだ。とても気持ちよくて」
トシちゃんはハナコの濡れたパジャマの上から先の丸い腕でハナコの胸のあたりを撫で回しはじめた。
「いやっ!」
声をあげたがトシちゃんはもうトシちゃんではなかった。
「ねえ、お願い」
じっとトシちゃんはハナコの顔を見た。シャワーの湯気のせいか、トシちゃんの目は、じっとりと潤んでいるようだった。どことなく淋しそうで、悲しそうな表情だった。
ハナコは胸が締め付けられるような気がして、心臓がドキドキ鳴っているのが分かる気がした。もう一度トシちゃんは訊いた。
「僕のこと嫌い?」
「好きよ」
声が震えているのが自分でも分かった。
「じゃあ、好き好きして」
トシちゃんはハナコの唇に唇を寄せた。
ハナコは目を閉じた。そしてゆっくりと手を伸ばしてトシちゃんのそれに触れた。固い。男の子ってこんなになるんだ、と思って、薄目を開けてみると鼻息が荒いトシちゃんはうっとりとした表情になっていた。ハナコは先端の丸くなったトシちゃんの腕の先が下着の中に入ってくるのを阻止することができなかった。
「あはっ! ママとは違う!」
トシちゃんは嬉しそうにいって、ねえ、ママのようにしてあげる。ねえ。脱いで、と言った。
ハナコの熱は翌日も下がらなかった。当然である。だから、またトシちゃんの家に行った。頭ががんがんするのも気にならなかった。そして今度は時間をかけてゆっくりとお話をした。そして、話を聞けば聞くほどトシちゃんは可哀想だと思った。そして自分がイケナイことをしてしまっているのだと思うと悲しかったし、嬉しかった。ハナコはどうしてよいのか分からなかった。それでもトシちゃんとのひとときは、どきどきとして心地よいものだった。
「前ね、公園でカブトムシ捕ってくれたよね」
「うん。雌だったね」
「また木に上りたいね」
「でも」
トシちゃんはうつむいた。
「そのうちママは元のとおりに戻してくれるって言ってるんだ」
ハナコの胸に熱いものがこみ上げてきて、トシちゃんの頬に軽くキスをする。トシちゃんはべろべろとハナコの顔をなめて、お返ししてくれる。普通は汚いと思うのだけど、どうしても思えなくて、嬉しくってハナコもトシちゃんの顔をべろでなめる
「ねえ、ずっと一緒にいれたらいいね」
「うん」
「このまま、ぼく、死んじゃってもいいや」
「イヤっ。イヤよ」
ふとハナコはトシちゃんとこのまま逃げてしまえばいいのではないかと思った。
「ねえ。逃げようよ」
「そうだ。それがいい。僕らは僕らで生きることができる」
ハナコはトシちゃんに服を着せて、庭に面した窓を開けた。「逃げよう」
トシちゃんは恐る恐ると窓に近づいた。
ハナコはトシちゃんを促す。
「いやぁぁ」
窓の所でトシちゃんはガラスにしがみついた。ハナコは驚いて、トシちゃんを介抱する。
「どうしたの?」
「こわいんだ。ママがいないと恐いんだ。お外に出られない」
ハナコは震えるトシちゃんを抱いて泣いた。トシちゃんの嗚咽が耳元でこだました。
「ごめんなさい」ハナコはようようそれだけの言葉を発することしかできなかった。
そんなことがあったのでハナコはもうトシちゃんをお外に出してあげることがかなわないと感じてしまった。トシちゃんのことを考えると悲しかった。トシちゃん。ハナコはじっといろんなことが自分の身体に覆い被さってくるのを悲しんだ。どうしようもない気持ちを悲しんだ。
ハナコは学校に行くのが無性に怖くなった。コイズミ先生が恐かった。
先生にばれちゃったら、どうされるか分からない。学校では、ハナコは俯いた子供で過ごすようになった。エミちゃんだけが「どうしたの? 何かあったの?」と心配してくれたけど、ハナコは首を横に振って答えるしかなかった。そして、学校が終わると急いでトシちゃんの家に行った。
家の中でいるかぎり、トシちゃんは安定していた。二人でいると、昔々の気分が蘇ってくるようで、トシちゃんはハナコが探し出した積み木を不器用に持って組み上げたり、二人で寝転がったりして遊んだ。本当にこのままずっとこの時間が続けばいいなあとハナコは思っていた。
でも、そんなことは長くは続かない。ある日、ハナコはうっかり寝過ごしてしまったのだった。玄関でトシちゃんを呼ぶ声が聞こえたかと思うと、慌てて身繕いしている間に、コイズミ先生の声が近くでして、トシちゃんの部屋のドアはいきなり開いたのだった。
ハナコの姿を見ると、コイズミ先生は目を丸くして怒った。
とても怒って、鬼のようにハナコを叩いた。トシちゃんは止めようとして泣き、ハナコは恐怖で泣いた。
「この雌犬。あんたは人の子を何だと思っているの。ハナコさん。あんたは、あんたは」
まだハナコを叩き足りないのか、ぶるぶると握り拳が震えていた。ハナコはもうおしまいだと思った。
コイズミ先生は続けてハナコを叩いた。散々叱られ、もう、二度とトシちゃんに会わないことを約束させられて、ハナコは首根っこを捕まれてひきずられた。
うちに連れられ、玄関先で驚くハナコのママに散々小言を言い、それからまた、ハナコはママに叱られた。ハナコはもうだめだと思った。このまま叱られ続けて自分は死んでしまうのだと悲しかった。
「もう、あんたはうちの子じゃありません」とママはハナコを玄関から外に放り出した。
ハナコは泣いて、ママ、もうしません。もうしません、と謝った。
何度謝ってもママは玄関を開けてくれなかったので、仕舞いにはハナコはしゃがんで隣の家から聞こえるトシちゃんを叱るコイズミ先生の怒声を聴きながら、涙が止まらなかった。
何時の間に眠ってしまったのだろうか。翌朝、目覚めてみるとハナコはベッドの上に寝ていて、ああ、あれは恐ろしい夢だったんだと思ったけど、それは本当で、朝食を食べている時に、パパが「転校しよう」と言った。
トシちゃんのママの家はこの町の立派な家で、もう、ここには居られないというのだ。
ハナコはまた泣いた。
泣くんじゃない。ちゃんとご飯食べなさいとママは無理矢理ハナコの口に卵焼きを放り込んだ。息ができなくなった。ハナコはパパとママは意地悪でそんなことを言っているのだ。嘘だと思っていたが、数日後からハナコの家に石が幾つも投げ込まれたりしはじめて、パパとママは狂ったようになって、ハナコは学校を替わった。
パパと一緒に小さなアパートに住み、やがてママがやってきた。新しい学校はもっと詰まらなかった。誰にも馴染めず塾にも入らされて、誰とも遊ぶことが出来なくなった。学校帰りにひとりでファーストフードのバーガーを食べていると、無性に悲しみがこみ上がってきて、どうしていいのか分からなかった。
ハナコは時々、塾を抜け出してトシちゃんに会いに行った。
もう裏庭の窓は開いていなかった。運良くトシちゃんがいると、ガラス越しに手を振りあって別れるだけだった。
ハナコはこうなってしまったコイズミ先生が恐かった。そして憎んでいた。恨んで、そして復讐をあれこれ考えながら眠りについた。先生に毒を盛ったら苦しんで死んでくれるかしら。大きな石を二階から落としたら死んでくれるかしら。先生の車のブレーキを壊したら事故になって死んでくれるかしら。そう夢想して冷たい夢に落ちて眠るのだった。
やっと眠れたと思うと、ハナコのパパはパパで、ハナコが寝ているベッドに潜り込んできた。「お前を愛しているんだよ」といい、ハナコに触れた。
「お前がそんないやらしい子だとは思わなかった」とも言った。
ハナコは怖かった。声がでない程怖かった。そのうちに、お前もチャームしてあげるね、といった。ハナコはパパの腕の中で泣いていた。大人達はみんな勝手だ。勝手だ、と思った。みんな死んでしまえと思った。
さて、それからハナコはどうしたでしょうか。
ハナコは自分の状況を変えたいのだ。そして大人達に復讐をしたいのだ。
選んだのは、月一に定期検診にトシちゃんを連れてコイズミ先生が出掛ける時に、電車のホームから突き落とすことだった。
こっそり背後から近付き、思いっきりぶつかると「ああ!」と叫んでコイズミ先生はホームの下に消えた。その直後電車が来た。
「やった!」とハナコは快哉を叫んだ瞬間に、あっけにとられたトシちゃんの表情が見えて、その後、それがハナコだったとトシちゃんが気がついた途端、トシちゃんの微笑みが残像を残して飛んで消えた。ママがもっていた鎖がトシちゃんを引きずってゆき、ホームとの間に小さな身体を飲み込んで消えた。その瞬間に真っ赤な血潮がハナコの全身に舞い降りてきた。
コイズミ先生のスカートから伸びるすらっとした足。あんな風に綺麗になりたいのだ。そしてトシちゃんに、と思うと、もう駄目だった。胸がはち切れそうになって、自分が分からなくなった。
ある日、ハナコは風邪をひいた。学校を休んで寝ていると、隣の家の窓が開く音が聞こえた。トシちゃんが居るのかも知れないと思い、起きあがって窓から覗くと、果たしてそれはトシちゃんだった。手のない腕でガラスを無理矢理開けたのだろう。トシちゃんは窓から顔をだして首を桟の上に置いてじっと外を眺めていた。
ハナコは久々にトシちゃんを見て嬉しくなった。でも、その淋しそうな表情からは、外に出たいのかなと思った。ハナコの中で外に出してあげたいと気持ちが変わるのに、そう時間はかからなかった。
窓から手を振ると、トシちゃんは酷く嬉しそうな顔をしてハナコを見た。
手のない腕を振り返した。
「外に出たいの?」
「うん。でも、出ちゃだめって、ママが言ったんだ」
ハナコは頭がだるいなあ、と感じながら、家をでて垣根をくぐる。
庭に面した大きなガラス窓をトシちゃんは背を伸ばして開けようとするが、手がないのでなかなか開けることができなかった。
裏庭に回って、この前の夜に開いていた窓が開いていたらなあと期待してると、やはり開いていた。どうやらコイズミ先生はこの窓の戸締まりを忘れるようだ。ハナコは嬉しかった。ハナコは忍び込んだ。帰りは玄関でいいやと思い、靴も忘れない。
「ハナちゃん」
部屋に滑り込むと、トシちゃんが駆け寄ってきた。ハナコは嬉しかった。が、トシちゃんはすっぱだかだった。びっくりして声をあげるとトシちゃんはソファーの影に隠れた。
「ごめんよ。ごめんよ。でもママが服、隠しちゃったんだ」
「大丈夫よ」と言いながら、トシちゃんの足の間に小さく見えるものから目が離せなかった。
ハナコはこんなに間近で男の子のおちんちんを見るのは初めてだったので、照れながら、でもトシちゃんのはこの前こっそり見てるのだし、好奇心は抑えられなかった。
「ううん。いいよ。そのままで」
「ごめん」といいつつトシちゃんはソファーの陰から出てきたのだが、やはり恥ずかしいようで、四這いになったまま、うつむいていた。
「久しぶりだね」
「うん」
「元気?」
「うん。でも、今日は風邪で休んでるの」
「大丈夫?」
「大丈夫よ」と言いながら、やっぱり頭痛がするのだった。ふと、トシちゃんの身体に幾つも傷や痣があるのに気がついた。
「それは?」と駆け寄ったハナコが聞くと、ママが、と答えた。
「僕はママを上手にしてあげれなくて、いい子じゃないから、ママが叱るんだ」
ハナコはその言葉を聞くと、どきりとした。トシちゃんを殴るコイズミ先生の姿が浮かんだ。トシちゃんが悪い訳じゃないのに、と思ったし、その言葉が示すことが、とてもイケナイコトを表わしているような気がしたのだ。トシちゃんがそのような生活をおくっているのかと思うと悲しくなった。
「ねえ、チャームされて、楽しい?」
「うん」そう小さな声で頷くトシちゃんの頭を、恐る恐るハナコは撫でた。
「うちもね、トシちゃんみたいになるかも。ママとパパが話し合ってる」
「じゃあ、また一緒に遊べるね」
ハナコはトシちゃんの笑顔を見ていると、本当に跳ね上がるかと思えるほど嬉しそうで、それでいて、チャーミングになったトシちゃんはどこか頼りなさそうな印象を受けた。以前、遊んでいた時のトシちゃんとは何かが違っていた。トシちゃんの身体に手を触れた。肌が冷たい、と思った。
居間のテレビがずっと喋ったままのおじさんの様子を映している。自宅学習児のための教育番組のようだ。なにやら難しそうな、ハナコには到底分からない奇妙な図を、指揮者のような棒で差し示していた。トシちゃんは毎日あんなので勉強してるんだ、とハナコが溜息を吐いたとき、トシちゃんは顔をあげた。
「うんち」
「え?」
トシちゃんは慌てて、部屋の奥からバスルームにある砂箱に身を隠した。ハナコは呆然と部屋の中を見た。以前、まだトシちゃんに手足があった頃、積み木や車のおもちゃがあった。でも今はもう、ない。ヘッドホン型の記憶インプット機器や、テレビ教科書がそのかわりに仕付けられていた。そして砂箱。トシちゃんの生活はもう以前とは随分変わってしまったのだ。たぶんそれらの調度は高価なものだろう。決してハナコの家では買えない機器も含まれているに違いなかった。
ハナコはそのときはじめて、なんか別世界だ、と思った。
バスルームから声が聞こえた。ハナコは心配しつつバスルームに駆け込む。
「うんちついちゃった。ママに叱られるんだ。どうしよう」
トシちゃんは今にも冷や汗をかかんとするように焦っていた。
ハナコは考えて、「じゃあ」バスルームを指さして、「あっち」と言った。タイルに座らせてシャワーをひねる。温かい湯気がふっと充満した。
トシちゃんの身体に湯を当てると、きゃっきゃとトシちゃんはくすぐったそうにして、身を捩らせた。
「お尻向けてよ」と苛立ってハナコがいうと、殊勝にトシちゃんはお尻を向けた。
シャワーをあてがうと、トシちゃんは気持ちよさそうな顔をした。うまく洗い流せただろうかと思っていると「ねえ。ママがしてくれるようにして」と、トシちゃんはハナコの側に起きあがって寄り添うように座った。なに? と思う瞬間、おちんちんが目に入って、それはさっきまでぷらぷら揺れていた小さなものとはちがって棒のようになっていた。ハナコは慌ててシャワーを落とした。パジャマにお湯がかかって身体があったかくなってくる。
「さわって」
「いやよ」
いいから、お願い。とトシちゃんは勧めたが、ハナコはそれは悪いことだと思った。ハナコは顔を逸らした。パジャマが身体にべっとりとまとわりついて、奇妙な感じがした。トシちゃんが迫ってくるので、慌てて逃げようとすると急に顔が近付いた。
「やめて」というのより早くトシちゃんはハナコの身体の上にのしかかってくる。
「ねえ。ハナちゃん。僕のこと嫌い?嫌い?」
トシちゃんはハナコの頬をぺろぺろと、まるで犬そのもののように嘗めた。突き出たそれをハナコのお腹に押しつけるようにした。
「ママはね、これをゆっくり手で触ってくれるんだ。とても気持ちよくて」
トシちゃんはハナコの濡れたパジャマの上から先の丸い腕でハナコの胸のあたりを撫で回しはじめた。
「いやっ!」
声をあげたがトシちゃんはもうトシちゃんではなかった。
「ねえ、お願い」
じっとトシちゃんはハナコの顔を見た。シャワーの湯気のせいか、トシちゃんの目は、じっとりと潤んでいるようだった。どことなく淋しそうで、悲しそうな表情だった。
ハナコは胸が締め付けられるような気がして、心臓がドキドキ鳴っているのが分かる気がした。もう一度トシちゃんは訊いた。
「僕のこと嫌い?」
「好きよ」
声が震えているのが自分でも分かった。
「じゃあ、好き好きして」
トシちゃんはハナコの唇に唇を寄せた。
ハナコは目を閉じた。そしてゆっくりと手を伸ばしてトシちゃんのそれに触れた。固い。男の子ってこんなになるんだ、と思って、薄目を開けてみると鼻息が荒いトシちゃんはうっとりとした表情になっていた。ハナコは先端の丸くなったトシちゃんの腕の先が下着の中に入ってくるのを阻止することができなかった。
「あはっ! ママとは違う!」
トシちゃんは嬉しそうにいって、ねえ、ママのようにしてあげる。ねえ。脱いで、と言った。
ハナコの熱は翌日も下がらなかった。当然である。だから、またトシちゃんの家に行った。頭ががんがんするのも気にならなかった。そして今度は時間をかけてゆっくりとお話をした。そして、話を聞けば聞くほどトシちゃんは可哀想だと思った。そして自分がイケナイことをしてしまっているのだと思うと悲しかったし、嬉しかった。ハナコはどうしてよいのか分からなかった。それでもトシちゃんとのひとときは、どきどきとして心地よいものだった。
「前ね、公園でカブトムシ捕ってくれたよね」
「うん。雌だったね」
「また木に上りたいね」
「でも」
トシちゃんはうつむいた。
「そのうちママは元のとおりに戻してくれるって言ってるんだ」
ハナコの胸に熱いものがこみ上げてきて、トシちゃんの頬に軽くキスをする。トシちゃんはべろべろとハナコの顔をなめて、お返ししてくれる。普通は汚いと思うのだけど、どうしても思えなくて、嬉しくってハナコもトシちゃんの顔をべろでなめる
「ねえ、ずっと一緒にいれたらいいね」
「うん」
「このまま、ぼく、死んじゃってもいいや」
「イヤっ。イヤよ」
ふとハナコはトシちゃんとこのまま逃げてしまえばいいのではないかと思った。
「ねえ。逃げようよ」
「そうだ。それがいい。僕らは僕らで生きることができる」
ハナコはトシちゃんに服を着せて、庭に面した窓を開けた。「逃げよう」
トシちゃんは恐る恐ると窓に近づいた。
ハナコはトシちゃんを促す。
「いやぁぁ」
窓の所でトシちゃんはガラスにしがみついた。ハナコは驚いて、トシちゃんを介抱する。
「どうしたの?」
「こわいんだ。ママがいないと恐いんだ。お外に出られない」
ハナコは震えるトシちゃんを抱いて泣いた。トシちゃんの嗚咽が耳元でこだました。
「ごめんなさい」ハナコはようようそれだけの言葉を発することしかできなかった。
そんなことがあったのでハナコはもうトシちゃんをお外に出してあげることがかなわないと感じてしまった。トシちゃんのことを考えると悲しかった。トシちゃん。ハナコはじっといろんなことが自分の身体に覆い被さってくるのを悲しんだ。どうしようもない気持ちを悲しんだ。
ハナコは学校に行くのが無性に怖くなった。コイズミ先生が恐かった。
先生にばれちゃったら、どうされるか分からない。学校では、ハナコは俯いた子供で過ごすようになった。エミちゃんだけが「どうしたの? 何かあったの?」と心配してくれたけど、ハナコは首を横に振って答えるしかなかった。そして、学校が終わると急いでトシちゃんの家に行った。
家の中でいるかぎり、トシちゃんは安定していた。二人でいると、昔々の気分が蘇ってくるようで、トシちゃんはハナコが探し出した積み木を不器用に持って組み上げたり、二人で寝転がったりして遊んだ。本当にこのままずっとこの時間が続けばいいなあとハナコは思っていた。
でも、そんなことは長くは続かない。ある日、ハナコはうっかり寝過ごしてしまったのだった。玄関でトシちゃんを呼ぶ声が聞こえたかと思うと、慌てて身繕いしている間に、コイズミ先生の声が近くでして、トシちゃんの部屋のドアはいきなり開いたのだった。
ハナコの姿を見ると、コイズミ先生は目を丸くして怒った。
とても怒って、鬼のようにハナコを叩いた。トシちゃんは止めようとして泣き、ハナコは恐怖で泣いた。
「この雌犬。あんたは人の子を何だと思っているの。ハナコさん。あんたは、あんたは」
まだハナコを叩き足りないのか、ぶるぶると握り拳が震えていた。ハナコはもうおしまいだと思った。
コイズミ先生は続けてハナコを叩いた。散々叱られ、もう、二度とトシちゃんに会わないことを約束させられて、ハナコは首根っこを捕まれてひきずられた。
うちに連れられ、玄関先で驚くハナコのママに散々小言を言い、それからまた、ハナコはママに叱られた。ハナコはもうだめだと思った。このまま叱られ続けて自分は死んでしまうのだと悲しかった。
「もう、あんたはうちの子じゃありません」とママはハナコを玄関から外に放り出した。
ハナコは泣いて、ママ、もうしません。もうしません、と謝った。
何度謝ってもママは玄関を開けてくれなかったので、仕舞いにはハナコはしゃがんで隣の家から聞こえるトシちゃんを叱るコイズミ先生の怒声を聴きながら、涙が止まらなかった。
何時の間に眠ってしまったのだろうか。翌朝、目覚めてみるとハナコはベッドの上に寝ていて、ああ、あれは恐ろしい夢だったんだと思ったけど、それは本当で、朝食を食べている時に、パパが「転校しよう」と言った。
トシちゃんのママの家はこの町の立派な家で、もう、ここには居られないというのだ。
ハナコはまた泣いた。
泣くんじゃない。ちゃんとご飯食べなさいとママは無理矢理ハナコの口に卵焼きを放り込んだ。息ができなくなった。ハナコはパパとママは意地悪でそんなことを言っているのだ。嘘だと思っていたが、数日後からハナコの家に石が幾つも投げ込まれたりしはじめて、パパとママは狂ったようになって、ハナコは学校を替わった。
パパと一緒に小さなアパートに住み、やがてママがやってきた。新しい学校はもっと詰まらなかった。誰にも馴染めず塾にも入らされて、誰とも遊ぶことが出来なくなった。学校帰りにひとりでファーストフードのバーガーを食べていると、無性に悲しみがこみ上がってきて、どうしていいのか分からなかった。
ハナコは時々、塾を抜け出してトシちゃんに会いに行った。
もう裏庭の窓は開いていなかった。運良くトシちゃんがいると、ガラス越しに手を振りあって別れるだけだった。
ハナコはこうなってしまったコイズミ先生が恐かった。そして憎んでいた。恨んで、そして復讐をあれこれ考えながら眠りについた。先生に毒を盛ったら苦しんで死んでくれるかしら。大きな石を二階から落としたら死んでくれるかしら。先生の車のブレーキを壊したら事故になって死んでくれるかしら。そう夢想して冷たい夢に落ちて眠るのだった。
やっと眠れたと思うと、ハナコのパパはパパで、ハナコが寝ているベッドに潜り込んできた。「お前を愛しているんだよ」といい、ハナコに触れた。
「お前がそんないやらしい子だとは思わなかった」とも言った。
ハナコは怖かった。声がでない程怖かった。そのうちに、お前もチャームしてあげるね、といった。ハナコはパパの腕の中で泣いていた。大人達はみんな勝手だ。勝手だ、と思った。みんな死んでしまえと思った。
さて、それからハナコはどうしたでしょうか。
ハナコは自分の状況を変えたいのだ。そして大人達に復讐をしたいのだ。
選んだのは、月一に定期検診にトシちゃんを連れてコイズミ先生が出掛ける時に、電車のホームから突き落とすことだった。
こっそり背後から近付き、思いっきりぶつかると「ああ!」と叫んでコイズミ先生はホームの下に消えた。その直後電車が来た。
「やった!」とハナコは快哉を叫んだ瞬間に、あっけにとられたトシちゃんの表情が見えて、その後、それがハナコだったとトシちゃんが気がついた途端、トシちゃんの微笑みが残像を残して飛んで消えた。ママがもっていた鎖がトシちゃんを引きずってゆき、ホームとの間に小さな身体を飲み込んで消えた。その瞬間に真っ赤な血潮がハナコの全身に舞い降りてきた。
了
| Back | # / # | Next |