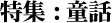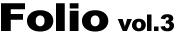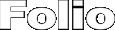それほどまでに栄誉は、賞賛は心に甘い。
自殺未遂を繰り返し、周囲の注目を集めようと必死になっていたかぐや姫を嗤う資格など私にはない。私は今も心のどこかで、再び自分に脚光が当たるのではないかと期待しているのだから。
有り得ないことと知りつつも、しかし毎日欠かさず太刀の手入れをしている私。仮にそんな機会が訪れたとしても、もはや今の私では存分な働きなどできるはずがないと解っていながら、それでも私は桃太郎であり続けようとしている。そしてもう私は桃太郎たりえない、それどころか社会に何ら寄与するところのない寄生虫なのだと自覚するたびに余生の長さを噛みしめる。
そんなとき氷の刃は強い魔力を帯びる。首筋にそっと触れたそれは脳髄を痺れさせ、私をしつこく誘惑する。
しかしいつもそこまでだ。見る影もなく落ちぶれた桃太郎が絶望のあまり自殺したなどとはいい物笑いだ、そう思うと手が止まる。そして長い夕刻をうなだれて過ごし、近頃とみに冷たさを増してきた万年床に潜り込む。
睡魔が私を捕らえるまでの間、脳裏をよぎるのは惨めな現在や不吉な未来。それを振り払うようにして二十年前のことを想起する。あの日、思いのままに暴力を行使する快感に私は酔いしれた。殺人、放火、傷害、略奪、思いつく限りの暴虐をふるったものだ。やっていないことといえば強姦くらいのものだろう。当時の私はいかにも童貞らしい傲慢さゆえに――すね毛を生やしたごつい女など私の相手には相応しくないと感じたのだ――女を辱めることに二の足を踏んだのである。
あの日、私がおこなったことはまぎれもない蛮行である。幸いにして鬼退治という大義名分があったから良いものの、行為そのものを見れば残虐非道の誹りを免れないものに違いない。だからいつの日か鬼ヶ島の生き残りが復讐にくるのではないかと、かつては内心で怯えていた。
だが今は違う。もしそうなったなら私は喜んで彼らの手にかかるだろう。刃で勝ち取った栄光は刃で奪われるのが相応しいからだ。
金棒で総身の骨を打ち砕かれ、四肢を引き裂かれる自分の姿を思い描いているときだけは、四六時中私を悩ます自己嫌悪から解放される。うっとりと自分の死に様を夢想する私。ありとあらゆる手法を検討し、想像できる限り最も残酷かつ屈辱的な最期が望ましい。末路が凄惨であればあるほど英雄の死は美しく彩られ、悲劇からやがて神話へと近付いていく。
つまり、どうしようもなく、私は桃太郎なのだ。桃太郎であり、桃太郎であらんと欲し、しかし桃太郎たりえない桃太郎なのだ。
毎日がうつらうつらと過ぎていく。何の張り合いもない、ひどく空疎な日々が続いていく。私の心に波立つ感情は自己嫌悪であったり焦燥感であったりで、およそ心地良いものなどひとつとしてない。だからだろうか、近頃の私はよく眠る。眠ることで更に現実逃避をしているのだろう。
日常とは対照的に、私の夢は大抵の場合、ひどく鮮やかで劇的だ。だがときおり、やけに素朴で現実的な夢を見ることもある。ついこの間見た夢もそんな感じだった。亡き養父母が私に遺してくれたこの家に、まるで畳の埃を拾っているかのように腰の曲がった老人が住んでいる。普段は独りで暮らしているのだが、盆や正月になると息子夫婦が孫を伴って帰省するのだ。私はそのありふれた、しかし幸福な光景を傍目で見ていてふと気付く。この老人こそが私自身なのだと。そして目が覚めたあと私は考えた。これが私の願いなのだろうか、と。
正直なところ、そんな退屈な幸せを欲しいとは思わない。今よりましというだけで、夢に見るほどのものではないと思う。ならばなぜこんな夢を見たのだろうかと、垢じみた寝床の中で煩悶しているうちに思い浮かんだ疑念は私の肝を冷やすに充分だった。
――あの夢は選択しなかったもうひとつの未来、実現しなかったもうひとつの現実なのではないだろうか?
鬼を退治するという英雄的人生が待っていると知らなければ、私は夢の中の老人のように人生に満足していただろう。だがひとたびスポットライトを浴びた今では、そんな幸せを一顧だにせず、英雄の末路を飾ることにのみ腐心しているのである。
幸せとはあくまでも主観的なものだ。本人が幸せと思えばそれはまぎれもなく幸福なのであり、いかに恵まれた境遇にいようとも本人が不幸を感じていたならば、それは間違いなく不幸なのだ。そもそも本当に幸せな人間ならば、自分が幸せかどうかなどということすら考えもしないだろう。
その日私は初めて、鬼退治に出掛けたことを悔やんだ。普通の人生が羨ましいのではない。三十数年前、桃太郎と名付けられた嬰児がその後妄執に囚われ、幸せのかたちを見失ってしまったことが気の毒でならないのだ。あの日、洗濯をしていた老婆に拾われた小さな生命が、その掌から幸せを取り落としてしまったことを思うと哀れでならないのだ。
幸せな一生とは何だろうか、そのことを考えるたびに今は亡き三年寝太郎のことを思い出す。彼の死因は不用意に寝入った末の餓死だった。何と惨めで滑稽な幕引きだろうか。彼の最期に向けられた世間の反応は失笑と嘲弄に満ちたものばかりで、彼の死を悼む者はほとんどいなかった。
だがそんな彼が無性に羨ましい。飢え死にするまで眠り呆けるとは、いかにも三年寝太郎に似つかわしい最期だからだ。今の私の幸福観によれば、物語の主人公としてその生をまっとうした彼は、間違いなく幸せ者だと思うのだ。
めでたしめでたし――。
だが容赦なく人生は続く。
了
| Back | 2 / 2 |