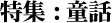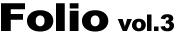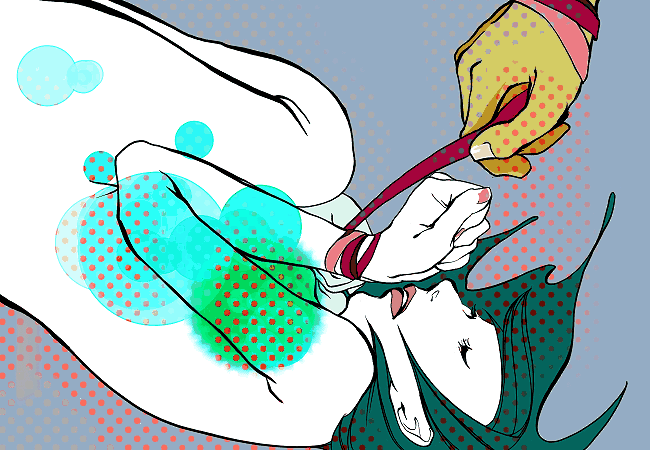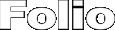彼はじっと手首を見ていた。もはや見慣れてしまった、あの忌まわしき傷跡の気配など微塵もないまっさらで綺麗な自分の手首。蛍光灯を反射して白くきらめくナイフをそこに押し当てようとしていた。初めてだったけれど失敗するはずはなかった。あんなにも多くの傷を見てきたのだ。いま彼が人生から学び取ったと言えることといえば、確実に自分自身に致命傷を与える方法、ただそれだけであった。風呂にたまったぬるま湯に手首をつけた。もう一度、呪われた自分にとどめをさすべく磨き上げられた冷たい刃物を見た。そんなに嫌いではない自分の顔が、ゆがんで映った。
* * *
「村上春樹の『ノルウェイの森』は、結局のところおとぎ話でしかないじゃないかって高校の初めに読んだときには思ったんだ。つまり、精神を病んだ女の子を救おうとして全く救えなかった特に取柄もない男が、都合よく現れた可愛らしい女の子によって救われるなんて、現実世界はそんな甘いわけがないってさ」
彼はそう言ってからしばし黙った。けれども、次に彼が何を言いたいのか僕には分かりすぎるほどよくわかった。そしてやはり彼は、僕の予想通りの言葉を続けた。
「でも実際生きてみたら現実世界は案外そんなものだということが分かった。俺が誰か女の子を傷つけてしまって終いには手に負えなくなって縁を切る、そうするとまた違う女の子が現れて俺のことを好きだといってくれる、そして俺も好きになる、でもまた傷つけてしまって別れて、しばらく経つとまた違う女の子が―ってね。そしていまでは思うんだ、ワタナベくんもこういう世界を生きていたんだ、って。つまり最終的に救われたみたいに読めないこともないけれどワタナベくんはまた同じことを繰り返して生きていくんだろうし、そう考えれば俺とやっていることはなんら大差ないことになるものな」
「じゃあ君はおとぎ話のなかに生きているのかい?」
僕はこんなことを聞いてみたけれど、もちろん、彼がそれを否定することも分かっていた。彼は小さく首を振った。
「いやそうじゃない、『ノルウェイの森』も僕の人生もおとぎ話なんかじゃない。そんな架空の話とは対極にある、極めてリアルでライブな物語だよ―言うなれば、童話なんだ。童話とおとぎ話の違いというのはつまり、現実の最も暗い側面を正確にえぐっているか否かだと思う。そういう意味ではおとぎ話なんてどこにも存在しないんだけどね。この世界において何かを語ろうとすれば、必ず逆説的にでも最も暗い部分に触れざるを得なくなるんだから」
彼は間違っている、と僕は思ったけれど僕は何も言わなかった。これ以上彼を追い詰めても何にもならないからだ。けれどもやはり彼は間違っている。ノルウェイの森は、やはりただのおとぎ話なのだ。彼の人生だって、彼が把握している部分においてはおとぎ話に過ぎなかった。そして少し先の話になるけれど、彼はそのことを知らないままに死んでいった。大抵の人間にとって、おとぎ話こそが最もリアルでライブな物語なのだ。僕らはおとぎ話を信じずには生きていかれないし、そのおかげで深い深い森へと迷い込む。自分の来た道に目印をつけておいたとしても、北極星を頼りに地図を描いたとしても、僕らはそこから出ることなどできない。なぜならおとぎ話を信じている限り僕らは歪んだ世界しか見ることができないからだ。まやかしの森―たとえばノルウェイの森―しか歩くことができないからだ。ではおとぎ話を捨て去った時、つまり彼が言うところの童話を理解することができた時、僕らはどこかに辿り着くことができるのだろうか。それがこれから僕がする話のテーマであり、そしてこの物語こそが、子供たちに―とは言ってもいままさに大人になろうとしている子供たちのために―語り継がれるべき童話である。彼らには、真実を知る権利があるのだ。知る必要があるのだ。それがどんなに暗闇に満ち、血で汚されたものであったとしても。虚飾に彩られた世界を生きているうちは、それは本当の生と呼ぶことはできないのだから。
そろそろ抽象論はやめにしよう。とにかく僕らは、ノルウェイの森よりももっとずっと深い森の中を生きているのだ。
1
彼が家に帰ると真っ赤に染まった湯船に女が裸で倒れこんでいた。それはもう彼が呼びなれた名前を持ったわがままだけれども可愛い女の子としてではなく、ただの女と表現するのが妥当だった。手首を切った彼の恋人は、これで四人目だった。これまでと違うのは、彼女が裸であったということと、本当に死んでしまったということだった。
彼は不思議なほど落ち着いていた。白い壁に飛び散った一滴一滴の血が、恐ろしいくらいにくっきりと見えた。彼は恋人が死んでいるかどうかを確認しようともしなかった。ただじっと風呂の入り口に立って、透き通るような白い肌を魅入られるように見つめていた。陽子が死んでいることなんて、帰る前から分かっていたのだ。少なくとも、いまの時点で彼にはそう思えた。彼女が死んでいるのはひどく当たり前のことなのだ、と。でも彼はそこから一歩も動くことが出来なかった。女から一秒たりとも目を離すこともできず、近づくこともできず、離れることもできず、無表情に立ちすくんでいた。彼が見ているのはもはや陽子の肌ではなかった。その奥にある何かだった。その奥にある何かが、彼女を揺さぶり死に追いやったのだ。彼はその奥にある何かのことをよく知っていた。もう幾度となく彼はそれを目にしてきた。初めは偶然だと思った。けれど偶然ではなかった。間違いなく彼自身が、その奥にある何かを女の子の中に生じさせてきたのだった。
彼が恋人を愛していなかったわけはもちろんない。手首に傷跡を残したまま、彼を捨てたあるいは彼に捨てられた他の三人の恋人と同じように、彼は彼女を心から愛していた。
2
彼だって、高校生時代までには血が流れるような恋愛をしたことはなかった。ちょっとしたことで喧嘩して別れてしまったり、お互い忙しくなって自然消滅してしまったりとそんなありきたりな終わり方だった。血が流れずして恋愛が終わらなくなってしまったのは大学に入ってからだ。(もっとも、僕は大学で彼に出会ったのでそういう彼しか見たことがない。)彼は大学生になってからより切実に他者を求めるようになった、と言った。たとえば将来への不安、社会との相対性の中でゆらいでいく自分の像、そういうマイナスの感情を癒してくれる誰かを求めていたのだ。慣れない都会での一人暮らしが孤独感を増幅させたのだと思う、彼はそうも言った。「他者」というのは多くの場合特定の異性であり、彼の場合も例に漏れず女の子にその役割を求めるようになり、やがて大学に入って最初の恋人を作った。
最初はうまくいっているように思えた。恋人と一緒にいると心が安らいだし、自分を愛してくれる存在がいるというだけで孤独感は随分とましなものになった。どんなことでも話すことができたし、恋人はそれを受け止めてくれた。しかしそんな幸福は半年も続かなかった。恋人がリストカットを始めたのだ。そうした傾向がある女の子では全くなかったし、二人の間には何の問題もなかったのに突然そんなことになって彼は途方にくれた。彼女を救いたいと欲したけれども、一体どうすれば彼女を救えるのかなど彼にはさっぱり分からなかった。
恋人は「あなたのせいじゃないのよ」と言った。それはそうだろう、と彼は思った。彼は彼なりに彼女を真面目に精一杯愛していたし、できるだけ支えてきたつもりだったのだ。しかし、もちろん自分のせいでないというだけでは不十分だった。彼が恋人の彼氏であるからには、彼女のそうした状況を救ってあげるべきだったし、また救うことができるはずだった。しかし彼が救おうとしてあがけばあがくほどに恋人は手首を切り、そして次第に彼から遠ざかっていった。最後の電話で恋人はこう言った。
「あなたのせいじゃないの、ただ疲れちゃったの。だからごめんね。あなたにはきっともっといい女の子がいると思う」
そして唐突に電話は切れた。彼はすぐにかけ返したけれどつながらなかった。送ったメールもあて先不明で返って来た。彼は生まれて初めて、声を上げて泣いた。二日後に僕がたくさんのカップ麺を買い込んで彼の家へ行くまで、何も食べず、眠りもせず、ただじっと床に座っていた。
| 1 / 2 | Next |