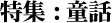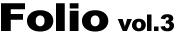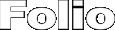王は象徴王だった。象徴の王は制度の王であった。権力の王であり、国家の王でもあるが、実行力より存在の王であった。王はその生まれを不満に思っていた。「わからない」と王城の奥の部屋で呟く。
「隣国の王は指ひとつで大勢の人々を動かし、テレビで見るとあんな風に綺麗なマスゲームを指揮してる。彼は本当の王だ。だがわたしは一体なんなのだ」
王は象徴の王であるからして、王室行事は全て大臣達の円卓で決められた通りにしかすることは出来ない。いや、こう言ってもいいだろう。大臣達が決めた通りに、王は働いているのだ。無償で。王の父の時代からの慣習で、誰もが忘れているが、王は王という制度に仕えているという、非常にやっかいな立場だったりするのだ。
もちろん王城は王のものだが、人々は王のことなどただ、車の中から手を振っているおじさんとしか見ていない。王はそのことを考えるだけで腸が煮えくり返るほどに苛立つのだった。隣国の王にしても大臣達にしてもハーレムでうはうはしてるのに、なぜわたしは王であるということだけで、全ての行為を監視され、うやうやしく「お床入り」とか書いた紙をドアに張られたりしなければならない? わたしは王なのだ、と。
毎度毎度の王室行事の際、カメラマンは王を取り囲んで訊く。
「御子さまはまだですか」。
知ったこっちゃねーよ、と王は思う。后はアナル派なのだ。
全国植毛祭とやらに出掛けて行き、王様お手植えの毛髪だとやんややんやと感謝される。ある男などは「もう決して私は髪を洗うことは出来ないでしょう」と感激のあまりに宣言してしまった。毎年毎年決まったように西川口のご静養所に行かねばならないし、時々外国にも飛ばされる。
まったく嫌になるよ、と王は思う。
テレビで散々隣国の様子が写っていた。
なにやらピカドンやらタコポンやらのミサイルを開発して、我が国に飛ばそうと計画しているようだといって、マスコミが騒いでいる。おまけに、人々を拉致監禁改造食品加工輸出してうちのカレーの肉は一〇〇パーセント人肉です。ご安心ください、ということをしてるというらしい。もう明日には開戦かどうかというほどに盛り上がっていて、おもしろおかしく隣国の様子を報道している。やれやれ、と王は頭を抱えた。
あんな一糸乱れぬマスゲームを見れば、どれだけこの国が遅れてしまったのか、堕落してしまったのかが悲しくなったのだった。
彼我の差、というのは、王が実質上の王であるのか否かということに問題を発していた。
わたしもちゃんとした王になりたいと、象徴の王は考えた。
それにしても隣国についてのマスコミの情報は全くのでたらめだった。
昨夜もこんな風に電話をよこしてくるほど、隣国の王は舎弟だと思えるほどに仲がよかった。
「よう。アニキ。そっちはどうだい? 俺の作ったモスラ映画見てくれたかい? おっかしぃーだろ」
王は苛立ちながら返事をする。
「おまえ、なんだ? あの美女軍団っていうのは。いつの間にあんなハーレム作ったんだよ」
隣国の王ははははと「ばれちまったか」と笑う。
「テレビ見て見ろよ。ずっとお前のことやってるぞ」
「俺っち、かっこよく映ってるか?」
「ああ」
王はすぐにじくじくとした思いを抑えられなくなった。やがて適当に相槌をうつようになる。
「お前もつくってみろよ」
「はあ? こっちは法治国家だぞ」
「おれんちも一応法治国家だぜ?」
「建国の王の息子と、何千年もだらだら続いていた王とは立場が違うよ」
王は溜息を吐いた。
「そんなことあるか」隣国の王は声を大きくした。
「千年が百年だって関係ねーよ。やりたいかどうかだろ?」
そうかなあ、と返事をするが、それでいて隣国の王がうらやましくて溜まらなかった。ヤツのように押しが強いわけではないし、どっちかといえば研究者タイプのひょろちい男だと自分を王は卑下するのが常だった。
「まったく、うじうじしてんじゃねーよ。人生なんてやったもん勝ちじゃん」
と隣国の王は励ましだか嘲笑だか分からぬ物言いで、一方的に「じゃーね、うちの弟今度遊びに行くからよろしくね」と電話を切る。そして王は煩悶するのだ。
さて、これはフィクションである上に童話であるから、教訓が含まれている。
「人生はやったもんがち」これが一つめの教訓。
二つ目は「実現したければ明確な目標を持て」そして「成功のためには小さなことでも手間をかけよ」ということだ。
王はしばし煩悶し、一月が経ち、二月が経った頃、ようやく重たい腰を上げた。
計画を話し、「それは、ちょっと」と渋る側近に「いちばんの上玉を譲るから」といい、それでも渋っているので「幼女も連れてくるから」と説得し、これが第一の協力者となった。
彼に黒塗りの車でお堀端をぷらぷら歩いている女子高生を買って王城に連れて帰ったきてもらう。
「え〜。おじさん、五万円、先に頂戴」
王は女子高生に金と薬を与えた。
なははははうきゃうきゃ。
しばらくすると女子高生は奇妙な笑い声をあげて、踊りだした。どうやら薬が効きすぎたせいだろう。こんどからはちゃんした薬を打つべしと側近を叱り、けたけた笑う女子高生を縄でしばったまま抱く。しばらくしても女子高生はそのままおかしい様子で、やがて、口から涎をだらだら垂らして妄想が始まり、そのまま狂ってしまっていたので、王城の一室に閉じこめた。
今度はテレクラで主婦を呼びだしたけど、また同じような事態に陥ってしまった。
三度目も同様な結果になり、どうやら隣国から輸入した薬は、質が悪いと判断して、今度は米より麦を喰ってるのに米の国の酋長に話を通して薬を譲って貰った。
ヤツからも電話があった。
「君も気をつけた方がいい。うちの前の酋長は薬と女の問題で首を切られた」
英語だったので、よくわからなかった。まあいい。と王は思ったが、今度は身近なところで問題になった。十五人目を過ぎた頃だろうか、一番大臣が飛んできた。
「王よ。やめた方がいい。外聞が悪い。こっそりやるのはよくない。ばれた時のことが心配だ」というので「今なら拉致監禁は隣国のせいにできる」と答え、それでも「外国の薬というのはよくない。これ、使いなさい」と言語失調のようにたどたどしい言葉で渡すのは、秋原葉町製のスタンガンで、女は男にしびれたいと思っているのだ、という説明だった。
なるほどと納得し、更に数人びりびりさせて王城に連れ込んだ。
威力はさすが世界一の電気機器大国製だ。王の国の誇りが結集した技術だった。
やがて一番大臣は「わたしも加えてくれ」といい、「わたしは母のような女がいい」といったはいいが、九十のババアとは驚いた。その上、勢いあまってしびれさせ過ぎて殺してしまうのだから面倒だ。一番大臣はこまったなあとライオンのようにぼさぼさした頭を抱えるので、王城の周りの掘に重石をつけて沈ませた。彼は第二の協力者となった。
三人目は法務大臣だった。
どこから話を聞いたのか、一番大臣が呼び込んだのか。
「そんな行き当たりばったりでは駄目です」と、計画書を提出した。王はそれを見て、さすが法務大臣だと思った。
「計画は具体的に」
1 王室典範の改正
2 王政復興運動と軍備拡大
3 国家を権力者のためにするための条項(計三〇条)
4 教育基本法の改正
5 後宮建造
と延々と続く報告書には、王が神になるまでの道筋が描かれていた。
まずは国民を国家に従わせることから始めなければならない。王はだんだん話しが大きくなった、と思ったが「後宮」という響きはこたえられない魅力を持っているのは否めなかった。三人は内密に協力する証として桃園で血判状を提出し、王が喜ぶと彼らは「全ては王のために!」と万歳三唱したのだった。
象徴の王を象徴の王として残し、王という存在をポップでキッチュのものであるとする「キッチュ思想」これこそが、新しい王のあり方ではないかというのが報告書に書かれていて、BGMはロリロリロリポップであって、王の御姿を華麗に装飾したポスターが作られた。これはかつてない実験だと彼らは考えた。資本主義の蔓延した現代世界でもっとも神の力を体現しているのは、力ではない。ポップの神である。ポップにまみれた情報の中で、徐々に我々の王の象徴のレベルをあげて行くのだ。
そして彼らは、昼夜の励みの合間に、それを実行した。
もう国会などそっちのけで、適当に終わらしたいのが人の常。
頭の中は、妄想と欲望が渦巻き、それを実現する手段が目の前にぶら下がっている馬だ。心は駆けめぐるものだ。
第一大臣は「えー、我が国の高齢者の問題は、あの梅干しみたいに美しい乳が減りつつある」と国会でうっかりと喋ってしまいそうになり、法務大臣は「我が国の法律は勃起に非常に不平等だ」と思わず言いそうになる。
側近一号は宮中晩餐会の祝辞に、間違って奴隷契約書を渡してしまって、あたふたとした王に叱られたりする。王は王で黒塗りのお手振りベンツを改造して中に簡易ベッドを持ち込もうとして、車検場で露見しそうになる。
ただ、国家のトップなので、口封じは簡単。力か金か女(男)で話はつく。だからことは隠密裏に運ぶのだ。それに、なにはともあれ、元首のババ専が発覚すれば国家の威信は失墜するので、事情を知る者は口を閉ざした。国家反逆の刑には服したくないのは心情。長いものに巻かれることは日本人の信条。
木を隠すには森の中。エロ本隠すにゃベッドの下なのだ。
街角にはキッチュでポップな王の御真影が所狭しと飾られ、逆にマスコミの現場には決してでることはなくなった。要は街行く女子高生に表向きだろうが何だろうが「王様ってミステリアスでかっこいい」と思わせればいいのだ。
民は虐げるほど、忠誠を誓う。
古今東西、民衆の支配にはこれ以上の特効薬はなく、また、他に手はない。
飴と鞭。安穏的な方策で国民の意識改革を行ない、一方で権力は権力の集中する所を構築してゆく。例えば密かに王城に地下宮を作ることだって民衆に対する誇示の現われなのだ。
民衆に知れたところでそれは王の力の象徴なのだから。
だが、先手を打つことを忘れない。フェミニズム団体がうるさくなると後々面倒なので、成人式の時に、国民全てに男女にラテックス製のオメコとバイブレーターを記念品として配る。それでもややこしくなった時のために、順次、男娼制度を用意し、男女平等という建前を維持するようにする。公平な社会という建前のもと、税率をあげ、後宮の建設に着手する。
利権のシステムというのは利権に絡めば誰もが利益を享受することができるという幻想を配置するシステムであり、そのシステムを外れると一気に利益を失うという幻想も暗示させる。それは既存のシステムを補完するように、または成長させたものであるべきで、案外、この既存のシステムの拡大解釈には国民は無反応だ。
反論するものは、軍備を拡大させた警察権力などに任せればいい。国家反逆の刑に処する、という印籠が通用する世界は、元首や王にとっては、いや、利権に関わる全ての者にとって安全な世界なのだ。
あからさまであるほど国内の民衆にとって政策は見えにくいものだ。
王は徐々に布陣を敷いた。
一旦やり始めるとやるべきことが次々と見えてきた。様々なことが象徴王の脳裏に浮かび上がり、そしてそれについて考えを巡らせる。これまで、まったく他人事として見ていた政治というものが急に親しいものになり、それはとても心躍るものだった。
女女美女美女。それこそが我が道なのだ、と王は充実感と共に思う。
国民の教育は数年であっという間に完了する。ブームと国家的な意義という建前の前には誰も彼も弱いものだ。
美女コンテストがあちこちで行なわれる。
美女は三日で飽きるから、醜女コンテストも同時に行なわれる。たまには奇妙な者ともというので、奇人変人コンテスト(女だけ)も行なわれる。
もちろん、国民が不満を持ってはイケナイ。美男子コンテストをマッチョ軍人のために行なう。そうこうしている間に、徐々に後宮は繁栄してきた。王はうはうはである。
国家的ルネサンス運動として、夜這いや吉原も復活し、どうせもともとフリーセックスの国なのだから、一夫一妻制も廃止する。「人道的ではない」という国連諸国に、性の自由化のどこが人道的でないと言えるのかと突っかかり、もちろん、それは承認される。当たり前だ。手抜かりはない。
そのうち後宮は放っておいても人数が揃ってきた。たとえば、それぞれの県から一人ずつ集めればよい。一年の神の巫女として召し抱え、気に入った娘だけ残して、あとは放逐する。巫女はそれぞれの県に戻って、それぞれのミニ王宮を作り、そこから新しい娘が上納される。
レズビアンに励む二人の巫女の背後から順に犯すのは何とも言い難いではないか。
王はようやく望みが叶ってきたのだと、長い年月を無駄にしてきたのだと後悔し、もっと早くやればよかったと側近に漏らす。
側近は涎を垂らしながら幼女に嘗めさせながら頷くのだった。
隣国の王からしばらく振りに電話が入った。
「アニキ。最近、がんばってるじゃん。俺の国を見習って王の力を取り戻してるって訳かい?」と誉めた。
いや、そもそも君の国の国家論は私の国の国家論を大仰にまねただけだということではないかと、文句も言いたくなったが、そこはぐっと我慢。象徴王はかなり自信を持っていた。
「私は父とは違う新しい国家を作るのだ。私は人の子であると共に神の子なのだから」
隣国の王は大袈裟に笑った。
「なはは、神の子だって? なはなははは」
象徴王はむっとした。
「聖なるものは性なるものだ!」
隣国の王は「俺の国ではずっとそうだった。人民の一挙手一投足は俺のものだ。わが人民を見て見ろ。俺の人民は俺に抱かれたくて、オメコ水たらたら流してるぞ」
象徴王は、彼の人民が欲しくなった。
「お前の人民をくれ」
電話の向こうで笑い声がした。
象徴王は腹を立てた。
テーブルに用意したボタンを押した。すると国家にある全てのテレビから、隣国からミサイルが発射されたという警報が鳴った。それと共に、国民総動員法で集めた軍隊が一斉に隣国に向かってミサイルを発射した。
雌雄は一瞬で決まる。先手必勝。これこそが戦略の第一歩だ。
隣国の王は電話の中で慌てていた。「なんだ? なんだ?」と戸惑ったまま、ぷつりと電話は切れる。象徴王は微笑む。ドコモの携帯を持ったままほくそ笑む。この瞬間の映像をビデオに撮らしたらいいコマーシャルになるはずなのに、と思う。そして、美女軍団に命令してテレビを持ってこさせる。美しいプロポーションの胸と腰がタプタプと揺れて、テレビの冷たそうな画面に当たるのを眺める。うひうひ。
象徴王は開戦の映像を見て、成果が上がる様子を嬉しく思う。
ヤツは死んだ。ヤツは死んだ。
これで、象徴たる王、神の子としての王は私だけになったのだ、とワカメ酒で喝采を祝う。そしてこう思うのだ。ああ、なんたる美酒だ、と。
こうして象徴王は隣国の土地と人民を手に入れた。
彼らは半ば教育されていて、王は神である、というのがデフォルトだったので、非常に都合が良かった。象徴王は、象徴の王である上に、こうして神となった。精一杯努力をして、気が付いた時には立派な後宮に美女を侍らすことができる地点まで辿り着いたのだった。
さてさて。
この話の教訓は、「駄目なヤツでもしっかりやれば望みのものが手に入る」ということである。欲望は人生の繁栄の象徴なのだ。「自信をもってやればなんでも叶うのだ」