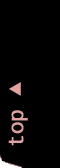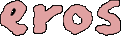性的聴覚過敏症
端辺 圭
彼女が両手に抱えた花瓶を落とす瞬間だけが脳裏に焼きついている。それは数秒の間、空中に静止しているように思えた。硝子の砕け散る音、テーブルと床面に水が叩きつけられる音など全く聞こえなかった。僕の視覚世界が再び再生を始めたのは、テーブルに残った花瓶の残骸から水が滴り始めた瞬間、そのピタピタという雫の音を耳にした時からだ。何故手を滑らせてしまったか、彼女自身にも解らないとのことだった。僕の脛から流れ落ちる大量の血に我を取り戻すまでの間、意識が軽く飛んでいたのだという。
僕は彼女の匂いの染み付く寝具に横たわってベッドエンドに足を乗せ、患部を心臓よりも高い位置に置いて必要以上の出血を防いでいる。止血に使われたのは生理用ナプキンで、僕は介護人の立てるガサガサという開封音の合間、微量の唾液が混じる彼女の息遣いを聞いていた。花瓶に落ち着く筈の花束は静かな午後のテーブルに放置されている。それは万両の花で、初めて部屋に招かれたことへの返礼だった。
キスは夕暮れまで続いたが、その感触にはまるで覚えがない。僕は粘りを帯びた唾液が宙に弾ける音だけを聞いた。何度も何度も。押し殺しながら搾り出すような声は、彼女の何処かに存在するはずの空洞の在処そのものだった。
二人の粘液が摩擦音を発する最中、いささか通常の鼓動を取り戻した僕は彼女の裸を細部まで見たいと思ったが、そう意識するたび、僕の見る映像は前時代のコンピューターのように何度もフリーズした。聴覚の容量が脳内メモリの大半を占有していることがそれらの原因であるのは自明だった。
今ここで白状するに、僕はある種の水滴音にすら性的興奮を覚えることがある。しかしながら未だに解らないのは、あの暗闇で聞いた一滴の音、僕が絶頂を迎える瞬間に聞いた音である。果たしてテーブルから水が垂れたものなのか、互いのどちらかが発した音なのか、それとも僕の意識の中だけに鳴り響いた音だったのか。それは不思議な記憶まま、僕が固執し続ける性的聴覚を操っている。