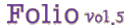警察の包囲網を突破し、脱兎のごとき加速を見せる黒塗りのカブトムシ。一向に速度を緩める気配はない。見事なハンドル裁きで夜の曲がり角を抜ける。胆の据わった男だと、いまさらながらに感嘆する。だが感心してばかりもいられない。明智小五郎もブレーキに足を乗せず、そのままの勢いで曲がりきる。瞬間、尻が振られて汗が出る。
二十面相との対決はもう何度目になるだろうか。二人の闘いはいつも痛み分けだった。二十面相は財宝を盗み損ね、明智は盗人を捕らえ損ねる。いつか決着をつけねばならない。そのいつかとは今夜だと、明智の掌に汗が滲む。
危険な曲がり角を何度超えたことだろう。不意に乾いた音が静寂を驚かせる。そして重いものが転がるような響きとともに、金属の擦れるいやな音が続く。
速度を落とした明智の視界にカブトムシが転がっていた。見事にひっくり返って、下っ腹を空に向けている。四つあるはずのタイヤがひとつ潰れていた。
「おい、大丈夫か」
死んでいるのではないかと思いつつ声を掛ける。窓の奥でごそごそと動いているのを見て一安心する。
「――すまん、手を貸してくれ。出られないのだ。窓ガラスを割ってくれないか」
逆さまになって自由に動けないらしい。明智はトランクの工具袋からドライバーを取り出すと、助手席の窓枠に先端を差し込み、ぐい、とひねる。割れた窓から這い出てきたのは、帝都を騒がす大盗賊、怪人二十面相だ。
「いやはや、ひどい目に遭った」
どことなしに山羊を思わせる細面の男だった。むろん、これが素顔ではないのだろう。どうやら足を怪我したらしく、地面に座り込んだまま立とうともしない。
「折れたかもしれない」
「ボクを追ってじきに警察もやってくるだろう。さすがの怪人二十面相も年貢の収めどきというわけだ。さあ観念したまえ」
だがキザに肩を竦める二十面相。
「怪我が治り次第脱獄するさ」
「お好きなように。そうなればまたボクにお呼びがかかる。商売繁盛大いに結構。君には足を向けて寝られないな」
「そう思うのなら、この場は見逃すのが利口だぜ」
ひとけのない夜の路地にからからと明智の笑い声が響く。
「何を馬鹿なことを。犯人を突き止め、捕まえ、警察に引き渡すのが探偵の仕事なのだ。ここで君を見逃せば、ボクは探偵失格ということになる」
ところが二十面相は苦笑いで首を振る。
「わかってない、わかってないねえ明智くん。探偵の仕事とは浮気調査や人捜しのことをいうんだぜ」
「ふふふ、ボクくらいの格になると、そんなみみっちい仕事は請け負わないのだ」
だが二十面相はなおも、わかってないね、と小馬鹿にした物言いで、
「明智くん、君は探偵なんかじゃない。スターという奴だよ」
もちろんそうだ。明智小五郎はただの探偵ではない。二十面相との対決を通して、今や知らぬ者のない国民的ヒーローなのだ。そしてその英雄が今夜、宿敵に引導を渡す。明日の新聞が実に楽しみだ。
「で、私が捕まったあと、君はどうするつもりだい?」
「そうだな、しばらく暇だろうから旅行でもするか」
幸い、今回の依頼でまとまった報酬が手に入る。サマーシーズンは海外で過ごすか。
明智の脳裏に空を映した南の海が現れる。彼は軽い麻のジャケットを身にまとい、お供は白いうなじもなまめかしい小林少年である。そうだ、小林くんには身体にぴったりした水着を買ってやろう。細くしなやかな少年が泳ぐ様は、ターコイズブルーの海によく似合うに違いない。
明智の心を読んだわけではないだろうが、二十面相は呆れ果てたように言った。
「呑気なものだな、明智くん。君はまだ気付いていないのかい? いま君が手にしている栄誉、賞賛、名声、それらは全て私との闘いによって勝ち得たものなんだぜ」
「そうさ。神出鬼没の大盗賊怪人二十面相と、不世出の名探偵明智小五郎の闘いは日本人なら誰だって知っているさ。小説にもなったし映画にもなった。そして今夜、ボクの勝利によって幕は下りる。ハッピーエンドという奴だね」
「わかってない、わかってないぞ明智くん。ならはっきり言うぞ。明智小五郎の価値は、怪人二十面相があればこそなんだぜ。いま君がもらっている法外な報酬も、あの二十面相と渡り合える人物だと目されているからだ、違うか?」
「違わないさ。で、それがどうしたというんだ?」
「本当に察しの悪い男だな、それでも探偵か? もし私が収監され、二度と日の目を見ないとすれば、君はその後どうやって暮らしをたてるつもりだ。カメラ片手にラブホテルの入り口を見張るのか? 男と駆け落ちした娘を警察犬よろしく追跡するのか? かつての名探偵明智小五郎が事務所のゴミ箱をあさったりできるのか?」
探偵業とは本来そういうものだ、と二十面相は諭すように続ける。
「石川五右衛門の言い種じゃないが、世に盗人の種は尽きまじ、だ。しかしな明智くん、そのほとんどはただのこそ泥、空き巣だろう。わざわざ名探偵が出張ってくるほどのものじゃないさ。名探偵が必要とされるのは、警察の手に負えない天才的悪漢が現れた場合だけなんだよ。私がリスキーな夜を愉しんでいるからこそ、君は重宝され、スターにもなれた」
徐々に話が飲み込めた明智はしかし、二十面相の言辞に耳を貸すつもりはなかった。第一、この悪漢がお縄になってそれで終わりのはずがない。自分でも言っているように、また脱獄しては悪事を繰り返すのだ。そうなればまた明智との第二ラウンドが始まる。
何といっても明智は二十面相の特効薬なのだ。今では二十面相といえば一も二もなく明智のもとに依頼が舞い込むようになっている。確かに捕縛に至ったことはないが、二十面相の犯行をことごとく未遂に終わらせてきた彼の名声は世に隠れもない。
――ことごとく?
ならば二十面相はいったいどうやって稼いでいるのだろう。疑問がよぎる。毎度毎度二十面相は大がかりな仕掛けを用い、大勢の手下を使って犯行を企てる。その費用はどこから捻出しているのだろうか。
「まさか」
二十面相の通り名は、誰にでもなりすます巧みな変装術にあやかったものである。それほどの技術があるなら、何もわざわざ二十面相と名乗って相手を警戒させずとも、その場限りの盗人として顔と名前を使い捨てにすればよさそうなものだ。盗みだけが目的なら、そうしたほうがずっと合理的だ。
なのにあえて二十面相と名乗って盗みを働く。それはつまり「怪人二十面相」というブランドを大切にし、育て上げようと意図しているからではないのか。そして、あくまでも「二十面相」は趣味であり、本業は無名の盗人としておこなっているのではないか。そんな疑問が次から次へとわき上がる。
明智の心中を知ってか知らずか、さらに当てこするように二十面相が言う。
「何と言ったっけな、最近頭角を現してる探偵は。金田一とか、そんな名前だったか。いずれ彼ともお手合わせしたいものだ。二十面相といえば明智小五郎、そういうのもそろそろ食傷気味だ」
二十面相の技術をもってすれば、また新たな怪盗を演じることも可能だろう。そのとき明智が招かれるとは限らない。金田一耕助かもしれないし、わざわざ海外から名探偵を招聘するかもしれない。今こうして明智が呼ばれているのは、相手が二十面相だからだ。過去の実績があるから明智に声がかかっているのだ。
「何も明智小五郎だけが名探偵ではないよ」
そのひとことが明智の胆を冷たく凍らせた。
遠くでパトカーのサイレンが聞こえる。
「おいでなすったか」
足を怪我してへたり込んだままの二十面相は、首を回してサイレンのする方向に視線をやる。
「怪人二十面相は今夜で終わりだ。もう君と会うこともないだろう」
「ま、まてよ」
いつになく狼狽した明智は右往左往したあと、二十面相に肩を貸す。
「どういうつもりかな」
「――いいから乗れ」
自分の車まで連れて行くと、急いで助手席に二十面相を押し込む。明智は運転席に乗り込んで、キーを回す。あとに残るは二十面相が用いた逃走車両の残骸のみだ。それを見て警察は何と思うか。車の事故、徒歩で逃げ出す二十面相。それを明智が車で追う、そう考えてくれたら幸いだ。
夜の街を往く二人。
明智は思わず呻き声を洩らす。とんでもないことをしでかしてしまった。
「何を嘆いているんだ?」
明智の苦悩もどこ吹く風、二十面相は呑気にたばこを吹かしている。すでに立場は逆転した。今後、どこかで二十面相が逮捕された際、今夜の話を洩らしたならば――。そう思うだけで明智の股間が縮みあがる。二十面相は絶対に捕まってはならないのだ。
「うぅ…コバヤシくぅん」
小林少年がこのことを知ったら大いに失望するだろう。目に涙を浮かべてなじるに違いない。あの少年は、いかにも少年らしい正義感と潔癖さを持ち合わせている。決して大人の妥協を理解してはくれないだろう。
我知らず明智はすすり泣き、最愛の恋人の名を呼んでいた。それを見て二十面相はせせら笑う。
「おいおい、明智先生ともあろう御方が、あんな小僧っ子に惚れているのかい?」
「うるさい、おまえに何がわかる」
「わからないねえ、お稚児趣味ってのはどうもよく解らない。後学のために尋ねたいが、君はあの小僧を愛しているのか? それとも単に男の子が好きなのか? あるいは男が好きなのか?」
「私が愛してるのは小林くんだけだっ」
反射的に言い放つ。