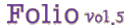ベッドに寝そべったまま明智小五郎は朝刊に目を通す。あの夜以来、組織的な犯行や大胆な手段、大きな被害といった事件の陰には二十面相がいるような気がして仕方がない。そもそも怪人二十面相、それすらもあの男――男かどうかも確信が持てないのだが――の数ある仮面のひとつに過ぎないのだ。
「何か面白い事件がありましたか、先生?」
隣からパジャマ姿の小林少年が覗き込む。白く延びた華奢な首。あまりに可愛らしくて、首を締め上げ、へし折ってしまいたい衝動に駆られる。
「いや、特に何もないな」
読むか、と差し出す新聞に小林少年は首を振る。そのしぐさも少女めいて実に愛くるしい。
――少女めいて?
ならば少女を愛玩すれば良いのではないか。なぜ少年にこだわるのだ? さらにいえばなぜ小林くんでなければならないのだ? 彼のように美しい少年は他にもたくさんいるだろうに。
明智は疑問を追い払う。事件を推理し、事情を詮索するのは得意だが、自身を見つめるのは苦手なのだ。
紳士と少年のコンビは絵になる。何度も女性週刊誌の表紙を飾っている。これが少女とのコンビならまた話が変わってきて、逆に変な詮索をされるに違いない。紳士と少年だから良いのだ。そう彼は見当違いの結論で自分を納得させる。
明智小五郎の名声は今も高い。最近では金田一耕助の名前もよく聞くが、それでもなお第一人者といえば明智小五郎だ。確かに金田一は個性的な男で、そこが受けてもいるのだが、明智に言わせればそんなのは物珍しさだけだ。浮浪者じみた風貌で、しかもヒロポン中毒の前歴があると噂されるような男など決してヒーローになり得ない。何よりも金田一には宿敵がいない。彼の解決した事件はいつも、最後に犯人が毒をあおったりして使い捨てに終わる。その点、明智は好敵手に恵まれている。可愛い従者もついている。
相変わらず二十面相はあちこちで悪さをしている。セオリーどおりの犯行予告。そのたびに明智は駆り出され、すんでの所で取り逃がす。故意にやっているわけではないのだが、いつもそうなってしまう。たぶん二十面相が手加減しているのだろう、そう最近の明智は思うようになってきた。奴が本気を出せば明智を出し抜き、まんまと財宝を盗み出せるに違いない。だが彼と明智との闘いを盛り上げるためにわざと手を抜いているのだろう。
それを惨めと感じないことはないが、しかし自分の名声を維持し、巨額の報酬を得るには仕方ないことだと諦めている。そう、何も名探偵は彼一人ではないのだから。
こうしている間にも金田一耕助が追い上げている。金田一の後にも、今はまだ無名の探偵が雌伏の時を過ごしている。目を海外に転じれば明智の座を脅かす俊才がごまんといるのだろう。それらから王座を守り続けるには手段を選んではいられない。ボク一人が卑怯なのではない、あのシャーロック・ホームズ氏だってやったことだ。
しかし考えるにつけ不思議なことだった。なぜ二十面相はホームズ氏の秘密を知っていたのだろう。他に誰一人として知るはずがなく、決して知られてはならない性質の秘密なのに、だ。
「まさか、な」
確かに二十面相は変装の達人だ。年齢、性別、人種まで変えてみせる。だからといってすぐにあの二人を結びつけるのは早計というものだ。第一あれは二十面相の作り話かもしれないではないか。嘘つきは泥棒の始まり。けだし名言だ。
「どうしたんですか、そんな難しい顔をして?」
見れば不安な様子の小林少年。いたいけな、という言葉がぴったりだ。
「何でもないよぉ」
ことさらおどけて言うと、明智は小林少年に飛び付いた。パジャマの襟元、剥き出しの鎖骨に唇を押しつける。
「あはは、よしてください。くすぐったいじゃありませんか」
「いいや、やめないね。キミが悪いんだ。可愛すぎるキミが悪いのだ」
接吻の雨を降らせる明智小五郎。小林少年の顎はつるりと滑らかだ。明智は知っている。小林少年は年相応に毛深くなっていく自分の身体を恐れているのだ。一日でも青年になるのを遅らせようと、毎夜毎夜、今はまだ濃い産毛程度の体毛を毛抜きで処理しているのである。涙ぐましい努力じゃないか。
しかし明智は気付いている。小林少年の背中は日ごとに厚くなり、肌もかすかに獣じみた匂いを帯びはじめている。それはどうしようもないことなのだ。誰も子供のままではいられないし、老いから逃れる術はない。
少年を組み伏せ、じゃれつきまわる名探偵。白く滑らかなこの肌も、いつかは毛穴の目立つ大人の皮膚に様変わりする。すらりと長く延びた二本の脚も、そう遠からぬうちに逞しい筋肉に覆われていく。精悍さを増し、力強さを湛える一方で失われていく少年の美。果たしてこの先も、ボクはこの少年を愛し続けることができるのだろうか。
パジャマの裾をたくし上げ、あらわになったわき腹に吸い付く。薄い皮膚は食餌制限のたまものだ。過剰な筋肉がつくのを恐れ、小林少年は野菜中心の食生活に切り替えている。肉はもとより、米、小麦といった炭水化物も控えている。そうすることで幼さを維持し続けようとしている。
以前の明智なら、小林少年の努力に何の疑問も抱かなかっただろう。ただ嬉しいと思い、いとおしいと思うだけだった。だが二十面相との夜以来、彼は無邪気に物事を肯定できなくなっていた。
やがてボクらは老いる。小林くんは小林青年になり、明智小五郎はかつての名探偵になる。あるいは老いた明智が安楽椅子に身を埋め、小林青年の報告に耳を傾け知恵を巡らせる、そんな形の探偵でいられるかもしれない。だが往年の明智を知る者は、それを見て寂しい気持ちになるに違いない。明智小五郎とは揃いのスーツに身を固めたダンディな男。事件の山場で颯爽と登場し、ときには悪漢と立ち回りを演じ、危険な追跡を試みる、そんなヒーローであるべきなのだ。
「――小林くん」
「何ですか?」
明智が視線を上げると、頬を紅潮させ、かすかに息を乱している小林少年がいた。
「もし、仮にだよ。ボクが探偵を辞めて、盗賊に転身するとしたら、君はどうする?」
小林少年は真っ直ぐ明智の瞳を見つめる。何の冗談だろうかと探っているような目つきだった。
「そうですね――」
少し言い淀み、微笑を浮かべる小林少年。
「そのときは、ぼくが先生を捕まえて差し上げます」
「ボクは手強いぞ」
「もちろんぼく一人じゃ無理でしょう。だから仲間を増やすんです」
言うと、小林少年はいそいそと身を起こす。実は前から考えていたんです、と息せき切って続ける。
「尾行や張り込みって手間も人手もかかるでしょ? だから子供を集めて少年探偵団を作りたいなあって」
「少年探偵団?」
「ねえ、いい考えだと思いませんか? 子供なら時間もとれるし小遣い程度で雇えます。まさか賊だって子供に見張られてるとは思いませんよ。探偵団の面倒はぼくが見ますから。ねえ先生、いいでしょう?」
ああ、小林くんも大人になった。いつまでも丁稚小僧でいたくないのだ。小さいながらもボスとなり、手下を従え、先輩面をしたくなったのか。
「少年探偵団かぁ」
悲しい気持ちで呟き、小林少年の太股に頬を寄せる。もうじき、彼も半ズボンが似合わなくなるのだろう。どうしたって背は伸びる。いくら毛を抜いても、子供のままではいられない。
なおも玩具をねだるように、小林少年は「ねぇ」と繰り返す。
明智小五郎は想像する。
安楽椅子に腰掛ける老紳士。その隣には貴公子然とした青年が立っている。彼らを取り囲むようにして寄り添う大勢の美童。
――こいつはちょっと素敵じゃないか?
「ねえ、お願いしますよ、先生ぇ」
「うーん、少年探偵団ねぇ」
夢想は膨らむ。少年探偵団という名目なら少年ばかりを集められ、なおかつ齢がいけば卒業させることもできる。国民的ヒーローの座はそのまま小林青年に継承させればいい。そして明智は大御所気取りで、美少年たちの崇拝の眼差しを一身に集めるのだ。
悪くない、悪くないぞ、と明智小五郎はほくそ笑んだ。
「でもなぁ」
生返事を繰り返す明智小五郎。
肚は八割方決まっていた。だが少しくらい焦らしてやらないと、おねだりの有り難みが薄れるというものだ。
――明智小五郎と美少年の王国。
少年探偵団。それはきっと素敵な光景に違いない。