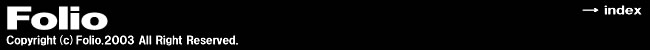世界は振動している。穴蔵にいるとそれが余計理解できた。庸子は私にみんななくなっちまえばいいんだといい、そんな言葉を鼻で笑いつつも半ば同意していた。
先日はどこどこで空襲があった、今日はどこどこで空襲があったといい合い、人々は物見高く焼けた町を見に行き、散々女の死体やら赤々と燃える炎やらを見物をし、戻ってきてこういう。「酷かったわあ。次は私たちよ。疎開しなきゃ」
といいつつどこにも行く気配はない。冗談じゃあない。逃げることもせず、戦うことさえしない。そして、ああ、燃える燃えるといって悲しみに打ちひしがれる顔をして泣きわめき、全てを忘れる。配給に群がる人々は、餓鬼草子に描かれた異形の姿そのままに醜悪で、奴等こそ焼夷弾に焼かれて炭になってしまうべきやつばらなのだ。
私はそう唾棄したが餓鬼よりもっと畜生に近いのも事実だった。
「奮戦」「陥落」「前線」「勝利への撤退」と日々ああしろこうしろと言われたことを、そのままにくだらなく記事にするブン屋で、記事が刷り上がった頃には「奮戦」が「撤退」となり、そのうち書くことを禁止される。真実など何処にもなく官憲のいいなりにやもすると「空襲予想」や「平安期における方違えの現代的応用」さえ書く始末だ。いっそ米国万歳とか怨呪鬼畜米英と書けと言われればそうするかも知れない。どこからどこまでも絵空事で、もし、真実など計りきれないものだとすると、それは当然の事態だし、真実がどこかに存在するのだと熱心に追いかけるような心意気のものならば、気が狂ってしまうだろう。
戦地へ赴く人々が立派であるのかと言われれば、そんなこともなく、万歳の対象が米国ではなく天皇であるということで、我々はこの国家に忠君する事を佳しとするのだろうか。我が皇国は真の繁栄と神の薫陶を受け天下に誇る万世一系の、と諳んじてみても空しい。虚実が正反対に入れ替わってしまっったのはいつからだろうか。真実を追跡することは反逆であり、そもそも何処からが事実で何処からが虚構なのかは判別がつかない。つまるところ、この国自体が皆総じてそのような三文文士の戯曲に踊らされているノータリンであるだけのことで、餓鬼もお国に奉公する人も私も、それぞれがみんながみんなそれぞれの度量に見合った阿呆なだけだ。だが、阿呆でないものなどいるのだろうか。いやしない。いっそのこと全て灰になってしまえばいい。すべからく焦土と化してしまった方がいいのだ。そうすればどんなにか分かりやすくなるだろう。
私は穴蔵の中で早くこの街に空襲が来ないかと願い、そして穴蔵自体が崩れて、庸子共々埋めて欲しいと願っていた。一介の阿呆の妄想に過ぎないのはよく知悉していて、やれ空襲だ、やれ配給だと騒ぐ人々の群に混じって私は空疎でのっぺらぼうの自我を持て余していた。
くだらない。すべてくだらない。
そう。それは穴蔵と呼ぶにふさわしい場所だった。実家の隣の織物問屋の暁屋が疎開した際に使用を許された防空壕で、豪奢な母屋と同じく防空壕も立派なコンクリート製で、彼らは見事な松を切り倒し、岩をどかして作ったのに一度も使わず、時勢に押されて家業を閉じて三月を待たず疎開した。内部は案外狭く見えたが、実際は四畳半ほどもあり、私は一目で気に入った。早々に私は様々な物を詰め込んで我が別荘とした。
その時の私の快哉を推し量るがいい。私は愁傷な顔をして、その時ばかりは暁屋に食い下がったのだ。何故か。私はそれほどまでに穴蔵を手に入れたかったのだ。理由はない。安全が欲しかった訳ではない。実際、物資不足のコンクリートは脆いのは当たり前で、いざ爆弾が落ちてくればひとたまりもないだろうと思えた。だからこそ、それは私の心を強く惹き付ける場所だった。
隣家の管理を任されたのち、私は以前から夢想していたように穴蔵に住み、祖母が死んだ後に私の他に誰もいない家は借家として貸した。空襲で焼けだされた人は残った次の標的になる町にやってくるわけはないと思ったが、案外早くに五つある部屋は埋まった。私は祖母の届け出をしなかったので、その分と、屋敷を管理する居もしない女中を雇ったと届け出をし雀の波ほど配給が増えることができた。店子はそのために必要だった訳で、彼らの店賃には何の期待もしなかった。彼らはは見かけ倒しの防空壕(押し掛けられるのを嫌い狭く見えるよう細工したのだったが)を見ると、自分たちで庭に掘って良いかと提案してきて、私が庭を好きに使わせると数日のうちに彼らは自分たちだけの穴を掘った。それからずっと部屋に籠もりきって、どこから手に入れたのか禁酒を交わして日がな一日中花札に興じていた。
彼らの心配が去ってしまうと、私は灯火管制で電気が消されるまで穴蔵にに棲み、やがて暁屋の母屋を捨て穴蔵に寝床も用意した。
案外、地中の中は快適だった。
蝉がむんむん騒ぐ外気は蒸し暑く気が狂いそうになるが、静寂と幾分湿ったこもりがちの空気は私に気があった。贅沢にも母屋からは電気が引かれていたし空気穴が二つ三つ開いていたのでそれほど窒息的な雰囲気はなかった。なおさら私は箪笥が減り押入の中の物も減っていった母屋には近付かなかった。
暁屋は長年の間、隣家である私の実家を大層軽蔑していて、父は組合医院の雇われ医師だったが、敏坊、敏坊といくつになっても私を呼び、お宅は大変ねえと痩せた婦人は私を嘲笑した。積年の恨みといえばそうかも知れない。いっそのこと母屋に火でも付けてやろうかと思うが、まだ売るものが残っていたので私は待った。虫の居所を騒がせる母屋より、穴蔵を好んだ理由はそういうことでもある。
私はその穴蔵に庸子を閉じこめた。
閉じこめたというのは、いささか剛毅な物言いで、庸子は好んでその中を選んだのだった。
庸子は五月の空襲の際に橋の側で拾った女だった。
惨状を取材に行ったその町の橋の側に庸子はいて、飯喰わせてくれれば、と慣れない様子で私に尋ねた。まだ女の側では焼けた家はくすぶっていて真っ黒なマネキンに似た死体が煙を吐いていて、私は笑ってこんな焼け野原でどこに時化込むのだといえば、どこかへ連れていってくれとせがんだ。着ているものも、表情もどこか品を感じる作りだったが、だいぶ汚れていた。どこかの娼館に勤めてたのかとも思い、ならば、と私はしばらく連れて歩いて混雑する一膳飯屋に入った。「朝からあそこにいて買ってくれたのは、あんただけだよ」と雑炊を啜りながらいった。あたりまえだ。焼けた死体がくすぶり匂う中で女を抱きたいと思う奴など居ない。ましてや焼け出された避難者にとっては、石を持て追う行為に等しい。社に戻るためにビルディングの間から抜け出したときに、どこに住んでいるのかと女は訊いた。
疲れて社から戻ると、駅前にぼんやりと女は佇んでいて、私の顔を見ると微笑んで連れてけとせがんだ。歩いて来たといい、腹が減ったと答えたので、私は連れて帰って芋をやった。
庸子は穴蔵の中をきょろきょろと見回した。
「こんなところに住んでるの」と訊き、興味もないような表情で万年床に散らばる本を脇に避けて布団に寝転がった。手にした芋を頬張りながら「ね。しよ」と戸口に立つ私を呼んだ。あっけらかんとしたものだった。庸子がはだけた浴衣の下からは白い肌が現われ、つやつやと漆黒の闇の中に汗をかき、くねくねと蛞蝓が蠕動するようで、幾つだと訊くと二三と答え、しばらく居ていい。何処にも行くところがないのよといった。
まったくもって変な女だ。私が母屋に夕食を作りに行き、持って帰ってきても、どこに行ってたのかとか、何をしていたのかも一切訊かず、身体を合わせること以外は知らないように、食べ終わると熱心にせがみ、ことが終わると何知らぬ顔でぐーぐー寝てしまう。昼間は何をしているのかと思ったら、寝てたとだけ答え、私の荷物がすっかりなくなり女も消えていると思っていたので、案外拍子抜けした。
やがて庸子は私を真一と呼んでいいかと訊いた。その名前は庸子の弟で、脳の足らない子だったそうだ。初めはいい気はしなかったが、次第にどうでも良くなった。所詮、だれもがフーテンなのだ。
ある日の早朝、私の名前を呼ぶので穴蔵から出て行くと、行商の石館という男だった。
「先生、何やってるんです? そんなとこ入って」
元は国民学校の先生だったというが、どう見ても小間使いのような性格と腰の低さで私を先生と呼ぶ。先生どころか幇間のような男なのだ。私は誤魔化し、石館のリュックのなかを見聞した。
「今はもう何にも手にはいらねえ」
実際中身は貧相なもので、値段もふっかけてきたので、仕方なく適当に仕入れて茶を濁すと「あっしは」と長々と山梨まで出掛けて仕入れた話が始まり、夜行で帰ってきたと愚痴をこぼしているのをほうほうの態で追い返したが、手にした物を見ていよいよこいつはもう使えないなと思った。だが自ら仕入れに行くのも面倒だ。なにより布施鍋にたかる餓鬼どもの間をゆくのかと思うと幻滅するのだった。なんにせよ、手に入れるのに苦労する。
「おい、赤薩摩が手に入った。今蒸してやるから、あっちに行こう」
庸子はいいえ、こっちがいいと答えて、「真一はねえ」と庸子は切り出した。
「日野屋の跡取りなのよ」
私は一瞬、それが何を意味するのか分からなかったが、やがて思い出して驚いた。暁屋と日野屋はライバル関係の織物問屋で、かつて競い合っていたのだった。ならば仇(かたき)だろう。
「跡取りが気狂いならいっそ大変だったろう」と言った途端に思いだし、相次いで旦那夫婦が死んだ後は、番頭が家を乗っ取ったのだという噂を聞いたはずだ。
「私たちは倉の中に押し込められて育ったのよ」
「まさか」今時分にそのような前時代的なことはあるまい。
「倉の中に座敷牢を作ってよ。お客が来たときに私は呼ばれて、奥の座敷に行った。焼けた時には心底ほっとしたわ」
「何故客引きを」
庸子の話はどこで仕入れた話なのかと胡散臭く感じた。
「いくら頑丈な倉でも崩れる時にはちゃんと崩れるの。わたしはなんとか抜け出せたけど、真一は柱に足を潰されてたので、必死になって助けてやると歩きだして。屋敷の方は見なかったわ。轟々と炎が上がってて、閻魔の炎に包まれてて、近づけなかった。そして」
そして、真一は私にいったの。「お姉はお姉の好きなようにすればいいって」
庸子は首を俯けた。私は頭のなかで芋のことを考え、蒸し器の場所を探していた。
「でも、好きなことなんて何もないじゃない。どうしようと思ったわ。真一はびっこを引きながら歩いて、止めようとしたのだけど振り向きもしないで炎の町に消えて、私は残されたの。真一が一番この戦争を望んでいたのよ」
「消息は?」と私は肩を掻きながら訊いた。庸子は首を振った。
だからといって私は庸子に対してなにをすればいい。庸子は何故そのような話をするのだろう。最初こそ驚いたが、話を聞いているうちに何の感情も沸かなくなった。没落。流転。転落。ははは。そんなものに価値はない。良くある話でもあるし、本当か嘘か分かりっこないのだ。客に聞いた話をそれらしくでっちあげてるだけだろう。私にとって庸子は便所で庸子にとって私が便所だ。それでいい。猫を拾ったのと同じことだった。
そういえば、と思い出す。日野屋にも娘がいた。まだ庸子の年齢にはならなかったが、庸子を犯すと日野屋の娘を抱いているような錯覚を覚え、一宿一飯の礼というのか、庸子は私の好きなようにやらせた。穴蔵はやがて庸子の匂いが染み付いていて、むっとする暗闇の中で「真一が突く度にどんどん音がすぅる」と庸子はいう。
「もっとつよく。みんな殺して」と。
人が人であることの長所は忘却にある。
出征する人間を喝采をもって送り出し、やがて過去の記憶を流し去り、運良く帰還した死骸の人々の棺に寄り添って「銃後」といい、あたかもここは地獄かなにかのようだといい、そしてまた再び忘れて、飯を喰うだけに拘泥してやがて漫然と生きる。平和には慣れず、絶望に慣れ親しむのは人間の暗い情動であって、自殺者の心意気に近付く華やかな手段だ。それは同情や悲しみではなく嬉々として絶望に接近して快楽の産声を放つのだ。私は、ただ、それらの様子を見ていたいと思った。地獄だか天国だか分からぬこの廃墟を片っ端から見ていたい気がした。
爆弾よ。もっと降れ。米国の貯蔵庫にある全ての爆弾よ降れ。降り注いで何もかも焼けてしまえばいい。私もろとも焼いてしまえばいい。
戦況はなお一層悪くなっていて、私はあちこちの撤退を知った。「大本営発表」と見出しに踊る文字が、何の意味も持たなくなってから久しかった。あまり状況を知らぬ人々の気分もまた、膿んでいた。毎日のように空を敵機が飛べば、戦況が分からずともおおむね理解できただろう。中には夢去らぬ者がいて、町中で大声を上げ、心で負けぬのなら決して負けぬのだと威を振るっていたが、町内会の役員などに就くのはその手だろう。人々は不承不承消防訓練に従い、参加し、無駄話で誤魔化していた。ここ二年ほどの間に都合百回以上空襲が行なわれたのだという話を聞いて、案外少ないのだ、と声があがったりした。
市内のあちこちにだだっ広い焼け跡が広がっていて、徐々に人が少なくなってゆくのが分かった。それは奇妙な静けさに包まれていた日々だった。逃げる場所がある者は逃げ、死ぬしかない者は焼け死んだ。それでも街には人が溢れて、駅は人で埋まっていた。いつこんな狂騒が終わるのだろうか?
私はそんな人々の様子を段々奇妙に感じ、犬の子を愛でるのに似た慈しみを感じた。崩壊した街の写真を撮り、戻った社で地図に印をつけながら瓦礫と灰の地帯が広がってゆくのを痛快に思う。そしていつ震災の時より瓦礫の量が増加するかと心待つのだった。
ある時、私は庸子との毎夜の営みが、また一日生き延びてしまった区切りとして機能し始めているのだと気がついた。そうすると見たくもない胃の中を探られるような気分がして、私は庸子の目を見ないように布巾で顔を覆った。
「見えないわ」
「どうせ停電になる」
私は庸子を立たせて壁まで歩かせた。
「見えないわよ」
手を左右に探るように揺らして前方を探し、程なく庸子は扉にぶつかった。白い肌の胸と腰が揺れた。
「逆に歩け」
庸子はふらふらと身体を反対側に向けて、歩き出し、やがて積み上げた本の山にぶつかって一緒に崩れ込んだ。
「なにがおもしろいのよ」
私が笑っているのに腹を立てたようだ。
「こんなもの。埋もれて死ねばいい」と私に向かって手当たり次第投げつけ始めた。「そしたら私の仏壇に何でもいいから一つでも飾ってくれ」と私は冗談めかした。
「いやよ。その前に私が焼いてやるわ」どうせ塵でしょ。
私は、笑って、そうかも知れないと答えた。
暗闇だったり目隠しをしたりすると庸子は頬を赤らめた。そういうときには「妖艶」という言葉が似合うだろうか。私は庸子が美しいと思った。
ことが終わると、不意に素面に戻り、何気なく素っ気ない表情で、客は仏間で私を抱いたといい、悲嘆の表情をした。私が手を差し伸べるとまた再び、酔った表情を浮かべて、どうでもいいじゃないと突っ放す。どうでもいいじゃない、というのはどうでも良くないことと同義で、実のところはそのどうでもいいことを纏われて厄介に感じているということでもある。だが、それさえも嘘である可能性が高い。私は偽悪的な心境で「何故逃げなかった」と訊くと、真一がいたのよ。置いてはいけないわと、答えた。それで結局こんな穴蔵に潜っているのか。どちらにしても皮肉な運命だ。
「何処かへ行きたいとは考えないのか」
「いいえ。私が邪魔?」
「邪魔だね。一日中こんなところにいて、飯も作らず何もしない女など」
庸子はちょっと首を傾げて、微笑んだ。素面の表情の時の庸子は織物問屋の令嬢といった風情そのものだ。
「昼はねえ。自分で慰さめて。眠って、また慰めて、飽きたら読んでるわ」
「何を」
枕元に置いた本を庸子は手にした。
「京都から来る客がいたの」
庸子の手にした谷崎は卍だった。
「えらうしつこうかったん。わて、そのお人にわやにされたんよ。わかる」
男か女かと問うと、いつもの調子で「どっちでもいいじゃない」と答える。
「なあ、そんなにわたしの昔のことが、なんで気になるん?」
「別に」
「そう。おかしな人やったわ。男の人のようでも女の人のようだった」
庸子は身体をくねらせた。
「わたし、女の人、好きよ。男みたいに無神経じゃないもの」
「じゃあ。やめればいい」
「爆弾を落とすのだって、男よ」
「女を抱くのだって男だ」
私は庸子を除けた。庸子は私の腕を掴んだ。
「女の人は男にもなれるけど、男の人って女にはなれないのよ。わかって」
私にはその理屈は分からなかったし、夢想に付き合う義理はなかった。私は庸子にもう一度目隠しをした。「ばか」庸子は身体を縮込ませた。
「わたしを縛って。きつく縛って」そしてそう繰り返した。
男は女の過去に嫉妬する。女は男の現在に嫉妬する。私が仕事に出掛ける際には、庸子は、いつ帰ってくるのか念を押し、そのくせ帰宅するといぎたなく眠りこけていた。庸子のそれは嫉妬ではなく単に確認だったのかも知れない。私は庸子の過去を確認し、そして安心するのだった。
だが、いったい、何を安心すればいい?
人も時代も戦争もぼろぼろと櫛が欠けてゆくように老いてゆくものなのだ。あらゆる物は腐敗してやがてどろどろに崩れてゆく。小町の九層観だ。そして何が残る? 骨か。神社の境内の軒下で枯れて繊維だけになったほうずきの実なのか。
巨大な爆弾が地方都市に落とされたのは、丁度その翌日だった。甚大な被害がでていて、私はもたらされる情報を整理し記事を書きながら、不覚にも衝撃を受けた。そして今まで皆、死んでしまえと思っていたことが、いかに甘っちろい考えであったのかと思い知った。私は崩壊を愛した。この街全てが崩壊してくれることを願っていた。そして、圧倒的な崩壊の前にいかに自分が無力であるか知らされ、私が夢想する崩壊など何様のものだ。お前が望んでいるものを与えてやった。ならばそれで恍惚とするのか。それは何をもたらすのだ? 電報の情報はそういって私を責めていた。数万の人間が一度に死んでしまう。巨大な都市を一度に崩壊させてしまう、それほどの威力のあるものがこの世に存在してよいのかと身体の芯が震えた。
一体何を記事にすればよいのだろうか。私は戦争を愛していたのだから。愕然とし、確信が焼夷弾のように降ってきた。
「終わったのだ」という確信だった。
その夜、夜遅くなって穴蔵に帰ると、庸子の姿はなかった。
私は昨夜の「邪魔だね」という言葉を思い出し、どこかへようやく逃走したのか、と考える一方で、爆弾のニュースをラジオから聞いて自暴自棄になった庸子の水死体を思った。水面に浮かびながらケラケラと笑い、胸に手を添えて、真一のように吸ってよ、と微笑む。両手が差しのばされて抱きかかえるような格好のまま水に沈む。
近所を散々探したが、何処にも庸子の姿を発見することができなかった。
そのうちに「これでよかったのだ」と思えた。世を捨て鉢にし、不貞寝をするだけの女房に逃げられるような男やもめをひっ掴んでいるよりも、どこかで誰かの胸に抱かれている方がずっとましなのだと思えた。喪失感と共にさばさばした感情が生まれた。
穴蔵に戻りかけて、ふと母屋を見ると、小さな明かりがちろちろと揺れているのが目に入った。母屋に入ると座敷で庸子は寝ていた。全裸に深紅に蝶の文様が入った単衣を纏ったままいぎたなく眠っている。手前の卓袱台にはふたつの椀に入った長い間冷えて、置いておかれたままの芋粥があった。揺れていたのは短くなった蝋燭の炎だった。
私の気配を察して目覚めた庸子は目を擦りながら報告した。身を売って芋粥を買ったということで、私は急に胸がこみ上げてきて庸子の身体に取りすがって、初めてその胸の中で懺悔した。庸子は私の頭を撫でながら真一の昔話をした。私は黙って聞いているうちに眠っていた。
広島からの詳しい情報と写真があがってくる頃、もう一つの崩壊が起こった。
デマといい加減な話が伝わってきて、おおっぴらにではないが、人々は諦念を表明し始めた。
いや、とうに自分たちが諦めていたことに気が付いたのかも知れなかった。まことしやかに次は東京が狙われると囁かれはじめ、改めて逃げ出す者もあった。私は崩壊した街を歩き、写真を撮った。私の中がまるで廃墟のように平坦な瓦礫のようになるまで、写真を撮り、母屋で庸子と眠った。
残された織物問屋の棚から、幾つもの着物を引っぱり出して、庸子に着せた。庸子は姿見にその姿を映して、ぐるりと回ったりして無邪気な様子を見せた。私たちは階段で、仏間で、台所で交わった。手足を縛ってと庸子はいい、いや、私はそれを望んでした。階段の手すりに手を縛り、目隠しをして私は背後から抱いた。停電した真っ暗闇の中で、籐の椅子に縛り付け、縛り付けられた。濡れた身体を押し入れの反物で拭いて放り投げたままにした。戦争が終わったら一緒にどこかへ行こうと言いつつも、決まって行き先は決まらなかった。「一緒に焼かれよう」ともいった。私ははぐらかし、庸子もはぐらかした。
戦争、時代というものは、気性の荒い馬に引かれる馬車のようなものだ。落とされまいと踏ん張りつつ降りたいと願いながら、豪放に駆ける馬車の中で人はおどおどと悲鳴をあげる。悲鳴は爆弾の音なのか人の声なのか。
何度か小規模な空襲があったが、残念ながら私たちの居る街には爆弾は落ちず、例の新型爆弾も落とされなかった。私はじれったい気分でいて、まだ放埒の中で死ぬことを諦めていなかったのだし、一方で何処にも行く場所はないのだとも思っていた。その一週間は昼間は何もない、ただ漠然とした日光が燦々と照る、一見平安を装った日々だった。新聞ももうほとんど用を成さず(書けないことが多すぎるのだ)、少しだけ社に顔をだし私は街をあるいた。時には庸子を連れだして、焼け跡の銀座を黙って歩いた。カフェに行ったことがないという庸子に、ここが跡地だと説明したりした。
町で「先生」と呼ぶ声がした。石館だった。
「誰ですか、そのべっぴんさんは」と吟味するような視線で庸子を見た。
私は不快を隠さず「焼け出された従姉妹だ」と答え、「いいところで会った。飯でも喰いませんか」と誘う石館を置いて去った。奴はまたたかる気なのだと説明しつつ焼けた銀座を背景に庸子を撮った。
社で密かに現像した写真はピンぼけで、庸子は笑っているようにも泣いているようにも見えた。
写真を見ると庸子は笑って「最低ね」と投げ捨て「あんたのひどい顔も撮ってやればよかったわ」といった。私はむっとして庸子の頬を叩いた。
「なによ」と、庸子は両手をばたつかせて私の腕を叩き、頬を殴った。私は力任せに庸子を押し倒した。「ばかぁ」と繰り返す声がいつまでも耳に残った。
ある日の午後、陸軍が奇妙な動きをしているとデスクにいわれた。だが、行ってはならないと念を押されたので、私は早々に退社してこっそりと首相官邸にクーデター見物をしに行った。庸子と共に近くの空きビルの一室から覗いていると、夜半に炎が上がって、黙々と煙が風に靡いているのを見ながら、交わって窓から小便をした。クーデター見物とは最高の道楽なのだ。庸子は燃え、私も耽溺した。だが、もう私たちには交わす言葉がなかった。
耽溺の果てなのか互いを崩壊させるためなのか、互いを殴り合って官能のおこぼれを期待した。「ばか。ばか。ばか」と庸子は私を殴った。私は庸子の身体を蹴るようにして脇に避けて転がし、尻を本で叩く。赤く腫れたような尻を抱きしめて交わろうとしたが庸子は逃れて、また私の前に立つ。だが、二人ともどもインポテンツに陥っていて直前までは辿り着くが感極まることはなく、だからこそ一層、気狂いのように身体を求めた。
翌朝、怠惰な時間に街のあちこちから昼に重大放送があると宣伝が聞こえてきた。私は庸子と二人で穴蔵の中で屋敷の前を歩く人の声に「終わった」と聞いた。終わったことは分かっていた。そんなの知ってたよ。初めから終わっていたのだ。私たちは祝杯をあげ、酔った勢いで、有り金をはたいてガソリンを買い込んだ。そして穴蔵にあった本を暁屋の座敷に積み上げて、火を放った。安物のガソリンだったが、あっという間に炎が屋敷を包んだ。庸子は一つだけ持ち出した緋色の単衣を着て「綺麗だね」と呟いた。
「うん」
「何処にゆくんだ」
「分からないわ。あんたは」
「分からない」
私たちはそう言葉を交わした。静謐な感情が沸き上がってきた。庸子に銀座の写真を渡した。「死ねなかったね」と笑って庸子は受け取り、そして「グッドバイ」といった。
「うん」
炎を発見した近所の者たちが門の外でがやがやと騒がしくなったので、私たちは裏口から逃げて橋の側で分かれた。しばらく去って行く庸子の後ろ姿を見ながら、やがて私は呆然とした。そして私は焼ける家から逃げるように歩いた。ひどく感傷的な気分だった。何処へ行けばいいのか分からず、庸子も何処へゆこうとしているのだろうか分からなかったが、もう私たちは人混みに紛れてしまった。私も庸子も人混みの中へ置き去りにされた気分がした。
私は見なければならない、と思った。慌てて高台に上る。消防団などもういない街で、炎は近隣に延焼し私の実家も焼き、全てを灰にするように広がってゆくのだ。立ち上る暗煙の背後に見える街の廃墟は深淵のように黒い地平線を描いていた。黒煙を見ながら、全てのことが夢であって欲しいと願った。いっそ夢でさえなければいいと私は思った。漆黒のたゆたい流れるような夢なのか意識の停止状態なのか分からぬ時間。目覚めてみると、私は生き残ってしまったことに気がつくのだ。そしてゆっくりと私の戦後が始まってゆく。
了
(030823)
|