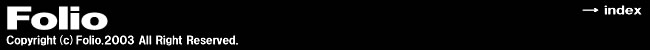|
そうね、私、同年代の女の子から見たら、精神年齢高いほうじゃないかしら。特に男と女の方面。その何割かはお姉ちゃんのせい。真面目でうじうじしてて友達のいない娘が、短大卒業したとたん既婚者の餌食になったってのは、まあ、よくある話なんだと思うけど、お姉ちゃんってば、いくら友達がいないからって、小学生の私に相談することないじゃないって思う。そりゃ私、小学生にしては話がわかるほうだとは思うけど。
でもやっぱり若いOLが結婚してるおっさんに、なんて話聞いてると、なんだか恋だの愛だのに希望が持てなくなっちゃう。そういう話を前途ある私に話さずをいられないお姉ちゃんを思うと、それだけ必死なのね、と微笑ましい気持ちになることはなるんだけどさ。
そんなことよりお姉ちゃん、彼氏(って言っていいのかしら)ができてから、みるみる垢抜けた。この人死ぬまで処女なんじゃない、なんて、こっそり思ってた私は素直に驚いたんだけど、もちろんお姉ちゃんには内緒ね。
私たちは通知表が渡された瞬間に、スイッチを切り替えたようにくっきり、季節を夏に変える。そして私は、夏期講習にさえ顔を出していればごきげんのお母さんに、やっぱり両親は共稼ぎに限るって、実感する。
例えばその夏期講習で娘がどんなことしてるのかお母さんは全く知らない。まあ、普通はちゃんと勉強してるって思うよね。だからうちのお母さんが特に愚鈍な親ってわけでもないでしょ。ただ私が彼女が思っているより子どもじゃないってだけ。
6時きっかりに目覚ましをセットしている娘が親に秘密を持ってるなんて、いかにも夏休みって感じで、私をわくわくさせる。
ミニーちゃん時計の電子音に跳ね起きて、さささっと服を着替える。今朝は涼しげなワンピース。鏡に映った自分はなかなか悪くない感じ。勢いよく台所に飛び込むと、お父さんとお母さんはもうとっくに出かけたところだ。通勤に随分時間をかけている彼らと、彼らがようやく手に入れたマイホーム。そして2人が丹精込めて育てたふしだらなお姉ちゃん。
いつもだったら私が出かける頃に起きてくるってのに、今日は珍しく私より先に起きていた。麦茶を金魚柄のコップに入れながら、ちょっと顔色悪いみたい。
うじゃじゃじゃじゃ、と、蝉がうるさい中、パジャマ姿のまんま、けだるそうに私を見る。
「ずいぶん早起きね」
「ラジオ体操あるもん」
「健全ね」
そこでお姉ちゃんが、はぁ、とため息をついた。いかにも私は不健全なのよ、という湿気たっぷりのやつ。それは少しだけお姉ちゃん自身を撫でているようにも見えるので、いいことだ、と、私はひとり納得する。
「お姉ちゃんこそ早起きだね」
「んー、生理痛で目が覚めちゃって」
会社休んじゃおっかな。彼女はちっちゃく呟いた。私も半年くらい前に初潮を迎えたけど、幸いにして、お姉ちゃんみたくお腹痛くなったりは、ない。本当に自分は恵まれていると、こういうときに神に感謝したくなっちゃう。
「いっしょにラジオ体操行く?」
あどけなさを装って誘うと、さすがにお姉ちゃんは失笑した。私なんかが行ったら浮いちゃうよ。そう言うと、イブA錠をふたつぶ、麦茶でぐぐぐいと飲み込む。
夏の私はラジオ体操から。朝一番に体を動かすのは、美容によさそうな気がして満更でもない。顔だけ洗って玄関を飛び出すと、まだ昇りきってない太陽だとか、そのくせうるさい蝉だとか、間抜けな鳩の鳴き声だとか、すべてすべて私を祝福してくれているみたい。
ラジオ体操が終わると全速力で家に戻るのは、他の子ども達のように、見たいアニメがあるから、じゃなくて。
ドアを開けるとお姉ちゃんのミュールが出かけたときのまま転がっていた。本当に会社休んだんだ。私は寝直したであろう彼女を起こさないようにそっと洗面所のドアを開けた。
着たばかりのワンピースをさっさと脱ぎ捨てる。だって汗でべとべとになった服なんて用なしだもの。身に付けたものすべて洗濯機に放り込んで、あっという間に全裸になると、風呂場でシャワーを浴びる。シャンプーして洗顔して体も洗って。そういうのが夏の女のたしなみって言うんじゃないのかしら。ね。
それからまた着替えて(今度はキャミソールにカプリパンツ。いかにも夏って感じ)、髪の毛をセットして、ご飯を食べる。歯を磨いたら、ちょうど8時半くらい。その後ちょこちょこっと宿題をやって、気付いたら9時半。だいたいいつもどおりだ。
私はお姉ちゃんのドアをノックした。
「んー……?」
寝ぼけた声に、ドアを開けないまま呼びかけた。お姉ちゃんは自分の部屋に入られるのがあまり好きじゃないらしい。
「お姉ちゃん、夏期講習行ってくるね」
「あぁ、うん……」
まだ寝ぼけているみたいだ。
「帰りは夕方になるから」
「……お昼はー?」
「向こうで食べるよ」
「……私のお昼は?」
「多分、カップラーメンの買い置きがあると思うけど」
「んー……それでいっかー……」
「じゃ、行ってくるね」
「夏になると変質者増えるし、気をつけるんだよー」
のん気なのか、ぎりぎりなのか、よくわからない声。恋する女って大変ね。まるで他人事みたいにそう思って、思った自分がなんだかおかしい。だって、お姉ちゃんより私のほうが、ずっとのん気で、ずっとぎりぎりかもしれないもの。
センセのアパートは今時こんなんあるんだってくらいぼろっちい。壁にへばりついている階段は、一歩一歩踏みしめるたびに子猫の悲鳴みたいな音を立てるし、廊下の隅っこなんて腐食が進みすぎたちっちゃな穴まで開いている。もちろんインターホンなんてしゃれたものはついてないから、私はそっくりかえったように歪んでいる木のドアをそぉっと優しくノックする。
「どうぞー」
センセは私が来る時間をくっきり把握してるから、本当はノックなんていらないのかも。最初の「こつ」だけで、まるで魔法みたいにドアは開かれる。隙間から覗くのは、ふち無し眼鏡に伸びぎみTシャツのセンセの笑顔。
「あかりちゃん、麦茶でいい?」
麦茶でいい、も何も、貧乏学生であるセンセんちの冷蔵庫に、それ以外の飲み物が入っているのを見たことない。だから私は笑顔で頷く。男の優しさとプライドを無下にしないことくらい、小学生の私でも知ってるんだから。
先にちゃぶ台に毛の生えたようなテーブルで待っていると、両手に麦茶のコップを持ったセンセが、畳に腰を下ろしながら微笑む。
「暑かっただろ? 鼻のてっぺんに汗がいっぱい」
「やだ、もう、かっこわるい」
慌ててハンカチを掴もうとする私の手を、センセがぎゅっと握り締めた。ちょっとだけびっくりして彼の瞳を覗き込むと、待って、の色をしている。それに気付いた途端、そうね、まるでくたくたの毛布みたいにおとなしくなっちゃう。次の予感っていつも私を使い込んだ毛布にする。結果、自分が男の人に優しく馴染むということ、ちゃんと知っているから。
だのに、センセのほうは、そんな私を見て我に返っちゃったみたい。何度かまばたきした後、私の手首を、そしてそれをがっちり掴んでいる自分の手を、困惑したように見つめる。
「あーっと……。ごめん。痛いよね、こんな強く掴んだら」
ばかね。何言ってるのよ、この人ってば。
「ううん、大丈夫」
「あ、うん、だったらいいんだけど……」
恐る恐るといった感じで手を離すと、そのまま畳の毛羽をぐじぐじやりだす。信じられない、私の手首の後にそんな無骨なものを触るなんて。でも、私はこの人のこういうところが好きだから、もう、しょうがないんだ。
「で、センセ。汗」
どうしてくれるってわけ? これを。
目を閉じると、つんと鼻を差し出した。彼が本当は何をしようとしてたかは、わかんない。だって私たちは違う人間なんだものね。でも彼がすることはいつだって私の喜びにつながるから、だから、昼寝しているような気分で、ずっと目をつぶりつづけた。どうぞお好きになさっていいのよ? なのに聞こえてくるのは、「えーっと、えーっと」だなんて、もう。童貞クンか、君は。
永遠みたいな数分間。さすがにいらいらしだしたころ、センセはようやく私の鼻に口付けをくれた。
わかってたけど、それでもくすぐったくて、勝手にくすくす笑いが漏れちゃう。
「そんなの舐めたら、しょっぱいんじゃない?」
「うん、そうだね」
センセはめちゃくちゃに照れていた。私よりずっと年上のくせに、私よりずっとうぶなセンセ。愛しさが胸を満杯にする。
「で、今日は、えっと」
「理科だよ、センセ」
「そうだったそうだった」
そう、私は家庭教師と恋愛しちゃっている。小学生のくせにって? やだ、友達で彼氏がいない子なんて、一握りよ。
これはお父さんもお母さんもお姉ちゃんだって知らない、友達にすら言ってない、ふたりだけの秘密。
おねえちゃんが初めて私に自分の恋愛の話をしたとき、本当、今にも飛び上がりそうだったわ。だって、お姉ちゃんとお姉ちゃんの彼氏の年齢差は10。ちょうど私たちと同じだったんだもの。
鏡を睨みつけて乳液をすりこんでいると、ノックもせずにお姉ちゃんが雪崩れ込んできた。自分はちょこっと部屋に入るだけで怒るくせに、勝手なもんだわ。思わずため息。
入ってきた途端、ベッドに身を投げ出して泣き崩れるお姉ちゃん。この人ってば、ここを絶対第2の部屋だと思ってるに違いない。
「サトウさんがサトウさんが」
サトウさんっていうのはお姉ちゃんの恋人だ。
「サトウさんがどうしたの?」
「旅行行くって約束してたのに」
最後の「に」は「ひ」と混ざって、そのまま嗚咽になった。私はすっかり観念して、乳液の蓋をきゅっと閉めた。
「……駄目になっちゃった?」
お姉ちゃんは泣きながら何度も何度も頷く。約束を破られて悲しい気持ち、そりゃ私にもわかるけど、でも事が不倫となっちゃうと、あまり同情できないのが不思議。
「どうして?」
やっぱり世間的に認められてないのって損よねぇ。しみじみそう思いつつ、お姉ちゃんの肩に手を乗せると、それは外敵だらけの小動物みたく震えていた。
「こ、子どもを、ディズニーランド連れてく約束したから、って……」
その日は私とディズニーシー行く約束してたのに。よりによって似たようなとこ行かなくてもいいじゃない。
お姉ちゃんはおいおい泣いて、お盆休み、お父さんにディズニーランド連れて行ってもらう約束をしている私は、困り果てて彼女を見つめた。恋する女って本当、馬鹿もいいとこだ。そりゃ人のことえらそうに言える身分じゃありませんけど。
だけど私、絶対って決めてることがあるのよ、お姉ちゃん。相手がいないところで相手のせいで泣くような、そういう恋だけは、死んでもしない、ってね。
私のため息なんて全く気付かないまま、お姉ちゃんはただ泣き続ける。私はちょっとだけ自棄っぱちっぽくなって、彼女の細っこい肩を撫で続ける。あーあ。どっちが姉でどっちが妹かわかりゃしない。ホント、私たちっていかれてると思うわ。
こういうときってなんでだかセンセを思い出す。私の中のセンセはいつも伸び伸びのTシャツで照れくさそうに笑っている。ああ、もっと格好をぴしっとして、ちょっと自信をつければ、誰もが振り向くいい男なのに。もったいない。
想像にわがままな憤慨をしながら、でも、私の心は勝手に甘い蜜を精製しだす。それは春の蜜蜂よりも自動的で働き者だ。いくら落ち込んでたとしても、悲しかったとしても、蜜はとろとろとろとろ、やがて毛穴から吹き出しちゃうんじゃないか、そんな幸せになっちゃう。
ねえ、そういうものじゃないの? 私の小さな手の平の下で、小さな体を震わせている、
「お姉ちゃん」
私の声に、彼女はきょとんと顔を上げた。毎朝10分くらいかけてアイプチしてる瞼がすっかり元通りで、自然に学生時代の彼女を思い出す。真面目でつまんない女だったけど、今みたいに苦しそうじゃなかったお姉ちゃん。さて、昔と今と、どっちが幸せなのかしら?
「お姉ちゃんは好きな人の幸せが、自分の幸せじゃ、ないの?」
お姉ちゃんはきょとんとしたまま、一重瞼をぱちぱちさせた。
「僕はロリコンだよ」
私とセンセがそういうことになって、しばらくたってからのことだった。いつもみたいに100均のコップに麦茶を淹れながら、ふいにセンセがそんなことを言い出した。何をわかりきったことを。唖然として、彼のよく動く肩甲骨を眺める。
「同年代の女性にまったく興味が湧かない。年上もそう。いつだって目が行くのは、あかりちゃんみたいな若い子ばっかり」
若いってキミ。思わず突っ込みたくなったけれど、それをするにはセンセの声が真剣すぎた。だから私は自分の足をつねって、何も言わないよう、けなげに努力した。
「けどね」
センセが振り返った。両手に握られたコップは彼の額と同じくらいに汗をかいている。
「若かったら誰でもいいってわけじゃない。あかりちゃんがあかりちゃんだから、よかったんだ」
コップの汗がつうっと伝った。私はただ、彼の瞳を見つめた。真っ黒の底に横たわる湖は漣さえ立てていない。なんだろう。喉元がぎゅんとしめつけられる。
「たとえあかりちゃんが、大人になっても、おばあちゃんになっても、好きでいつづけるって、そう思ったから、それで」
ああ、もう、ああ、もう、ああ、もう、この人ってば!
私はたまらず立ち上がると、まだ無駄口を叩こうとするその口をふさぐべく、彼の唇に唇を押し当てた。ファーストキスにしてはちょっと強引すぎたかも。一瞬センセが瞳をぎょっと丸めたのが見えたけど、後は知らない。だって私は目を閉じていたから。
センセの両手のコップが滑り落ちた音がする。裸の足に冷たいしぶきがかかる。それは火照りきった体に優しすぎて、本当に世の中うまくできているって感動する。めでたく空っぽになった手が私の背中に回されたのは、やっぱりうまくできてるってことで。私はますます満足する。
私の可愛いあなた、100の言葉より1のキス、っていうのが世の真理なのよ。
センセの舌がそっと私の唇を割った。私はシェイクを吸うみたいに、それを無心にかわいがってあげた。自分の望むことが相手の望むことでもあることの、ああ、恍惚。
お姉ちゃんは瞼を無理やり持ち上げるのでなく、その分厚い瞼がいいよ、と、言ってくれる男の人に可愛がられるべきだ。そう思うとやっぱり悲しい気持ちになる。大切な家族だもん、もし約束を破られたとしても、次があるわ、と笑う女でいてほしい。
「お姉ちゃんは、好きな人の喜びが、そのまんま、自分のものになったり、しないの?」
そんなの嫌じゃないの?
泣きすぎたせいで真っ赤になっちゃっているお姉ちゃんのほっぺた。小さな吹き出物がひとつ浮いていて。ああ、お姉ちゃんが今しなくちゃいけないのは、会えない日を嘆くんじゃなく、お肌のお手入れをすることなのに。
お姉ちゃんの涙はびっくりしすぎで引っ込んでしまったみたいだった。なんだか複雑な表情で自分の部屋に戻っていく彼女に、私は自分の言葉が過ぎたことを知った。間違ったことを言ったなんて思ってない。ただ、ちょっと、私の秘密に入り込みすぎた。
次の朝が週末であることを呪う。だってそれってお姉ちゃんが家にいるってことだから。もいちど適切な距離をとるには濃密すぎて。
だから次の朝、私はいつまでもベッドでぐずぐずすることになった。ようやく覚悟を決めてダイニングに降りていくと、果たしてお姉ちゃんはお母さんとぺちゃくちゃおしゃべりしていた。つけっぱなしのテレビがファーストフードの夏限定メニューを歌っている。
「おそよう、寝ぼすけ」
機嫌よさそうにさえ見えるお姉ちゃん。ああ、これ知ってる。躁って言うんだよね。どかーんと落ち込んだ後にそうなるか、この後またどかーんと落ち込むか。お姉ちゃんのいつものやつだ。
「今日は夏期講習とやらはないわけ?」
これにはお母さんが答える。
「お休みの日くらい、勉強もお休みさせてやってよ」
なまいきね、どうせ夏休みなんてずーっと休みじゃない。不満げなお姉ちゃんと、週5日もデートしてたら、さすがに充分よ、と、お腹の中だけで答える私。見た目だけは全く平和な夏のだんらん。
「お父さんは?」
「さあ……またパチンコなんじゃない?」
お腹すいたら帰ってくるでしょ。お母さんのため息。お姉ちゃんは知らん顔でテレビに夢中になっている。本当は心の半分くらいサトウさんと絶望なんだよね、お姉ちゃん。
「やだ、気持ち悪い!」
そのお姉ちゃんが急に素っ頓狂な声を上げたのに、私はやれやれ、と心の中だけで肩をすくめた。
「いったい何」
ほら、お母さんも呆れてる。
「変質者みたい、ほら」
お姉ちゃんが指差した向こうは、テレビがお昼前のニュースを流しているところだ。さすがに寝坊しすぎたな、と、ぼんやり思う。
「やあねえ、夏って気味悪い事件が増えるから」
年の功なのか、のんびり答えたお母さんも、次の瞬間目を丸くした。
「やだ、うちの近所じゃない。これ」
3分に1回は「噛む」地方局の女性アナウンサー(美人なのかそうでないのかよくわからない)が、それなりに真剣な顔でニュースを伝えている。何やら、隣町の山奥で真っ裸にされた小学生が保護されたそうだ。私はふーん、と思った。ふーん。
「あかりも気をつけるのよ」
お母さんが妙にそわそわしながら私を見やる。
「夏期講習の帰りとか。もっと早い時間に帰してもらえるよう、先生に頼もうかしら」
「送ってきてもらえばいいじゃない、あの大学生クンに」
お姉ちゃんがテレビから目を離さずに答える。あら、お姉ちゃんにしては、いい考えじゃない。これで胸を張ってセンセと外でデートできる。
「あ、でもそんなことしたら」
お母さんはまだそわそわしながら、お姉ちゃんをすがりつくように見る。何がそんなに心配なのだろう。最悪のことってあまり起こらないから最悪なのに。
「下手したら、先生が変質者扱いされちゃうんじゃないかしら。近所でこんな事件があったばっかりだし」
へんしつしゃ。そうか、へんしつしゃ。瞬時にそんな汚らわしいものとは正反対の場所にいるセンセの笑顔が浮かんだ。相変わらずくたびれたTシャツで、眼鏡とほっぺたをぴかぴか光らせて、笑っている。そう、健全と純粋を辞書で引いたら、凡例で登場しちゃいそうな青年がそこにいる。そりゃ、中身はとっても変態だけど、それがますます私の芯を濡らすというのに。
お姉ちゃんが緩く笑いながら、何か言おうとしたときだった。
「大丈夫だよ」
たまらず声を上げている私がいた。パジャマの裾を無意識のうちに、ぎゅう、と、掴んでしまう。
「あんな善良な青年をそんなふうに思う人がいたら、その人のほうが悪人だよ」
こら、失礼な言い方して。お母さんは怒り、お姉ちゃんは、善良、わはははは、と笑った。ちょっと馬鹿にした感じだったけど、このくらい油断しておいてくれてちょうどいい。そもそもあの人の素敵さは私だけのものだし。
周りなんて知ったことか。お腹がぐつぐつするほどにそう思う。だって私たちは本当に愛し合ってる。歳の差なんて関係ないのは当たり前。あとたったの10年で普通のカップルに成り果てる私たちにとって、それは笑い話でしかない。もし私が幼すぎると言う馬鹿がいたら、そんなことで不確かになるようだったら、それはそもそも愛じゃない、くそったれだと答えてやるんだ。
元々わかっていたことじゃない。言いたい人には言わせておこう。少なくとも私は知ってる。私たちが生半可じゃないってこと。それで恋には充分のはず。そう、私は今、晴れてセンセと外でデートする権利を獲得したのよ。それって喜ばしいことじゃない。
それなのに。
今年の夏休みはとても楽しくてとても充実していて、きっと私のこれからの人生を合わせても、1、2を争う素敵っぷりだったろうって断言しちゃえるほどだ。ディズニーランドにも行けたし、半年ぶりのおじいちゃんは「お母さんに内緒だよ」とちょっぴり多めのお小遣いをくれた(それで、ずっと欲しかった口紅をついに手に入れた!)。本当は海外くらい行きたかったけど、住宅ローンに苦しむ両親を見てたら、これでもう充分すぎるくらいでしょ。ホント、満足してる。
けっこう要領のいい私は、宿題を溜め込むこともなく、いくら今日が31日だって、まったくのんびりしたものだ。そりゃ去り行く夏休みは胸をきゅんきゅんさせるけど、でも私は学校だってそんな嫌いじゃない。鼻歌まじりに乳液をはたいて、級友たちとの再会に備えているときだった。
「ただいま」
絶対この人、自分の部屋がふたつあると思ってるわ。私は何度目かの確信をしながら、ノックもせずに入ってきたお姉ちゃんをため息交じりで見上げた。
「おかえんなさい」
お姉ちゃんはどうやら酔っ払っているみたい。真っ赤なほっぺたで、るんるん言いながら、ベッドにどっかり座る。
「どうよ最近」
「どうよもなにも、明日から学校だよ」
「あ、そっかそっかー。忘れてた。あはは、ざまあみろ」
笑い声と一緒にお酒の匂いがぷうんと漂う。
「ざまあみろって?」
「長い長いお休みが終わるんでしょ? だから『ざまあみろ』」
「……長かったのかな?」
「ばかね、社会人になったら、連続1ヶ月半なんてお休みないよ」
無職になる以外ね。最後の一言だけ妙にしおらしく呟くと、お姉ちゃんは、ばふっとベッドに転がった。
別れた。
どさくさまぎれみたいなその台詞は、お布団の音に消え入りそうなほど弱々しいくせに、私から言葉を失わせる力を持っていた。なるだけ音を立てないように乳液の蓋を閉じて、そっと振り返ったけれど、お姉ちゃんは顔の前でしっかり両腕を交差させている。
ぽかりと開いた沈黙が苦しくって、私はおずおず言葉を落としてみた。
「……そう」
どうして? と聞くこともできたけれど、理由はわかっている気もした。私が彼女に感じていたことのひとつひとつが全て折り重なったものが、きっと。
「もう、会社行きづらいなあ。よりによって同じ部署だよ」
返ってきた声は笑っていたけれど、肝心の顔が見えない。腕を頭に巻きつけたまま、やめちゃおっかな、彼女は呟く。この世の悲愴を全身であらわしているようなお姉ちゃん。彼女の悲しみが空気を伝って、私の中の悲しみまで震わせようとする。その震えを握りこぶしにぎゅっとしまいこんで、私は彼女を見つめた。
「お姉ちゃんが本当に望むんだったら、やめてもいいんじゃない?」
お姉ちゃんは無言だった。
「だって、私たちって、まだ、嫌になるくらい若いもの」
そう、私たちは好きな人を失ったあとも、まだまだ生き続けなくちゃいけないんだ。死ぬまでずっと彼をこびりつかせているには、絶望するほど若すぎる私たち。泣けちゃうくらいに長い人生。
「……あんたもなの?」
腕のせいでくぐもってしまっているお姉ちゃんの声は、そのせいなのか、何割か増しで優しく響く。
「あんたも、好きな人と別れたの?」
ふんわりと壁に反響するその声。やだ、と思う。優しいお姉ちゃんなんて嫌だ。勘のいいお姉ちゃんも嫌だ。……珍しすぎて涙が出そうになるじゃない。
だって私は好きな男のせいで泣くのは、好きな男の前だけって決めてるのよ。
お姉ちゃんが、ストッキングの両足で反動をつけたと思うと、勢いよく立ち上がった。意外にも彼女は泣いてなくて、その代わり何かが抜け落ちたような瞳をしていた。それはあまりにも空虚すぎるせいで吸い込まれそうな美しさがある。けっこう図太かったんじゃない、それならすぐに次の男が見つかるよ。思わず頬を緩ませたら、お姉ちゃんはそんな私をいきなり抱きしめた。めちゃくちゃ驚いた。
「……ばかね、何泣いてるのよ小学生」
お姉ちゃんの細い体が温かい。あぁ、私、泣いちゃってたんだ。絶対泣かないって決めてたのに、悔しいな、せっかくずっと我慢してたのに。自分が泣いていることに気付いた途端、縛り付けていた何かがさらさらと落ちていった。私の決意って、けっこう脆かったみたい。もう無理だった。大声で泣かずにはいられなかった。だから私は素直に泣くことにした。
堪らずお姉ちゃんの背中を掴むと、彼女の腕がぎゅっと応える。それはついこの間までセンセの役割だった。肌触り、体温、匂い、全部そのまま思い出せるのに、あれはもう2度と私には起こらないことだなんて、どうしても信じられない。意味がわからない。
お姉ちゃんの腕では柔らかすぎる。お姉ちゃんの背中では薄すぎる。お姉ちゃんの匂いでは甘すぎる。センセはもっとしなやかで強くてちょっとだけしょっぱくって。
こうやって抱き合った後には必ずそぉっと口付けされる。最初は触れているだけのキスだけど、それじゃふたりは止まらない。やがて彼の舌が押し入ってくるとき、私はそれを他でもない自分が望んでいたことに気付く。ふたつの望みがひとつになる瞬間。その快感。脳が真っ白にスパークする。そしてただただお互いを求め合っているうちに、自然と私はアイスクリームみたいにとろけて、膝がやわやわと崩れ落ちてしまう。そんな私にセンセはまるで使い込んだタオルケットのように覆い被さってくる。
でもそれもこれも、もう「ないこと」だなんて。
「泣かないの。悔しいでしょ?」
お姉ちゃんの手がぽんぽんと背中を叩く。それが嬉しくて悲しくて、ますます声を上げてすがりつくと、センセの代わりにオードトワレの香りが、私を柔らかく包み込む。
最悪なことって、あまり起こらないから「最」も「悪」いことになる。もしかすると既に自分の爪先1センチで息を潜めてるかもしれないのに、あまりにも遠く感じるそれらたち。
テレビがわざわざ教えてくれた、夏休み中の小学生に起こった「いたたまれない」ニュース。それで、気付いた。気付いてしまった。お母さんにとって、社会にとって、私は愛し愛される幸福の存在なんかじゃなく、全裸で山奥に捨てられた哀れな小学生だということを。
もしそうだとしたら、それはまぎれもなく「最悪」だ。私も若いけれど、センセだって、まだ充分若い。そしていくら自ら服を脱ぎ捨てたと主張しても決して認めないだろう世間たち。
だとしたら、誰よりも悲しい目にあうのは、センセだ。
中途半端に成人だけして、そのくせ死ぬには時間が余りすぎて。その間ずっとずっと変質者と蔑まれて生きていかないとしたら? どうして愛する人にそんな思いをさせられるだろう。私にはとてもできない。自分の快楽のためだけに、センセをつなぎとめておくだなんて。
あの後1度だけセンセに家まで送ってもらった。そしてそれがふたりの最後の日だった。街角のショウウィンドウに映ったふたりは、変質者とその被害者に見えない代わり、恋人同士にも見えなくて。私はセンセに気付かれないよう、少しだけ泣いた。
「センセ?」
純朴な家庭教師の青年は、こまっしゃくれた小学生に呼ばれて、うん? と微笑む。
「私、センセに惚れちゃったみたいなんだけど、どうしよう」
センセは困ったように笑って、何を言ってるんだい、と答えた。さあ、ふざけてないで、勉強しよう、勉強。
「実は僕もあかりちゃんのことがずっと好きだったんだけど、でも、どうしようもないよね」
何日か後にひどく悲しげな笑顔で告白した彼の背を押したのは、誰でもない、私だ。どうしようもなくなんて、ない。どうして愛し合ってるのに遠慮しなくちゃいけないの? 私は初めて彼の前で泣いてみせた。だから私が責任をとらなきゃいけない。それが小学生にだってわかる世の真理なのだから。
「前にも言ったと思うけど」
彼はひどく難しい顔をしていた。
「僕は10年後も20年後も、お互いヨボヨボになっちゃっても、あかりちゃんのことを好きでい続けると思うんだ」
「……私もよ」
「だから、今、いったん離れ離れになることくらい、なんでもないって、心からそう思ってる」
もしかすると、あかりちゃんのほうはすぐに新しい恋人できちゃうかもしれないけどね。だってあかりちゃん可愛いし。
そんなふざけたことを言うセンセを黙らせるべく、私は無言で唇を押し当てた。いつもだったらやがて舌が入ってくるのに、この時はふっと唇を離され、その代わりに全力で抱き締められた。
センセの熱い息が首筋をくすぐっている。センセの鼓動が触れ合っているところ全てから伝わってくる。いっそふたりがひとりになってしまえばいい。そう思いながら、私も全力でそれに応えた。
それがふたりの夏休みのおしまい、だった。
「私たちさぁ」
夜の部屋、センセの気配のない部屋、私の頭だの肩だの、むやみやたらに叩きながら、お姉ちゃんが殊更に元気な声を出す。
「けっこういい女だし、性格だってまあまあだし、きっとすぐに、もっといい彼氏ができるって、そう思わない?」
泣きじゃっくりを必死でこらえながらお姉ちゃんを見上げると、瞼にはくっきり線が入っているし、ほっぺたはつるつるだしで。私は自分が泣いてたのも忘れて、吹き出しちゃった。もう、この人ってば本当にゲンキンなんだから。時々、小学生の私でさえあっけにとられちゃうほどにね。
だから私言ってやったの。
「そもそも別れたからって、その恋が終わっちゃうわけでもないしね」
するとお姉ちゃんは、まるでさくらんぼを種ごと飲み込んじゃったような顔をして、ため息をついた。
「あんたって、本当、小学生のくせにナマイキね」
|