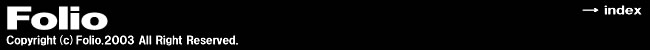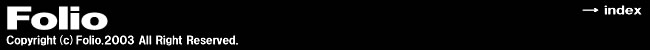|
「あの頃は、大変だったなぁ」
彼はことある度に過去の話を持ち出す。まだ私たちが出会う前のことを。
二人何も話すことがなくなると彼はセブンスターに火をつけて、時々咳込みながら、遠い目をしながら紫煙の中で過去を想起する。
出会った当初は彼の全てが知りたくて、私が知らない彼の過去のことまで興味があった。しかし二人の間に少しでも会話の空間が空いてしまうと彼はすかさずその隙間に彼自身の過去の話を埋めようとするので、もう彼の過去のことは知らないことはないくらい知ってしまったし、同じ内容を繰り返し話すので今となっては少し興醒めしてしまった。
それでも彼は、―――私には遠い目で話しているように見えるのだけど―――彼は、その「過去」が鮮明に、その光景が現に目前に広がっているように、時々目を細めたり、眉間に皺を寄せたり、楽しいとも悲しいともとれない表情をしたりする。
「あの頃は、大変だったなぁ」
再び彼は呟く。私は彼に気付かれないように小さな溜息を吐く。自分ばかり大変だったようなことを言うけど私にだって辛い過去の一つや二つ、いや、女には女にしか理解できない辛い過去が山ほどある。ただ男は自分の話さえすればそれでよくて、話相手がその(大したことない)自尊心を認めてくれさえすれば、万事満足するという自己完結の世界で生きている。彼と一緒になって、もう長い月日が経ったけれど、彼は付き合った当初と全く変わらない表情で、我が家の台風被害を自慢する子供のように無邪気に「過去」の不幸を話し出す。
「あの頃は、大変だったなぁ」
彼は身体に悪いという理由でエアコンを嫌うので、扇風機が弱々しく首を振っているこの部屋は窓という窓が全て開け放たれ、一年中ぶら下がっている風鈴が気が向いたときに小さく揺れる。何十匹ものミンミン蝉が我が声を互いに争っている。彼は相変わらずここではないどこかを目前に広げ、その世界の中に立っている。額から汗が一筋流れて首を伝い、私の胸の中に浸透していく。
彼が言う「大変だった」頃、私はまだ学生だった。学生といっても今の女子高生みたいに外人のように髪の毛を染めて道路の隅にしゃがんでいるような学生ではなかった。私の家は当時の事情で父も兄もいなかったので、学校が終わるとすぐに家に戻り、家事を手伝っていた。あの頃まだ五歳だった妹の手を引いて買い物に出掛けていた。新しい洋服を買うお金もなくて、明日食べるお弁当のおかずをどう工面するかということばかり考えていた。
「あの頃は、大変だったなぁ」
彼はしばらく天井を眺めながら過去の追憶に耽っていたが、近所の犬の鳴き声で我に返り、再び同じ言葉を口にした。天井を眺めたままで。左手にセブンスターを持ったままで。私も彼と同じ天井を眺めている。ミンミン蝉が鳴いている。風鈴が小さな音を立てる。小さな棚の上に乗っているラジオが午後十二時を知らせる。
「今日は、何日だ?」
蝉の鳴き声が止み、十二時のサイレンに呼応する犬の遠吠えだけが響く中、彼はセブンスターを揉み消して私に話し掛ける。
「八月、十五日です」
私は天井を眺めたまま呟いた。このベッドの上で寝たきりになってから、今年で五度目の夏を迎える。五度目の八月十五日を迎える。
「あれから五十八年経ったのかぁ」
彼は様々な想いを凝縮させた吐息と共に小さく呟く。『鐘の音と共に黙祷を始めます』私が身体を壊して寝たきりになったときに彼が買ってくれたラジオからアナウンサーの厳粛な声が聞こえる。
「あの頃は、大変だったわね」
私たち二人はそっと目を閉じた。水を打ったように静かになった庭のミンミン蝉も、今はそっと目を閉じているのだろう。
|