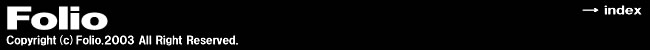|
じわわわという濁った声を頭上に聴く。街から撤去され殺伐とした構内に積み上げられた電柱群の頂点に、ただ一匹の蝉がいた。僕の担当する地区に残った最後の電柱たちの墓場だ。
その孤独な蝉の祖先たちが交尾の権利を無数に争っていた時代──彼にすれば5世代前の昔、折り重なる夏の騒音を耳にしていたのは浴衣を身に付けた20代の女で、彼女は自ら直輸入の手続きを踏んだヨーロッパ製の小さな車の中にいた。普段は無造作に梳いたままの髪を綺麗に纏め、今日の自分は最高にイカしている、そう信じていた。
彼女が道ゆく一人の少女に声を掛けたのは、そんな余裕が生んだお節介と好奇心がピークに達していたからで、いくぶん幻想的な暗示のように思えるのとは何の関係もない。数年後にコンクリートの柱に衝突してこの世を去る彼女は、白んだ朱色の着物を着てとぼとぼと歩く少女のことを軽い熱中症、もしくは脱水症状を起こしかけているのではないかと案じた。それが無用な心配に過ぎぬことは、少女が無事に成長し、自分の意志とは裏腹に電柱の撤去を生業とする──そんな冴えぬ男と恋に落ちる事実からも明らかだ。
「蝉か! 久しぶりじゃねえかオイ。ヤれる女もいるまいによう」 知らぬ間に僕の脇に立っていた主任が言った。僕は気のない返事をして、この作業が終わったらどの現場に回されるのだろう、今度こそ解体撤去ではなく建設構築の仕事をしたい、そんなことをぼんやりと考えていた。
「この蝉も付けてやりゃあ、今度の話にゃバッチリの小道具になんじゃねえか?」
「何の話ですか?」
「電柱一本買い取りたいって女が来てんだよ。何だよその顔。可愛かったぜ。インなんとか映画とか何とかに使うんだと。おまえ段取りつけてやれよ」
正直面倒だった。電柱を買う? 気狂いとしか思えない。そんなもの田舎に行けばいくらでも残ってるじゃないか。何より金をかけないのが自主制作ってもんじゃないのか。
西日と冷気空調が激しく鬩ぎ合いながら辛うじて常温が保たれた部屋の中、彼女は幾種ものケーブルが伸びるパソコンに向かって編集作業を繰り返しながら、僕の車の中に流れていたバンドの名前を再度尋ねた。僕の返答──スロッビング・グリスルというバンド名について、今度は何の意味かと問う。意味など考えたこともなかったし、興味もなかった。
「調べりゃ分かるんじゃねえの?」
彼女はそれに応えることなく、あの時耳にしたのは間違いなくそのバンドの音だったと主張した。それは彼女の少女時代の出来事で、近所を歩く最中、一人の女性から声を掛けられたという。交わした会話に覚えはなく、女の車の中からは僕のいうバンド、スロッビング・グリスルが流れていたらしい。そして女は忽然と姿を消し、彼女は道路の先に揺らぐ蜃気楼だけを覚えていた。短い映画で彼女が再現しようとしてるのは、そんな情景だ。彼女は世の中に発生する偶然の出来事を、何かしら縁のような不思議な事象として、なおかつ理知的に捉えようする。それでも自分のフィルムに訴えたい内容など無いに等しく、他人に伝えたいことなど自らもよく分かっていないのだった。彼女は言った。
「夏っぽいじゃん。こういうの」
自分の名前がクレジットされた画面を見詰めている。記録した映像を吐き出しているハードディスクがキリキリと音を立て、奇妙にザラついた映像処理の施された彼女の横顔が映る。その横顔の持ち主は別の男の子供を身篭っているのが分かったのちも僕と過ごす事を選んだが、僕は寸断なく続く胸の動悸や吐き気に勝てなかった。
かつて僕に名刺を差し出した時と同じ顔、同じ髪型の彼女が画面を横切って行く。あの時、彼女に向かって作業着姿の僕は言った。「蝉付きでどうすか?100万円」 彼女はそんな軽口に微笑むことなく、真剣な面持ちで蝉を見上げた。僕はその視線の先を追わず、しばし彼女の薄い瞼に見入った。蝉はあっけなく地面に落ち、断末魔の叫びを数度上げたが、それっきりだった。
|