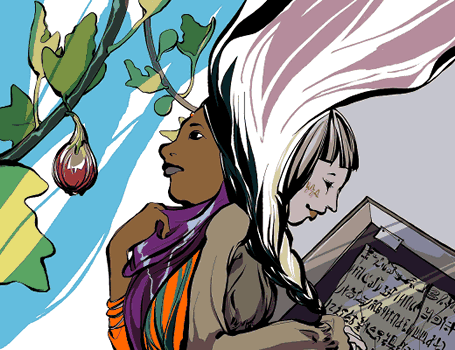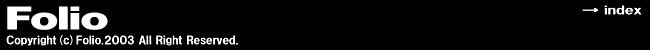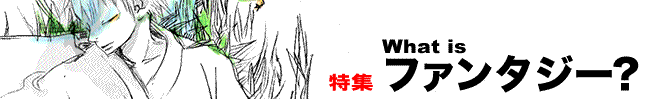彼はおそらく、若者だったのだろう。溢れる情熱を抑えることは出来ず、さりとて、その情熱に突き動かされて行動するだけの勇気は無い、控えめで、恥ずかしがりやの若者だ。
そして、神々に与えられたと言い伝えられる神聖な文字を私事に使えるほどに恐れを知らず、自由な感性を持ち、一般人には手が出せない程度に高価なパピルスを戯れに使うことの出来た裕福なお坊ちゃま。
彼の心を、それほどまでに繋ぎとめた「愛しい妹」は、一体、どんな女性だったのだろう。
同じ村の幼馴染? 旅芸人、はたまた思い届かぬ深窓の令嬢であったのか?
まさか、すでに人妻ということはあるまい――人妻であったなら、その恋は、相手の夫が死亡するか、彼女自身が離婚申し立てをしない限り、実らなかったことになる。
どんな相手を想うにしろ、詮索好きの、近所のおばさんに知れたら大事だ。恋をするならひそやかに、そう、逢引きは夕暮れのイチジクの樹の下で…この樹は、愛の女神ハトホルのお気に入りの樹だから、きっと二人の関係はうまくいくだろう。
彼は、想像だにしなかったに違いない。
それが人の一生をゆうに越える長い歳月ののち、人々の目に留まることを。
戯れに書いたその恋歌が、彼自身の若い想い出とともに、一個の人間に想像しうる限りの「永遠」にも近い、三千年もの歳月を越えてゆくことを。
ヘヌトラー、君は結局、その思いを口に出して恋人に伝えられたのか?
恋人は、それに対しどう答えたのか?
「彼」も「恋人」も、今はもちろん、この世にはいない。二人は三千年の遠い昔に生きて、私が生まれるより三千年早く居なくなってしまったのだから。
…それらは、今となっては、もはや知る由もないことである。
この恋歌は、考古学者たちによって掘り出されたあと、1954年、イギリスの考古学者A.ガーディナーの弟子によって英訳され、発刊された。日本語での翻訳が出版されたのは、それから20年あまりを経たのちのことだ。
わが妹の愛は向こう側にあり、その間には水流あり
しかも州に鰐がいる、
だけどわたしは水に入っていって流れを渡る。
わたしの心は水嵩の中でたくましくなり、
波はわたしの足には大地のよう。
くちづけして彼女の唇ほころべば、
ビールはなくとも心たのし。
寝床をととのえる時がくれば、召使よ、わたしはおまえに言う。
彼女の手足に上等な亜麻をかけ、
豪奢な亜麻布で彼女のための寝床をしつらえ、
飾りのついた白亜麻布に気をつけよ。極上の油を注ぎかけよ。
彼女のあとについていく、
彼女がわたしであったなら。
ああ、嬉しいことに、そのときは、いろんな彼女の姿が見られるものを。
いま、古代社会に大いなる恵みを運んだ大河ナイルは、上流に出来たアスワン・ハイ・ダムとアスワン・ダムの二基によって完全に塞き止められ、かつての一年周期で繰り返された増水も、澄んだ流れも失って、ただ死んだように流れるのみである。
鰐や河馬も、砂漠を駆けたライオンもいつしか居なくなり、エジプトビールの系譜は途絶えて、今では観光客用の薄い酒が用意されているだけの禁酒イスラム教国である。
かつて、あれほど頻繁に書かれた古代エジプト文字も、イスラム支配の紀元七世紀の禁止以降、急速に消滅していった。
永遠と思われたものが失われ、永遠と謳われたものが消え去るほどの長い時間が流れた。
だが、その時を越えて色あせない、これから更に未来へと受け継がれてゆく想いは存在する。
それは――永遠とは程遠く、ごく、僅かな時間だけ生きることを許された人間の作り出す、この国の奇跡なのだ。
「ついたよ」
いつしか車の中でウトウトしかかっていた私を揺り起こしたのは、日焼けした、モハメッドの大きな手だった。起き上がるとすぐ、目の前を通り過ぎていくロバの背が見えた。
現代の利器、自動車が行き交う中を、古代から変わらぬ移動手段が闊歩する。
この国は、今でも古代と現代という遥かに離れた時が自由に交差している。私はニヤリと笑って、埃っぽいモハメッドの車の後部座席から降りた。
そこはモカッタムの丘の上だった。カイロ国際空港を出て、すぐに南へ折れた先、スエズ運河へと続くハイウェイから少し逸れた岸壁の上からは、ナイルの流れが一望できる。河のほぼ向かい側、僅かに南に逸れた方向の高台には、かの有名な三大ピラミッドが、砂煙に霞みながら鎮座している。
「本当に、こんな辺鄙な場所で良かったのかい」
「うん、いい眺めじゃない。何しろ、ピラミッドより高い場所なんだから」私が言うと、ムハンマドはジョークと受け取ったらしく、白い歯を見せて豪快に笑った。黒々とした髭が口元に踊った。
モハメッドは年寄りの現代エジプト人ガイドだし、古代のことは何も知らない。イスラム社会の一部である、現代エジプトに生きる人々は、祖先たちの偉業などまるで気にしていないのだ。
その彼にとって、東洋人の私は、妹よりももっと若い年齢に見え、古代人と同じくらい、遠い世界の人間に映っているだろう。
私は今、恋をしている。
時空の入り混じるこの国に、時おり垣間見せる古代のままの姿に、或いは古代の人々が今に残した色あせない遺産に、そして、かつてこの大地に生きた人々に。
或いは――
魅惑的な歌をくれた三千年前の青年、ヘヌトラーに。
かれらはみずからのために鉄の墓石でもって、金属のピラミッドを建てることはしなかった
自身の名を知らしてくれる子孫である後継者をのこす方法も知らないで、
かれらは書き物の中に、そして自ら編纂した叡智の書の中に自身の後継者をつくったのだった
墓石はほこりに覆われ、墓所は忘れ去られてしまう
しかし彼らの名は彼らの手になった本ゆえに、
それらの本が立派である限り、
つねに人々の唇にのぼる。
それを創った人々の思い出は永遠に続く。
彼らは死んでしまい、名は忘れ去られてしまっても、なお書き物はかれらを記憶させておく。
それは、今から三千年ほど前の物語だ。
彼は今、筆記具を片手に家を出るところだ。家には母親と妹が二人。荘園を持つ裕福な家の長男で、いずれは家を継ぐことになっている。年は十五になる。…ちょうど成人の年だ。男は独立したら、すぐに妻を娶るのが普通だった。彼が自由に恋を探していられる猶予は、あと数年しか無かった。
「出かけてくるよ」入り口に近い場所にある台所で、昼用のチャイを作っている母に声をかけ、若者ヘヌトラーは足早に家を出て行く。
「ちょっと、どこ行くの? あんたの分まで用意しようと思ってたのに…」
「神殿に用があるんだ。すぐ戻るから、お昼は家で食べるよ」彼の村は、川を挟んで太陽神殿のちょうど対岸のあたりに在る。朝早い日差しが澄み切った空の下、春の大地を照らし、芽生えたばかりの若い作物が、いずれ彼の継ぐ荘園を、豊かな緑で覆っている。
誰かに呼び止められる前に、河べりの、いつもの場所に潜り込みたかった。
涼しい木陰を作るシカモア・イチジクの樹の根元、少し地面がくぼんでいて、座れば遠目には、そこに人がいるとは思われない。ちょうどいい隠れ場所なのだった。
そこは彼の所定の席で、一人でいるには調度良かった。学校をさぼるとき、もっと幼い日には母親に叱られて、そこで一日を過ごしたこともある。
だが、今日は違っていた。
いつものように訪れたその場所には、いつもは居ない先客がいた。
「あ…」目を上げ、驚きもせずに彼を見つめる少女は、洗い晒した白い亜麻布を纏っていた。細い首には、小さな赤いビーズを繋いだ首飾りをつけている。それ以外に装飾品は一切無く、硬く編んだ長い髪が、項から背中にかけてゆったりと流れていた。
どちらからともなく笑みが零れる。
「となり、座る?」少女の問いかけに、彼はぎこちなく、頷く。ほんのこぶし一つほどの間を空けて腰を下ろした彼の鼻に、少女が髪に染み込ませた、香油の良い香りがふわりと香った。
「……。」
「……。」
その一時、二人の間には、河も、鰐も無く、ほんの一瞬の時間さえ、永遠と感じられたに違いない。
了
[参考]翻訳出典
「筑摩世界文学大系1 古代オリエント集」杉勇・三笠宮祟仁 編訳原文 R.A.Caminos,Lata Egyptian
Miscellanies,1937,Brussels
※この物語は半分フィクションです。神官文字による恋歌は実在しますが、中身以外は想像に過ぎません |
|