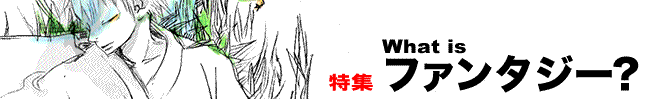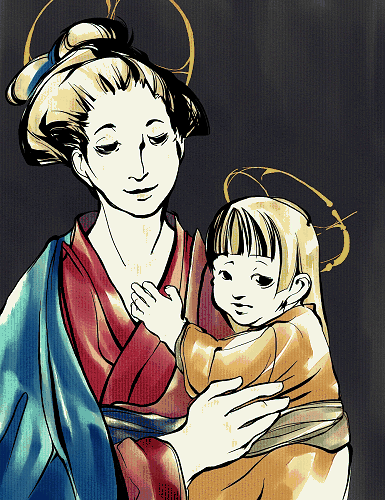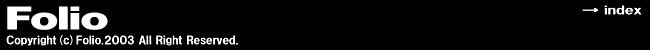それを彼が作り始めたのは何時のことだったのだろう。私が不意に気がついた時には石は人の腰の辺りまで積み上げられていて、長さは三十間に及んでいた。村の誰もが胎蔵を無視し始めてからどれほどの年月が経過していたのか不明だが、彼は人知れず石を積んでいた。
奉公で姿を見る以外では、酒屋で時たま胎蔵の姿を見たが、やはりずっと黙ったままでちびちびと酒を口にして、勘定だけを置いて去ってゆくのが常だった。彼の家に遊びにゆくような親しい友人なども居なく、村から離れた荒れ野の側にひとりで住んでいた。
私はその日、気晴らしに散策をしていた。馬を駆り、人道から外れた小道に分け入り、のんびりとした小春日和の木々の中をゆっくりと進んでいた。
山男が通るような狭い間道にぶち辺って、それでも頻繁に人が通っている形跡があったので私は追跡してみる気になった。くねくねと折り曲がった、緩慢だが起伏のある山道で、やがて馬を引く程に傾斜が厳しくなり、やがて、広場に出た。
その山あいの広場は何故か平坦で現実離れして石ころだらけだった。
ふとみると、木立のなかに人家のようなものが見えた。
近付くとおかしな垣根があり、酷く警戒した様子で私を見て、やがてもじもじと身体をくねらせた男は、私の屋敷で働く胎蔵だった。
「これはなんだ? こんな場所に住んでいるのか」
私が尋ねると彼は首を上下させた。
小屋の周囲を囲む石垣を指して私は、なんだと訊いた。胎蔵は酷く緊張した表情で答えた。
「へい。これはあっしの夢なのです」
彼の口から声がでるのをはじめて聞いた気がした。確かに、長い間、誰かと話している様子を見たことはない。村の集まりにも常に黙したままで、ただぼんやりと人々の様子を見ているという態度で通っていたので、誰も彼は言葉を失ってしまったのだと考えていた。実際、私もそう思っていた。
「夢? いったい何の?」
彼は地面を見ながら首を振った。再び押し黙り、また足下に置いた石に手を伸ばした。
私は次の言葉を待った。だが、彼は再び声を出そうとはせずに、頭を下げてひとつ石を拾い、石垣の一番上に置いて、会釈の後小屋に入った。
「全く気持ち悪いったら、ありゃしません」
と私の妻は胎蔵を評した。私は顛末を打ち明けたのだった。
「あいつは神(かん)結びの時にも御柱の側に、こそこそとこそと塩を置いてゆくので、みんな恐がって近付くと避けて通んですよ」
村の祭りのことだった。私はトキの膝を撫でながら、20年来胎蔵は村から忘れられた存在だったのだと気がついた。実際に奉公に来ても黙したままだった。妻と娘を連れて矢崎の崖の祠にお参りに行った時に、娘が足を滑らせて崖から落ち、それを見た胎蔵の妻は崖から飛び降りて死んだ。
「確か胎蔵一家と一緒にホコ吉のうちも一緒に行っていたはずです。そのうちに胎蔵が喋らなくなってから、誰もあの男と仲が良いものなど居なくなったのですわ」
確か、矢崎の崖に手摺りが付いたのはその事件以降だった。
かく言う妻も私も20年前はまったくの子供だった。
「これ! ハル!」
娘のハルが火鉢をかき混ぜて遊んでいるのを咎め、妻はハルの手を叩いた。
「なあ、どうして子供の後を追って飛び降りたのだろう」
トキは娘の手を擦りながら白々とした目で「あなたも母親になれば分かります」といった。そういわれてしまっては私はどうすることもできないのだ。
母と子の繋がりなど私には分かるべくもない。私がもしその母親の立場であれば何をするだろう? 私はしばし考えて、沈黙をする。
「石を積んでどうするんだ」
私の中で胎蔵の石垣は気になり続けた。
だが、積極的には胎蔵の住まいを訪れることはなかった。
時々屋敷で彼の姿を目にしたが、私は敢えて近付こうとはしなかった。下男としては寡黙にしてよく働くのだから、特別な苦情も文句もない。
再び胎蔵の住まいを訪れた時には半年が経過していた。私は石垣がかなりの高さに積まれているのに驚き、胎蔵はこけの一念でこの石垣を作っていたのかと驚いた。
「これは、城か?」
胎蔵は首を振った。「じゃあ、なんだよ」
「夢です」
私は呆れて聞き返した。
「ただ夢だ、って言うンじゃあ分かんねえ」
胎蔵は再び石に手を伸ばして、仕事を続けながら「寝てる間、ずっとわしの夢にこういうのがでてくるのです」と答えた。
「それで作っているっていう訳か?」
「はい」
「その夢というのは、このような石垣なのか」
「幾分かは違います。どうしようもないです」
それだけ答えると、もう私がそこにいるということさえ忘れてしまったかのように胎蔵は仕事を続けた。
「もし俺が誰かに言って、これを壊されたらどうする?」
意地悪な気分で私はいった。
胎蔵は顔を上げて「官兵衛さんがどうしようとも、私はこれを作るだけです」
「じゃあ、言うぞ」
「お好きになさってくださって結構です」
胎蔵は慇懃無礼に答えた。だから私はそうした。
村の集まりの後、酒場で酔った時に若い衆に口走り、じゃあ、今から行ってこようと決まって、若い衆と共に胎蔵の小屋に走り、そして彼らが石垣を崩すのを眺めた。
胎蔵は小屋からでてきて泣きながら彼らを押し止めようと必死だったが、若い衆に殴られて蹲った。石垣は跡形もなく崩された。そうなると、きっと長い年月をかけたであろう胎蔵の石垣はただの石の堆積に過ぎなかった。
胎蔵と目が合った。虚空を見詰めるような目で私を見た。私は目を逸らした。
それから私は胎蔵に対して居心地の悪い思いをした。
彼が村人から、これまで以上に非難され苛められてゆくのを苦々しい思いで見ていた。彼の石垣がまた壊された、と噂話で聞くたび私の胸がちくりと痛んだ。
だが、やがて人々は忘却する。私もさほど苦にならないようになり、人々の口に胎蔵の話題が登らなくなった頃、私は再び胎蔵の小屋を訪れた。二冬が経過していた。
石垣は再び、そこにあった。崩されては積み直し、また崩されては積み直したようだ。もう誰も彼も胎蔵の邪魔をするのを諦めたようだった。
胎蔵は黙々と作り続け、石垣は再び元の高さ以上になっていた。殆ど背に届くほどだった。門の部分(だろう)だけが残されていた。私は近付いて胎蔵に謝った。
「いえ、いいのです。いずれ誰かがこれを見付けて、私を責めたでしょうから」
胎蔵は非難せずに板切れに描いた図面を私に見せた。
図面といっても子供の落書きのような絵だったのだが、見たこともない図面で、上部が弓なりになった石造りの門だった。こんなものは作れない、というと「作れるはずなのです」と答えた。「私は夢の中で、この街の中で暮らしていました。そこで石組みの仕事をしていました」
「街?」
「はい」
「門の中に街があるのか」と私が聞くと、彼はええ、と答えた。
「ここにはお前の家がある」
「やがて街も造りたいと思っています」
私は胎蔵の年齢を考えた。あと二〇年生きるだろうか。それまでに街を造るだけの年月は残っていないだろう。
私は何故、そのような奇妙に憑かれた思念に彼が染まってしまったのか、と全く要領を得ないので、しつこく問い質すと、彼はボソボソと答えた。
彼は妻子が死んでしまって以降、ずっと毎夜その異郷の街で暮らす夢を見ており、そこには妻子が共に住んでいる。人々は奇妙な格好で、侍と坊主がここと同じように威張って百姓を苦しめていた。耳の長い奇妙な言語を喋る異人や、背の低い異人が共に同じ街に住んでいたり、遠くの洞窟には龍が人を喰うというので、侍達が成敗しにゆくというのだ。
私は混乱した。
「官兵衛様のような詩吟を誦する人々は詩人といいます。琴のような楽器を持って歌うのです」
と、胎蔵は唐突に耳慣れない声で歌を唄いだした。
気分が悪くなるような高い声と節回しで、私は面妖な、狐狸に化かされたかと思い、ならばいっそここで斬って捨てようかと考えたが、ふと、漢書の古い物語でそのような話があるのを聞いたことがあるような気がした。
「花果山の猿の話のように奇々怪々な街なのか、それとも山海経のような魔物なのか」
胎蔵は歌を止めて「私は文字が読めません」と答えた。ずっと庄屋の下人だったのだ。
「龍の話は俵藤太の話のようだ」
「それは知っております。ですが、だいぶ違います」
「何にも役に立たぬものを何故しているのだ」
胎蔵ははっきりと私を見た。
「官兵衛様はなんのために生きているのですか」
「なに?」
「わたしは人は何かをするために生きるのではなくて、何かをしているために生きているのだと思います」
「意味がよく分からぬな」と答えた私は胎蔵の眼光に射すくめられる気がして、顔を背けた。
「石屋が石を穿つ行為に何の意味があります? 鍛冶屋が刀を鍛錬する時も彼らは何の意味を求めて打つのです? 彼らは必要だからこそそうするのだと思います。そこには他の何もありません。私だって同じことです。ただ、石を積むだけです」
「供養なのか」
「分かりません」
そう答えた胎蔵は再び沈黙の世界に立ち戻った。それっきり私の言葉には何の反応もなかった。私は為す術もなく山を下りた。
それからしばらく私は胎蔵のいつになく鋭い視線と言葉が残像のように脳裏にこびりついて離れなかった。
狐狸に化かされた「夢」を見ているのだ、と嘲笑しても済まない何かが胎蔵の話の中に存在していた。私は「家を守り勤めを果たしているのだ」と言えばそれだけで、果たしてそれがいったい何のためになるのだろうという考えは、無用の極みだ。捨て去らねばならなかった。
私は何度も胎蔵の元に通った。
やがて、おおよその胎蔵の思念の概略を感じ留めることができたと思えたが、胎蔵は年老いている。彼が望む全ての構築物は彼の生存中には完了しないだろう。そう聞くと、彼は微笑みを浮かべて淋しそうな瞳をした。
胎蔵ははじめ、夢の中ででてくる街を信じなかった。なにが何だか分からぬその街で、右往左往して、乞食のように浮浪した。やがてその街に定住するようになり、夢の中で描かれるまことではない、奇妙な街のことが徐々に岩に水が染みるようにして心の中を占めていったのだと語った。
胎蔵が語る街の細部の様子は私には分からなかった。
「私はその街を作りたいのです」
と彼はいい、板の図面に墨で念入りに描かれた絵は全く始めて目にする様式で、殆ど全てが石で作られていた。そのような街を作れるのか、と訊くと胎蔵はええ、ここに全て入ってますと頭を指差して、軽く笑った。
汚れた空きっ歯が見えた。
NEXT
|