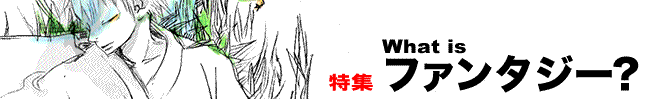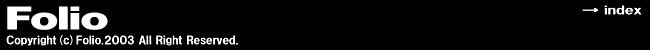雨だった。
煌蒼(こうそう)は、妓楼の奥にある部屋の窓に腰掛け、軒から落ちる雨滴を手に受けた。黒に紫の縁取りのついた上着。漆黒のびろうどのズボン。外出するときは、フェルト地の黒い手袋を嵌める。髪も漆黒だったが、対照的に、腺病質とさえ思えるほど肌は白く、目だけが強烈な光を発していた。
眼下に県城の通りが見える。
19世紀末の上海。
上海租界から南へ外れた県城の通りは、雨水が泥をつくり、荷車の車輪が泥をこねて沼のようだった。通りに面した安食堂の裏手からは残飯の腐臭が漂う。煙館(阿片窟)からは質の悪い阿片に酔って廃人と化した男たちのうめきが聞こえる。窓の破れた妓楼(売春宿)からはおんなの嬌声が聞こえたが、租界の賑わいと比べてそれは空疎で、どこか力がなかった。
殷賑を極める租界とは対照的に、「県城」は病んでいた。
1840年のアヘン戦争後、上海に流民としてやってきた清人の大半が住みついたのが県城だ。
上海の都市は13世紀に完成した。当初は安全な都市だったが、16世紀に海賊・倭寇(わこう)の来襲により幾度となく全滅の危機に瀕した。そこで建設されたのが、周囲6キロに及ぶ城壁に囲まれた県城なのだった。
上海の都市そのものはアヘン戦争後、英米仏が設けた都市植民地「租界」によって繁栄を享受している。
租界が建設される以前は、上海の海運や商業の中心地は県城だった。しかし1853年に秘密結社・小刀会による武装蜂起で、県城が占領されてからは住民が租界へ避難し没落。1年半後に解放されてからも繁栄は戻らなかった。
その荒廃ぶりは外灘(バンド)などとは対照的で、県城は巨大なスラムだった。中ではおいはぎ、強盗、殺人をはじめ、人々の誘拐があとを断たなかった。誘拐することを「上海する」と言うほどだ。誘拐された人々は、女は娼婦に、男は苦役人夫として売られるのが常である。
部屋にはさっきまで女がいた。
唇が厚く、卵形の顔で、おとがいを立てていつも男を侮蔑するように見る女だった。
煌蒼は、女を上に乗せて抱く。自由に動かせて相手がたっぷり満足するまで抱いてやる。代わりに、部屋を襲撃されたときは盾にした。弾丸を受けさせ、青龍刀を躯で銜えさせた。その間に、煌蒼は刺客の頸動脈を断つのだ。煌蒼は入り口が狭く窓がある部屋しか借りなかったので、それで十分間に合った。
「ねえ、あんた。居どこはあるの」
太い阿片煙管をくゆらしながら、女は尋ねた。
「金はあるが、居どこはない」
「あたしゃ、両方っつもないよ」
おんなの瞳は阿片のせいで溶けかけた黒砂糖の結晶のように、どろりと濁っていた。食事もろくにとってないのかもしれない。頻繁に咳き込んでいた。
女に十日分の上がり賃くらいの金を与えて部屋を去らせ、煌蒼は一人きりになった。
煌蒼(こうそう)は、しばらくの間、部屋の隅を凝視していた。
寝台の反対側の壁際に、新しい影がうずくまっている。これまで見かけたことのない影だ。しかも生前、煌蒼の知っている人物だった。
それは死霊だった。
煌蒼は、頃合いを見計らっていた。死んだばかりの霊は、まだ現世との結びつきが深く、強い未練を抱いている。
死霊は、よるべない。
孤独にさまよっている。ひとつ間違えば、よるべなさを消すために、生きている人間に寄り掛かってくる。気を許せば、魂魄が死霊に銜(くわ)えられる。銜えられれば、薄暮の冥界へと連れ去られてしまうだろう。
煌蒼は、引きをかわしながら、死霊の話を聴かなければならない。
煌蒼は、清全土を探しても滅多にいない「鬼視」だった。見鬼などとも言うが、この世に彷徨う死霊の姿を見ることができ、死んだ時の状況を聴くことができる。県城では殺しが多いので、この特殊能力は仕事を行うのにずいぶんと役だった。
煌蒼は、懐から小さな陶器の壺を出し、栓を取って死霊の影の前で傾けた。
床に中身がゆっくりこぼれ出る。
墓場の土だった。昨晩、埋葬されたばかりの妊婦の墓から取ったものだ。
床に細長い土盛りができた。煌蒼は、その上で手のひらを振って、手に受けた雨水を土盛りの上に垂らした。
そしてその前に座ると、床に指で文字を書き始める。もちろん跡は残らない。梵字(サンスクリット文字)のようだった。
書き終えると、息を凝らして待つ。雨音だけが部屋を支配する。
しばらくすると、壁や床から、木がきしむような破裂音が鳴りはじめた。ビシッ、ビシッと続けざまに大きな音が発生する。戸を叩くノックのような音もする。すべて霊の世界が生み出すものだ。
煌蒼は音を聴いても何も反応しない。目を細く開けて、ただ目の前の土盛りを見つめている。
やがて土盛りがゆっくり膨らみはじめた。いくつもいくつも、あぶくのように膨らみが生まれてくる。膨らみは、人の形をとった。
人型は、座って書き物をしているようだった。そこへ、たくさんの別の人型がやってきて、羽交い締めにする。人型はなにか脅されているようだった。刀で斬りつけられる。左腕が落ちた。
「襲撃か」
煌蒼はぽつりとつぶやいた。もう人型が動き出したので、あまり気を遣う必要はない。
別の人型の集団が、少し小ぶりの人型を捕まえ、連れ去っていく。人型の集団は、左腕を斬り落とした人型の顔をさらに傷つけると、床になにかをばらまき、立ち去っていった。
人型はそこで崩れ、元の土塊に還った。
「人攫い。殺し。火付けか」
煌蒼は顔を上げた。そこには、左腕のない死霊が闇に溶けるように佇んでいた。白髪の老人だ。
雨音だけが聞こえる。
「程鳳讃(ていほうさん)」
煌蒼は死霊に呼びかけた。
「天京(てんきょう)で私を救ってくれた程鳳讃。ひさしぶりだな」
死霊はゆっくりと頷いた。
天京は、南京のことだ。1851年に南京を占領した太平天国軍が命名したものだ。
「私は、こんな身に落ちてしまった。しかし程鳳讃、恩義は忘れていない。命にかえて、お前の恨みを晴らそう。お前の望みは何だ」
死霊の口がゆっくりと動いた。煌蒼は唇の動きを読みとった。
「娘。焔。略奪。わかった」
死霊は、もう少しばかり別のことも話した。その一言一言に、煌蒼はうなずいた。
聴き終わると、煌蒼は死霊になった程鳳讃の目をじっと見つめた。目を逸らしたり、魅入られたりしないようにだ。
煌蒼は、死霊を見つめながら下腹部に力を込めた。深く息を吐き、両腕で一瞬に土盛りを吹き飛ばす。程鳳讃の死霊は、一瞬驚いたように口を開くと、かげろうのように揺れて消えていった。
煌蒼は、小さな手箒で墓地の土を掃き集め、呪を唱えながら窓の外に捨てた。
煌蒼は、寝台から袖無しの外套(マント)を手に取り、腕に抱えた。
出かけなければならない。
NEXT
|