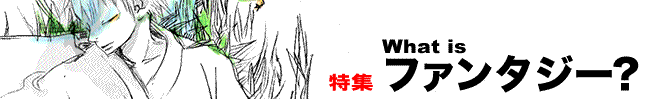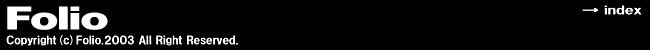3.黒鳥姫
「また、彼に遊んで貰ったのね」
良かったでしょう? 耳元で低く甘く囁きかけると、白鳥姫は怯えたように瞼を引きつらせて否定しようとする。その表情がいとしいと思いながら、わたしは微笑した。可哀想に、と囁いて、指の背で滑らかな頬に触れてやる。
「ひどい顔よ。青ざめて、憂鬱で」
そのくせ、伏せた瞼のあたりには、快楽の水際を漂ったあとに独特の、疲れたような甘い靄が掛かっている。ゆるく合わせられた白い衣の胸元に、絹のような肌が覗いている。愛だろうが悪意だろうが、注がれるものを決して拒まない、しなやかな肌。何を受け入れても純白の魂が汚れることはない、だからこそ男達は、自分の欲の汚さを棚に上げて、彼女を求めてやまないのだ。
その純粋さが、歯がゆくて、憎らしくて、たまらなく愛おしい。切なげな表情を舐めるように見つめながら、わたしは時々、自分を抑えられなくなる。
「その顔で王子様に逢うつもり? 止めておきなさい。軽蔑されるだけよ」
鞭を振るうようにぴしゃりと言ってやるが、本当のところ、それはまったくの脅しでしかない。白鳥姫がどんな姿を晒しても、あの王子なら眼を背けはしないだろう。怯えているのは白鳥姫のほう。お願い、こんな姿では、あのひとの前には出たくない。あたしの代わりにあのひとに逢って。そう請われてわたしは何度も、白鳥姫の白い衣装をまとって彼を迎えた。
「別にいいけど…それじゃ、あのペンダントを借りるわ。あんたが王子様に贈られたムーンストーンのやつを」
こんなとき、白鳥姫は決して厭だとは言えない。彼女のものはわたしのもの。それはアクセサリイだけではなく、男も同じことだった。白鳥姫は今でも信じている。わたしが完璧に彼女を演じ切り、白鳥姫として王子に逢っていることを。でも、本当はそうじゃない。怖いほどまっすぐで、確かな目を持った男。あの男は、何度か逢瀬を重ねただけでまもなく、わたしのことを見破った。完璧に白鳥姫とシンクロしていたはずの、わたしの本当の魂の所在を。
「…あなたは誰?」
ある黄昏時、わたしを腕に抱きながら、王子様はさらりと訊ねた。まるで、たった今髪から抜き取った鼈甲のバレッタを指先で可愛がりながら、どこで買ったのかと訊ねるように。わたしは平静なつもりだった。何の動揺も見せず、完璧に応えたと、自分では思っていた。
「あたしがどうかした?…何かおかしい?」
「あなたは白鳥姫じゃない」
王子は静かに言った。わたしを腕に抱いたまま、突き放しもせず、凛とした声で。
「全く同じ顔をして、同じ服を着ているけど、何かが違う。あなたは僕の知らない誰かだ」
あまりの確信の強さに、嘘を重ねて打ち消す気にもならなかった。黙り込むわたしに、名前を教えて、彼はそう言った。
「名前なんて」
そんなもの、なんの必要があるのだろう。その率直さが不愉快で、わたしはほんの少し眉をしかめた。
ひとに逢うときはいつも、白鳥姫の仮面を被っていた。純白の衣装を着て、彼女の装身具を身に付けて。歩く姿勢も眼の色も、声までも変えてしまうのが当たり前になっていた。騙し続けるための手管は簡単、決して視線を合わせないこと。相手を焦らし、微妙なところでするりと逃げる。わたしはそれが巧みだった。白鳥姫に仕える侍女たちや、あの悪魔ですら、わたしがしおらしく首を傾けていれば、黒鳥姫だとは見抜けなかったくらいなのだ。
それなのに、気づかれてしまったということは。わたしはいつの間にか、見つめてしまっていたのだろうか。自分に課した禁忌を忘れて、この男の濁りない眼を、奥深くまで。
わたしは取り繕うことをあきらめて、薄笑いをうかべた。男の腕のなかで、ゆっくりと、頭を振る。お行儀よく結われていた髪は、髪飾りを外されて自由になっていた。ばらりとこぼれた髪をそのままに、わたしは王子を上目遣いに見上げた。
「それじゃあ、改めてご挨拶するわ。わたしは黒鳥姫」
声音を偽らずに、白鳥姫以外の誰かと会話するのは初めてだった。わたしの声は白鳥姫よりもずっと低い。王子は少し驚いたように眼をみはる。その表情が可愛らしくて、わたしはゆるりと微笑んだ。
「もっと馬鹿な男かと思っていたわ。簡単に騙せると」
本音をぶつけると、王子はふと苦笑した。その表情を飽くことなく見つめながら、わたしは彼の頬に手を沿わせ、ゆっくりと撫でてやる。何も装わず、わたし自身として振舞うことは心地よかった。
「悪いけど、僕はそれほど鈍感じゃないよ。気づいたのも、今が初めてじゃない」
たとえば、この前の半月の晩も。悪魔が湖畔を離れていて、二人で過ごすことができた一昨日の午後も。僕の前にいたのは君だろう? 見事なまでに言い当てられて、わたしは肩をすくめた。
お伽話の王子様なんて、甘ったれか愚鈍かのどちらかに、相場が決まっていると思っていたわ。それなのに、騙されたふりをした男に騙されていたなんて。わたしらしくない失態だけれど、欺かれたという怒りも屈辱も湧いてはこなかった。
「完敗だわ。今まで、誰も気づかなかったのに」
「誰も?」
わからないほうが不思議だとでも言うように、王子は聞き返す。たとえ目鼻立ちがそっくり同じであろうとも、魂の形さえ異なれば、見て取れるのが当然とでもいうように。
「今までも…こういうことをしてきたのか?」
黒鳥姫が白鳥姫に成り代わって、ふたりで一人の男を分け合うような。わたしは平然と頷いた。
「そうよ。彼女を本当に監視し、操っているのはわたしなの」
此処へ閉じこめられる前から、白鳥姫は美しい少女だった。街を歩くだけで多くの男たちが彼女を欲しがり、白鳥姫は馬鹿正直に、そのすべてに応えようとした。拒むことを知らない白鳥姫のかわりに、わたしが純白の衣装を纏い、そのひとりひとりの品定めをするのが常だったのだ。
自らの存在を偽るほかは、わたしは自由に振る舞っていた。自分の眼鏡に適った男だけを選び、白鳥姫のもとへ近づけてやる。わたしが気に入らなければ、いくら白鳥姫が恋しがっても無駄だった。どんな手段を使っても、二度と逢わせない。でなければ白鳥姫は、彼女を求めようとする男達すべてに踏みにじられて、今頃めちゃくちゃにされていただろう。
「わたしがいなければ、白鳥姫はずたずたに引き裂かれてしまうわ。世間知らずで、自分では何も決められないんだから」
悪魔なんか、彼女を閉じこめたきり、朝と真夜中、彼女をおもちゃにしたい時しか姿を見せようとしない。こんなに無垢で綺麗な女の子を放っておいたらどうなるか、少し考えればわかりそうなものなのに。あんな男でも、白鳥姫にとっては救いだったなんて。憤りで頬がかっと燃え上がる。
「黒鳥姫」
王子はわたしの名前を静かに呼んだ。彼の膝に抱かれた姿勢のまま、強く引き寄せられる。その声は鼓動のリズムとシンクロするように、身体全体にじかに響いてきた。
「今わかったよ。閉じこめられていたのはあなたのほうだ」
なんですって。わたしは絶句する。わたしはこんなに自由に生きている。白鳥姫も、男たちも、時にはあの悪魔すら支配して。
「それでも、今までだれも、あなたを本当の名前で呼びはしなかった。あなたはずっと、白鳥姫の影としてしか存在することができなかった」
可哀想に、と彼は囁き、わたしはなかば自失してそれを聴いていた。可哀想だなんて、今まで誰にも思われたことはない。いや、誰もわたしに思いなど掛けはしなかった。みんなわたしを素通りして、白鳥姫ばかりを求めていた。それでいいとずっと思っていたはずなのに。認められたい、愛されたいと必死でもがいている白鳥姫を、わたしは軽蔑していたはずだったのに。
初めてわたしの存在を認め、迷わず黒鳥姫と呼んでくれた男。彼の腕のなかでわたしは、警戒も虚飾も解けてしまって、まるで心を裸にされたように茫然としていた。感情は麻痺したまま、涙だけがあふれた。王子はわたしを抱きしめ、子供でもあやすようにゆっくりとわたしの背を撫でていた。
わたしは黒鳥姫。白鳥姫の片割れ、鏡に映った影。わたしなしで彼女は生きられないし、彼女なしではわたしの存在も意味を失ってしまうだろう。だからこそわたしは彼女の側にとどまり、彼女を守りつづけるのだ。それでもわたしにだって心はあって、愛したい男もいる。それは白鳥姫の忠実な恋人。それでいて心からわたしを求め、情熱に灼かれることを厭わない、いとしい男。彼がわたしを、他の誰でもなく黒鳥姫として愛している。それはわたしが初めて白鳥姫に抱いた秘密だった。
「あなたも本当は、彼が好きなんでしょう」
薄々気づき始めているのか、白鳥姫は時折、そんなふうにわたしに問い掛ける。その口調は咎めているようでもあり、同時に卑屈に何かを伺うようでもある。わたしは笑う。自分だって悪魔と二股を掛けているくせに、そんなことを気に病める立場ではないと突き放す。
わたしたちはひとりの男を争い、分かち合い、ともに満たされている。憎みあい、時には激しく諍いながら、お互いにどうしようもなく憧れあい、欠けたものを与えあう。
わたしたちは二人でひとつ。鏡を挟むように向き合うことで、完璧な女となる。
4.王子
最初に逢う前から、彼女に関するだいたいのことは知っていました。ここへ到着する前に、予め報告を聞いていたのです。けっして本名では名前を呼ばせず、白鳥姫と名乗り続けている美しい患者に関するさまざまな事柄は。
口唇からこぼれ出すのは、彼女にしか見えない幻の物語。彼女にとってこの湖畔の病院は、自分を幽閉している悪魔の古城です。彼女の主治医は、彼女を幽閉している悪魔の化身であり、白衣の看護婦たちは姫君に仕える侍女でした。
新しく派遣された看護助手として、初めて彼女の病室を訪れたとき、彼女は主治医の手で、ベッドに手足を拘束されていました。白い病衣を着た腕が大きく広げられ、疲れきった翼のように横たわっていました。なるほど、彼女が自分を白鳥姫と呼ぶのも無理はない、僕は内心呟きました。
確かに彼女は、眠っていてさえ美しい患者でした。瞼は薄く閉じられて、顔は血の気が失せたように白く静かでした。その白さのまま首筋から胸元へつづく肌。思わず見入ってしまった自分を誤魔化すように、僕は上司である主治医をその場で詰問したのです。
「なぜ、こんな酷いことを…拘束する必要はないでしょう」
医師は動じもせずに肩をすくめました。暗い色の眼が伏せられ、私も本当はこんなことはしたくないのだ、と呟くのが聞こえました。
「刃物を持って暴れまわる大男だけが危険とは限らない。自由にさせてみろ、大変なことになる」
目に付いた男はかたっぱしから誘惑して歩く女だ。そう言い捨てた表情を見て、僕は直感しました。誰でもなくこの医師こそが、恥知らずにも彼女を誘惑し、関係を持っているのだと。そうであれば彼女が、彼を悪魔と呼ぶのも納得がいく。
僕はそのとき、自分の上司を心底軽蔑しました。然るべき手続きを取り、公の場で告発してやろうと本気で思ったのです。
なぜそうしなかったかって? 結局は、僕も彼と同じ道を辿ってしまったからです。まずは彼女に魅入られ、次には、もう一人にも恋をしてしまった。つまり、彼女の中に棲むもう一人の女、正反対の人格を持つ黒鳥姫のことをも、愛するようになってしまったのです。
白鳥姫はとても優しく、何処までも純粋なひとでした。ある昼間、僕は悪魔の目を盗んで、彼女の部屋を訪れました。あの非人間的な拘束ベルトを解いてやろうと、それだけを思っていたのですが、内心では、僕はひどく警戒していました。信じまいと思っても悪魔の言葉が胸の底に焼き付いて離れないのです。男と見れば誰でも誘惑する女だと…悪魔の言うとおり、彼女がすぐに僕を誘おうとしたなら、きっと僕は彼女に幻滅していたでしょう。
けれど、白鳥姫は、悪魔が言うような女ではありませんでした。誘惑したのがどちらかなんて、今となってはわかりません。少なくとも、初めて彼女が僕に触れたとき、僕には既に準備ができていた。必然に導かれるように彼女に応え、必ずここから連れ出すと約束していたのです。
黒鳥姫に出会ったのは、僕と白鳥姫が愛し合うようになって間もなくのことでした。白鳥姫が僕に心を開くようになるにつれて、ふと、彼女の意識が遠のくことがありました。眠るように意識が抜け落ちて…やがて、その隙を縫うように、もうひとつの人格、黒鳥姫が現れるようになったのです。
黒鳥姫は悪魔の娘と名乗り、表向きには白鳥姫の敵役を演じていました。けれど実際には、彼女は白鳥姫の守護者だったのです。白鳥姫を見下し、嘲笑的な態度を取りながら、実際には自らを盾に差し出すようにして、彼女に害を与えるものを遠ざけていました。白鳥姫が口にすることのできない怒りや拒絶を表に出す役割を引き受け、あらゆる汚れから守り抜こうとしていたのです。
「わたしがいなければ、白鳥姫はずたずたに引き裂かれてしまうわ。世間知らずで、自分では何も決められないんだから」
漆黒の翼の下に全てを抱き込もうとでもするような献身。僕は黒鳥姫が憐れで堪らなくなりました。もうとっくに引き裂かれているよ、あなたがその片割れだ。そう告げてやりたい思いに駆られましたが、口にすることはできなかった。誰もが白鳥姫の妄想と決めつけていた黒鳥姫。けれど、せめて僕だけは、彼女をひとりの女として認めてやりたかったのです。
「黒鳥姫…閉じこめられていたのはあなたのほうだ」
僕の言葉の意味を、彼女はすぐには理解できないようでした。彼女自身は主導権を握っているつもりでいたし、白鳥姫もそれに頼っていたのだから、無理もありません。けれど、同じ身体に棲んでいながら、視線を注がれ、愛されるのは常に白鳥姫であり、黒鳥姫はその影としてしか存在することができなかったのです。僕は、黒鳥姫を黒鳥姫として認めた初めての男でした。そのときを機に、彼女は僕だけには偽らない姿を見せるようになり…僕のほうも、やがて抑えようもなく、彼女に惹かれていったのです。
これからどうするかって?
どうせこの病院は破滅です。医師と看護助手が、揃いも揃って患者に手を出すなんて、何も知らない人間にしてみれば醜聞の極み、狂気の沙汰としか思えないでしょう。医師は姿を消しましたが、僕は逃げるわけにはいかない。ありのままの彼女を引き受け、何も損なうことなく愛してやれるのは、僕だけなんですから。
これからは彼女と結婚し、一緒に暮らすつもりです。治療を続けるつもりはありません。このままで…いや、このままがいいんです。
治療するということは、ふたりの女をひとつに融合させることです。一方の魂が死ななければならないのです。白が黒に取り込まれるのか、黒が白に取り込まれるのか。どちらにしろ、僕には一方を選ぶことなど到底できません。
白鳥姫と、黒鳥姫。全く似ていない、けれどどちらも本当に美しい女です。柔らかで傷つきやすい純白と、しなやかで強い芳香を放つような、漆黒。ひとつの身体を愛するだけで、二人を平等に満たしてやることができるんです。どちらも僕を必要としていて、どれだけ愛しても互いへの裏切りにはならない。これほどの幸福がありますか?
理屈しか見えない人たちにとっては、幼稚な「ごっこ遊び」に見えるしれません。確かに、囚われの姫君も、王子も悪魔も、現実の世界には存在しませんからね。けれど彼女にとってはそれが真実であり、ならば僕も、彼女の真実の一部で居続けたいのです。
世界中のみんなが、無味乾燥な現実の基準だけに従う義務はないでしょう。僕と彼女の間に、小さく密やかなお伽の国を創り上げることくらいは、どうか許してもらいたいのです。その国で、僕は彼女を彼女を愛し、守り抜きます。その覚悟はとうに出来ています。
それでは、僕は行きますよ。王子として、彼女が住むのと同じ世界にね。
憐れみなど必要ありません、それよりも、どうぞ祝福してください。
さようなら。
結 狂言回し
こうして王子様とお姫様は手を取り合い、聖なる誓いのもとに永遠に結ばれました。その後彼らを見たものはありません。ただ、風に乗ってきた瑠璃色の蝶が囁いて聞かせるには、彼らは今も、誰も知らない愛の国で、仲睦まじく幸福に暮らしているそうです。
さあ、今夜のお話はこれでおしまい。めでたし、めでたし。
了
|