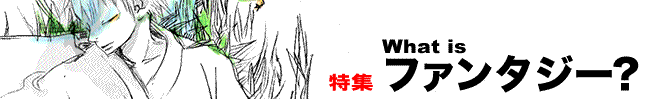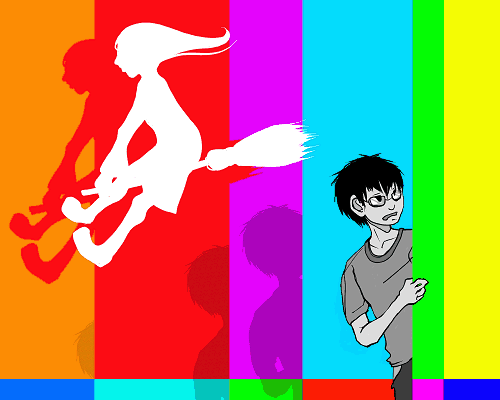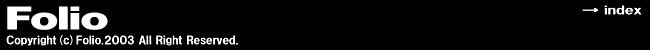高山が久しぶりに俺の家にやってきたのは、その二週間後だった。親と妹と兄を除いて俺が普通に話すことができるのは、この幼稚園時代からの友人だけだ。高山はいつも黄色く見える。友情の色。
部屋に招き入れると、高山はまずセーターを脱いだ。暦は十月に足を踏み入れている。外に出ない俺にとって、季節を感じられるのは窓から吹き込む風と他人の服装だけだった。
「元気か」
「元気だ」
答えながら、顔をしかめた。高山が俺に意味のない挨拶をするときは、面白くない話を持ってきたときに決まっている。ため息が漏れた。
「で、どうした。ペットが死んだか? 家が燃えたか? まさか誰かが死んだとか言うなよ」
「どれも違う、でも最後は惜しい」高山は言い難そうに視線を泳がせた。「今朝から桐原が入院してる。意識不明だってよ」
絶句した。桐原は高山と俺の幼馴染だ。今も俺の家から歩いて三分のところに住んでいる。アイツが男に生まれていたら、高山以外にもう一人話せる人間が増えていたに違いないのだが、残念ながら、目と異性という二つの障害を乗り越えることは俺にはできなかった。
「理由は?」やっとそれだけ聞けた。
「わからん」俺が嫌な目で睨んだことに気付いた高山が、慌てて付け足した。「いや、これは俺が知らないって意味じゃなくて、医者も家族も分からんらしい。昨日寝る前までは普通だったのに、今朝からずっと起きないんだってよ。脳波がどうこう言ってた」
「見舞いには?」
「その帰りだよ。本人には会わせてもらえなかったけどな」
高山でもダメだったのなら、家族以外は面会謝絶なのだろう。だとすると、相当危険な状態にあるに違いない。俺は髪を掻き毟った。
「落ち着けよ。おばさんが言うには、完全に昏睡してるわけじゃないらしいぜ。たまに目覚めてボソボソ何かを呟く程度のことはするから、このまま起きない確率は極めて低いって話だ」
高山の話を聞きながら、俺は考えを纏めていた。
「ここ一週間くらいおかしいよな。一昨日は木下さんが病気だって話も聞いたし。呪いにでもかかったかね、ここら辺の家は。斎藤の婆さんも昨日から魔女の仕業だとか騒いでるし。百歳越えて走れる婆さんが一番魔女みてえだよな」
原因不明の体調不良、夜寝てから起きない。つまり、寝ている間に何かがあったと考えるのが妥当。そう、たとえば、空を飛ぶ人間の悪夢を見た、とか。
「その桐原の呟きの内容、わかるか?」
高山は、わざと明るく答えた。
「ああ、おばさんから聞いた。魔女とか箒とか、よく分かんねえ言葉の羅列だってよ。ずいぶん楽しそうな夢だと思わないか?」
思わなかった。
拳を握り締める。顔をあげると、目の前の壁に狂ったような炎の色が見えた。赤。敵意の色。茜雲の向こう、地平の彼方に夕日が落ちる。
許さないと思った。
夜が来た。
高山はもう部屋にはいない。勉強も筋トレもする気分になれなかったので、俺はベッドに横たわっていた。窓の外に星空が広がっている。
今夜、サリーは来るだろうか。窓に切り取られた夜空を見上げた。月が白い。
星と星を繋ぎ合わせているうち、もう桐原の顔さえ思い浮かべられなくなっている自分に気が付いた。顔を合わせなくなってどれほど経つだろう。いつまでもアイツの色が黄色から変わらないことが我慢できなくなったのはいつからだろう。
友情だけで満足できなくなった。淡い期待さえ抱かせてもらえない自分の体質が心底恨めしくなった。それが、引き篭もりの本当の理由。
空に一筋の軌跡が入った。
流れ星ではなかった。真っ赤な、本当に赤一色に支配された人影が見える。敵意に満ちた、禍々しい色。箒のようなものにまたがって、空を駆っている。頭が痛い。眩暈がする。
意識が、遠のいていく。
気付くと、目の前にサリーがいた。いつかと同じ妙な格好で、やっぱり箒も持っている。
「大丈夫? 真っ青になってたけど」サリーが窓際に座った。「あんまり目に負担かけちゃダメだよ」
俺は何も答えなかった。
「まだ気分悪い?」
「悪いね、すごく」
俺は拳を握り締めて殴りかかろうとする自分を必死に押し殺した。
「お前、帰れ。二度と来るな」
サリーを睨みつけたが、表情に変化はなかった。
「お前がやってるんだ。桐原もみんな、お前のせいで倒れた。空を飛ぶ魔女を見た人がみんな倒れてるんだ。人の夢に入り込んで、何か悪さしてんだろ。それが魔女の仕事なんだろ!」
「仕事じゃないよ。そうしないと、魔女は生きていけないだけ」
「だからって、そんなことしていいワケじゃないだろうが」
「そうだね。でも、寝てる間に生気を吸うだけだから、死人は滅多に出ないよ」
「桐原は意識不明だ」
サリーは一瞬息を飲んだみたいだった。
「分かったろ。早く帰れよ。そんで、どっかに行け」
「でも」
「うるせえ!」
俺の振るった拳は、サリーには当たらなかった。サリーはため息を吐いた。
「もともと今日はバイバイしにきただけだから、仕方ないね」
窓の外に、箒にまたがって浮いているサリーの姿が見えた。悲しそうな顔のまま、サリーは「じゃあ、バイバイ」と言った。箒は空ではなく、下の地面に向かって降りていった。
サリーの背中には、やっぱり色がなかった。
ベッドに腰掛けて、俺は考えていた。桐原は回復するだろうか。サリーは生気を吸っただけと言っていたから、安静にしてれば問題ない気はするが、確証はない。それだけでも聞いておけば良かったと、無色の背中を思い浮かべた。
立ち上がった。急いで考える。それから、上着を羽織った。窓の外を見る。通行人は少ない。今なら外に出れる。どうせ、長い距離じゃない。行くべき場所はすぐそこだ。第一、そんなことを考えていられる事態じゃない。
サリーに追いつかなくてはならない。
久しぶりに外に出た。街灯と月光が、アスファルトを白く濡らしている。
周囲を見渡すと、電気のついていない家が一軒あった。古い平屋。うちのすぐ隣にある家。
駆け寄って扉に手をかけたが、鍵がかかっていて開かなかった。少し考えてから、塀を越えて庭に回り込んだ。探すと一つだけ鍵の開いている窓がすぐに見つかった。サリーが開けたものだろう。
迷わず土足で踏み込んだ。耳を澄ますと、奥のほうから何か物音が聞こえてくる。広くもない家だ。声を頼りに走ると、すぐに現場に行き着いた。
サリーの足元に、若い女が倒れていた。生気を吸われたのか、女は動けないらしい。顔は見ていなかったが、彼女はおそらく二週間前に引越しの挨拶に来た人と同一人物だろう。
「やっぱりここに来たのか」俺はサリーに向かって一歩踏み出した。「箒が地面に降りていったから、変だと思ったんだ」
俺はサリーから視線を逸らし、床に這いつくばっている女を見た。苦しそうに顔を歪めている。女の傍までゆっくり歩いていって、思いっきり足を振り上げた。
女の足に、俺のつま先がめり込んだ。呻き声が響く。本当は腹か顔にでもぶち込んでやりたかったが、見た目が女なのでそこまではできない。
「こいつが魔女なんだろ」俺は言った。
「そう。私が魔女だと思ってた?」サリーは微笑んだ。
「魔女と魔法使いは別って言ったのは自分だろ。生気を吸い取るのが魔女なら、魔法使いのお前は関係ない。それに」と俺は間をおいた。「お前には色がない。俺が見たのは真っ赤な人影だった」
そのことに気が付いたのは、本当についさっきだった。
「なるほどね」言いながら、サリーは魔女に触れた。魔女の体が少女のそれに変わっていく。「この娘が吸い取った生気のほとんどは私が取り返しておいたよ。さっき元の場所に飛ばしたから、そろそろみんな元気になると思う」
「魔女を捕まえるのが、魔法使いの仕事なのか?」
「まあ、仕事はそれだけじゃないけどね。どうしてこの娘が魔女だって思った?」
「さあ。色々あるな」
初めてサリーが部屋に来たとき、サリーは俺のオーラではなく、他の嫌なオーラを追って来ていた。オーラが急に弱くなったのはサリーの接近に気付いた魔女が隠蔽したからだろう。なら、俺の部屋の近くに魔女がいることになる。
高山の話だと、ここら辺の人間の体調がおかしくなったのはここ一週間。なのに、二週間前に家を訪ねてきた女はすでにそれを知っていた。これから起こる騒ぎを知っていたのは、自分が騒ぎを起こす張本人だから。不自然に思われないよう、自分が越してくる前から周囲がおかしかったことを印象付けようとしたのかもしれない。大体、この平屋に一人暮らしをすることがそもそも普通じゃない。
さっきサリーは俺の部屋から去るとき、地面に降りた。今夜は別れを告げに来たとも言った。ということは、サリーの最後の目的地は俺の家から歩いていけるところ。サリーは魔女を探していたのだから、そこに魔女がいる。
俺はそれだけを話した。もっと早く気付いていなければならなかった。
「悪かった。お前を疑った」
「いいよ別に。私も変わらないから」窓から差し込む月光が、サリーを照らしていた。「私も昔は魔女だった。魔法使いの仕事はね、魔女を捕まえて一人前の魔法使いに育てることなんだ」
「育てる?」
「魔女も魔法使いも元は変わらないの。未熟な魔法使いが魔女呼ばわりされる。魔女は悪さをするから、それを管理して育て上げるのが魔法使い。上位の魔法使いは他の仕事も色々するけどね。私も魔女だった頃、色んな悪さをした。この娘よりもっとね」
サリーは動けない少女を背負った。これからどこかへ連れて行くのだろう。魔法使いに育て上げる場所がどこかは知らないが、きっと近くではない。
「でも、今はお前も良い子になった」
俺は笑った。サリーも笑った。
「ねえ」サリーが言った。「外、出れたじゃん」
「ああ、そうだな」
「悪い子だって良い子になる。人間だって変わるもんだよ。気持ちだって、いつか変わるかもしれない。悪い人ばっかりなわけでもない」
「魔法使いは心まで読めるのか」
「少しはね」サリーは舌を出した。「学校はまだ無理かもしれないけど、今の君なら病院にお見舞いに行くことくらいはできると思う」
俺は窓から空を見上げた。夜空には、サリーと同じ色の白い月があった。
「まだ面会できるかどうかも分からないんだぜ?」
返事はなかった。視線を戻すと、サリーが立っていた場所には、もう何もなかった。ただ月光に照らされた埃だけが浮かび上がっていた。サリーは、テクマクマヤコンの呪文も言わずに消えてしまった。
呆然とする俺の頭上に、ひらひらと一枚の紙が落ちてきた。そこには、思ったよりも丁寧な字が書いてあった。ただし、字がきれいであればあるほど、内容はとんでもなく間抜けに見えた。
"テクマクマヤコンは、『ひみつのアッコちゃん』だよ"
俺は声を出して笑った。
「さすがは魔法使いだ」
家に帰ろうと思った。秋の夜風は少し肌寒い。上着の前を掻きあわせ、小走りになった。風邪を引かないように、家に帰ったらゆっくり風呂に入ろうと思う。
なにせ、明日は病院にいかなくてはならないのだ。
了
|