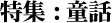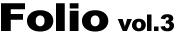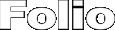赤ずきんちゃんほど世界中で愛され親しまれている少女が他にあるだろうか。この少女の物語を知らずにおとなになった人がいるとは思えない。多くの人びとがこの少女の魅力に憑かれ、研究者たちはその源を探り、分析医たちは解釈を試み、作家たちはそれぞれ自分なりにこの物語を書き換えた。
わたしたちはどうしてこんなにもこの少女が好きなのだろう。ベッテルハイムはいう、「それは、赤ずきんがよい子で、しかも誘惑に弱いからだ」。そう、たしかに「よい子」でしかも「誘惑に弱い」から愛されるのだ。
しかし、おそらく生まれてから三〇〇年以上経つこの少女は、その歴史を通じてつねに狩人(すなわち父親=大人=男性)によって保護されなくてはならない、かよわい女の子だったわけではない。民衆が生んだ最初の赤ずきんはもっと賢く、自分の力で自分の身を守った。それを、男が保護してやる必要のあるかよわい少女に仕立てあげたのはペローであり、グリムである。彼らがつくりあげた赤ずきん像は、この二〇〇年以上の間ほとんど変化せず、そっくりわれわれの抱くイメージに受け継がれているが、それは精神分析家がいうような普遍的な少女像なのだろうか。いやむしろペローの時代から現代にいたる「近代」という時代に特有の、女性や子どもにたいする偏見に裏打ちされたイメージなのではあるまいか。
ところで、この少女には名前がない。メトニミックに「赤ずきん」と呼ばれている(正確にはペローの物語は『小さな赤い乗馬ずきん』、グリムのそれは『小さな赤い帽子』)。この「ずきん」は何なのか。どうしてそれは赤いのか。
エーリッヒ・フロムがこの赤いずきんを月経の象徴であると断言したことはあまりに有名だ(『夢の精神分析----忘れられた言語』)。「このおとぎ話の象徴的意味を理解することはじつに簡単だ」と豪語するフロムによると、この物語は性の問題に当面した少女の物語である。「道草を食わないように」「瓶を割らないように」との警告は、処女を失わないようにという警告であり、残酷でずるい狼は男性の象徴である。性的行為は、狼による人食いとして描かれている。これは「男と性にたいする深い敵意の表現」であり、狼は生きている人間を腹のなかに入れることによって、すなわち僭越にも妊婦の役を演じようとしたことによって処罰を受け、不妊の象徴である石によって殺される。この物語は、祖母、母、娘という女の三世代を代表する人物を中心をした「男性対女性の葛藤」の物語であり、「男を憎む女の凱歌」であり、女の勝利で結ばれる。
フロムの『赤ずきん』分析は二ページにも満たない簡単なものだが、ブルーノ・ベッテルハイムは、フロイト派による昔話研究の金字塔ともいうべき『昔話の魔力』において、詳細にこの物語を論じている。
彼は『ジャックとマメの木』を論じた章で、「昔話は、生きていく上でのさまざまな基本問題、中でも、成熟するための闘いから生まれる問題を、文学という形で扱う。そして子どもが、一人の人間としてより高いレベルに到達し、責任を果たしうる自己を確率しないと、どういう恐ろしい結果になるかを警告する」と、昔話にたいする自分の基本的な見方を述べているが、『赤ずきん』が扱っているのも、「無意識ではエディプス的なつながりを断ち切れずにいる学齢期の少女が解決しなければならない問題」である。
ベッテルハイムはこの物語のさまざまなモチーフについて、じつに興味深い指摘をしている。まず、親の家とおばあさんの家は、『ヘンゼルとグレーテル』における親の家と魔女の家と同様に、じつは同じ一つの家であり、それが心理的状況の違いから、別の家として経験されているのである。そしてヘンゼルとグレーテルはまだ口唇期に執着しているので、母親的人物(母親、魔女)が重要な役割を演じるが、赤ずきんは口唇期を過ぎているので、母親もおばあさんも、赤ずきんを脅すことも保護することもできず、それにたいして父親像のほうが重要になっている。この父親像は誘惑者(狼)と救出者(狩人)の二つに分裂している。赤ずきんは「男性のパーソナリティのあらゆる側面にぶつかって、男性というものの矛盾した性質を理解しようとしている」。
赤は、荒々しい性的情動を象徴する色であり、おばあさんが孫にずきんをあたえることは、「年上の女性が、男性にたいする彼女自身の魅力を放棄し、それを若い娘にゆずりわたすこと」であり、「性的魅力が、未成熟な相手に伝達されたこと」を象徴している。
どうして赤ずきんは狼に、おばあさんの家がどこにあるのかを教えるのか。それは赤ずきんが無意識のうちに、おばあさん(=母親)をなきものにしようとしているからだ。
また、狼はどうして赤ずきんと出会ったときに食べてしまわなかったのか。おばあさんの家のありかを聞きだしたのだから、後からおばあさんを食べてもよかったのではないか。ベッテルハイムはこう考えるべきだという。つまり、「赤ずきんを手に入れるためには、まずおばあさんを取りのぞいておかなければならない」のであり、「祖母(=母)がいる限り、赤ずきんは狼のものにはならない」。「邪魔な祖母(=母)がいなくなれば、母がいる間は抑圧されていたことが、なんでもできるように思える」。つまりこの物語は、「狼(=父親)に誘惑されたいという娘の願望」を扱っているのだ。
狼は腹を引き裂かれただけでは死なず、石を詰め込まれて死ぬ。昔話は人間の成長の物語なのだから、狩人(=父親)が狼を殺してはいけないのだ。実際、石を詰めることを提案するのは赤ずきんだ。また、子どもに出産にたいする不安をあたえないためでもある。「もし狼が、帝王切開のように腹を切り裂かれたのがもとで死ぬと、聞き手の子どもは、生まれる子どもが母親を殺すのではないかと思ってしまう」。
ここまでくると、いささかこじつけめいているようにも思われるが、それはともかくとして、こうしたフロイト派の分析にたいし、ユングはどのように分析しているのだろうか。
ユングはその『精神分析の理論』のなかで次のように述べている、「この[赤ずきんの]モチーフは世界じゅうにある無数の神話のモチーフであり、聖書のヨナの物語のモチーフである。このモチーフのすぐ下には宇宙神話的な意味が隠されている。太陽が海の怪物に呑みこまれ、朝ふたたび生まれる。もちろん宇宙神話というものはすべて、本質的には天体に投影された心理----無意識の心理に他ならない。[・・・]神話がたんに気象や天体の動きを説明するだけのために創られたとは考えられない。神話は何よりもまず、夢のような無意識的衝動のあらわれである。その衝動は無意識のなかの退行的リビドーによって発動される。表面にあらわれる素材は、いうまでもなく幼児期の素材、すなわち近親相姦コンプレックスと結びついた空想である。だから、いわゆる太陽神話のなかにはかならず、生殖、誕生、近親相姦的関係についての幼児的な理論化がみられるのだ。『赤ずきん』の話の場合、それは、母親はなにか子どものようなものを食わなくてはならない、そして子どもは母親のからだを切り裂くことによって生まれてくる、というファンタジーである」。
ユングは別の論文でも、『赤ずきん』では、神話に登場する「呑み込むもの」としての蛇あるいは魚が狼に置き換えられている(『変容の象徴』)とか、『赤ずきん』の狼は「呑み込む母親」という元型の表現である(『分析心理学と教育』)と述べている。このように夢や物語にあらわれたイメージを古代神話に還元するというのはユング心理学の本質的特徴であるが、『赤ずきん』解釈史の側からみると、このユングの解釈は、十九世紀後半から今世紀初頭にかけて数多く提出された神話的『赤ずきん』解釈の流れを引いたものである。そうした解釈においては、ずきんの赤色が太陽あるいは光の象徴とされ、この昔話の起源は日の出と日没の神話である、とか、光すなわちキリスト教的善を呑み込もうとする闇の邪悪な力についてのマニ教の神話がもとになっている、といった仮説が提出された。むろんこうした仮説は、宗教の起源に関する仮説と同様に、永遠に立証されることなく仮説にとどまるしかないわけだが、今日の民話研究者たちは一応この仮説を否定しており、『赤ずきん』の原型は、中世末期頃に生まれ、十六、十七世紀まで、フランス、チロル、北イタリアに広く伝わっていた警告物語であると考えられている。ペローがそれを知っていたことは確実であり、彼はそれを上流階級向けに書き換えたのである。
ペローの『赤ずきん』は「大ヒット」し、さらにグリムによるそのヴァリエーションはそれを上回る勢いで世界中に広まり、文学的おとぎ話としてはむしろ例外的なことだが、ふたたび民衆の口承伝統のなかへと入っていって、原型となった伝承物語を駆逐しつつ、世代から世代へと語り継がれることになるが、『原・赤ずきん』のほうも、細々ながら、ペローおよびグリムの影響を免れて、語り継がれ、十九世紀末に研究者によって採話されることになる。それはどうやら次のような物語らしい。
昔あるところにひとりの女のひとが住んでいました。その女のひとはパンを焼いて、娘に言いました。「この焼きたてのパンとミルクをおばあさんのところに届けてちょうだい」。
それで女の子は出かけました。道が二つに分かれているところで、女の子は人狼に会いました。人狼は女の子にこう言いました。
「どこへ行くんだい?」
「この焼きたてのパンとミルクをおばあさんのところにもっていくの」。
「どっちの道を行くの? 針の道、それともピンの道?」
「針の道にするわ」。
「そうかい、それじゃわしはピンの道を行くとしよう」。
女の子は夢中になって針を集めました。その間に人狼はおばあさんの家に行き、おばあさんを殺して、その肉のかたまりを戸棚のなかに入れ、血は瓶にいれて棚の上におきました。女の子がやってきて、戸をたたきました。
「戸を押しておくれ」人狼は言いました。「濡れた麦藁が一本引っかかってるんだよ」。
「こんにちわ、おばあさん。焼きたてのパンとミルクをもってきたわ」。
「戸棚のなかに置いておくれ。中にある肉をお食べ。それから棚の上にあるぶどう酒をお飲み」。
女の子が肉を食べてしまうと、そばにいた子猫が言いました。
「うへー! 自分のおばあさんの肉を食べて血を飲んでしまうなんて、なんてひどい娘っこだ」。
「服を脱いで、わたしといっしょにベッドにおはいり」。
「エプロンはどこに置いたらいい?」
「火にくべておしまい。もういらないから」。
女の子は洋服、ペチコート、長靴下を脱ぐたびに、どこに置いたらいいのかたずねました。人狼はそのたびに、「火にくべておしまい。もういらないから」と答えました。
女の子はベッドのおばあさんのとなりにもぐりこむと、こう言いました。
「まあ、おばあさん、なんて毛深いの!」
「このほうがあったかいんだよ」。
「まあ、おばあさん、なんて爪が長いの!」
「かゆいところがよくかけるようにさ」。
「まあ、おばあさん、なんて大きな肩なの!」
「薪をかつぐためさ」。
「まあ、おばあさん、なんて大きなお耳なの!」
「おまえの話がよく聞こえるようにさ!」
「まあ、おばあさん、なんて大きなお鼻なの!」
「タバコの匂いを吸うためさ」。
「まあ、おばあさん、なんて大きなお口なの!」
「おまえを食べるそのためさ」。
「でも、おばあさん、おしっこがしたくなっちゃった。外に行ってもいいでしょ?」
「ベッドのなかでしちゃいなさい」。
「でも、おばあさん、お外に行きたいの」。
「わかったよ、でも急いでするんだよ」。
人狼は女の子の足にひもを結びつけて、外に出してやりました。女の子は外に出ると、そのひもを庭のプラムの木に結わいつけました。人狼はじれったくなって言いました。「おまえ、そこでしてるの? まだしてるのかい?」
答えがないので、人狼はベッドからとびだし、女の子が逃げてしまったことを知りました。あわてて女の子を追いかけましたが、女の子はすんでのところで自分の家に逃げ込みました。
これをペローの物語と比べてみると、ペローが「カンニバリスム」と「ストリップ」を削除したことがわかる。上流階級向けに書いたのだから当然といえよう。
ちなみに、人肉を食べるというモチーフは、時代を下るにつれ、ますます人びとに忌み嫌われるようになってきた。グリム童話でさえ、当てずっぽうに開けば、こんな話に出くわす----小さな男の子が箱のなかからリンゴをとろうとしてかがんだとき、箱の蓋が落ちてきて首がちょん切れてしまう。よこしまな継母は息子の体をテーブルの前にすわらせ、その上に頭をのせておいてから、小さい妹に、兄を食事に呼んでくるようにと言いつける。兄が返事をしないので、妹が兄をゆさぶると、首がころがり落ちる。継母は息子をシチューのなかで煮て、仕事を終えて帰宅した父親に食べさせる。「ああ、なんてうまいんだ。食べたものがすっかり身についたような感じがするよ」。
いまどき自分の子どもにこんな話を語って聞かせる親がいるだろうか。そういえば、本屋に行って『かちかち山』をみてみると、どの本も、たぬきがばあさまを殺し、帰ってきたじいさまがその死体をみて嘆き悲しむ、となっているが、われわれが子どもの頃に聞かされた話はそうではなかったはずだ。たぬきはばあさまの皮をひっぺがしてそれをかぶり、ばあさまになりすまして、山から帰ったじいさまにたぬき汁ならぬ「ばばあ汁」をだす。
「ばあさま、ばあさま、なんたらおかしな味のたぬき汁だべ」。
「そりゃ年老ったたぬきだもの。屁臭い味すんだべや」。
「んだべなあ」。
首っこかしげかしげ、じいさまはそれでも三膳三椀食べたそうな。
「ちった屁臭えども、うまかった、うまかった」。
じいさまがそういうて、歯をせせっていると、たぬきはばば皮をべらりと脱いで、
やーはいやーはい
ばばあ汁食ったじじい
ばんばぁ奥歯にひっついた
流しの下の骨を見ろ (松谷みよこ 『日本の昔ばなし』より)
いったいに、このカンニバリスムのモチーフに限らず、おとぎ話は、ペローやグリムその他によってブルジョワの子女向けに書き換えられる前は、今日の形よりもずっと生臭く、どぎつく、残酷だったのである。たとえば、『眠れる森の美女』のもとになった民話では、隣国の王子が眠っている姫を強姦し、姫は眠ったまま子どもを生む、というストーリーだったのである。『赤ずきん』に話を戻すと、少なくとも『原・赤ずきん』のテーマはベッテルハイムやユングがいうような「なにかに呑み込まれる不安」ではなく、文字通り人肉を食うことだったのである。
さて、『原・赤ずきん』とペロー版との、いまひとつ重要な相違は、『原・赤ずきん』には、ずきんも、赤という色も登場しないということである。太陽の象徴だ、月経の象徴だ、というのはペロー版『赤ずきん』の解釈にはなりうるとしても、その原型となった民話の解釈たりえないのである。
啓蒙主義時代のフランスを専門とするアメリカの歴史家ロバート・ダーントンの名は、われわれにとっては『メスメリズム』(一九六八)の著者としてかねてより馴染み深かったわけだが、一昨年出版されて話題を呼んだ『猫の大虐殺その他、フランス文化史のエピソード』に収められた論文「農民が物語をかたる----マザー・グースの意味」において、精神分析的おとぎ話解釈を激しく非難している。
ダーントンいわく、フロムの解釈は、赤いずきん(月経)、少女がもっていく瓶(処女性)、それを割らないようにという母親の警告、狩人、狼の腹に詰める石(不妊)など、十七、十八世紀の農民の間に伝わっていた話には登場しないものばかりにもとづいている。フロムは、「かつて一度も存在しなかった、少なくとも精神分析の出現以前には存在しなかった心的世界へと、われわれを連れ込む」のだ。どうしてこんなにとんでもない見当違いが生じるのか。その原因は、精神分析医の職業的ドクマティズムではなく、「民話の歴史的次元にたいする無知」である。
また、ダーントンいわく、ベッテルハイムの民話解釈は四つの誤った前提にもとづいている。(1)たいていの民話は子どものために作られた。(2)民話はハッピーエンドに終わらなくてはならない。(3)民話は「超時代的」である。(4)民話は、現代アメリカ人によく知られている形そのままで、「どんな社会」にも適用しうる。
精神分析医の手にかかると、アラジンが魔法のランプをこするのはマスターベーションになり、ジャックが登るマメの木は勃起したペニスになる。もちろん、ダーントンも誤解を避けるためにはっきり言明しているが、民話に無意識的、不合理的要素があることは否定できない。しかし民話の歴史的変遷、すなわちメンタリティの変化を無視することは許されない。ベッテルハイムにせよ、フロムにせよ、『原・赤ずきん』のカンニバリスムやストリップを解釈しなければならない。もし彼らが自分の用いているペローやグリムの話を「普遍的」と見なすならば、それが『原・赤ずきん』よりも深く人間の深層に根ざしていることを証明しなければならない。
ダーントンは「メンタリティの歴史的変遷」という立場から精神分析的民話解釈のアナクロニズムを批判しているが、やはり女性や子どもや性的なものにたいする社会の態度の変遷という観点から、ダーントンよりも詳細にわたっておとぎ話のイデオロギー性を分析しているのがジャック・ザイプスである。ザイプスの『赤ずきんの試練と苦難----社会文化的コンテクストにおける「赤ずきん」物語の諸ヴァージョン』(一九八三)には、ペロー(一六九七)からティーク、グリム、デ・ラ・メア、サーバー、アンジェラ・カーター(一九七九)にいたる三一の代表的な「赤ずきん」物語が収録されていて、ザイプスは巻頭論文のなかで、政治的、文化的要請によっていかにこの物語が変遷してきたかを詳細にあとづけている。ペロー、グリムに関しては、ザイプス独自の研究というよりは、諸先達の研究をまとめて紹介しているという感じだが、そのためにむしろわれわれにじつに有益なパースペクティヴをあたえてくれる。以下、このザイプスの論文に拠りながら、農民が生んだ民話がペローやグリムによってどのように書き換えられ、それが十九世紀から今世紀初頭までいかなる機能を担ってきたのかを追い、さらに第一次大戦以降にあらわれた、ペロー、グリムに反逆した作家たちの『赤ずきん』をいくつか紹介することにする。
マリアンヌ・ルンプ(一九五五)の研究によると、『原・赤ずきん』に登場する狼は、夜の象徴でも反キリスト教的な闇の力の象徴でもなく、まさしく「人狼」だった。十六、十七世紀フランスでは、女性にたいする魔女裁判に相当する、男性にたいする人狼裁判が伝染病のように流行した。夥しい裁判記録が残されているが、罪状はたいてい、狼の姿になって子どもを食ったというものである。そして、十九世紀末から今世紀にかけて口承版『赤ずきん』が採録された地方と、十五世紀から十七世紀にかけて人狼裁判がもっとも盛んだった地方とがぴたりと一致するのである。『原・赤ずきん』は、太陽信仰やキリスト教神学などではなく、当時の農民の性質の物質的条件と伝統的な異教的迷信とに彩られているのである。人びとは森には邪悪な魔物が住んでいるとかたく信じ、実際、森や野では子どもが獣あるいは人間のおとなに殺されていたのである。
しかしこの民話はたんなる訓戒物語ではなく、同時に、一人前の女になった少女にたいする祝福でもある。イヴォンヌ・ヴェルディエの研究(一九七八)によると、ピンの道と針の道というのは、農民の若い娘たちが一度は通らなくてはならないお針仕事の見習いと関係があり、お針を習うということは、その娘が年頃になり、女として社会に受け入れられることを意味していた。そして赤ずきんが祖母の肉を食べることは、伝統の継続と再活性化を象徴している。この世代交替はすんなり行われたわけではなく、女と女の闘いによって少女は伝統を身につけていったのだ。ここで重要なことは、この伝統が上からあたえられるものではなく、少女がみずからの力で身につけていくということであり、この民話は、ペローやグリムの版とは違って、少女の自力による独立を讃えているのである。
ペローはこの民話を上流階級向けに書き換えたのだった。対象はおとなと子どもの両方であったが、どちらかといえばおとなに受けるようペローは工夫している。ペロー版『赤ずきん』はエロティックな教訓物語であり、末尾には次のような教訓が付されている。
ごらんの通り、年端のいかない若者は
とくに美しく愛らしく人好きのする女の子は
どんな相手と口をきいても間違いのもとになるから御用心。
狼は食べるのが商売なのだから
食べられたって不思議はないのです。
もっとも、一口に狼と申しましても
いろいろ種類がありまして
牙をかくし、爪をかくし
御機嫌とりの、甘い言葉をささやきながら
若い娘のあとをつけまわし
こっそり家の中まで、寝室まで
押し入ってくるような抜け目のない性質のものもある。
いろいろ種類のあるなかで、
この甘ったるい狼ほど、
危険なものはないのです。 (澁澤龍彦訳)
先に述べたように赤いずきんというのはペローの創作である。ずきんは、十六、十七世紀に貴族や中流階級の夫人が被ったおしゃれ帽である。どうしてペローが民話にこれを付け加えたのかは不明である。ただ、当時、赤は一般に罪・官能・悪魔を連想させる色であった。祖母から赤いずきんを贈られたということは、この少女が最初からスポイルされていることを示唆していると同時に、この少女がなにか社会から逸脱した要素をうちに秘めており、魔女になりうる素質をもっていることを示しているとも考えられる。赤ずきんが狼(森に住む悪魔的なもの)と言葉を交わすことも、この物語を聞く当時の人びとには、赤ずきんの魔的な素質を感じさせたにちがいない。そして、社会からはみ出した者は罰せられ、みずからの命によってその罪を贖わなくてはならない。
民話の赤ずきんは素朴で、勇敢で、機転をきかして狼を欺き、だれの助けも借りずに逃げおおせた。ところがペローの赤ずきんは、可愛いけれど甘えんぼう、人を疑うことを知らず、機転がきかず、なんとも頼りない。
新旧論争において近代派の代表的論客のひとりだったペローは、民話をも「近代化」「文明化」しようという姿勢のもとに、おとぎ話を書いた。彼にとって子どもは野蛮であり、未開であり、文明化しなくてはならない。ペローはそのおとぎ話を通じて、子どもはこのように育つべきだという規範を示そうとしたのだった。これは何もペローに限ったことではなく、十六、十七世紀にはテーブル・マナー、寝室でのエチケット、会話術などに関する本や、「子どもかくあるべし」という育児書が数多く出ており、貴族階級や上流ブルジョワジーのなかで、そういった書物の影響をまぬがれずにいることは不可能であった。
いまひとつ、ペローの『赤ずきん』には作者の女性にたいする偏見が色濃くあらわれている。子ども同様、女もまた誘惑に弱い愚かな生き物であり、男性が保護してやらなくてはならない。したがって、ペロー版『赤ずきん』が口承版あるいは農民版のそれを駆逐しつつ全世界に広まったことは、社会史的にみてひじょうに大きな意味をもっているといえよう。
ペローの物語は「大ヒット」し、一七一二年には英訳され、一七九〇年にはドイツ語に訳された(かなり遅かったという印象を受けるが、ヨーロッパの貴族やブルジョワはフランス語を話し、あるいはフランス人の女中を雇っていたという事実を忘れてはならない)。印刷物で広まっただけでなく、先にも触れたように、この物語はふたたび民衆の口承伝統のなかへと入っていった。
グリム版『赤ずきん』(一八一二)のもとになったのがペローの物語であることは確実である。ハインツ・レールケの研究によると、フランス・ユグノーの流れを引く家族の出で、フランス風雰囲気のなかで育ったマリー・ハッセンプルークという女性が、一八一一年か一二年に、この物語をグリム兄弟に聞かせた。またグリム兄弟は、ペローの物語を下敷きにしたティークの戯曲『赤ずきんの生と死』(一八〇〇)を知っていたはずだし、おそらくは子どもの頃、じかにペローの物語を読んでいただろうと考えられる。
ペロー版『赤ずきん』とグリム版との最大の相違は結末である。ペローの話は、赤ずきんが狼に食べられてしまうところで終わるが、グリムの話では、狩人が狼の腹を引き裂いておばあさんと赤ずきんを助け出し、狼は腹に石を詰められて死ぬ。この結末は、いうまでもなくドイツ民話『狼と七匹の子やぎ』から借用したものである。さらに、グリムは狼を一度殺すだけでは飽き足らず、後日談を加えている----あるとき、赤ずきんはやはりおばあさんにお菓子を届けに行く途中、森で別の狼に出会うが、今度は脇目もふらずにおばあさんの家にいく。狼は屋根の上で赤ずきんが帰途につくのを待つが、おばあさんと赤ずきんは力を合わせて、大きな水桶を腸詰を煮た湯でみたし、狼は匂いにつられて屋根から水桶のなかに落ち、溺れ死ぬ。
昔話はすべてハッピーエンドでなければならないとするベッテルハイムは、ペロー版を糞味噌にけなし、グリム版のほうこそ本来の昔話の姿と見なし、この後日談をこう解釈している----「赤ずきんは、ひどい目にあったあと、自分はとても狼(誘惑者)に立ちむかうほど成熟していないと気づく。そして、母親と力をあわせて狼に対抗することにする。[・・・]このように子どもは、同性の親としっかり協力しあう必要がある。子どもはそれによって親と自分を同一視し、また意識的に親から学んで、うまく大人になっていくのだ」。しかし、このハッピーエンドが農民版『赤ずきん』のハッピーエンドとは違うのだということ、すなわち赤ずきんは自力で自分を救うのではなく、最初は狩人によって、次はおばあさんの知恵によって救われるのだということを忘れてはならない。
このハッピーエンドにたいしては別の見方もできる。ペローが『原・赤ずきん』の人狼をただの狼に変えたのは、彼の時代にはすでに魔女裁判・人狼裁判の流行は去っていたからだが、聞き手のほうは、もはや人狼を恐れていなかったにせよ、狼によって人狼の記憶が呼びおこされたにちがいなく、彼の物語の結末が示しているように、悪魔的なものと関わったものは処刑されなければならなかったのである。だが、グリムの時代になると、すでにそうした態度も過去のものとなり、悔い改めることによって過ちは許されるという態度に取って代わられたのであり、教訓的要素がさらに前面に押し出されている。
グリムの話でも、ペローと同様、赤ずきんは自分で自分を救うことはできない。子どもはおとなの言うことを聞かなくてはならないのだという姿勢がつよく押し出されており、命令と服従、違反と処罰という図式がペローよりもいっそう強調されている。
ペローは貴族と上流ブルジョワのために書いたが、グリムが対象としたのはブルジョワの子弟であったから、性的な仄めかしは表面から消し去られているが、人びとはそのなかに容易に性的なメッセージを読みとったのであり、フーコーが『性の歴史』において指摘しているように、『赤ずきん』は十九世紀には、とくに中流家庭において、子どもにたいする性教育の材料として用いられたのである。
もうひとつ、グリム版『赤ずきん』には政治的メッセージが籠められている。グリムが『赤ずきん』を採話したのは、カッセルとラインラントがフランスのナポレオン軍によって占領されていた時代であり、ハンス=ヴォルフ・イェーガーの研究(一九七四)によると、グリム版『赤ずきん』には、反フランス、反啓蒙主義のメッセージが籠められているという。狼はフランス啓蒙主義であり、赤ずきんはドイツの無垢な若者である。実際、当時のドイツ文学にはフランスを狼にたとえた作品が多かったという。狼=フランス革命軍はドイツの若者に自由をあたえ、ドイツ精神を破壊するためにやってきた。無垢な若者は、革命軍の誘惑に負け、邪悪なフランス軍によって野蛮な革命の渦に呑み込まれるが、ドイツ絶対主義(の番人=警察権力)によって救われるというわけである。今日、こんな読み方をする人がいるとは思われないが、この話の底に、個人の自立と想像力にたいする法と秩序の優位性の主張があることは容易にみてとれよう。グリムは、ペローによって貴族・上流ブルジョワ向けに書き換えられた物語を、さらに、ブルジョワ的に書き直したのだった。以降、十九世紀を通じてこの物語は、子どもはおとなの言いつけに従うべし、女は男に服従すべし、というブルジョワ・イデオロギーの強力な道具として用いられ、多くの作家たちがそれに合わせてさらにブルジョワ的に書き換えていくことになる。
グリム以降、第一次世界大戦まで、グリムの物語はほとんどそのままの形で継承され、他の作家たちによるヴァージョンも、グリム版からほとんどはずれておらず、驚くほどの一貫性をみせているが、第一次大戦以降、変化が起き、このグリムによってつくりあげられた定型にたいする大胆な実験が次々に試みられるようになる。
そのはしりとなった実験のひとつが、ヨアヒム・リンゲルナッツの『クッテル・ダッデルドゥが子どもたちに赤ずきんのお話を聞かせる』(一九二四)である。このリンゲルナッツの物語では、赤ずきんの先回りをしておばあさんの家(シュヴィガー通り一三番地一階)に行った狼が、おばあさんに食べられてしまう。赤ずきんは森の中で道に迷って泣いているところを狩人に助けられ、おばあさんの家に急ぐが、「どうしておばあさんの口はそんなに大きいの?」という質問に、「子どもが祖母にいうことばか!」と怒ったおばあさんに食べられてしまう。通りかかった狩人もまた食べられてしまう。
キャサリン・ストー『ポリーずきん』(一九五五)では、『赤ずきん』の話を読んだ狼が、そのストーリー通りに少女ポリーとおばあさんを食べようと、ポリーに声をかける。
「こんにちわ、ポリー」狼がいいました。「どこへ行くのか、聞いてもいい?」
「もちろんよ」ポリーは答えました。「おばあさんに会いにいくのよ」。
「そうだと思った!」狼はじつに満足げに言いました。「ぼく、この間から、おばあさ んに会いに行く女の子のお話を読んでるんだ。とってもいい話なんだ」。
「『赤ずきん』のこと?」
「そう、それ! 毎晩、寝る前に声に出して読むんだ。ぼくはこの話が大好きでね。狼
がおばあさんと赤ずきんを食べてしまうんだ。狼が本当になにか食べるものを手に入れ るっていうのは、この話くらいしかないんじゃないかな」狼はちょっとさみしそうに言 いました。
「でも、わたしがもってる本じゃ、狼は赤ずきんを食べないわ。あやういところで、お 父さんがきて助けてくれるのよ」。
「そんなの、ぼくの本にはでてこないよ。たぶんほくの本のほうが本当の話で、きみの はつくりものだと思うよ。でもとにかく、いいアイデアだな」。
「なにが?」
「おばあさんの家に行く途中の女の子をつかまえるっていうことさ」狼は言いました。 「ところで、ぼくはどこへ行けばいいんだい?」
「どういう意味?」
「つまり、『きみはどこへ行くの?』ってことさ。あ、そうだ、ぼくはここで『おばあ さんはどこに住んでるの、ポリーずきんちゃん?』って聞かなくちゃいけないんだっ た」。
「町の反対のはずれよ」。
狼は顔をしかめました。
「『森の向こう』でなくちゃいけないんだがな。でも、たぶん町でもいいんだろう。ど うやっていくの、ポリーずきんちゃん?」
「電車にのって、それからバスよ」。
狼は足を踏み鳴らしました。
「ちがう、ちがう、ちがう! 間違ってるよ。そんなこと言っちゃだめだ。『森のなか の曲がりくねった道を通って』とかなんとか言わなくちゃいけないんだよ。電車とかバ スとか、そんなもので行っちゃだめだよ。フェアじゃないよ」。
狼は金をもっていないので、電車にのれない。次の機会には金を用意してくるが、そのときにはポリーは両親の自動車で出かける。結局、狼は『赤ずきん』の物語通りに事を運ぶことができないで終わる。
こうしたパロディは、物語をたんにそのまま繰り返すという現代の語りにたいする批判であり、かつてのダイナミックなパフォーマンスとしての語りを想起させようとする(ちなみに子どもというものは、わが家の二歳の娘でさえ、いったん昔話を覚えるとすぐに、ストーリーを勝手に変えて面白がるものである)。ジョヴァンニ・ロダーリの『緑ずきん』(一九七三)は、こうした「語り」を問題にした実験のなかでも、もっとも過激なもののひとつだ。
昔あるところに、みんなから『黄色ずきん』と呼ばれている女の子がいました。
「違うわよ! 赤ずきんよ!」
「そうそう、赤ずきんだ。さて、ある日、おかあさんが言いました。『緑ずきん
や・・・』」。
「赤!」
「ごめんごめん、赤だった。『いい子だから、メアリーおばさんにこのポテトをもっ ていっておくれ』と・・・」。
「違うわ、そうじゃないわ。『おばあさんにこのお菓子をもっていっておくれ』って言 うのよ」。
「そうだったな。それで女の子は出かけていきました。森のなかで、女の子はキリンに 会いました」。
「めちゃくちゃだわ! 狼よ!」
「狼は言いました、『八かける六はいくつだね?』」
「うそよ、うそよ、『どこへ行くの?』ってきくのよ」。
「そう、狼はそう言いました。すると黒ずきんは答えました」。
「赤! 赤!! 赤!!!」
「女の子は『マーケットにトマトを買いにいくの』と答えました」。
「違います! 『病気のおばあさんをお見舞いにいくの。でも道に迷っちゃったの』っ て答えるんだわ」。
「もちろんそうさ。すると馬は言いました・・・」。
「馬ですって! 狼よ」。
「そうさ、狼はこう言いました、『75番のバスにのって中央広場で降り、右に曲がる と、最初の家の玄関に階段が三段ある。階段はのぼらず、そこに10セントおいてあるか ら、それでチューインガムを一箱買いなさい』」。
「おじいちゃんて、お話がへたくそね。ぜんぶ間違ってるわ。でもいいわ、チューイン ガムはわるくないわ」。
「よし、ほら10セントだよ」そう言うと、老人はまた新聞を読みはじめました。
こうした「語り」の問題をめぐる、伝統的ストーリー・ラインの解体実験のほか、たとえばナチス暗黒時代に書かれたウールリヒ・リンクの『赤ずきん』(一九三七)や、スターリンの大粛清時代に書かれたエヴゲーニイ・シュヴァルツの戯曲『赤ずきん』(一九三七)のように、作者の切実な政治的メッセージが盛り込まれたものも多い。マックス・フォン・デル・グリュンの『赤ずきん』(一九七四)では、小さな白い星のついた赤い帽子を祖母からもらった少女が、友達にほめてもらおうと思ってそれを被って学校に行くと、突然みんなからいじめられるようになる。母親といっしょに買い物に行くと、近所の人は白い眼で見、店の人の対応も冷たい。ある日、バイクにのった少女は、やはりバイクにのった「いじめ」グループに襲われ、赤い帽子を失くしてしまう。すると、級友も近所のひともころりと以前の態度に戻る。ユダヤ人を象徴しているのか、共産党を象徴しているのか。
われわれの関心にとってもっとも重要だと思われるのは、ペローあるいはグリムの性的偏見に敏感に反応した作家たちの作品、あるいは女性にたいする社会的態度の変化を反映した作品である。そうした作品のひとつ、ジェームズ・サーバーの『少女と狼』(一九三九)は比較的よく知られている現代版『赤ずきん』のひとつだろう。途中までは伝統的なストーリーを踏襲しているが----
少女がおばあさんの家のドアをあけると、だれかがナイトキャップをかぶってベッド に寝ているのが見えました。少女がベッドから二五フィートのところまでくるかこない うちに、それがおばあさんではなく狼だということが分かりました。だって、たとえナ イトキャップをかぶってたって、狼がおばあさんに見えるはずがないじゃありません か。メトロ=ゴールドウィンのライオンがカルヴィン・クーリッジに見えますか? そ こで少女はバスケットから自動拳銃をとりだし、狼を撃ち殺してしまいました。
教訓----昨今、少女を騙すことはむかしほど簡単ではありません。
これを気のきいたパロディとして笑って済ますこともできるが、赤ずきんを愚かで無能な少女に仕立てあげたペローやグリムにたいする批判として読むこともじゅうぶん可能である。
また、トミ・アンガラーの『赤ずきん』(一九七四)では、赤ずきんは祖母のことなどほったらかして、狼と結婚してしまう。これは、自分の本性・自然な欲望に従うと身を滅ぼすというペロー、グリムの教訓にたいするアンチ・テーゼである。自分の自然な欲求に従ってなぜ悪い。
また、口承版『赤ずきん』の世界を下敷きにした、アンジェラ・カーターのゴシック・ノベル『狼の友』(一九七九)では、少女は捨身で狼に立ち向かい、ついに狼を手懐けてしまう。
しかし、このような、ペローやグリムにたいするフェミニズム的批判として読むことの可能な『赤ずきん』はあくまで例外的存在であって、今日、本屋にいって児童書売場に並んでいる『赤ずきん』を片っ端から開いてみればわかるように、どれもすべてグリムの『赤ずきん』である。そして、グリムはペローの話を残酷すぎると感じたのだったが、現在の子どもたち、いやむしろ親たち(そして作家たち、すなわち本をあたえる側)にとってはグリム童話でさえ残酷すぎるように思われ、たとえばディズニー・プロダクション版『赤ずきん』では(筆者の知っているのは紙芝居だが)、狼の腹を引き裂く場面さえ削除され、正義の味方である熊が狼をさかさにして振ると、中から赤ずきんとおばあさんが出てくる。おまけに冒頭に「これは狼のでてくるちょっとこわーいお話です」というナレーションまでついている。このように砂糖でまぶされているとはいえ、やはり巷に流布しているのはグリムの『赤ずきん』である。
ベッテルハイムはこのグリム版『赤ずきん』を、時代を越えて人間の普遍的な心理発達を象徴する物語と見なす。たしかにグリムの話は一八〇年近く経った今日でさえ、子どもたちに強烈な印象を刻みつける。しかし、グリム以降(あるいはペロー以降といってもいいが)今日にいたるまである一貫性がみられるのにたいし、農民が生んだ『赤ずきん』とペロー以降のそれとの間には大きな断絶がある。それは近代と前近代との断絶であり、ペロー=グリムの『赤ずきん』はこの近代の産物に他ならないのである。ベッテルハイムのようにグリムを普遍化することは近代を人間文明の普遍的形態ととらえることに他ならず、病としての近代という視点がごっそり抜け落ちている。グリムの『赤ずきん』が愛されてきた歴史は、子どもの自然な成長が歪められ、女性が差別されてきた歴史であり、近代という病が生んだ「赤ずきん症候群」なのである。
しかしもちろん、『赤ずきん』における性的偏見・社会的抑圧を指摘することと、この物語を全面的に否定することとは別のことである。最後に、ザイプスの論文の結びの一節を引用する。
「以上いろいろと述べてきたが、わたしは、この物語は時代遅れだとか、全面的に否定されるべきだとか主張するつもりはないし、女性開放運動や学校の教員会議で検閲修正されるべきだとか、性差別の要素を削って書き換えるべきだとか主張するつもりは毛頭ない。問題はこの文学作品のなかにあるわけではないし、検閲修正によって解決されるわけでもない。女性が男の犠牲になってきたという西洋の社会的条件を考えてみると、この物語には積極的に評価されるべき要素があるといわねばならない。性的暴行を受けるかもしれないというこの物語の警告は、いまだに社会的目的に役立っているのである。現在、私が教えている大学において、図書館や校舎やキャンパス内では、強姦や暴力にそなえて、女子学生は(赤ずきんならぬ)ホイッスルを携帯していなければならない。こういう学問施設はけっしてめずらしくない。男性が、自分の生をまっとうするためにはかならずしも狼や狩人になる必要はないのだということを習得するまでは、『赤ずきん』の物語は女性たちにたいして貴重な教訓をあたえつづけるだろう」。
<参考文献>
Bettelheim, Bruno, The Use of Enchantment, 1976. ブルーノ・ベッテルハイム『昔話の魔力』(波多野・乾訳、評論社)
Fromm, Erich, The Forgotten Language : An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths, 1951. エーリッヒ・フロム『夢の精神分析----忘れられた言語』(外林訳、東京創元社)
Jung, C. G., The Theory of Psychoanalysis, 1912, in The Collected Works of C. G. Jung, vol. 4.
Darnton, Robert, 'Peasants Tell Tales : The Meaning of Mother Goose' in The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, 1984.
Zipes, Jack, The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood : Versions of the Tale in Sociocultural Context, 1983.
---- , ' On the Use and Abuse of Folk and Fairy Tales with Children : Bruno Bettelheim's Moralistic Magic Wand ', in Breaking the Magic Spell : Radical Theories of Folk and Fairy Tales, 1979.
Bettelheim, Bruno, The Use of Enchantment, 1976. ブルーノ・ベッテルハイム『昔話の魔力』(波多野・乾訳、評論社)
Fromm, Erich, The Forgotten Language : An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths, 1951. エーリッヒ・フロム『夢の精神分析----忘れられた言語』(外林訳、東京創元社)
Jung, C. G., The Theory of Psychoanalysis, 1912, in The Collected Works of C. G. Jung, vol. 4.
Darnton, Robert, 'Peasants Tell Tales : The Meaning of Mother Goose' in The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, 1984.
Zipes, Jack, The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood : Versions of the Tale in Sociocultural Context, 1983.
---- , ' On the Use and Abuse of Folk and Fairy Tales with Children : Bruno Bettelheim's Moralistic Magic Wand ', in Breaking the Magic Spell : Radical Theories of Folk and Fairy Tales, 1979.
| 戻る |