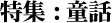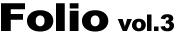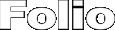メルヘンとは何か。メルヘンはどこから生まれ、何を語っているのか。この問いに答えるのは容易ではない。「民俗学は昔話を文化史的・精神史的資料として研究し??心理学はその物語を心的過程の表出として考え??文芸学は昔話をして昔話たらしめるものを確認しようとつとめる」と、メルヘン研究の世界的権威とされているマックス・リューティはその『ヨーロッパの昔話──その形式と本質』のなかで書いているが、実際、メルヘンにたいするアプローチはじつにさまざまで、民俗学、心理学、文芸学にとどまらず、宗教学、文化人類学、歴史学、社会学、犯罪学にいたるさまざまな分野の学者が、我こそがメルヘン研究の権威であると主張してきたし、更に、イデオロギーを異にするさまざまな人びとが、それぞれメルヘンに自分たちの主義主張を投影してきた。
メルヘンとは何か──この問いにたいして、さまざまな立場から多種多様な答えが提出されてきたのである。
世界中でもっとも人気のあるメルヘンのひとつ、『赤ずきん』を例に挙げよう。グリム童話を「聖典」として崇めた第三帝国のファシストたちはこの物語を、ゲルマン民族を象徴する「赤ずきん」が、ユダヤ人という狼によって脅かされ、欺かれ、最後には解放される物語と解釈した(ユダヤ人は同じ物語にたいし、ナチスとは正反対の解釈を下したであろう)。このナチ的解釈は、いつの時代にもメルヘンは政治的に利用されうることを示しているが、ある学者の研究によると、グリム兄弟自身からして、この物語に政治的メッセージを籠めているという。赤ずきんはドイツの無垢の若者の象徴であり、いっぽう狼は、グリムがこのメルヘンを採話した当時、カッセルおよびラインラントを占領していたフランス軍を象徴しており、この物語は、自由と解放をあたえるというフランス啓蒙主義の誘惑に負け、革命の渦に巻き込まれたドイツの若者が、ドイツ絶対主義という狩人によって救われるという物語なのだという。グリム兄弟自身にそうした政治的意図がどの程度あったのかはさしおき、当時のドイツ文学にはフランスを狼にたとえた作品が多かったのは事実であり、『子どもと家庭の童話』の読者のなかに、政治的な読み方をする者が少なからずいたことは確実だと思われる(ちなみに、わが国でも第二次大戦中、かのアニメ映画の名作『海の神兵』からも窺われるように、鬼を征伐する桃太郎の物語が、「鬼畜」英米と戦う日本を象徴するものとして利用されたことは周知の通りである)。
子どもに『赤ずきん』を読んできかせるときに、「この狼はユダヤ人のことなのだよ」とか「この狼はフランス人なのだよ」と言い聞かせることによって、ユダヤ人やフランス人にたいする恐怖と嫌悪をその子に植えつけることは可能だろう。だが、もしなんの註釈も加えずにこの物語を聞かせたら、子どもはそこからどんなメッセージを受け取るだろうか。この点に関してもさまざまな議論があるが、ごく素直に考えれば、やはり子どもはこのお話を、決められた道を一歩踏み外すと怖い目にあうぞという警告物語として受け取るだろう。実際、今日人口に膾炙している赤ずきん物語の原型はペローの『赤ずきん』だが、そのもとになったのは中世末期に生まれた警告物語であるといわれている。
レイプの寓話
何にたいする警告か。ある研究者によると、赤ずきんを食べようとする狼はいわゆる人狼だという。十九世紀末から今世紀にかけて、メルヘンが盛んに採話されたが、口承によって伝えられた『赤ずきん』が採話された地方と、十五世紀から十七世紀に人狼裁判がもっとも盛んに行なわれた地方とがぴったり一致するのだそうだ。しかし、今日この物語が子どもにあたえるメッセージについて考えるとき、そうした歴史的解釈が意味をもたないことはいうまでもない。ブラウンミラーはレイプ告発の書としては古典的名著となった『私たちの意志に反して』のなかで、「『赤ずきん』はレイプの寓話である」と言明する。すなわち、この物語に籠められた警告は子ども一般にたいする警告ではなく、女の子にたいする警告であり、子どもがあう怖い目とはまさしくレイプに他ならない。それが証拠に、『ピーターと狼』ではピーターがじつに巧みに狼の攻撃をかわすではないか。『三匹の子ぶた』の末っ子にしてもそうだ。男の子は狼をやっつけることができるが、赤ずきんもおばあさんも狼にたいしてまったく無力で無抵抗だ。『赤ずきん』に限らず、ガラスの柩のなかに横たわって王子を待つ「白雪姫」や、茨に囲まれて百年間眠り続ける「眠り姫」は、女の子はひたすらじっとしていなければいけないというメッセージを送り続けているのだ、とブラウンミラーは告発する。
書かれたメルヘン
メルヘンとは何か。メルヘンにたいするさまざまな解釈のなかで、一般にもっとも人気のあるのは精神分析学者によるものだろう。彼らはほぼ一致して、メルヘンを人間の心的過程の表現とみなし、とくに子どもが成長してゆく過程で出会うさまざまな心理的問題を扱っていると解釈する。だが、たとえば、『赤ずきん』に登場する狼を、フロイト派は男性と解釈し、ユング派は母親と解釈するといったふうに、心理学者の間でも同じ一つのメルヘン、一つのモチーフにたいする解釈は、さまざまに異なる。
ここでは心理学的解釈の詳細には立ち入らないけれども、心理学者たちに共通してみられるのは、あらゆる細部に解釈を下そうという姿勢である。たとえば、『白雪姫』の冒頭で后(白雪姫の実母)が針で指を刺し、血が三滴たれるが、フロイト派もユング派もこの三という数の意味について詳細に論じている。もちろんこうした姿勢はごく自然である。ある方法論にもとづいて何かを研究する際に、その方法論では解釈ができない部分があってはならないのであるから。ただ問題は、そうした細部にたいする解釈がメルヘンの場合にどの程度意味をもつかということだ。結論からいうと、メルヘンには多数のヴァリアントが存在し、一つの「原型」を確定することはまったく不可能だから、細部の分析はメルヘン研究としては意味をもたないのである。偉大な作家が書いた文学作品の場合には、その一節を取り上げて、その意味について詳細に論じるということも意味をもつが、特定の作者がおらず、いわば集合的な想像力によって生み出されたメルヘンの場合にはそれはあてはまらないのである。
実際、ヴァリアントが多数存在することを無視してメルヘンを論じることは危険である。アメリカ・インディアンのポタワトミ族の民話にはプティージャーという主人公が登場するが、これはもとを辿ればフランスの民話に登場するプチ・ジャンであり、このことを知らない民俗学者は、アメリカ・インディアンの文化について見当違いの結論を出しかねない。また、精神分析学者は『シンデレラ』『白雪姫』『眠れる森の美女』などの物語は本質的に女性の心の成長の物語であるというが、十八世紀以前のドイツには男のシンデレラ物語が女性のそれに劣らず流布していたこと、トルコ民話にはシンデレラや白雪姫の男性版があること、ロシア民話にも眠り姫の男性版があることを、彼らはどう説明するのだろう。赤ずきんの赤色は処女の流す血を、シンデレラのガラスの靴は壊れやすい処女性を象徴しているという解釈が人口に膾炙しているけれど、赤いずきんもガラスの靴もペローのまさしく天才的着想であって、もとになった民話には登場しないのである。
ただし筆者は、歴史学的・社会学的メルヘン研究の立場から精神分析を糞味噌にけなす人びとに全面的に賛同するものではない。たしかにメルヘンの本質的部分について考えるときに、個々のメルヘンの細部にたいする精神分析的な解釈は意味をもたないが、私たちが幼い頃から慣れ親しんでいるメルヘンは、口承で伝えられてきたものではなく、バジーレ、ペロー、グリムらによって「書かれた(=固定された)メルヘン」であることを考えれば、細部の分析が意味をもたないとは思われない。
史実と超自然
だが、それはあくまでメルヘンの現代的意味を論じる上でのことであって、その起源と発達を考えるとなると問題はまったく異なる。心理学的な解釈のほぼ正反対に位置するのが、歴史学的メルヘン研究、すなわちメルヘンは史実にもとづいたものだという立場である。先に挙げた、『赤ずきん』の狼はいわゆる人狼であり、この物語は実際に頻発していた幼児殺害にたいする警告なのだという説は、この立場に属する。メルヘンの物語はまさしく奇異であって、その奇異性こそが本質であるとさえいってもいいが、その背後になんらかの史実があるのではないかという疑いが生じるのも自然といえよう。阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男』を思い出してみればよい。しかし、そうした探求心も極端に走るとじつに馬鹿げたことになる。トラクスラーの『「ヘンゼルとグレーテル」の真相』に紹介されている某しろうと歴史家は、ヘンゼルとグレーテルの物語が歴史上のある事件にもとづいたものだと確信し、調査に取り組んだ。数年後、彼はこの兄妹の住んでいた家を、フランクフルトとヴュルツブルクを結ぶアウトバーンに隣接した地点に「確定」し、付近の森の中で、魔女の家の土台や炭化した菓子を「発掘」したという。
プロップが指摘するように、メルヘンにおいて、状況・背景には時代性・地域性が色濃く影を落としており、現実的であるが、その本質的部分はじつに「超自然的」なのである。プロップはいう、「ロシア民話には、真実味のあるプロットなどただの一つもない」。
心の物語化
メルヘンとはいったい何か。その起源はどこにあるのか。十九世紀の比較神話学者たちは、神話(およびメルヘン)を自然現象、とくに太陽の運行の物語化と考えた。龍を退治する英雄は闇を克服する太陽の象徴であり、彼らのもつ剣や槍や矢は太陽の光を表わしている。英雄たちの苦難にみちた旅は、東から西へと向かう太陽の運行の譬喩である、と。ちなみに、こうした解釈はいわゆるヴィクトリア朝的道徳観と合致していた。というのも、この解釈によれば、子どもを食う親は、極悪非道の親がいることを示唆しているわけではなく、雲を飲み込んだり吐き出したりする天空の象徴に他ならず、ヘンゼルとグレーテルのように、森の中に置き去りにされた子どもも、冷酷な親の存在を仄めかしているわけではなくて、夜の闇を照らしだす星々にすぎないのだ。したがって『赤ずきん』も、狼という闇に飲み込まれては復活する太陽の物語とされる。もちろん赤い色は太陽の輝きの象徴だ。
しかし、どう考えてみても、天体の運行などの自然現象を説明するだけのために人間が神話やメルヘンを生み 出したとは思えない(ただし、外界の現象に接したときにそれを物語化するという性向が人間に本来的にそなわっているものであることを否定するつもりはない。物語本能とでも呼ぶべきものを否定してしまっては、いっさいの議論はなりたたないように思われる)。C・G・ユングもまた、古代人が天体の運行を説明するためだけに神話やメルヘンを生み出したはずはないと考えた。ユングによれば、古代人は天体を物語化することによって、じつは自分の心の中の動きを物語化しようとしたのである。より厳密には、ユングはレヴィ=ブリュールのいう「神秘的関与」を念頭においていた。すなわち、古代人においては天体という外界と自分の内面とが分離していなかったと考えるのである。神話やメルヘンの起源について考えるとき、これがもっとも妥当な説明だと思われる。が、この説明では、古代人の心性が失われたにもかかわらず、今なおメルヘンが強大な影響力をもちつづけている理由を説明することはできないし、ことメルヘンに関する限り、その起源はかならずしも古代にまで遡らないという事実をうまく処理することはできない。にもかかわらず、 この説明は、歴史的・事実的起源説と心理的起源説の対立を解決するのに有効なのではなかろうか。心は外界と独立して活動しているものではないからである。
| 戻る |