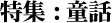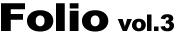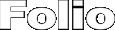何事かを為すに人生はあまりに短く、無為に過ごすにはあまりに長い。私の人生のハイライトは二十年前のあの日に過ぎ、残りは余生と成り果てた。今から思えば悪友三匹を連れただけで、孤島の集落をひとつ壊滅させたのだから、まさに奇跡というよりほかはない。その有り得べからざることをやってのけ、おまけに彼らの蓄財を戦利品として持ち帰ったことで、私の人生は道を誤ったのだと思う。
少年期に見られる全能感、自分は特別であるという思い込みは、学校や社会の軋轢に喘ぐうちに角を落とし、やがて丸みを帯びた人格へと形成されるのだが、私はいかなる場合も「あの」桃太郎だった。出来が良ければ「さすが桃太郎」、不出来であっても「桃太郎だから」のひとことで許される。非常識な振る舞いでさえも「やはり桃太郎は凡人とは違う」と褒めそやす。
そのような扱いが心地良かったことは否定できない。他の少年たちと同じ土俵に上がらず、常に高い位置から彼らを眺めていられるのは快感だった。同世代の少年たちが身の振り方を考える時期になっても、依然私の家には略奪してきた金品が残っており、私個人は相変わらず桃太郎然として、目先の諸問題に躍起になっている連中を鼻で嗤っていた。
そして辿り着いた現在はひどく矮小だ。
書店に行けばカラー刷りの絵本が置いてある。年々その顔ぶれは変化している――洋物が幅を利かせてきているようだ――が、まだ私の物語は忘れ去られていないらしい。頬を紅く塗った前髪立ちの少年が、イヌサルキジを引き連れて勇ましく刀を突き出している表紙――。
おとぎ話はめでたしめでたしで終わる。だが更に人生は続く。
私の知る限り、おとぎ話の主人公たちのほとんどが精彩を欠く“その後”を送っているようだ。
打出の小槌で大きくなった一寸法師はもはやただの人であり、素封家の女房と離婚したあと、ずっと独り身を通している。
一時はトレーディングの神様などともてはやされていた藁しべ長者も、バブル崩壊の余波に呑み込まれて破産した。
浦島太郎は昨年他界した。百歳を超える大往生というが、玉手箱を開けたのはつい十年ほど前のことである。実質三十年ばかりの生涯だったわけだ。
昔から虚言癖があり、少し精神を病んでいたかぐや姫は、何度もリストカットを繰り返し、ついに措置入院の運びとなった。二十年経てばかつての容色も衰える。しかし彼女はまだ物語の主人公でいたかったのだろう。
唯一の例外といえば金太郎くらいだろうか。金太郎は現在、源頼光という武者の家来になり、名も坂田金時と改めている。しかし頼光四天王とは名ばかり、実状はていの良い荷物持ちなのだそうだ。「馬鹿力があるだけですから」と彼は自分を卑下するが、それでも身の程を知っているだけ利口というものだ。彼はよく解っている。熊に相撲で勝ったくらいのことを鼻に掛けていては世の中を渡っていけない。
そして私はといえばお百度を踏むかのごとくハローワークに日参する毎日。学歴もない、職歴もない、免許も資格も何もない実に簡素な履歴書を一瞥し、ハローワークの職員は気の毒そうな、しかしあからさまに軽侮した視線を寄越す。備考に“鬼退治の経験あり”。
「いやぁ、鬼退治ですか、はぁ」
言わなくても解る。快楽殺人者にも人権を認めるこの世の中、そんなスキルは需要がない。だが言わないでくれ、その先は。それを言われてしまえば、私の過去は白紙になる。
物語は終わる。だがなおも人生は続く。
| 1 / 2 | Next |