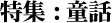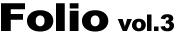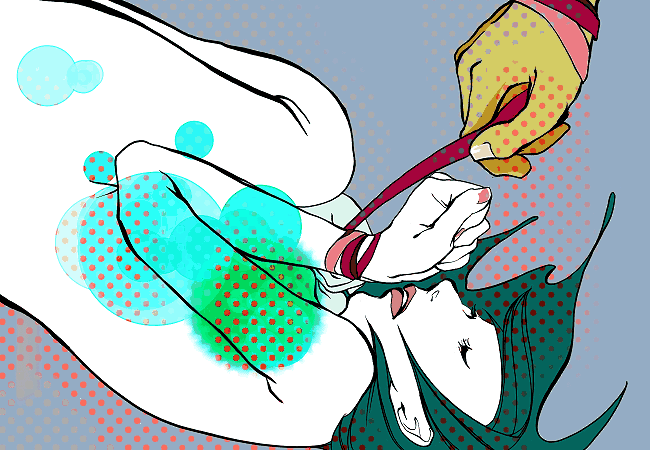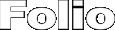そうした経験は、僕にとって初めてではなかった。そうした経験というのはつまり、友達の彼女が手首を切って友達がひどく傷ついている、という経験だ。そして僕の経験は、もう少し多くのことを知っていた。
彼は遅かれ早かれ、自殺することになるだろう。僕のかつての友達がやはり手首を切って死んだのと同じように。
手首を切って死ぬのは、簡単なことではない。リストカットは、完全に自殺するには実に不向きな方法だと昔聞いたことがある。死ぬなら薬やガスや、首を吊る方が確実である。だから僕の友達の元恋人たちはほとんど死ななかった。手首を切って死ぬには相当な覚悟が必要なのだ。死にたいというとてつもなく強い欲求だけが、致命傷になるほどの深い傷を自分に与えることができる。
高校時代の友達は、三人の恋人に手首を切られた。三人目は、そのせいで命を落とした。そして友達もすぐに後を追った。遺書にはこうあった。
「もうこれ以上、誰かを傷つけたりしたくありません」
友達の葬式はひそやかに行われた。同級生で来ていたのは、僕と、友達の一人目の恋人だけだった。彼女も、手首を切った一人だ。彼女はこう言った。
「わたしのせいよね」
僕は小さく首を振った。
「誰のせいでもないんだよ。僕のせいでもあるかもしれないし、君のせいでもあるかもしれない。両親のせいかもしれないし、他の女の子のせいかもしれない。でも、誰も悪くないんだ。この星は、こういう星なんだ。仕方がないよ」
彼女はしばらく黙って考えていた。そしてぽつりと
「あなたっていい人なのね」
と言った。いい人?そんなことを言われたのは初めてだった。
「みんな、私のせいじゃないわよ、って言ってくれるの。でも、それはただの慰めで、本当に私のせいだと思ってない人なんてどこにもいないの。あなたはそうじゃないわ。あなたは本当に、仕方のないことだと思ってる。それは、正しい考え方なのねきっと」
僕はその時から本当に、僕だって悪くはないと思っていた。最も親しい友達をこのような形で失ったことは比喩でなく死にたいほどに哀しい出来事だったし、その友達を救えなかったことはあまりに残念なことであった。それでも、彼が死ぬということは予め決まっていたように思えた。僕がどうあがいても―その時までにだって十分あがいていたのだけれど―、どんなに正しいあがき方をしたとしても、彼は手首を切って死んでいただろう。そういう気がした。
その時抱いた漠然とした考え方が、多少間違っていたにせよ本質的には正しかったのだということを知るのは、もう少しだけ後のことになる。けれどその考え方によって僕は、この世界の真実に一歩近づいていたのだった。
4
彼が恋人と別れてから沈み込んでいた時間は、そう長くなかった。一週間くらい、彼は自分の中に深く閉じこもってほとんど何も話そうとはしなかったけれど、その時期を過ぎると僕を初めとする限られた友達にぽつぽつと話をするようになった。僕らは彼が悪いわけではないということをひたすら説明した。彼が恋人を愛していたのは明らかだったし、彼は彼女を裏切ったわけでもなんでもないのだ。
だから、彼と恋人の関係を知っているものからすれば恋人がリストカットを繰り返してやがて離れていったというのは極めて不可解な事実であった。どんな人にでも不安や孤独感はある。人はそれを埋めるために他人を求める。彼もそうだったし、おそらく恋人もそうだった。しかしながら、彼女の場合どうやらその漠然とした寂寥感や言いようのない生きることに対する恐怖心が、彼と一緒にいることによって増幅され、そして一層彼を求めるといったような悪循環に陥っていたようだったのだ。
僕はそうした関係性から、死んだ高校の友達を思い出した。同じだ、と僕は思った。本当はもう少し早く気付くべきだったのだ。けれど、彼は自分の恋愛についての悩みを人に話すようなタイプではなかったし、僕は極めてうまくいっていると思い込んでしまっていたのだ。
やがて彼は再び恋人を作った。それは実に自然な成り行きだった。彼は傷を癒してくれる誰かを心から求めていた。そしてその関係は今度こそ上手くいくように思えた。彼は優しく実直で、人を愛するということに実に長けた人間であったし、また彼女もそうした愛を受けるのに適した人間であるように見えた。けれども結局この恋愛もほぼ前回と同じ道を歩むことになった。命は失われなかったものの血が流れ、そして彼の傷はまた深くなった。
僕は、そのころにはどうやら気付いてしまっていた。高校でも大学でも親友がこのような不幸な道を歩むことになるのは、僕のせいであるということに。高校の頃、僕は自分の中に自分ではどうしても制御することの出来ない闇が存在することを感じ取るようになった。それをためこんでしまうと僕はパンクしてしまいそうだった。だから僕は山ほどの小説を読み、そして書いた。演劇を作り、映画も作った。そうしたものを発散せずに生きることなど出来なかったのだ。そしておそらく、その余波は友達に対してさえも向かった。僕の口から流れ出る言葉は、知らないうちに友達を不安にしてしまうようだった。もちろん高校の時にはそんなことには気付かなかった。いまから思えば、ということだ。
闇を抱えるものは、何か特別なものを知っているように見えるらしい。だから僕にも何人かがその特別さに魅かれて近づいてきた。その第一の犠牲者が高校の親友とその恋人たちであり、第二の犠牲者が大学の親友と恋人たちであった。
彼が三人目の恋人と別れることになった時、僕は彼に僕らは離れたほうがいい、と宣言した。これは全て僕の抱える闇のせいなのだ、と。そうして僕は人との交わりを絶った。けれど僕にはそんなことは到底出来ないようだった。一人でいると僕の心は知らないうちに闇で押しつぶされて、気がつくとナイフを持って洗面所に立っているのだ。
だから、情けない恋愛ばかり繰り返す自分に愛想がつきて離れたいと思って僕があんなことを言ったのだと勘違いした彼が、頼むからまた友達に戻ってくれよ、と言ってきた時つい肯いてしまった。その行為が正しかったのかどうか、いまでも分からない。でもその時僕が思ったことは、僕が死んだとしても闇は死なないだろうということであり、もしそうであるなら僕が死んだとしても何も変わらないだろうということだった。いまでも、そう思っている。闇というのは、そんなやわな生物ではない。
でも間違いなくそのおかげで、四人目の恋人も手首を切る羽目になった。そして今度こそは、取り返しがつかなかった。
5
「僕のせいで、一体どれだけの血が流れたのでしょう。僕にはもう生きる権利などありません。僕が死ねば、みんなが救われます。だから死にます、ごめんなさい。」
彼の遺書にはこう書かれていた。僕には決してできないことを、彼はしたのだった。僕は人を傷つけてでも、命を奪い続けてでも生き続けたい臆病者で、彼は他人の命のために死ぬことのできる英雄だった。
けれど彼は所詮おとぎ話の中の英雄でしかなかったのだ。彼にはもっとしなければならないことがいっぱいあった。例えば、僕を殺すこと。闇を、断ち切ること。
彼は最後まで真実を知ろうとしなかったから、真の英雄にはなりきれなかったのだった。彼は実直すぎて、本当に僕の言っている通り彼の恋人たちが死ぬのは僕の闇のせいなのだ、ということを信じようとしなかった。もしそれを信じていれば、彼のとった行動は変わっていたはずだ。多分彼だって僕と同じく、死ぬことなんてできなかったのではないか、と思う。
もちろん彼のことを非難するつもりなんて毛頭ない。彼は、少なくとも僕よりは、ずっと優れた人間であった。僕はおとぎ話の英雄にすらなることができないだろう。つまり、僕が死ねば全ての人が救われると信じていたとしても、死ぬことなんてできなかったのではないか、と思う。正直に言って、僕は彼がひどく羨ましかった。僕だってあんなかっこいい遺書を書いて、おとぎの国の英雄として死んでいくことができたらどんなによかっただろう。でも、どちらにしろできないかもしれないにせよ、僕は既に色々なことを知りすぎていた。
エピローグ
彼の葬式が終わって、僕と僕の恋人は喫茶店に入った。恋人とは高校二年の初めからだから、もうずいぶん長い付き合いになる。黒いドレス姿の恋人は、白い肌が映えていつにも増して綺麗だった。
恋人の前に置かれたアイスティーは、一口も飲まれないうちに氷がもう全て溶けてしまっていた。僕のホットコーヒーも、ほとんど同じような状況だった。そして僕らはまだ一言も発してはいなかった。恋人は座った時からもうずっと横の白い壁を見つめたままだった。見つめているから何かがあるのかと思って僕もずっと見つめているのだけれど、少なくとも僕には何も見えなかった。
「ごめんなさいね、また、私のせいね」
彼女はやはり知っているのだった。僕の友の恋人が次々に手首を切った原因を、僕の友が二人とも死んでしまった原因を。もちろん僕も知っていた。彼らの闇が彼ら自身から生まれたものではないのと同じように、僕の闇も僕自身から生まれたものではないのだった。
「いや、仕方がないよ。君の闇だって、また違うところから来た闇なんだろうから」
恋人はそれには何も答えず、視線をようやく壁から外してずいぶんと薄まったアイスティーをかき混ぜ始めた。そうして今度は熱心にその液体の回転の中心部を凝視し始めた。今度は、僕にも見えた。そこには確かに、底のない闇があった。僕も吸い寄せられるように、そのアイスティーの奥をじっと眺めていた。僕は正しいことを言ったのだろう、と思った。
気がつくと、アイスティーに透明な粒がぽた、ぽた、と落ちていた。恋人はもうかき混ぜることはやめてしまっていて、座ったまま泣いているのであった。
「泣くなよ」
と僕は言った。僕だって泣きたかった。友の恋人を傷つけながら、そして友を殺しながら生き続けるのなんて、もうごめんだった。けれども僕が死んだところでどうにもならないから、僕はまだ生きているのだ。僕が死んだとしても、恋人はまた別の男と愛し合うようになり、そしてその男は僕と同じ闇に取り込まれるだろう。誰かにこの闇を押し付けるほど僕は無責任になれないから、死んでいった友のようにはなれないから(もちろん彼らは無自覚だったのだけれど)、僕はまだこうして生きているのだ。彼女を愛してしまったからには、僕はこの闇を背負っていき続けなければならないのだ。泣いてしまったら、そんな覚悟が一気に崩れてしまいそうだった。だから僕はどんなに泣きたくても泣くことなんてできなかった。
彼女はやがて泣くのをやめて、意を決したようにこう言った。
「ねえ、わがままだとは分かっているけれど一つだけお願いがあるの」
「なに?」
「死なないでね」
彼女が本気で言っているということを僕は知っていた。彼女だって、生きていくことの難しさをよく知っているのだ。そしておそらく、僕と同じような理由で彼女も死なずに生き続けているのだ。頼まれなくたって死ぬわけないだろ、お前を苦しませるようなことなんかしないよ、と僕は笑って言いたかった。言えるはずだった。でも恋人の潤んだ黒い大きな目を見ると僕の口は凍り、喉も凍った。言葉はアイスティーの闇の中に吸い込まれていった。視界がぼやけている。涙のせいだということは何とか分かったのだけれど、拭おうとしても手が動かなかった。体中の何一つとして僕の思い通りになんて動かなかった。心臓だけが熱く激しく僕を揺さぶっていた。そして、何も見えなくなった。
どれくらい時間が経ったのだろう、突然視界がクリアになって、僕の前にはまだ恋人がいた。そして、死なないでね、ともう一度言った。僕はすっかり冷めたコーヒーを一気に飲み干して、小さく肯いた。
了
| Back | 2 / 2 |