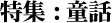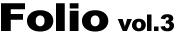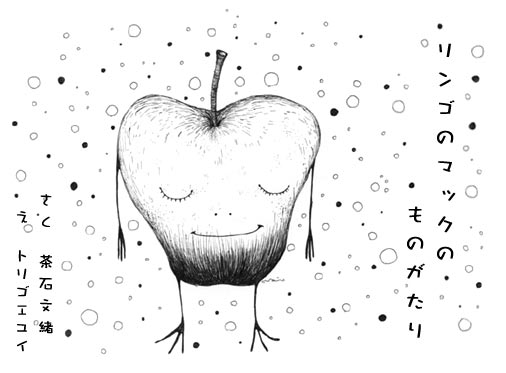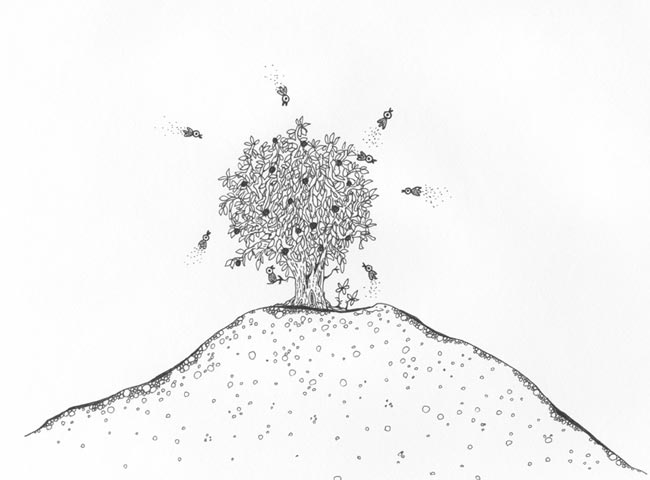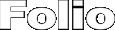「いままでどうしてお互いを知らずにいたんだろうね!」
マックはしみじみ呟いた。いままで見てきたものを、ぜんぶリナに見せてやりたかった。ひとりで切り抜けるのではなく、一緒に経験することができたら、旅はどれだけ素敵なものになっただろう!それはリナも同じだった。今までは悲しみだけに染まっていた虹探しの冒険だって、マックがいてくれたら、最高に楽しい思い出になったにちがいない。
ある時、ふたりは小さな村に立ち寄った。倉庫からほんのちょっと麦をもらって、おなかの足しにするつもりだった。村をぐるりと歩いて、扉があいたままの倉庫を見つけたリナは、いたずらっぽく微笑んだ。
「ちょっとだけ待っててね、マック」
うまくいけば、巣材にするわらくずも取ってこられるわ。そう言って扉の隙間から忍び入ろうとするリナを、マックは倉庫の外で待つことにした。風は静かで、雲がゆったりと流れている。暖かな陽気にほだされて、ついあくびをした、そのとき、わらがガサガサ鳴る音と、凶悪なうなり声が聞こえた。倉庫の守り猫だ。マックは飛び上がった。
「リナ!」
あわてて倉庫に駆け入ると、しなやかな筋肉を持った細身の猫が、宙を横切ってリナに飛びかかろうとしているところだった。リナは身軽にかわそうとしたが、わらくずに足をとられてバランスを崩した。猫の爪が彼女の羽根をかすめるのを見て、心臓が引きつるようにどくんと鳴った。
何とかしてリナを助けなきゃ。マックは素早く頭をめぐらせた。アーヴァインと一緒に学んだ戦闘の極意を思い出す。
決して闘いを長引かせないこと。はんぱな反撃を受ける前に、相手の急所に痛烈な一撃を与えること。相手の動きを読みとること、自分の武器を最大限にいかすこと…それらを全て実行に移して、アーヴァインは11頭のドラゴンとの戦いを、わずか一昼夜で勝ち抜いたのだ。
マックは倉庫の柱をよじ登った。梁の上に立ち、素早く戦況を見おろした。リナはなんとか左右にからだをかわしているが、狭い倉庫の中では思うように動けない。マックは胸いっぱいに息を吸い込む。最大の武器はマック自身だ。紅くて堅い、ドラゴンの息吹に祝福された弾丸。
「いくぞー!」
マックは恐怖を振りきるように叫ぶと、勢いをつけて梁から飛び降りた。狙いをたがわず、猫の眉間に体当たりする。猫はぎゃっと悲鳴を上げ、しっぽを丸めると倉庫から逃げだした。
「マック!」
猫の額に思い切り打ち当たったマックは、反動で倉庫の隅まで転がっていた。リナがあわてて飛んできたが、マックは起きあがることができなかった。
「どうしちゃったの!? 大丈夫なの、マック?」
マックは床にごろりと転がったまま、力なく呟いた。
「着地しそこねちゃったみたいだよ」
前にリンゴの木から飛び降りたときは、うまく飛べたのになあ。今にも泣きそうなリナに向かって、笑って見せようとしたけれど、全身の痛みがじゃまをしてうまくいかなかった。
 ここにいたら、いつ猫が戻ってくるかわからない。リナは自分の爪でマックを掴んで、やっとこマックを倉庫から引きずりだした。今までは、つややかな紅いからだを傷つけたくなくて、決して爪を立てたりはしなかったのだけれど、もうそんなことを言っている場合ではなかった。
ここにいたら、いつ猫が戻ってくるかわからない。リナは自分の爪でマックを掴んで、やっとこマックを倉庫から引きずりだした。今までは、つややかな紅いからだを傷つけたくなくて、決して爪を立てたりはしなかったのだけれど、もうそんなことを言っている場合ではなかった。必死で飛んだけれど、小さなひばりに丸のままのリンゴはあまりに重くて、リナは何度も空中でよろけた。それほど遠くへ逃げることはできず、近くの家の屋根の上に、そうっとマックを降ろした。
「マック、しっかりして」
リナはその場に座り込んで泣き出しそうになった。喉の奥に、差し込むような痛い塊がせり上げてきたけれど、それをぐっと飲み込んだ。傷ついたマックを休ませるためには、柔らかな寝床が必要だった。
「ねえマック、動かないでよ。ここで待っててね」
疲れ切った羽根と、くじけそうにな心をふるい起こして、リナはもう一度屋根から飛び立った。枯れ草を必死で拾い集めて、屋根の上に小さな巣をしつらえる。リナに言われるまでもなく、マックはどこかへ歩いていくことなどできなかった。リナの手で巣に招かれると、目を閉じてぐったりと眠ってしまった。
何日も、何日も、リナはマックの看病をした。薬草を集めてきたり、新鮮な水を含ませた綿花で磨いてやったり。でも、マックがふたたび立ち上がって歩き出すことはなかった。
「リナ、僕はもう、土に還るときがきたのかもしれない」
「そんなこと言わないで」
リナは涙声で言い返したけれど、その声には、もう、かつて天にまで届いた春の歌の華やかさはなかった。マックは悲しい笑いをうかべた。
「ほら、僕のせいで、リナだってこんなに疲れてる」
「マックのせいじゃないわ。秋のせいよ」
秋はどんどん深まり、気温は日に日に下がっていった。夜にはほとんど冬と言ってもいいような寒さが襲い、リナは少しずつ弱っていった。
「ほんとなら、とっくに、南の国へ帰っている頃なのよ。でも…」
一日いちにちと、自分の命が危険の方へ追いやられていくのを感じながらも、リナはマックから離れることはできなかった。自分がいなくなったら、きっとマックは、回復の望みもなくしてしまう。そう思うと、もうここを発たなければと口に出すことはできなかった。
「へんな子だなあ、リナは。最初に言ってたじゃないか。うそをついてまで友達のそばにいるなんて、ばかげてるって」
「そんなこと言うなんて、マックのバカ!あんたはただの友達じゃないのよ!わかってるくせに…」
何もできない自分がもどかしくて、リナは感情を爆発させ、わあっと泣き出した。その激情が、かつての元気だったリナを思い出させて、マックは嬉しくなって微笑んだ。
「リナ、大丈夫だよ、君はまだ飛べるよ。南の国に帰るんだ」
「いやよ!マックを置いていくなんて!」
置き去りにされる寂しさは痛いほど知っている。それをマックに味わわせると思うだけでぞっとした。マックを置き去りにするくらいなら、いっそ自分が取り残されるほうが耐えられる。だからこそリナは、さいごまでマックのそばにいようと決めたのだ。
「リナ、よく聞いて。僕も一緒に行くんだよ」
「無理よ。あんたを抱えては、そんなに長く飛べないわ」
そうじゃない、とマックは笑った。少し考えて、ゆっくりと、けれどはっきりと自分の決心を口にした。
「僕の実を食べて」
「…いやよ」
リナはぞっとして声を震わせた。愛するマックを食べてしまうなんて!
「そうすれば、君は元気になれる。南の国にも帰れるよ」
「やめてよ!マックこそ、誰かに食べられるのが嫌だから旅に出たんでしょ?」
「僕も同じなんだよ、リナ。君はほかの誰かとは違う、特別な女の子なんだ」
たしかに旅に出たときは、誰かに食べられて、芯だけになって捨てられるのはごめんだと思っていた。自分には、もっとやるべきことがあると信じていた。
でも、今となっては、それこそが自分のするべきことなのだと素直に思えた。誰よりも大切なリナを救うこと。アーヴァインが世界を護るドラゴンとして闘うことを決めたように、マックにも決断のときがきていた。
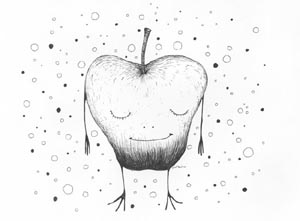
リナは黒い瞳を涙でいっぱいにしてマックを見つめた。マックにいい子と呼ばれることは、こんなときでもやっぱり、リナにとっていちばんの幸せだった。
「僕を食べて、種を持って帰って。君のふるさとに植えるんだ」
そうすれば、ずっと一緒だよ。いつまでも、どこに行っても。
そのひとことを言ってしまうと、心のどこにも後悔はどこにも残っていなかった。
とても静かな気持ちで、マックは、すうっと目を閉じた。