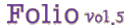「やあ」
僕は片手を上げて雨の部屋に入り、ベッドに座った。腰がぐいんと沈んでいく感覚には、どことなく背徳という言葉が似合う気がする。
「そこはわたしのベッドなんだが」
机に向かって座っていた雨が、開いていた雑誌を閉じながら眉を寄せた。病的に白い頬と額が蛍光灯を反射している。
「知ってるよ」頷いて、笑う。「だから?」
「それは何よりだ」雨は言った。「知っているなら、どいてくれ」
「どく理由がないと思う」僕はさらに深く腰掛ける。
「ふむ」白い壁、白い顔、白いカーテン。雨の赤い唇が開く。「女性のベッドの上に平気で腰掛ける理由や、女性の部屋にノックもせずに入り込んでいい理由よりはマシな理由がきっとある」
「なるほど」僕は頷いた。「ところで、僕はわざわざこの家まで学校から歩いてきたんだ。雨のために。雨のために。足も疲れるし、外は暑かったから一服したい」
「それが何か?」
「僕がベッドに腰掛けていい理由の他に解釈があるかな?」
不満そうな雨の目の前に、持ってきた紙袋を突きつける。中身はプリントばっかりだ。
「なんだ」手にとらず、中身を覗き込んで唇を尖らせる雨。「誕生日プレゼントじゃないのか」
「雨の誕生日は五日後だろ」
「へえ」雨は目を細めて嬉しそうに笑った。そのまま抱きついてきそうな勢いだ。「覚えててくれたんだ」
「当たり前だ」僕は頬を膨らまして視線を逸らした。「僕が雨の誕生日を忘れるなんて、自分の誕生日を忘れるくらい有り得ないぞ」
「そうか」雨は紙袋を受け取って笑みを収めた。「それはそうだ」
はあ、と僕は溜息を吐いた。「いい加減に学校にくらい来いよ。毎回こんなものを届ける僕の身にもなってくれ。学校からじゃ、僕の家とここは正反対の位置にあるんだぞ」
「わざわざ郵便屋を引き受けてるのはそっちの方だろう」
「なら、僕以外が届けにきても雨は文句ないんだね?」
「だいたい、あんな低レベルな授業ばかり繰り返す中学になんて、行く意味がない」
「答えになってない」
「なってる」雨は紙袋を開けてガサゴソと中身をほじくり返しながら、つまらなさそうに言う。「カーくんの理解力と努力が足りないだけだ」
「雨の愛想ほどじゃない」
「愛情でカバーだ。――なんだこれ」雨が紙袋からほじくり出してきたのは、赤い「重要」マークのスタンプされたプリントだった。
「見て分かるだろ」
「これが紙であること以外は分からない」
「それは重症だ」言いながら、少しは頭を働かせろと雨の担任の間抜け面を思い浮かべた。化粧の厚いその顔を、頭の中で殴る。グーでパンチだ。「僕が見る限り、そこには授業参観のお知らせと書いてある」
雨は「なるほど」と頷いたあとに首を傾げて、「なんだそれ」とボヤいた。くしゃくしゃに握りつぶしたプリントを、ゴミ箱に投げ込んだ雨のストロークは美しかったが、球は外れてしまったようだった。ゴミと化したプリントが、ゴミに相応しく床に打ち捨てられる。「教師の化粧が濃くなるだけのイベントのことかな?」
「さあね」頭の上で腕を組んだ。「僕らには関係のないイベントだろう」
「こういうイベントは嫌いなんだ」確認するように雨が呟く。「すごく、嫌いなんだ」
「知ってる」頷いてから、意味のない質問をする。「ちなみに、どれくらい嫌い?」
「そうだな」雨は視線を上に投げて、さっきまで読んでいた雑誌を一瞥してから、少し笑った。「カーくんの次くらいに嫌いだ」
「おいおい」僕は傷ついた顔をする。実際、傷ついたのだ。「嘘だろう? それはさすがの僕だって傷つくぞ」
「さあ」雨はわざとらしく小首を傾げた。「どうだろうね」
「らしくないな」ベッドの上に倒れこむと、ボサっと音がした。「なんだか、そういう嘘は雨らしくない」
「違いない」雨はその僕の上に重なるように倒れこんできた。僕が髪の毛を撫でてやると、雨はくすぐったそうに目を閉じた。「確かに、違いない」
雨の重みを感じながら、揺れるカーテンを見た。空は良く晴れていて、外はとても暑い。涼しい風が僕らの上を通り抜ける。ベッドはふかふかで、午後三時の快晴は眠気を誘うには十分に穏やかだった。
僕は雨の背中に左手を回して、右手で白い頬に触れた。雨は相変わらず目を瞑っている。睫が濡れたように黒い。断っておくが、椎名薫と花実雨が肉体関係に及んだことは一度もない。
僕は囁くように雨の耳に唇を寄せた。「面白い話をクラスメートから聞いたんだ」
「カーくんのそういう話は、たいていつまらない」雨は目を閉じたまま、無表情に答える。
「じゃあ、話さなくてもいいか」僕は雨と体の位置を入れ替えて、立ち上がろうと膝を立てた。
「どんなにつまらない話でも、聞いて死ぬことはないと思う」目を開けた雨が僕を見る。
「たぶん、死にはしないと思うけど」僕は言って、体勢を元に戻した。「たぶんだから、約束はできない」
「上等だ」雨は再び目を閉じて、真顔のまま唇を引いた。「聞こう」
僕は話し始めた。
1/3