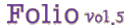2003年の暮れ、テレビ朝日で放送された、コンビ活動歴10年以内の若手お笑い芸人による漫才の頂上決戦、「M−1グランプリ2003」において、関西では数多くのコンクールで最優秀賞を獲得している「フットボールアワー」が遂に念願のグランプリの栄冠に輝き、日本国内の若手漫才師の最高峰の位置を不動のものとしたのは記憶に新しい。
私は、この「フットボールアワー」と同時期にNSC(吉本興業の芸能養成所)を卒業し、彼等と共に大阪の劇場で下積みを経験し、現在ではフリーでライブ活動を細々と行っている、妻1人、子供1人を持つ三十路の専業主夫(平たくいえばヒモ)である。
自己紹介はさておき、私には幼少の頃から「女性のスカートの中」に対して異常なまでの執着心を抱くという特殊な性癖があった。一般的に「パンチラ」と呼ばれるシチュエーションに対する憧憬が人一倍強く、それは私の思春期の人格形成に少なからず影響を与えたといっても過言ではない。通常の視線において見えない状態の女性のスカートの中を故意に覗くというのは明らかに犯罪であるのだが、10代の頃を振り返ってみると、若気の至りともいうべきなのか、かなり強引な手段で女性のスカートの中身を確認しようと命懸けになっていた思い出がある。
階段を登る女性のスカートの奥を手すりの隙間から覗き込んでいる時でも、女性と目線が合ったとしてもお構いなく覗き続けていたし、電車の中で向かいの座席にスカートの女性が座った時でも席に浅く腰掛けて目線を低くするような姑息なマネはせず、逆に前屈みになって身を乗り出すようにタイトスカートの奥の三角地帯の暗がりに視線を集中させていた。高校では女子部員の割合が多い部活動に所属していたのだが、部室が畳敷きだったため、女子生徒が体育座りで畳にしゃがみ込んでいる事が多く、他の男子部員はしゃがみ込んでいる女子生徒のスカートの中を見てない素振りをして視野の端でそれとなく焦点を合わせているような覗き方をしていたのだが、私は女子に嫌われる事を恐れず、堂々と女性の正面に寝転がって覗き込んでいた。
それぐらい自分の中で「女性のスカートの中」の光景は「女性に好かれる」という可能性を全て放棄してまでも手に入れたい「何物にも代えがたい宝物」のような存在なのである。
ところが、大人になってくると誰しも「社会的体裁」というやっかいな荷物を背負う事になるため、女性のスカートの中を露骨に覗き込む事が堂々とできなくなる。しかし重度のパンチラ依存症である私が女性のスカートの中の光景を見るという機会に遭遇するチャンスが減り、精神バランスの破綻をきたすという事態に陥る事なく現在まで至って良好なメンタリティを保っていられるのも、何がラッキーだったかというと、「お笑い芸人としてライブ活動ができる」という環境に恵まれているおかげかも知れない。
私は主にイッセー尾形のスタイルを彷彿とさせる、いわゆる「1人コント」の形式をとった15分ほどの芸を舞台で披露しているのだが、私がライブ活動の主戦場としている大阪市内の某劇場は客席の床がフローリングになっており、観客は床に一定間隔に配置された座布団に座り込んで私の芸を鑑賞する格好になる。全く売れないまま無駄に芸歴を重ねてきた私にとって、
ある時期を境に、舞台で芸をやって客を笑わせるという結果があくまで副産物的な達成感に過ぎなくなり、この、客席に座っている女性のスカートの中を覗くという行為が主目的になりつつあるのだ。つまり社会的な成功よりも自分の性的欲求の充足を優先する人生を選択したといっても良い。
舞台芸人にとって「観客席の女性のスカートの中が気になりだす」というのは「芸を客に『見せる』べき人間が、逆に客を『見ている』」、つまり客の(スカートの中という)誘惑に自分自身の芸がコントロールされているのと等しいわけで、これは「芸人の死」に値する堕落かも知れない。しかし私にとって1人でも多くのパンチラを記憶に焼き付けるというのは人生そのものを費やしても遂行すべきライフワークであり、「生き甲斐」であり、自己の存在理由そのものなのだ。
舞台で「ネタ」を演じている最中、床に座り込んでいる女性のスカートの中が確認できるチャンスはそう多くはない。女性にとって「正座以外のリラックスする座り方」というのは、
「両足を斜め横にする座り方」か、「両膝を内側に曲げて足を床にピッタリくっつける座り方」か、「体育座り」のどれかだが、よほど警戒心の薄い女性で無い限り、舞台に立っている男性の視線からモロにスカートの中を見られる体育座りの姿勢をとるという事はほとんどない。
ただ、体育座りの状態でも、脚をピッタリと閉じてこちら側の目線がスカートの奥に届くのをガードしたり、ちょうど股間の部分にカバンや荷物を置いて下着が見える領域を巧みに隠しているパターンは比較的多く見受けられる。
舞台でネタを演じている私が女性のスカートの中を覗こうとする場合、女性のどういう動作の瞬間を見逃さないように注意しなければならないかというと、「体育座りで股間に荷物を置いている女性が荷物を移動させる瞬間」か、「両足を斜め横に座っている女性が足を逆の方向に揃えなおそうとして姿勢を変える瞬間」である。
私は観客席の、特に最前列の女性のほんの僅かな姿勢の変化にも即座に反応できるように、常に視線を少し斜め下に落としながらネタを演じているのだ。当然こんな状態では芸に集中できずにネタも噛みまくる。私は自分の作ったネタが客にウケるという圧倒的な確信を持ちながらも、このどうしようもない性癖のせいで「見えるかどうかも分からないパンチラ」を追い求めるために「芸人としての評価」まで犠牲にしているのだ。この舞台空間において完全に客と演者の立場の逆転が生じているというか、女性客の側が「見えそうで見えないスカートの中」という、いわゆる1つの「エロネタ」としての作品を演者の僕に披露している、不思議な関係性が成立しているのである。
自分のネタの持ち時間が終わるまで、一度も女性のスカートの中の下着が確認できなかった時には、それこそ自分が人生の敗北者になったような空虚な劣等感が襲ってくるのだが、そんなリスクを背負ってまでも女性のスカートの中に異常な執着心を抱き続けるのはもはや病気であるとしか言いようがない。しかし自分が自らの芸の完成度を犠牲にして女性のスカートの中に視線を集中させ続けた結果、一瞬でもスカートの奥の暗がりの向こう側の景色が目に飛び込んできた時には、まさに「精神の射精」ともいうべき強烈なカタルシスを手に入れる事ができるのだ。
先ほど述べた「パンチラマニアとしての自分の精神のバランス」はこのようにして保たれているわけで。まあそんな幸運が訪れた時には、精神の射精では済まず、舞台が終わった後、楽屋でズボンの中に手を突っ込み、スカートの中の景色を脳内のスクリーンに浮かべながら激しく陰茎に刺激を与え、実際にトランクスの中に大量の精液を放出するのであるが。
私にとって女性のスカートの中を見るという事は「その女性と性交する」にも等しいのである。
その女性の下着、彼氏以外の男性には通常見せる事の無い下着を自分だけの視界に収める事で、その女性の全てを自分が独占したという満足感を得る事ができるのである。
ネタ中に1度もパンチラを捕獲できなかった時でもまだチャンスがある。我ながら「女性のスカートの中に対する執念には恐るべきものがある」と実感するのだが、自分以外の人間がネタを演じている時、その様子をビデオに収録するふりをして、ビデオカメラを持って舞台の後ろに立ち、芸人のネタを背後から撮影しているように見せかけて最前列の女性のスカートの中をカメラ越しに覗き込むのだ。
これが特に女性芸人がネタを演じている時だと同性に対する性的な警戒心はほぼ無いに等しいので、こちらのカメラ撮影の真の狙いに気付かない限り、自分のスカートの中の広がり具合に必要以上の注意を払うような様子は見せない。ただこれは明らかに犯罪なので、最前列に陣取る常連の女子中高生の客のうち、私の性癖に対して理解を示している女の子のみを狙って撮影している。私の主催するライブにおいては「客のスカートの中を覗く事」がもはや私の「芸風」として確立されつつあるのだ。
しかし最近の女性は、スカートの中に見せてもいいような短パンを着用しているにも関わらず、男性にスカートの中を見られる事にことさら拒否反応を起こす。よって開演時に座った姿勢のまま、一度も足を組みかえたりする事なく、両足を貝のように閉じたまま最後までライブを鑑賞する女性も大勢存在する。いやむしろそういう女性の方が大多数だろう。そういう現状が更に私の性的フラストレーションを煽っているわけなのだが、実はスカートを履いた女性というのは、床に直接座っている限り、ほぼ確実に一瞬だけスカートの中を周囲に見せなくてはいけないシーンが訪れるのだ。それは「立ち上がる時」である。この場合、ライブ中に大胆な体育座りの姿勢でネタを見ていた女性は逆に「お尻を浮かして体を前に倒してから立ち上がる」という作戦を使われるのでパンチラに遭遇できない場合もあるのだが、ライブ中に私を警戒してずっと足を閉じていた女性は、立ち上がる際、一旦軽く尻餅をついて重心を後ろに置きながら膝を立てた状態になって起立する必要が出てくるので、膝を立てる瞬間に「スカートの奥の素晴らしき光景」を私の眼球に提供してくれる可能性が非常に高いのだ。
ただ、客が立ち上がる瞬間というのはあくまでもライブ終了後である。客は大抵、ライブのエンディングMCが終わり幕が完全に閉じてから立ち上がろうとする。
これでは幕一枚隔てた向こう側に自分の股間の栄養分となるべき光景が広がっているにも関わらずその現場に立ち会う事ができない。そこで私は自分のライブでは幕を降ろさず、そのまま演者達がエンディングMC終了後に舞台袖に引っ込んでいくという方法を採用している。
この時重要なのは、自分は最後まで舞台上に残り、舞台のセット等を片付けるフリをして客が立ち上がる瞬間を意地でも見届ける事である。
フットボールアワーがM−1グランプリで優勝したのをきっかけに、彼等には全国ネットのバラエティー番組の出演依頼が殺到している。一方で私は「純粋な気持ちで芸に人生を捧げる」という当初の誓いを悪魔に売り渡し、完全な「女子高生のスカートの中を覗くオッサン芸人」としてのステイタスを築き上げようとしている。
でも私は思う。「それも『芸』なのではないか?」と。
先ほども述べたように、これは「芸風」なのだ。観客が隠そうとしている部分に視線を集中させ、ネタも噛みまくっている自分自身をピエロとみなし、1人の「狂人」が舞台上で自己の異常性欲を露呈している、それそのものが立派な「コント」の作品なのではないか、と。しかもこれは客の協力によって成り立つコントだ。
これまた先ほど述べたが、私が私自身の狂気性を観客に見せているのと同時に、観客も「パンチラマニアのマニア心をくすぐる『芸』」を私に見せているのだ。
私がネタを演じている最中、足を組み替えたり、スカートの裾をパタパタはためかしたり、見えそうで見えないギリギリのラインを演出する事によって私のイライラ感を極限にまで高め、結果としてより私が狂人化した状態を彼女達は楽しむ事すらできるのだ。
それは私が芸という無形の「作品」を生み出す上でのエネルギーになっている。演者(私)と観客(スカートを履いた女性)との間に相互作用が働いているわけで、
これこそ究極のインストラクティブ・アートとして、私は自身を持ってこの芸風を貫き通せば良いのだ。最近そう感じている。もしかすると、今、私が実践しているこの芸風こそが
「新しい笑い」として認識されていくのかも知れない。世の中捨てたもんではないじゃないか。
ところが、最近、平日よりも日曜日や祝日にライブを開催する機会が多いため、女子中高生客の服装の大半が、学校指定のセーラー服やブレザーでは無く、セーターにデニムのスカートというような私服になりつつあるのだ。
デニム生地のスカートだといわゆる「タイトスカート」になるため、足を組み替えたりする際にスカートの裾が極端に広がったりする事が無い。もちろん、タイトスカートにはタイトスカートならではの「スカートの中を見るためのセオリー」が存在する。
タイトは生地が固いため、フレアースカートと違い、股間の領域をスカートの裾を垂らす事によってガードする事ができない。つまり座っている状態のタイトスカートの女性は、太股をハンカチや手で押さえていない限り、普通の姿勢でもスカートの中を外側にさらけ出している事になるのだ。
ただ、タイトスカートの女性の、スカートの奥の、いわゆる「三角地帯」と呼ばれるゾーンを覗き込もうとすると、かなりスカートと平行に近い状態にまで視線を低いアングルに下げなくてはならない。私は普段立ってコントをする。これではスカートの中の楽園をこの手につかむにはほど遠いのだ。
ここで私は考えた。「最初から最後まで床に這いつくばって演技をするようなコントを作ろう」と。
そうすれば自動的に視線が最前列の女性客のタイトスカートの三角地帯と水平になる。当然女性は警戒し、手で股間を押さえるだろう。それでもいいのだ。ネタ時間は15分。時間は十分ある。
あの子のスカートの中をたっぷり眺め回してやる。そのうちチャンスはきっと来る。15分のうち1度は手を股間から離すその時まで、私はスカートの中に視線を集中し続ける。このパンパンに硬直した陰茎をこすりながら思い浮かべる映像を脳に焼き付けるために。私にとってパンチラが人生の全てであり、「笑い」を世の中に送り出す動力源なのだ。
こうしてできたコントが
「道端で『足が痛いからもう歩きたくないよ』と寝転がってダダをこねる男」というタイトルの作品である。
私は信じる。
あまりにも古典的な設定のコントだが、これが「新しい形の笑い」なのだと。
2004.3.6
カネミノブ
http://www.kaneminobu.com/bokesozai/
http://d.hatena.ne.jp/kaneminobu/