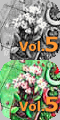- 特集「見る」
- 哲学者からの手紙
- 「書」
- 難しさにこそ、魅力が
- Talk Session
- みることからふれることへ
- 「見る」から「描く」へ
- Novel
- スイッチング・ウォッチング
- 同じことを考えていた。君とまったく同じことを、いま
- よくばりな眼
- 秋の夜の夢
- 王子の見た景色
- ちいさなひとひら
- 宣告
- バードウォッチング
- see
- 見る
- Use your eyes
- おしりやぶれたズボン
- アイズ
- 万華鏡の世界
- Coffee Break
- ズレないBookCover
- Series
- メッセージをどうぞ
- おいしい水
- 不愉快なテクスト
- "いろは"の先のCSS
- Player's Side
- from editor
- 次回予告

不愉快なテクスト
加納 景第二回 如何に書くか――サブ・テクスト
読者の種類
文章にも様々な種類があるわけですが、それは文章を書く目的が各おの違ふからで、たとへば、上司に提出する報告書に、「電車がトンネルをぬけると、海であった。太陽の光をチリチリに裂いていた。砕かれた光は車窓を通過し、数分間暗闇にいた私たちに猛烈に襲い掛かった」などと書けば、見せられた上司は怒りをとほりこして呆れるでせう。それは、文章の目的が、敍述のそれではないからですね。上司が知りたいのは業務の結果報告であり部下の目にした敍情的な風景ではないわけです。同様に、小説の文章が「今年度の決算は前年度を大きく上回り、当社の実質成長率は大幅に上昇した」とはならない。
これはつまり、小説には小説の、職人的な特殊な文章技巧が存在するといふことです。
ところが、みなさんは、無意識には判別してゐても、それがどのやうに違ふのか、といふことまでは意識してゐない。かういふ読者とさうでない読者について、三島由紀夫が『文章読本』(中公文庫)で実に明晰な分類を紹介してゐます。
チボーテは小説の読者を二種類に分けております。一つはレクトゥールであり、「普通読者」、と訳され、他の一つはリズールであり、「精読者」と訳されます。
レクトゥールは趣味として文章を読む人のことです。文章と云ふものにはそれほど興味がなく、したがつて小説を読むときにも、いはゆるオチや謎解きだけに感心がある。一方リズールは、文章そのものに興味をもち、文学というものが仮の娯楽としてではなく本質的な目的として実在するその人
のことを言ふわけです。
言ふまでもなく、これから小説を書かうとするならば、リズールでなければならない。しかし一体、どうしたらリズールになれるのか。今回はそれを、優れた作品を紹介しつゝ、述べてゆきたいと思ひます。
文章の種類
文章大別
先にも述べましたやうに、文章には様々な種類があつて、実務的な文章、明晰さだけを要する文章は小説のそれではなく、新聞記事や週刊誌、政治家の答弁などは明確に前者と呼べ、一方、小説はもちろんですが、一部のエセーや哲学書などが後者に属することがあります。これらの違ひは何であるかと言へば、私はかう答へることにしてゐます。
それは、修辞、レトリックが、どれほど文章に影響を与へてゐるかの違ひである、と。
新聞などは、読者に間違ひが伝はらないやうに、明晰に、狂ひのない文章を書かなければならない。そこには修辞といつたものは不要なのであります。しかし小説は、読者に想像力を喚起させる文章を書かなければならないため、修辞によつて、より深みがあり、面白みのある文章にしなければならない。そこが、決定的に違ふ。それは冒頭に示した、二つの文章を見比べれば、自づと得心されることと思ひます。ところが、修辞を用ゐる文章も二つに分かれます。それは、韻文と散文であります。前者は詩や歌など、詠嘆の情を込めて作られたもの、後者は、小説などのことであります。韻文はかなり独自な発達をしてゐますし、本稿で取り上げる題材ではないので触れません。ここでは、散文について考へてゆきます。
小説における文章の種類
しかし、一口に散文、小説と言ひましても様々でありまして、たとへばヘミングウェイのやうなハードボイルドな文体、プルーストのやうな明晰な文体、谷崎潤一郎のやうな流麗な文体、森鴎外のやうな簡素で力強く、格調高い文体、と古今東西どの作家も独自の文体を創作しきたのであります。逆に言へば、職業的な物書きであるためには、自分にしか書けない、取り替へのきかない文章を作らねばらならないといふことであります。たしかに、ある程度までの文体模写は可能です。それはウェブ上に数多く存在する小説サイトを見れば、すぐに分かることで、村上春樹風の文体はそこかしこで見られますし、今は町田康氏を真似た文体も数多くあります。しかし、よく読みこめば、やはり模写しきれてゐないのがわかる。それはその作家が一流である証拠なのです。一流のものを簡単に真似られる道理なんぞありません。私たちができることは、さういつた文章を検証し、己の糧とし新たに文体を作ることであります。
小説の「調子」
では、様々にあるといふ文体は、各おのどのやうに違ふのか。
まづ大きな面では、「調子」ですね。
調子とは、すなはちリズムのことです。みなさんも中学高校の国語でお読みになつたと思ひますが、古典の多くは「七五調」で書かれてゐます。俳句とか短歌はこれをさらに押し進めたものですね。この七五調もリズムの一つです。日本人ならば、だいたい分かるかと思ひます。今私たちが七五調の文章を読んでみても、その流れるやうなリズムはすぐに分かる。
しかし、現代に書かれる文章では、七五調が少くなつてゐることも、お分かりになるかと思ひます。端から端まで交通標語のやうな調子だと、ちよつと疲れますね。内容にもよりますが。では、どのやうな「調子」があるのか。例をいくつか挙げてみませう。
流麗な調子
元来書院というものは、昔はその名の示す如く彼処で書見をするためにああ云う窓を設けたのが、いつしか床の間の明り取りとなったのであろうが、多くの場合、それは明り取りと云うよりも、むしろ側面から射して来る外光を一旦障子の紙で濾過して、適当に弱める働きをしている。まことにあの障子の裏に照り映えている逆光線の明りは、何と云う寒々とした、わびしい色をしていることか。庇をくぐり、廊下を通って、ようようそこまで辿りついた庭の陽光は、もはや物を照らし出す力もなくなり、血の気も失せてしまったかのように、ただ障子の紙の色を白々と際立たせているに過ぎない。私はしばしばあの障子の前に佇んで、明るいけれども少しも眩ゆさの感じられない紙の面を視つめるのであるが、大きな伽藍建築の座敷などでは、庭との距離が遠いためにいよいよ光線が薄められて、春夏秋冬、晴れた日も、曇った日も、朝も、昼も、夕も、殆どそのほのじろさに変化がない。そして縦繁の障子の桟の一とコマ毎に出来ている隈が、恰も塵が溜まったように、永久に紙に沁み着いて動かないのかと訝しまれる。そう云う時、私は夢のような明るさをいぶかりながら眼をしばだたく。何か眼の前にもやもやとかげろうものがあって、視力を鈍らせているように感ずる。それはそのほのじろい紙の反射が、床の間の濃い闇を追い払うには力が足らず、却って闇に弾ね返されながら、明暗の区別のつかぬ昏迷の世界を現じつつあるからである。諸君はそう云う座敷へ這入った時に、その部屋にただようている光線が普通の光線とは違うような、それが特に有難味のある重々しいもののような気持ちがしたことはないであろうか。或は又、その部屋にいると時間の経過が分からなくなってしまい、知らぬ間に年月が流れて、出て来た時は白髮の老人になりはせぬかと云うような、「悠久」に対する一種畏れを抱いたことはないであろうか。
初めに紹介する文章としてはいくぶん分かり難いかもしれない。が、これはまぎれもなく名文なのであつて、私なんぞは、これをタイプしてゐてまことに快い気分になつてゐるものです。それはさておき、これは谷崎潤一郎の文章であつても小説ではなく、隨筆なのでありますが、谷崎の小説は文体が様々に変化し、初読の方にはいささか難あるので、分かりやすい隨筆を選んだ。それでも谷崎の文章には特色があり、それは「長文」といふことなのですが、これを読んでみても、たしかに句点までの一文は長い。谷崎の文章が、『源氏物語』以来の流麗な調子の文章であると言はれるひとつのゆゑんであります。しかし、そこはさすが大谷崎なのであつて、ただ長いだけではない。長い中に短文を挟むことにより、冗長になつて流れてしまひさうになるのを適度に引き締めてゐる。また、その語句の選定にも注目すべきです。「その名の示すやうに」ではなく「その名の示す如く」とし、「いつか」ではなく「いつしか」とするなど、ほか多く見出すことができる。これらは和語を基調した用語ですが、しかし和語だけでなく、漢語も多く存在する。「光線」「陽光」「濾過」「明暗」などがさうでありますが、これが文語調の文章に織り込まれることによつて、気品を感じさせるのです。
しかし、なにより注意して頂きたいのは、この文章のリズムなのです。
悠々とした、ゆつたりとしたリズムが、この文章にはある。
谷崎本人が書いてをります。
すらすらと、水の流れるような、どこにも凝滞するところのない調子であります。この調子の文章を書く人は、一語一語の印象が際立つことを嫌います。そうして、一つの単語から次の単語へ移るのに、そのつながり工合を眼立たないように、なだらかにする。
谷崎は、センテンスについても同様であると言ひます。
ふだん、私たちが、誰かに強く印象付けやうとすると、特異な言動に及ぶといふことが屡々あります。しかし、このやうな調子の文章を書く人は、むしろ、自然体であらうとするでせう。いや、ふだんよりもゆつくりとした動作で、相手をリラックスさせながらも、一分の隙も与えぬ迫力を与へるかもしれません。つまり、流麗である、といふのは、ただ長いだけではだめなのであります。読者が弛緩しないやうに、それでも緊張させないやうに、常にそれらの均衡を保つやうにしなければならないのです。
簡潔な調子
では、前節とは逆に、簡潔で一文が短いものはどのやうなものか。こんどは、志賀直哉を引用してみませう。
或朝の事、自分は一疋の蜂が玄関の屋根で死んでいるのを見つけた。足を腹の下にぴったりとつけ、触角はだらしなく顔へたれ下がっていた。他の蜂は一向に冷淡だった。巣の出入りに忙しくその傍を這いまわるが全く拘泥する様子はなかった。忙しく立働いている蜂は如何にも生きている物という感じを与えた。その傍に一疋、朝も昼も夕も、見る度に一つ所に全く動かずに俯向きに転っているのを見ると、それが又如何にも死んだものという感じを与えるのだ。それは三日程そのままになっていた。それは見ていて、如何にも静かな感じを与えた。淋しかった。他の蜂が皆巣へ入ってしまった日暮、冷たい瓦の上に一つ残った死骸を見る事は淋しかった。然し、それは如何にも静かだった。
教科書にも登場する有名な一節であります。谷崎の文章と比べれば、その違ひは一目瞭然でせう。
この文章でまづ注目すべきは、その文末、「た」止めであること。連続して「〜した」や「〜だった」と続けることで、硬質な感じを生んでゐます。さらに、ひとつのセンテンスが、きはめて短いこと。そして、漢字の使用率が高いこと。これらが、取り敢へず、ぱつと見ただけで読み取れる要点だと思ひます。
むろん、これらも重要なのですが、それよりも、構成の妙、といふことをみてみませうか。
まづ、作者の目は、死んでゐる蜂に向きます。そしてそれを、思ひ入れの少い、「足を腹の下にぴったりとつけ、触角はだらしなく顔へたれ下がっていた」といふ、表面的な描写ですませ、間髪いれず「他の蜂は一向に冷淡だった。巣の出入りに忙しくその傍を這いまわるが全く拘泥する様子はなかった。」と書くわけですが、かうすることによつて、作者の無感動さ、即物的な感じがより際立つことになります。そして、生きてゐる蜂と死んでゐる蜂といふ対比を傍観するやうに描く。この無感動さ、静けさは、「淋しさ」のカタルシスを呼ぶ可能性があります。事実、「それは見ていて、如何にも静かな感じを与えた。淋しかった。他の蜂が皆巣へ入ってしまった日暮、冷たい瓦の上に一つ残った死骸を見る事は淋しかった。」といふ文章は、「淋しい」の連続で、息の詰まるやうな、「淋しさ」の爆発を想像せずにはゐられません。けれども志賀は、直後に「然し、それは如何にも静かだった。」といふ一文をおくことで、そのカタルシスを避け、無感動さの中に舞ひ戻る。ゆゑにこの作品は、巷間に言はれる清澄な世界ではなく、鬱屈した精神の流れとでも言ふべき作品なのです。
より文章を楽しむためのヒント
むろん、今まで述べてきたことは、文章の違ひの中でも、殊に特徴的で、古今かはりのない違ひですが、雰囲気であるとか内容とかは、やはり、時代の感性によつてうつりかはるものです。たとへば、阿部和重氏の『アメリカの夜』から『公爵夫人邸の午後のパーティー』までは、蓮實重彦風の長文ですが、谷崎とは違ひ、一文の中に織り込む意味内容はさほど多くない。むしろ、一文で決着をつけようとするのではなく、同様の事柄を繰り返し問ふたり反復しながら進むためにとられた文体です。前期阿部氏のやうな文章の長さに対しては、例へば柄谷行人氏の文章を挙げればよいでせうか。今言つたやうに、そのやうな長文は、問題の処理をできるだけ先に延ばし、様々な横道に入りながら考へてゆくものであるとすれば、柄谷氏は、一文に過剰なまでに意味を込め、めくるめくスピードで問題を処理してゆく文章だと言へるでせう(ゆゑに氏の文章は時々、吃驚するやうな論理の飛躍が登場するが、その点氏は小林秀雄と似てゐる)。
とは言つても、中々そのやうな楽しみ方が解らない、といふかたがいらつしやるかもしれない。しかしそれは、殆ど才能といふか、能力的な問題で、わからない人には解らない、といふ類ひの問題です(谷崎も同様のことを言つてゐる)。しかしながら、誰でも初めから分かる、といふことはありませんから、気長に、ゆつくりと、文章を味はふぞ、といふ心持で、本と対面し、読み進めてゆくことをお勧めします。そのための一助、基礎とも言ふべきものを、今私は述べました。これからは、貴方次第です。
引用文献一覧
- Amazon.co.jp: 本: 文章読本(三島由紀夫)
- Amazon.co.jp: 本: 文章読本(谷崎潤一郎)
- Amazon.co.jp: 本: 陰翳礼讃
- Amazon.co.jp: 本: 小僧の神様・城の崎にて
参考文献は割愛させて頂きます。Amazonで「名文」や「文体」という風に検索すれば、山ほど見つかるでせう。

 加納 景(かのうけい)
加納 景(かのうけい)