 どれくらいセックスをしていないのだろう。半年、否、一年半は確実にしていない。こんな告白、まったくもって、どうでもいいことなのだが、今ふと、牛が見えたのだ。最後に、やった女が、牛だった。ピストンの動きに合わせて、モーモー、もーもー、モウモウモウモウ、と喘ぐ女。そんな女いるかよ! ところがいたのだからしょうがない。牛の片目は麗しく濡れており、その瞳はこの車を突き抜けて、山の麓の丘を見ている。まちがいなくラリっていやがる。喰っているそれは、やばいハッパに違いない。車線を失敗したか? と自問自答。左車線の方が流れていることに今さら気づく。しかしセックスをずいぶんしていないのはどうしたものか……。牛でもいいからしたくなる。ヴォエッ! のどかな田園に向かって、立ち小便しているお父さんが、ぷるぷる腰を振るわせて、前屈みになって、イチモツをしまい、そして、意気揚々とした足取りで車線へ戻ってきた。彼は、安堵の笑みを愛する家族へ向けてからワンボックスへと乗り込んでいった。いつからこんな状態になっちまったんだ。アイドリングのブレが激しいのである。だからお空の水色のブレも激しい。それを感じると、地球ってのは、確実に廻っているのだ、と改めて実感したりしてしまう。こんなところで止まっていても、地球ってのは動いているのだ。地球が廻らなければ、時間が止まるのだろうか? 知らない。自転しながら公転。自転だけが止まったら? 公転だけが止まったら? しかしつまらん。出会ってきた教師といえば、そういう疑問には一切ノータッチ。知りたいじゃないか! 地球が自転しない時の場合、公転しない時の場合。それに限らず、コロンブスがいなかったら、第二次世界大戦で原爆が落とされなかったら、とか。そういう話を教えて欲しかった。想像の中で復讐。牛とセックスさせてやる。モウモウモウモウ。アイドリングのブレは止まらない。牛がいる風景とは反対側の丘からグライダーが飛んでくるのが見えた。さぞかし鳥気分。ハハハハ。鳥気分って、この野郎、車道をなんなく越えていきやがった。畜生、それならこのまま牛舎へ落下してしまえばいい。そんな不運の呪いなどつゆ知らず、グライダーは上空を見事に旋廻し消えていった。さっきから一体なんなの? もう限界よ。いつまでそうやっているつもり? という気持にさせていることくらい承知している。大丈夫だ。もう少し辛抱してくれ。横道に逸れていることくらい知っている。そうだ! 名案閃く。この際、この振動に身を任せ、してみる、なんてのも、浪漫てっく、かもしれない。かも、だ。あくまでも、かも、だ。誤解はよしてくれ。一年半もセックスをしていないんだ。そういう男だから許してくれ。だから、つまり、俺は君とセックスがしたいんだ。そろそろ、答えみたいなもの、なにか明確なものを君に提示しなければいけない時間かもしれない。ちょっと進んでは停まる。またちょっと進んでは停まる。しかも急な登り坂で、ニュートラルと一速の繰り返し、そしてブルブルなアイドリング。たまんねぇーよ! 疲れた。よくよく考えて見れば、昨夜は俺も君もほとんど寝てないじゃないか! 夜の十二時半に出発し、国道四号を北上すること二時間、ひたすら走り続け、ファミレスで一服。この一服が盛り上がりすぎたものだから、こんな状況に追い込まれているのかもしれない。ってなことを言ってしまえば、君はキレるだろう。まるであたしが悪いみたいじゃない! と。俺は辛い。正直者だから言ってしまうかもしれない。ツライ、と。そしたら君は悲しむだろうか? 車線を変更するのも手かもしれないが、どうせ一緒だ。すぐそこで合流し一車線になっているのが見える。またグライダーが水色の中へ飛んでいきやがる。なぜ俺と君は出会ったのだろう? 否、寧ろ今は、なぜファミレスで俺と君は食べ物を一切注文せず、ドリンクバーのみでランチタイム前まで居たのだろう? という疑問が先のような気がする。モウモウモウ、もう牛は見えなくなった。ここまで時間がかかってしまい申し訳ない。そろそろ語らなければいけない。俺と君の物語だ。と、言ってるそばからまた横道に逸れてしまうが、こんなに時間をかけたのには訳がある。俺と君の物語を話す上で、セックスがどうとか、牛が、地球が、グライダーが、とやってしまったのは、奥行きと幅、そして深みのある俺と君の関係性を理解しやすいようにしたことだ。どうか了承していただきたい。しかし一方で、俺と君のことなど分かりたくもないと感じた者に、そうたやすく知ってもらってたまるか、という気持も無きにしも非ず、といった反抗的なものも含んではいる。が、停まった。ついに震えがピークに達し、アクセルを踏んでポシャッた。すぐにキーを捻り直し、空ぶかし。ウォーン、ヴォーン、山道で停まる古いホルクスワーゲン。二十万で車検一年付き。あぁ、君の白い膝が見える。珍しくミニスカート。そしてこげ茶のブーツを放り投げて、網タイツから覗く貧弱な薄い毛。退屈そうに助手席で膝を折り、刹那気に指先で髪の毛を弄っている。対向車線から四駆が猛スピードで下ってくる。後部座席の窓を開けて、そこからゴールデンリトリバーが首を出している。絵に描いたレジャーってやつだ。俺は窓を開け、鉄パイプを取り出し、それを外へ向かって伸ばしてやると、犬の頭部に見事激突。想像を遥かにこえた重い感触に手が痺れ、鉄パイプを落としてしまった。喧しい急ブレーキの音がして、サイドミラーを見ると、カーブの手前で四駆が急停止。後部座席のレトリバーが窓の外へ首をもたげて、舌を出して、耳から血を流して、生死彷徨う目つきをして、だらん。運転席からサングラスをかけた男、助手席からチリチリパーマをかけたオバハン、が同時に降りてきた。二人とも、アイラブブッシュのTシャツを着ている。ラブのところはピンクのハートマーク。オーマイガッー、と笑ってやる。そして君の方をチラリズム。その網タイツ好きだよ。今日は土曜日だ。ベイベーイッツユー、シャラララララ。四駆の二人は俺が落とした鉄パイプを拾って、怒りの形相でこちらへ向かってくる。しかし突然、ひょっこり鹿が現れた。二人は足を止めてしまう。ハハッ、鹿に怯えてちゃ世話ないよ、と思っていると、鉄パイプを持った男が鹿に向かって叩きつけた。鈍い音でシカ殺し勃発。オバハンは鹿の角を持ち、男は否応無く鉄パイプを振りかざしている。オーケー、アイラブブッシュ。また少し車は動き出している。ここはアメリカみたいだろ。登りのカーブのせいで、二人も見えなくなり、リンチの音も聞こえなくなったので、ここらへんで君の話に戻りたい。イシザッキってけっこうアレなんだよね、ね? アレでしょう? そんなことをファミレスの一番トイレに近い席で言われた。そうだ、俺はアレなんだよ、松子。よく俺のことがアレだと分かるな、松子。そうかそうか松子は俺のことを何でもお見通しってわけだな。だよねぇー、イシザッキってやっぱりアレだったんだぁ〜、ふふふ。おいおい、いくら俺がアレだからといって、ふふふ、はちょいと照れるでござんすよ、マツオ、じゃなくて松子。マツオだなんてひどいわ、イシザッキ! アハハハ、ゴメンゴメン。こんな調子で明け方が過ぎた頃、窓の外の光に、目の裏側が痛くなって、俺は心底松子に惚れていることを知った。漠然と、なんとかなるだろう、という根拠も裏付けもない思いによって、ここまできている。それを考えると、恐ろしさ、がやってくる。イシザッキは逃げ道なのよ、あたしにとって。そんなことをふとしたタイミングで松子は連呼し出す。俺は、そんな瞬間、松子を、幸せ、にしたくなる。混沌とした空気が漂う。窓の外、青みのある朝に、強化ガラスを割ってダイビング。バイパスのアスファルトに横たわって、五秒後、ダンプに轢かれる。俺の血肉の欠片が松子のカップの中、ホットココアが入ったカップの中に落ちて溶けてしまえばいい。そうすれば俺は松子に飲み込まれる。俺は松子に喰われたい。その映像を俺は松子に届けた。松子はその映像を再生してくれ、すると、イシザッキの愛は悲しいね、と涙を流してきた。ウエイトレスがメニューを乱暴に置きにき、ファミレスがランチタイムに切り替わることを知り、俺と松子は急いで店を飛び出した。ワーゲンは日光街道へ向かい、俺は考えていた。悲しみ、とはなんだろう? 俺は今まで悲しみを感じたことがあるのだろうか? もし悲しみを感じた時があるとすれば、それは、どれほど、のものだったのだろうか? 悲しみ、というやつは、無責任であり、特別と錯覚してしまう危うさをもった感情に思える。俺はそれとどう折り合いをつけてきたのだろうか? ひたすら自己陶酔なこの感情をどう昇華させてきたのだろう? それを松子に問い掛けた。悲しみ、って好きなの。ひとりよがり、だから。イシザッキの愛はひとりよがりでしょ。それを感じているのが悲しみなの。日光街道はひどい渋滞である。「西洋料理 明治の館」日光石を使った洋風建築のレストランは、明治時代に初めて蓄音機をもたらしたアメリカ人F・W・ホーンの元別荘。杉並立に囲まれた庭園を背景に食事を楽しむことができる。だって、すごくない? 百年前の建物の中で食事が出来るんだよ。行こうよ〜、ね、よし、決まりぃ! という展開になったのは、確かに昨日のはずだったのだが、もうずいぶん遠い昔のようで、俺は学校帰りに駄菓子屋に寄って、発砲材で出来た組み立て式の飛行機を買ったことを思い出していた。ナチスの飛行機が一番カッコ良くて、それを買い、次の日、組み立てた飛行機を持って教室で飛ばしていた。その日から俺のあだ名はヒトラー。心はいつも逆卍。松子はそんな俺を知らない。俺は小学校時代から心に逆卍をキープし続けることで、偏執病的な人間になってしまっている。どうぞベイベー、俺は松子にリカルデントを差し出した。松子はそのガムを受け取ったが、口には入れなかった。分かる。今、この状況で、俺を受け入れてくれない気持が、痛いほど分かる。だから俺は、もう一つ、リカルデントを差し出した。松子は、キレた。ワーゲンのドアを蹴り開けて、ブーツを履きもせず、網タイツのまま外へ飛び出した。そうだろう、そうするしかないだろう、俺は手に持ったリカルデントを松子のブーツの中へ落とした。松子は路肩を小走りに登っている。その後ろ姿にしばし見惚れていた。すると、サイドミラーに茶色の物体が映っているのに気づいた。路肩を駆け上ってくる生物。さっきのレトリバーだ。レトリバーは首から血を滴らせ、舌を地につくほど伸ばし、視点の定まっていない目をして松子を追っていた。逃げろ、松子。レトリバーが吠えた。松子が振り向いた。悲鳴が木霊した。五台ほど前方に黒のシーマがあり、その後部座席からパープルの柄のセーターを着たパンチパーマヤクザが松子の手を取り車に乗せた。レトリバーがガルルルー、とシーマの上に飛び乗った。ビッグジョン! ビッグジョン! アイラブブッシュの夫婦がレトリバーを追いかけてきている。ここで俺のことを話そう。俺は、サイドブレーキを強く引き、急いで車を降りてフルスモークのシーマへ向かい、窓ガラスをゴンゴン、おい、松子を帰せ! とパンチヤクザに言い放ち、ボンネットに乗ったレトリバーにリカルデントをやりご機嫌とって、そしてアイラブブッシュの夫婦に微笑み、後部座席で犯されそうになっていた松子を救うような予定調和な男ではないことを先に言っておく。ピストルの音を聴いたことがあるか? 生音でだ。それは想像以上に乾いた音で、生臭く飢えた無機質な悲鳴である。シーマの運転席からそのピストルが伸びて、レトリバーは無残に藪の中へ吹っ飛んでいった。リボルバーがレトリバーを殺す瞬間、松子の金切り声が鈍い生音と同時に聞こえた。シーマの中で網タイツは破かれているのだろう。ファッキンドッグ! ファッキンブッシュ! シーマの傍まで辿り着いた夫婦は助手席のイタリアンマフィア気取りのチンピラにそんなことを言われ、お漏らし。二人の尿がワーゲンまで流れてきている。さすがの俺もその光景には堪えた。そして松子のことを案じた。あんな人間が乗っている車の中に拉致られ、さぞかし変わり果ててしまったことだろう。俺が破るはずだった網タイツのことを思い、一人たそがれ、山々を見つめた。平和が贅沢だった。アイドリングのブレが安定してきている。静かだ。おぉ遥かなる山脈。松子の匂いとブーツが残る助手席。レトリバーの死体。スコップで穴を掘り始めるブッシュ夫婦。かなりきている。悲しみがきている。これが悲しみなのか? 平和の中で居た堪れない思い。不幸を高みの見物。安全な場所であたかも自分の身に起きたように感じ、涙までをも流す。悲しいよね、とかほざく。知らない。誰も知らない。おまえのことなど誰も知らないのに、おまえは誰かを悲しむ。そうだ、ランチはステーキだ。しかし松子はいない。もうすぐ見える看板。きっとあれが明治の館であろう。前方のシーマは日光東照宮へまっすぐ向かっている。明治の館の駐車場へと右折。やっとワーゲンを休ませることが出来ると目論んでいたのだが、駐車場はいっぱいで順番待ちをしている車両が数台いた。俺は窓を開け、一服ふかすことにした。オウ! イシザッキ! 突然話し掛けられ、俺は火を付け損なった。見たことのある男だった。その男は金髪で、一緒にいる女も金髪だった。おっと、よく見ればこの女も知っている。こいつは、モーモー喘ぐ牛女じゃないか。つまり俺が最後にセックスをした女だ。こいつは、やばい。って、なにがやばい? しかしこの男は思い出せない。上前歯が二、三本抜けているこの男。イシザッキ、もしかして一人? しかもなんでこんなとこにいるの? とかほざいて此見よがしな態度で俺を見下ろしている。見下ろしているのは俺が車内だからであって、並んで立てば俺の方が見下ろすことになるだろうと想像が出来るほど背の低い男。牛女は俺を上目で覗き込み、なにか秘密めいた合図を送ろうとしている。なぜ今さら金髪に……、しかもこんな場所で会うなんて、と頭の中を整理しようと、しているそばから男はシンナーを吸い始めた。こんな時代にシンナーなんて、ダサッ、と吹きだすと、そいつがマサミチだと分かった。なにがダサイってシンナーをデカビタの瓶に入れていることで、そんな奴はこの世の中にマサミチしかいない。ところでイシザッキ、オレんのオンナとなにかあったりした? カコに、つまり過去に? とかって、オレんは知ってんだけどさ、なぁ〜? まっ、許すよ。オレんは昔はどうでもいいと思うし、それにイシザッキはダチだからよ、なぁ〜? おいおい、そんなかしこまったツラすんなよ、分かるぜ、イシザッキ、こいつはよ、イシザッキからオレんのとこに逃げてきたオンナ、なぁ〜? マサミチはご機嫌のようだった。俺は金髪になった牛女のことを思い出そうとしていた。マサミチが言うように牛女は俺から逃げていったのだろうか? 俺は牛女に逃げられた? よく思い出せない。ラッキー、左前方の車両が出そうだ。前方のファミリーカーがバックライトを点灯させ、空いた駐車スペースを狙っているが、俺はワーゲンのハンドルを激しく廻し、そのスペースへ頭から突っ込み、横取り成功。ルームミラーで確認すると金髪の二人は手を繋ぎ、明治の館の中庭へ向かっていた。虚しさらしきものが首筋を触ってきている。あれれれれ? 牛女とマサミチに嫉妬しているのかい? 松子を失った今、誰のために俺はここにいるのだろう? それでも俺は、外に出てみることにした。久しぶりに地上に二本足で立つ快感。お空の水色を拝み、タカかトビか、悠々とハイジャックしている旋廻を眺め、松子のブーツの中の臭いを嗅いだ。リカルデントを落とした方の右足は、ほのかにペパーミントであり、さてさて左足はどうかな? と鼻から突っ込もうとすると、男の喚き声がして、そちらへ振り向いた。中庭に、古めかしい電話ボックスがあり、その中で男がやたらと芝居じみた声を出し騒いでいた。オウ、シット! ファッキュ! ファッキュ! ファッキュ! と絶叫し、泣き崩れた顔で受話器を振りかざし、電話ボックスの中で暴れ狂っていた。中庭に入り、俺は眩暈がした。人間がうじゃうじゃいやがる。ここにいる全員が明治の館に並んでいるらしかった。それに電話ボックスで暴れている男は、なんと、レトリバーを撃ち殺したイタリアンマフィア気取りの男ではないか。ということは、って、おい! パリン、パリン、パリン、彼は受話器でボックスのガラスを割り始めている。ファッキュ! ファッキュ! と短く太い声を上げ、またパリン、そして両手を血だらけにして、ボックスからヨタヨタ出てくると、胸ポケットからリボルバーを出し、中庭に群がっているハトに向かって連射し始めた。人間が一斉にどよめき、いくつもの悲鳴が木霊した。イシザッキ! ねぇ、イシザッキ! 受付に名前書いておいたわよ。もう〜、遅いんだから! おう、松子! 無事だったか松子よ! 網タイツ破れていないじゃなか、松子! は? イシザッキ、それよりブーツ! あぁ、ゴメンよ、ほら、履きなさい、履きなさい。やだ、なにこれ〜、右足にヘンなの入ってるぅ〜。やべッ! それは、それはリカルデントだよ、きっと。うん、ガムだ。マジで? イシザッキったら、いけずねぇ〜。ハハハハ。そうかい? でもそこがいいところかもね、なんてぇ〜。うーん、照れるなぁ〜。ハハハハ。ところで、松子。あの男たちと一緒にいたんだろ? 黒い妖しげな車に乗っていた奴ら。あぁ〜、イシザッキったら嫉妬? いやいや、そんなことはないでござんすよ。シット! ファッキンリボルバーを乱射しまくるイタリアンマフィアかぶれの男はハトを数羽殺して、明治の館の中へ向かった。名前が呼ばれたらしい。恰幅のいいタキシードの男が深く一礼をし、包帯を渡していた。男は血だらけの手にそれを巻き、帽子と上着を店員に預け、店内へと姿を消した。中庭には静寂が訪れた。ベンチに腰掛け、松子は網タイツとブーツにへばり付いたリカルデントを死んだハトの残骸である足の爪で落としていた。このままでいいの? こんなことでいいの? いつ終わるの? 渋滞のせい? あたしのせい? 松子は薄紫色のハトの足の爪を持ちながら、鬱々とした声で問い掛けてきていた。俺は、松子の愛もひとりよがりなんだな、と言った。ヒトリヨガリ? ガーデンテーブルのところでふざける子供たち。走り回り、地面の枯葉が昏迷したかのように舞い踊る。大人はじっと身を屈めてその心の塵芥を探り映す。やがて、悲しみ、がやってくる。ランチの順番が来るまで、そこはかとなく思い続けて、そうやって、ひとりよがりに悲しんでいる。人間の心の質など百年経とうが変わらない。眼前のサーロインステーキのこと、そしてセックスのことを考えている。素敵なランチね、などとステーキを目の前にして、ギャグなのか天然なのか分かりかねる言葉をほざく松子に、俺は心底惚れている。マサミチと牛女が隣の席に、その隣に股間にお漏らしの沁みが乾いていないブッシュ夫妻が、そしてその隣にイタリアンマフィア気取りの男が、皆同じようなものを百年前の建築物の中で食している。ワイングラスの隣にシンナーの入ったデカビタの瓶を置き、マサミチは前歯のないツラで牛女に微笑んでいる。店員がブッシュ夫妻のテーブルにいき、お客様のランチはビッグジョンのウエルダンでございましたがお味はいかがでしたでしょうか? その瞬間、ブッシュ夫妻は泣きながらデザートを口に運び出した。イタリアンマフィアな男は、どうやら仲間から取り分の件で裏切りに遭ったらしく、サノヴァビッチ、ファッキンジャパニーズ、とリボルバーに弾を込め、ナプキンで口を拭いている。遥か遠い昔この場所で、俺と同じように大好きな女を目の前にし、一年半もセックスをしていないことを訝りながらこの館の窓の外を眺めた奴がいるだろうか? もしかしたらF・W・ホーンというアメリカ人はそんな奴だったのではなかろうか? などと思いつつも、俺は帰り道の渋滞が気がかりで仕方なく、リカルデントを噛むことにした。![[fin]](img/main_lm.png)
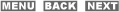
|

