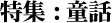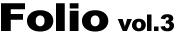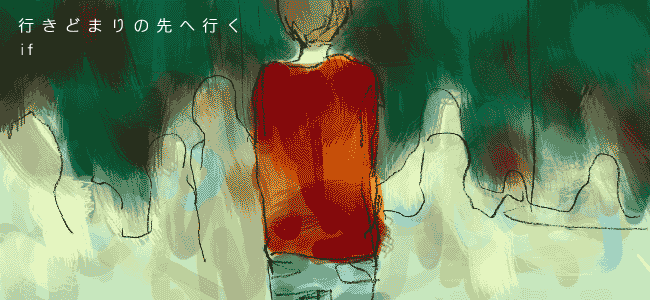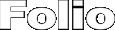携帯電話のバッテリーが壊れていて電源が入らないことに気付いた。今日の深夜12時頃に電話するねって彼と約束したというのに。明日はデートの予定なのだがまだ待ち合わせ場所も時間も決めていない。だから寝る前までには連絡をとって彼の都合を尋ねなくてはいけなかった。家の電話からかけようと思ったのだが電話番号が分からない。いつも携帯電話のアドレス帳からかけているのでどんな番号だったのかも覚えていない。いや、どこかにきっと書いてあるはずだと思って引き出しの中や財布の中をあさってみる。彼の名刺が出てきたけど会社の電話番号しか書いていなかった。次にPCを起動して今まで彼からもらったメールを一つ一つチェックする。署名欄には当然メールアドレスしか書いていない。しかし過去を遡っていくとついに本文中に電話番号を記したメールを見つけた。多分番号はあれから変わっていないはず。さっそく家の電話からかけようとしたけれど繋がらない。そもそも発信音がしない。そうだそういえば家の電話は2週間前から止まっていたのだ。別にお金がないわけではないのだが払い込みに行くのが面倒がっていたのが災いした。仕方ないので公衆電話からかけようと家を出る。しかし公衆電話が見つからない。5年前まではけっこうどこにでもあったような気がするのに繁華街に行っても全く見つからない。自転車で10分くらいうろうろしたあげくやっと見つけることができた。そこで財布を開けてみるもコインが入っていないことに気付く。万札しか入ってない。どこかで何かを買ってくずさなくてはならない。すぐ隣に煙草の自動販売機が置いてあったけど深夜なので販売時間外で電気が消えている。1ブロックほど走ってみるとジュースの自動販売機を見つけたけど、「ただいま紙幣は使えません」との張り紙がしてあった。更にもう1ブロック進むと、あやしげな100円ジュースの自動販売機を見つけた。聞いたことのないメーカーだったけれど今欲しいのは飲み物ではなくコインなのだからこだわっては居られない。適当なスポーツドリンクみたいなのを買って小銭をゲットした。そこでさっきの公衆電話に戻り電話をかけてみる。なかなか繋がらずやっと繋がったと思ったら留守番電話だった。仕方なく受話器を置く。こんなことで貴重な100円硬貨を使ってしまった。数分待ってからもう一度かけてみるけどやはり留守番電話。もう数分待っても留守番電話。更に数分待っても留守番電話。使えるコインは尽きてしまった。もう一度さっきの自動販売機まで戻り、500円玉でまたあやしげなスポーツドリンクを買う。お釣りの硬貨でまた電話をかけてみると、やっと繋がった。「すまん実は風邪ひいちゃって明日のデートはキャンセル」これが彼の答えだった。家に帰ってから飲んだスポーツドリンクはこれでもかというほど不味かった。
2.
僕が初めて赤い服を着て学校に行ったのは10歳の時だった。特に何か考えがあったわけではなく、ただたまたま母が買ってきたトレーナーが赤色で、普通に良いデザインだと思ったからだ。
ところがクラスメイトの男子たちは、僕が教室に入った途端、
「うわあ、男のくせに赤い服なんて着てる!」
と、囃し立てた。
休み時間にいつものようにみんなと野球をしようと思ったら、
「お前は女だから入れてやらない」
「赤い服を着た女はあっちでママゴトでもしてろ」
などと口々に悪態を付かれて仲間外れにされた。なぜみんながそんなに大騒ぎしているのかよく分からなかったけれど、自分が何かすごく恥ずかしいことをしてしまったらしいとは理解できた。その日1日は、なるべく目立たないように小さくなって過ごした。
その日以来、僕は3年間、決して赤い服を着ようとはしなかった。
3年経って、久しぶりに赤い服を着て学校に行ってみた。中学生にもなれば、多少は価値観の多様性というものを理解できるようになっている。1つの選択肢として、たまに赤い服を着てみるのもいいんじゃないかと思ったのだ。
そんな僕を見るなり、友達はきょとんとして、
「何かあったの? どうしたの?」
と僕を問いつめた。いや別にいいだろ、と答えると、まるで気の違った人に接するみたいに警戒の表情をされた。それ以上口では何も言われなかったけれど、明らかに距離を置かれているのが分かった。
クラスで前から気になっていた女の子には、
「なんか変。似合わないね。いつものほうがいいんじゃない?」
と笑われた。周りの女の子達もそれに同意している。悪意のない笑いだったけれど傷ついた。遠くからひそひそ声が聞こえてきたり笑い声があがったりするたびに、自分の背中が指さされているのではないかとびくびくしながら過ごさなければならなかった。
その日以来、僕は6年間、決して赤い服を着ようとしなかった。
6年経って、世間では赤い服が流行っていた。
赤い服を着た一流モデルたちがファッション雑誌の表紙を飾り、有名な服飾メーカーは競って赤系の色を多用した新作を発表していた。街に出れば、身体のどこにも赤を身につけていない男性を見つけることのほうが難しいくらいだった。
今度こそは自分が着てもバカにされずに済むかもしれない。ごく普通の行いとして、気に留めずに当たり前に受け取ってもらえるかもしれない。
僕はおそるおそる、本当におそるおそる、赤い服を着て街に出てみた。
バッタリ会った大学の友達は、僕を一目見るなり、
「へえ、お前も流行なんて気にするタイプだったんだ」
と軽蔑したような目で笑った。その瞬間、街に溶け込んでいたはずの僕の自意識が空気から浮き上がるのを感じた。街を歩いている人々の刺すような視線を僕に送っている。自意識の表面はみるみるうちに錆びて剥がれ落ち、ボロボロになった。
その日以来、僕は永久に、赤い服を着ようとはしなかった。
誰が何を言おうと、決して決して、赤い服を着ようとはしなかった。
3.
「おはよう」
「……」
「おはよう」
「俺に話しかけるな」
「いい天気だね」
「全然」
「ええっ? そう?」
「うるさい」
「晴れてるじゃん」
「お前の存在自体がうざいんだよ黙れ」
「晴れてると思うんだけど」
「お前ほんとうに頭悪いな」
「晴れ……」
「バカはここに居る資格ないんだよ、幼稚園からやり直せ」
「ところでさ」
「いいかげん失せろよデブ」
「田中先生が転勤しちゃったじゃない?」
「どうでもいいこといちいち言うなデブ」
「淋しいよね」
「お前の言うこといちいちキモいんだよデブ」
「いい先生だったのにね」
「お前にそんな台詞を吐く資格はねえんだよ」
「それでさ」
「いいからもう死んでくれ」
「明日の講義は休講って聞いてたと思うんだけど」
「お前の声聞いてるだけで気分悪くなるんだよ早く死ね」
「新しい先生が早めに来ることになって」
「黙らないと殺すぞ」
「やっぱり講義やるから時間に集まるように、だって」
「もう二度と俺に近寄るな」
| 1 / 2 | Next |