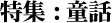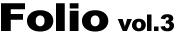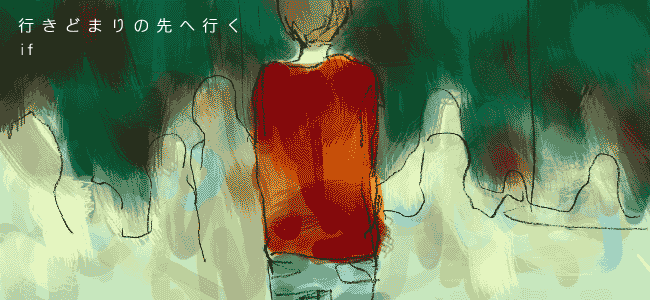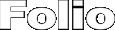引きこもりの自分だけど久々に家を出て街を歩いていたのですがとりあえず腹を減っては戦は出来ぬので食事をでもするかと思って財布の中身を確認しようとしたら小銭入れのファスナーが開いていて100円玉が滑り落ちてしまったのを拾おうとしてかがみ込んだらお気に入りだったスカートのすそが水たまりについてしまい慌ててもう一度立ち上がろうとしたら段差につまづき前のめりに倒れそうになって咄嗟に横の看板につかまったところ看板を電柱に縛り付けていた紐がほどけて看板はそのまま隣のビルの窓ガラスに激突してカシャンという乾いた音と共にガラスは割れ砕けて自分も結局水たまりに頭からつっこんで額に傷を作って上着も破いてしまった上に100円玉のほうはコロコロと転がって深い排水口の闇の中へ吸い込まれてしまったのと同時にガラスの破片に触れて指先に切り傷を作ってしまったらしい小さな子供が大声で泣き出して親に怒鳴られ公衆の面前で土下座させられて当然割れたガラスの弁償もさせられて身も心もボロボロになったのを紛らわすために酒でも買って飲もうと酒屋に入ったもののお金が100円足りなくて買えずにもう家に帰って適当に腹を満たしてさっさと寝ようと思ったら自転車が撤去されていて仕方なくとぼとぼと歩いて帰る途中に突然雨が降り出してびしょ濡れになってようやく家に着いて料理をしようと思ったら留守の間に電気を止められていて米を炊くことすら出来ませんでした。
5.
悲しくて流す涙には、ラクトフェリンというモルヒネの4倍の鎮痛作用を持った成分が含まれているらしい。いやそんなことはどうでもいい。問題は、僕の涙に入っている鎮痛成分は、普通の人よりもずっと強力で長続きするスペシャル仕様の奴に違いない、ということなのだ。その場限りで気が休まるだけではなく、元凶となっていた欲求や望みを永久に諦めることが出来る。おかけでいつでも物わかりの良い男でいられるのだった。
たとえば大学2年の時だ。付き合っていた女の子が留学した。始めの頃は毎日来ていたメールもだんだん2日に1回になり、1週間に1回になり、やがてたった1行の返信に1ヶ月も待たされるようになった。しかし、待ちに待ってやっと彼女が日本に帰ってくる日が近づいてきた。これからはまた、毎日会って好きなだけ話せる関係に戻れるのだ。帰ってきたら、一緒にどこに行こう、何をしようと期待に胸を膨らませていた折に、別れを告げるメールを受信した。僕は泣いた。一晩中泣いて、涙が枯れた頃にはもう彼女に会えないことが辛いとか恋しいとか思わなくなっていた。それ以来、他の女の子と付き合っても、「早く会いたい」とか「連絡が欲しい」とか思ったことがない。好きだという気持ちがなくなったわけではないのだけれど、何ヶ月も音沙汰なくても全然耐えられるようになってしまった。
たとえば大学4年、就職活動の時だった。第1希望の会社の採用枠は1名、最終選考に残ったのは僕ともう1人、合わせて2人だった。僕が修論で選んだテーマは、ちょうど社長が最近興味を持っている問題と一致していたらしくて、面接の感触は非常に良かった。ところが、東大生だったもう1人の奴が、最終面接の日に大幅に遅刻してくるという失態をやらかしたに関わらず受かってしまったのだ。それはきっと、僕が三流大学で彼が東大生だったから、という理由以外には考えられなかった。僕は帰る途中、通行人の人目もはばからずに泣きに泣いた。生涯を左右する問題だっただけあって、家に帰っても涙は止まらず、親の前でも泣き続けていた。それ以来は誰かに学歴をバカにされることがあっても、ちっとも傷つかないし悔しいとも思わない。それどころか自らカミングアウトしてへらへらと笑っていられるようになってしまった。
そして、ついこの前のことだった。僕はまた、付き合っていた女の子にふられた。彼女は「今のあなたは私が好きだった頃のあなたじゃない。鏡を見てご覧なさい」と言った。そこで改めて鏡を見て唖然とした。鏡にはまさに「デブのおっさん」という形容が似合う、醜い生き物が映っていたのだ。数年前までは、むしろ痩せているくらいだったはずなのに。道理で服がきつくなっているわけだ。これじゃふられても仕方ない。僕は久しぶりに泣いた。他の誰でもなく、自分自身への怒りで泣いた。二重の瞼が腫れて一重になるまで涙を流したあと、ダイエットを決意した。水とお茶以外のものを口にするのを一切拒否した。
それからもう3週間が経つのだけれど、まだ全然、お腹が空いたとか、何かを食べたいという感情がわき上がってこない。どれだけ痩せて立ち上がるのが苦痛になっても、歩くと足の骨が痛むようになっても、食べ物に興味はこれっぽっちも持てなかった。僕の食欲は、この前の涙のせいで全て麻痺してしまったのだ。たぶんこれから僕は、最後まで何も食べずに死ぬのだろう。それでも良いと思った。
6.
「今、何が欲しい? 叶えてあげるから、何でも言ってごらん」
「そうだな、実は今すごく喉が渇いてるから、出来ればみ」
「あ、そうそう“水”って答えはナシね。わたしそういう面白みのない答えって嫌いだから。せっかくの何でもって言ってるのに、叶え甲斐がないじゃない。遠慮のしすぎはかえって失礼よ」
「分かった。じゃあ、あのね、ビー」
「おっと、あとアルコール類も止めてね。身体に良くないんだから。知ってた? アルコールの身体依存性はヘロインと同程度なんだって。しかも肝硬変や肝臓癌だけじゃなく、食道癌や大腸癌の原因にもなるし、脳を萎縮されちゃって痴呆症になることもあるんだよ」
「うん……」
「さあ、それで今、何が欲しいの?」
「ええと、それならね、とにかく今は喉がカラカラなんで、コ」
「言い忘れたけど、もちろん紅茶とかコーヒーとかカフェイン飲料も駄目だよ。カフェインもアルコールと同じくらい毒性と依存性があるからね。栄養素を溶かして尿と一緒に排出させてしまうし、そのうち習慣化してくると、カフェインが切れただけで無気力になっちゃうよ」
「……」
「さあ、それで今、何が欲しいの?」
「だったら、ジュ」
「もちろん、ジュース類も不許可だよ。ああいうのって、実はかなり糖分が含まれているんだって。糖分を取りすぎると、カルシウムを溶かしてしまって骨が弱くなったり怒りっぽくなったりするし、免疫力を低下させるとか奇形児を生みやすくなるって実験結果もあるんだから」
「……」
「さあ、それで今、何が欲しいの?」
「……」
「ほら、叶えてあげるから、遠慮しないで何でも言ってごらん?」
「……」
7.
最初に運ばれてきた料理は一見すると焼いた肉の塊のように見えた。しかしかぶりつくとゼリーのように異様に柔らかく、鼻がツンとするような酸っぱい臭いがして、口の中に渋みが広がった。腐ってるんじゃないですか、と言いたかったけど、残すことは許されない。鼻をつまんで、なるべく噛まずに飲み込んだ。全て食べ終わってから何度も水で口をゆすいだけれど、ゲル状の残りかすがいつまでも舌に絡まっていて取り除くことができなかった。ゲップをするたびに口や鼻の中が再び悪臭で満たされた。
次の料理は、一見海草サラダのようにも見えた。が、口に入れていくら噛んでも噛みきれない。まるで髪の毛を食べているみたいだった。歯に挟まった繊維が喉の粘膜に触れて気持ち悪い。泥のような濃い茶色のドレッシングは味も泥臭くて苦かった。何度も胃から戻しそうになるのをむりやり喉の力で飲み込み、もう一口、あと一口と続けて詰め込んで押さえ付けた。
続けて出てきたのは、茶碗に入った白いつぶつぶだった。遠くから見た時はご飯のようだったが、一粒一粒がうねうねと波打つように動いていた。つまり生きている虫だった。僕は泣きながらそれをスプーンですくって口に入れた。噛まずに飲み込むと喉を通る間も中で動いている様子が分かった。間違って数匹を噛み潰してしまったら、プチっという音と共に渋い液が出てきて、生臭い味がした。なるべく何も考えないようにしながら、全てを掻き込むように胃に流し込んだ。
最後に出てきたのは、一粒のキャンディだった。用心しながらファンシーな包装紙を開けてみたが、砂糖で出来た紛れもない普通のキャンディーだった。舐めてみると、いかにも人工的なイチゴの香料の甘ったるい匂いがした。懐かしくて、優しい気持ちになれるような、あの芳香だ。口いっぱいに広がった砂糖の甘さは僕を恍惚とさせた。何て幸せな甘さなのだろう。僕は今の瞬間のために生まれてきたのかもしれない。キャンディがこんなに美味しい食べ物だったなんて知らなかった。
そして僕は死んだ。最後のキャンディーには青酸カリが仕込んであったのだ。これが僕の人生だ。
| Back | 1 / 2 |