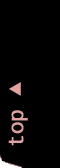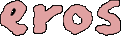j i i
歪
「ねぇ、見てよ」「ねぇ、見てよ」
彼女は今日もセックスの後、皺だらけのベッドの上に一人残り、火照りが残る白い脚をM字に拡げてオナニーを始める。
僕は彼女に背を向けた格好で煙草に火をつけながらコンドームを外す。精液にまみれた自分の陰部を拭く姿なんて、いくら彼女にでも見せたくはない。今の僕の姿は、世の中のどんな男の背中よりも小さいだろう。
煙草の煙に目を細めながら陰部にこびりついたティッシュを小指の爪で剥がす。
彼女は、誰にも見せたくない姿を僕に見せようとする。射精の後の倦怠感と絶望感に支配されながら僕は彼女の声の方へ振り返る。彼女はいつの間にかベッドサイドに座り、右脚を床の上、左脚をベッドの上に乗せて脚を大きく拡げている。
僕は大きく息を吐く。半分は煙草の煙で、半分は溜息。左手で煙草の灰を落とし、右手で精液を拭いたティッシュを、部屋は暗くてよくわからないので、ゴミ箱があった辺りに投げる。
彼女は左手で自分の身体を支えながら右手でベッドのライトを灯す。その間も彼女の陰部は生き物のように小さく動いている。まるで餌が足りなかった得体の知れない獣の口のように。白い流涎は床へ落とした彼女の右脚を伝っている。
「ねぇ、見てよ」
彼女は口元に笑みを浮かべ同じ言葉を繰り返す。いつものことだ。僕が見なければいつまで経っても同じことを言い続ける。時に艶を込めて、時に挑発的に、綺麗に磨かれた桃色の爪をまとった二本の指で優しく陰部を撫でながら。
僕は彼女の行為をぼんやりと眺める。ベッドのライトが射精後の、女性を見る冷たい視線まで届かなければいいと思う。僕は薄暗闇の中、スポットライトの中のストリップ嬢のような格好をした彼女のショーを見る。萎えた陰部を右手で弄びながら。陰毛の奥にはまだ彼女の白い愛液が絡まっている。
彼女は眠いような悲しいような、懇願するような視線を宙に漂わせながら左手で陰部を開き、右手の中指で円を描くようにクリトリスをこすり始める。綺麗に立った彼女の右手の小指は僕の方を指している。
僕には視線を合わせない。まるで僕自身が彼女の前に存在しないかのように。だけど彼女は僕にオナニーを見るように強要する。
だからいつも僕は暗い部屋に取り残されたような気持ちになる。
走り寄ってきた犬のような小刻みな息を吐きながら、時々喉の奥から搾り出すような声を挙げる。その声と同時に彼女の身体が一瞬だけ痙攣し、肛門が締まる。
僕は二本目の煙草に火をつける。煙草を口元に持ってくると右手から彼女の愛液の匂いがする。煙草の匂いと混ざり合った甘酸っぱい欲望の香りは毎晩のように僕の指にこびりついていく。
フィルターの先まで煙草の火が浸食したとき、彼女は歯を食いしばりながら今夜二度目の絶頂を迎えた。
「一度くらい手の抜いたセックスがあってもいい」
僕は疲れていた。彼女もセックスの前から疲れているようだった。一緒にシャワーを浴びた後、いつものように髪の毛を拭いてあげながら、もしかしたら彼女はこのまま眠ってしまうのかもしれないと期待していた。だから僕も少し手の抜いたセックスをした。
長い人生で数え切れないくらいの――それは回数の問題かもしれないし、人数の問題かもしれない――セックスをするのだから、一度くらい手の抜いたセックスがあってもいい。
2 / 3