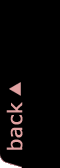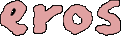彼女はシャワーの前には考えられない表情で自らの「内臓」を強くこすりつけ、地の底から湧き上がるような声を挙げた後、僕の上で硬直した。
硬直したまま自らの欲望の世界に浸るように眉間に皺を寄せて目を閉じていた彼女は、やがて静かに目を開き、彼女の中で硬さを失いかけていた僕の陰部を抜いてコンドームの上からそっと咥えた。
メントールが配合された冷たい感触のコンドームの外で、彼女の熱い舌使いを感じる。コンドームの先には僕の精子が溜まっている。疲れていたからあまり出ていない。彼女にそのことに気付かないで欲しいと思った。
彼女は精子が溜まった部分だけを口に含み、僕の陰部から力任せにコンドームを口だけで引き抜いた。僕の胸や腹に、白い液体が飛び散った。それは僕のものであって彼女のものでもあった。彼女は悪戯な笑みを浮かべてコンドームを口に含んだままベッドの上でパンティーを手探りで探し始めた。
今日はこれで終わるかもしれない。僕は少し安堵していつものようにベッド脇の小さな赤いソファーに座り煙草に火をつけながら自分の陰部を拭くためのティッシュを探した。セックスの前にティッシュの場所を確認すればいいのに、いつもそれを忘れてしまう。
テレビの脇にあったティッシュに手を伸ばしたとき、彼女の声が聞こえた。
「ねぇ、見てよ」
彼女はいつものようにM字に脚を拡げていた。いつもと違うところは今日は下着をつけている。陰部の部分だけが布で覆われ、残りの部分はレース状になっている白い下着。
僕はベッドライトが届かない暗闇の中で顔をしかめる。今日も、また始まる。
彼女は陰部のラインに沿ってパンティーを食い込ませ、紐状になったそれを自分でくいと引っ張る。パンティーが彼女の陰部に食い込むたび、インターホンのように彼女の声が反応し、大陰唇が両側から白い紐を咥える。彼女の荒い息遣いが僕の耳に厭味なほどに届く。左手で自分の身体を支えながら、必至に右手でパンティーを引っ張っている。
彼女のそれは、クリトリスを刺激し、枯渇を知らない欲情の泉を更に溢れさせる。彼女の二本の指がパンティーごと彼女の中に入っていく。
まるでパンティーと戯れているように白い布を駆使しながら、自らを絶頂へ誘導させていく。
今日仕事帰りに買ったばかりだという純白のパンティーは、既に欲情の色に染められていた。
「白い液体が人参と、彼女を濡らす」
彼女がセックスの後にオナニーを始めるようになってから、どのくらい経っただろう。どんなに疲れているときも、どんな酷い喧嘩をした後も、僕たちは毎晩セックスをして、彼女はその後にオナニーを始めた。
食事の後に食器を片付けるように、それは通例化していたし、僕もそれを日常の一部として自然に受け入れようとしていた。彼女が僕に見せつけるように自慰に耽る理由を聞こうとは思わなかったし、彼女から口を開くこともなかった。
「ねぇ、見てよ」
彼女は道具を使うこともあった。それは自らの快感に忠実な彼女自身の進化ともいえるし、エスカレートした行動ともいえた。口紅から始まって、香水の瓶、箒の柄、そして今夜は人参にコンドームをかぶせた。
彼女の行為に鈍磨していた僕は、彼女のその行為よりも残り一個のコンドームを野菜に使われたことに顔をしかめた。明日コンドームを買いに行くことを忘れないようにしなければいけない。薬局なんてコンドームを買いに行くときしかいかないから、もしかしたら店員に顔を覚えられているかもしれない。明日はコンビニで買おう。ここから少し離れているけど忘れないようにさえすればいい。
コンドームに包まれた人参は、見る見るうちに彼女の中へ入っていく。愛液と人参が絡まりあう淫らな音が聞こえ浸出液のような白い液体が人参と、彼女を濡らす。彼女の上半身を蛇のようにくねらせている。開いた右手で形の良い乳房を鷲掴みにしている。指と指の間から柔らかい肉塊がはちきれそうに顔を出している。
まるでAVを早送りで見ているように、彼女の左手は忙しく動いている。人参を自らの内臓に突き刺し、歓喜の声を挙げている。
僕は明日の夜になるまで硬くなることのない自分の陰部を下着に収め、炭酸の抜けたビールを飲み干した。セックス前に分泌されたカウパー液がまだ僕の下着の中で乾かずに、僕の陰部を悲しく刺激させた。
部屋中が、彼女の匂いで満ちていた。
2 / 3