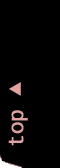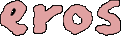リンゴとエロスについて、彼女の考察
ぱそ子
ある時、彼女は、リンゴってのはとてもエロティックな果物なんじゃないだろうか、と考えた。彼女はデパートのエレベーターガールだった。不景気な世の中に似合わない仰々しい言葉使いで、お客様を上から下へと運び続ける、絶滅が危惧される仕事の一種だった。「上へ参ります」
と、彼女は一階のフロアに降り立つと、白い手袋をはめた左手をチューリップのように顔の横で咲かせて見せる。肩をすぼめた買物客が乗りこむと、彼女は優雅な動きでボタンを操作し、重いエレベーターの自動扉を閉めるのだった。彼女は一度微笑んで見せた。客から希望の階を聞き出して、手もとのボタンを操作する。客たちはお互いの体が触れ合わないよう肩をすぼめて、息苦しそうに扉の上の光る数字を見つめ、自分の存在を無に帰そうとしている。彼女は消えたがっている客たちに向かって、澄んだトーンで各階のご案内をするのだった。
「3階婦人服売り場でございます。足元にお気をつけ下さい」
エレベーターにわざわざ人を配置して案内をするデパートは最近ではあまり見かけなくなり、この界隈ではこのデパートだけだった。彼女の勤めるこのデパートはエレベーターに接客の人員をわざわざ裂いていることを他のデパートとは違う利点の一つである、と自負しているようだが、そんなの全く見当違いだわ、と彼女は思っていた。エレベーターは子供だって使えるように出来ている。何も客たちだって生まれて初めて乗るわけではないのだ。他のデパートでは、全てセルフサービスで、客が自分で希望のボタンを押せば、エレベーターが機械音で「3階婦人服売り場でございます」と答えてくれる。機械で済む仕事である。この点を踏まえて、このデパートのエレベーターの彼女だって仕事は自動運転だった。彼女が微笑むのも各階をご案内するのも、彼女の意志とは無関係で自動でこなせるる妙技を彼女は何年間かの勤務で身につけていたので、彼女の頭の中では引き続きリンゴとエロスの関係について考察し続けることができるのだった。
「4階紳士服のフロアでございます」
まず、リンゴってのはとても赤い。ええ、偽物みたいに赤いわ。つやつやと軽薄で自己主張の激しい赤。そのくせ薄い皮一枚剥くとやわな白肌で。つるりと皮を剥かれたリンゴのなんと卑猥なこと。皮ごと歯を立てられたあとのあの歯型もエロい。ああ、でも違う、そうじゃないわ。だからといってリンゴとエロスが結びついているとは言えないわ。リンゴとエロスの関係はもっと違うところにあるんじゃないかしら。
「6階、子供服とおもちゃのフロアでございます」
彼女は、自分が一体どうしてリンゴをエロティックな果実だと思ったのか、その理由を突き止められないでいたが、リンゴがエロティックであるという思いつき自体には、そっと興奮していた。
でも、なんでリンゴがエロティックだなんて思ってしまったんだろう。リンゴに欲情するなんてあたしがただの変態だからだろうか。
彼女は立ったままそっと足を組み替えて重心を右足から左足に移した。エレベーターの中はいつのまにか閑散としていて、中にいるのは彼女と直方体の隅っこに立っている髪の長い眼鏡の女学生だけだった。
ねえ、あなたはリンゴとエロスの関係についてどう思うかしら? と、彼女は女学生に聞いてみたかったが、エレベーターガールである彼女の唇は沈む間際の上弦の三日月のようににこりと持ちあがった形を保ったまま、「9階、書籍のフロアでございます」と言っただけだった。女学生は9階で降り、彼女はエレベーターの扉の向こうに立っている客に対して、上に参りますと断ってから扉を閉めた。扉を閉めてから彼女はほっと溜め息を吐いた。お客さんにこんな妙な話を持ちかけたことが誰かに知れたらすぐに仕事を首にされてしまうだろう。この問題に関しては、相談相手を慎重に選ばなくてはね、と彼女は考えた。それから彼女は、今日の仕事が終わった後、ロッカールームで顔を合わすであろう同僚の顔を思い浮かべる。化粧品のアドバイザーをしている同僚だ。彼女は、鏡に向かって下着姿のまま念入りに化粧を直しているその同僚に、「ねえ、リンゴってエロティックな果物だと思わない?」と提案するシーンを想像する。
ああ、駄目。全然駄目。彼女にはきっと分かってもらえないだろう。白い目で見られるか、まるで何語を喋っているのか分からないというような積極的な無反応で口紅を塗りつづけるか、もしくは見当違いに自分の性生活について赤裸々に語るのかもしれない。
エレベーターが屋上で止まる。「下へ参ります、」と彼女は微笑んで、手押し車を押す老女を一人乗せた。
その夜、自分の部屋に帰った彼女は、彼女の部屋を我が物顔に占拠している男を第一の相談相手にすることにした。
「ねえ、リンゴってエロティックな果物だと思うのだけど、どうかしら?」
と、彼女が男の反応を窺うようにそっと提案すると、男は「いいね。全く賛成だ」とすぐに答えた。男が同意してくれたのが嬉しくて、「どこがどう賛成なの?」彼女は顔を輝かせながら男にさらに尋ねる。
「そうだなあ、」
男は彼女が座っているベッドの前で、フロアにあぐらをかいて雑誌を読んでいたが、彼女の質問に雑誌を読むのを止めて顔を上げた。男は三ヶ月前に別れた彼女の元恋人であったが、別れるまでの五年五ヶ月の間恋人であった気安さからか、別れたあとも男は相変わらず彼女の部屋に遊びに来て自分の家のようにくつろいでいったし、彼女のほうも男が自分の家にいることに違和感はなかった。
「リンゴとエロスの関係か、」
と、男は、読みかけの雑誌を放り投げると、あぐらの姿勢のまま彼女の足元まですり寄ってきた。彼女のストッキングを脱いだばかりの素足の前に男の顔が近づいていく。
「分かったぞ」
突然男は彼女の足を掴んで持ち上げる。彼女はバランスを崩してベッドに倒れこんだ。
「ちょっと、やだ、何」
男は素早くスカートの中に頭と手を突っ込んで、彼女のショーツを脱がした。そしてとスカートを捲り上げ、両手で彼女の足を広げさせて彼女の性器を露にした。彼女が足をじたばたさせて嫌がっているのに、男は一向に意に介していない。男はしばらく彼女の性器を観察し、それから自分の唾液で湿らせた指を彼女の性器に這わせながら、
「分かったんだ、リンゴとエロスの関係」
と、言った。
「お前のここ、リンゴを半分に切ったのと似てるだろう。リンゴの皮が付いてる方の丸い部分がけつで、断面の穴の形が、ほら」
それから男は彼女のスカートのフックを外すと、するするとスカートを脱がせ彼女の足から抜き取った。彼女のセーターに下から手を入れて丸めるように頭から脱がせ、ついでにブラジャーのホックを片手で外し、腕からブラジャーを抜きとった。彼女はあっという間に全裸になってしまった。
「確かに、エロい。リンゴはエロい果物だ、」
と、男は自分の思いつきに満足そうににやにやと笑っている。男の思いつきをそのまま認めてしまうのが悔しくて、彼女は男の執拗な愛撫に身をよじりながらも、何とか反論の言葉を紡ぎ出す。
「エロスってのはそんな短絡的なものじゃないわ。もっと、」
「もっと何だ?」
男のくぐもった声が下の方から聞こえた。男の顔はいつのまにか彼女の太股の間にあって、男は彼女の女性器に舌を這わせているところだった。
彼女は言葉を続けようとしたが、彼女の口から出てきたものは言葉ではなく熱い吐息。言葉の続きは、普段体の中心で眠っているもう一人の彼女のこみ上げるような喘ぎ声にかき消され、もうそれ以上彼女は言葉を続けることは出来なかった。
「蜜が出てくるところまでそっくりだ」
と、男は言った。
彼女にとって男は恋の対象ではなく、むしろ家族のような空気のような存在で、彼女は彼に対してもうエロスを感じることはなかったが、触れられれば体は勝手に反応するのだった。
「エロスってのは短絡的なものだ、体の条件反射だ」
と、裸になった男が彼女の耳元で囁きながら彼女の上で体を揺らす。
違うわ、体の反応はエロスじゃなくてただの快楽よ、と彼女は思ったが、もう目を開けることすら難しく、彼女の意識は白く遠く快楽の向こうへかき消されていくのだった。
1 / 4