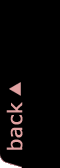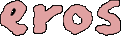「おつかれ」
と、待ち合わせ場所に現れた友人に彼女は声をかけた。彼女の友人は彼女を上から下まで素早く眺めて、
「久しぶりだけど何も変わってないわね。いいわ。どこに食べに行く? どこか予約した? 今日は何時まで空いてるわけ? 明日の仕事は何時から?」
と矢継ぎ早に彼女に言葉を浴びせた。彼女は友人の言葉を頭の中で一つ一つスロー再生しながら、
「イタリア料理にしましょう。予約はしてないけれど、きっと空いている店を知っているわ。今日は夜遅くまで大丈夫、あなたに合わせるわ。明日は休みなの」
と、一つ一つゆっくりと正確に答えた。そして小さく息を吐く。
「あなたのそのテンポ、どうにかならない?」
「職業病よ」
と彼女の友人は答えた。
店は彼女の予想通り、席の空きがあった。アルバイトの子一人と店長一人でやっていけるような小さな店だ。まだ開店して一年足らずのため客足がしっかりとしていないようで、こんな平日の夕方には席が埋まっていないことが多いのだった。
「でも、味は保証するわ」
と、彼女は言った。彼女の友人は、こじんまりとした店を見渡して、いい感じねと満足そうに肯いた。
メニューを手にした友人はてきぱきとワインはこれ、前菜はこれとこれと、パスタは……と彼女の理解が追いつかない速度で注文し、店員が下がると鞄から煙草を取り出し一本咥えて火をつけた。そして頬をへこませて深々と煙草を吸い込むと、ふうと煙を吐き出した。
「たまにはこうしてゆっくりするのもいいわね」
と、友人は言った。
「ええ、そうね」
と彼女は一応相槌を打っておいた。
テーブルに、丸く膨らんだ大きなワイングラスが二つ置かれた。そのグラスの形が彼女にリンゴを彷彿とさせたので、彼女はいい機会とばかりに友人に話を切り出した。
「今ね、リンゴとエロスの関係について考えているの」
「エロス? 何それ。面白そうね」
そのとき赤ワインのボトルを右手に提げた店員がやってきた。友人は、店員に「テイスティングはいいわ、味知ってるから。注いでもらえます?」とにこりともせずに早口に指示した。そして、エロスねえと嬉しそうに一人ごちた。彼女は友人の分まで含めた二人分の愛想笑いを店員に送っておいた。
「まずはエロスって何かをはっきりさせないといけないわ」
と、言って彼女の友人は煙草をもみ消して灰皿を押しやると、赤ワインの入ったグラスを手にとって光にかざした。ゆらり、妖艶な赤が白いテーブルクロスに映って揺れた。
「エロスって一口に言っても人それぞれだろうけれど、まず私にとってのエロスって何かを考えるとね」
乾杯、と軽くグラスを持ち上げて、彼女の友人がグラスを唇につける。ワイングラスの中の赤い液体は、水面をゆらゆらと波立たせながらグラスのカーブをゆっくりと滑り落ちる。一筋の赤い液体が彼女の友人の唇に貼りつき纏わりつき、唇の奥の穴へと吸い込まれた。白い喉がぴくぴくとと震え、赤い液体たちを受け入れたのが体の外からでもありありと観察できる。彼女は自分のグラスの足を指で摘んだままそのグラスに口をつけることなく、友人の唇に見惚れていた。彼女が見惚れている間にも、その唇は液体の洗練を受け赤々と濡れながら言葉を漏らす。
「そうね、まずは私がどんなときに一番エロスを感じたか考えるのがいいと思うわ」
彼女の友人がエロスエロスと連呼している間に、店員は次々と前菜を運んできている。一体店員になんて思われているのだろうか、と彼女はちょっと不安に思ったが、しかし、彼女の友人は他人の目を気にするようなタイプではないから忠告しても無駄だった。ここは友人の話に集中すべきだ、と彼女は考えて自分もワインを一口飲んだ。クランベリーのような華やかな香りが口いっぱいに広がり、淡い渋みが舌の上に快く残った。もう一口ワインを口に含む。彼女の友人はいつの間にか、料理をさっさと二人分に取り分けていた。彼女の目の前には取り分け皿に綺麗に盛られた一人分のサラダと真鯛のカルパッチョが並んでいた。
以下は彼女の友人のエロスについての考察である。
私が学生の時、医学部の人体解剖を見学に行ったわ。その話はしたわね? 私達看護学生は各台に配置されて、医学部の学生たちが遺体を解剖して行く様を見学するの。本当は頭の先からつま先までを何週間にも渡って少しずつ解剖して行くわけで、医学部の学生は何週間にもわたって実習をしているんだけど、私達が見学できたのは一回だけだったから、ちょうど腹とか胸とかで、臓器がいろいろ出てくる辺りだったわ。(そのとき、店員がトリッパのトマト煮を運んできたので、この友人は人間の胃とは随分違うわねと言って、彼女を嫌がらせた。)
解剖実習の見学の日は夏だったんだけど、その解剖室は地下にあって、しんと暗くて、何だかひんやりしているの。そして部屋中にホルマリンの臭いが充満していたわ。慣れるまでは本当にひどい、一度嗅いだら1週間は鼻に残る臭い。部屋の中には台が10個あって、その各台に1体ずつ、遺体が寝かせられているの。
死んだ体が10体。
その密室には濃厚な死があった。固くて絶対的な死なんだけれど、でも一方ではその死を、20歳そこそこの生気に溢れた学生たちが取り囲んで、その死を解剖している。知識欲と好奇心に突き動かされるメス。そしてそれを見学している私たち。
私ね、そのときとても不謹慎なんだけれど、そこに横たわる死体が自分だったらどんな気分だろう、と思ったわけ。老いてしわしわになって、頑なに無抵抗に横たわって。それもホルマリン漬で皮膚が変色して。その私の裸体を5、6人の若い医学生が取り囲む。もちろん彼らの手に持たれたメスにはエロスの一粒だって介入する余地はないわ。ただ彼らは、人体への興味と畏怖と、あとはちょっとした義務感に突き動かされ、私の皮膚を切り裂き黄色く変色した内臓の脂肪をこそげおとし、解剖の図解と見比べながら、ここが十二指腸だなんて囁きあっているの。彼らの冷静な目と無心の手作業に曝された自分の卑猥な裸体。皮膚の奥の誰にも見せたことのない臓器が、自分でも見たことのない体の内部が、引っ張り出され観察され無数の手に弄くり回される。
それってとてもエロスを感じるシチュエーションだと思わない?
2 / 4