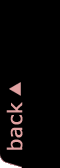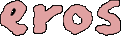「新しい薬を作ったんだ」
ヤシマは得意げに言うけれど、それほどアリスの気を惹くわけでもない。化学部の人ってどうしてこうなのかしら、黒い実験テーブルに頬杖をつきながら考える。試験管をいっぱい並べて、色鮮やかな試薬のグラデーションを作るのが何よりの愉しみらしい。
「好きなのを一本あげるよ」
「ふーん」
気のない様子を装って、12本の試験管を見比べる。よくよく見ると、どれもすごく綺麗。しばらく迷って、アリスは2本の試験管を選び出す。シャンパンのように細やかな泡を立てるフューシャピンクと、ムーンストーンを思わせる蒼白の半透明。セルフレームの眼鏡の奥でヤシマの目が笑った。
「どっちか選んで、飲んでみればいい」
「なんの薬よ」
アリスは唇をとがらせて訊き返す。向こう見ずにガラス瓶の中身を飲み干した不思議の国のアリスだって、いくらなんでも、大きくなる薬か小さくなる薬か、くらいのヒントはもらえたはずだ。
「媚薬だよ、どっちも」
「……」
オーマイガッ、もしあたしが外人ならそう呟いて頭を左右に振ることだろう、アリスはそんな馬鹿みたいなことを一瞬考える。ほんと、あきれた奴。
「ピンクのほうは、身体を僕に捧げたくなる薬。白のほうは、心を僕に捧げたくなる薬。どっちを選ぶ?」
「あのねえ、あたしには彼がいるの。あんたも知ってるでしょ、シン」
「知ってるよ。だからなおさら、薬でも使わないことには」
悪びれずにヤシマは言い、白衣を着た肩をちょっとすくめた。
「効き目は一時間、それ以上は何も要求しないから。さあ選んで」
ゲームというのは不思議なもので、具体的に選択肢を示されると逃げ場がなくなってしまう。他にもたくさんの試験管があったことを、アリスはぎりぎりのところで思い出した。
「ああ、やっぱりやめ。そのオレンジのにする」
「いいの? オレンジのは、男を全身舐め回したくなる薬。ヴァイオレットのはエクスタシーにイッちゃったきり帰って来れなくなる薬、藍色は縛られたくなる薬で、イエローは外でやりたくなる薬。このグリーンのはからだ中ぜんぶ感じちゃう薬。髪の先まで全部」
「あ、それでいいわ。その緑のちょうだい、シンと試すから」
「いいよ、どれか一つ僕のために飲んでくれたら、グリーンのをあげるよ。さあ選んで」
追い詰められて逃げ場をなくしたアリスは、いつのまにか試験管を持つヤシマの手を見つめている。色白で、骨張っていて、恋人の手とはまったく違う。この手がこの色をみんな創ったんだわ。
アリスはその仕草を想像する。茶色の薬瓶から注意深く粉薬を計って、さらさらと薄紙に載せる。三角に折った薄紙の上で何種類かの粉薬を混ぜ合わせ、試験管に流し込んで準備は完了。肝心なのはここから。先の長いスポイトを細口瓶に挿し込み、ほんの僅か液体を吸い上げる。スポイトを押すと、試験管の内側を、ゆっくりと液体が伝い落ちていく。最初のしずくが、試験管の底で待ちこがれていた粉薬に触れた瞬間、焼けつくような匂いと煙が立ちのぼる。その煙の色は…
「何色?」
「……ピンク…か、な」
アリスはようやく呟いた。恋なんて脳内麻薬の分泌にすぎない。そんなことはわかっているつもりだったけど、心を操られてしまうのはやっぱり怖かった。それに、そんな無形のものを捧げられても、ヤシマだって嬉しくもなんともないだろう。案の定ヤシマは、アリスの答えを聞くと、やったね、と小さく呟いた。
「ヘンタイ」
「天才と言ってくれ」
ヤシマは最低限のマナーとして、理科室の黒いカーテンをしっかりと閉める。まあいいか、とアリスは溜息をつく。あたしたちの他に、ここにいるのはガイコツの標本だけ。からっぽの眼窩にはなんの証拠も残りはしないだろう。
「そこに座って」
ヤシマはアリスを黒い実験テーブルに座らせる。ピンクの試験管を取り、液体を自分の口に流し込む。上向いた顎の端にも、くっきりと骨の線が浮き上がっていて、このひとは痩せているのにひどく貪欲に見えるとアリスは思う。
ヤシマは少しふてくされた様子のアリスを捕まえ、むりやりキスをした。口移しに流れ込んでくる薬を必死で飲み下す。すごく甘くて、その裏側にざらつく苦みがある液体。これって、ただのシロップ薬じゃないの。そう思ったときにはもう、なんだか頭がぐらりと一回転するように意識がねじれていた。身体の芯をずんと貫く痺れが走り、まるで重い陶器の人形になったよう。
「どう?」
「息が、苦しい」
かすれた声で訴え、アリスは眉をしかめる。不安で震えそうなのに、ヤシマは憎らしいほど落ち着いている。ねえ、楽にして。アリスがお願いすると、ヤシマはアリスを見下ろしたまま、膝の内側に手を入れてゆっくりと開かせた。脚はもうだらりと垂れて、自分ひとりの力では動かすこともできない。ヤシマは自分の優位を示そうとでもするように、彼女の腿にかるく爪を立ててぎゅっと掴む。毒に触れたような痺れが走るけれど、それが彼女を奇妙な具合に酔わせるようで、もっと支配してほしいと渇望してしまうような、自虐的なもどかしさを運んでくる。
「こわいよ」
「すぐに良くなる。大丈夫、一時間だけだから」
冷静な声で囁き、ヤシマはもっと内側に指を進める。アリスはもう逆らいようもなくなって、居たたまれずに眼を閉じる。脳裏には色鮮やかな試験管の映像がいつまでもちらついていて、やがてヤシマが身体の中に入ってきても、まるで冷たく残酷な硝子管を受け容れているような錯覚が消えない。恐怖とないまぜになった混乱が、快楽という脳内麻薬に形を変えて、アリスを容赦なく呑み込んでいく。
2 / 4