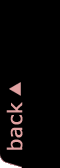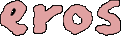シンの部屋がアリスは大好きだ。西向きで、夕方になると黄金色の陽が入る。それを浴びながら、狭いベッドでシンに抱かれるのが好き。どこか懐かしい太陽の匂いは、なんの不安もなかった子供時代を思い出させて、まるで無邪気な二匹のうさぎにでもなったような気持になる。成長したシンに抱かれながら、幼かった頃の彼の姿を思い浮かべる。それだけで、ふと泣きたくなるような愛しさが胸を突く。
制服を一枚ずつ脱がされながら、夢中になって口づけを繰り返す。ふわりと広がった紺のスカート。その下にシンの手が忍び込む瞬間、自分が彼のための女の子であるという幸運に恍惚となる。
されるのも好きだけど、してあげるのも好き。アリスはそう囁いて、長い髪が流れ落ちるのも構わずにシンの全身にキスを這わせる。熱を帯びた性器に口づけを重ねていると、ふとシンが溜息と同時に呟いた。
「アリス、それ、すげえ上手だよ。上手すぎる」
アリスはシンを見つめ返す。
「そうなの? 自分じゃよくわかんないよ」
でも、単純に褒められてるわけじゃないみたい。ひとりで寒いところに置き去りにされたようで、黙って身をすくませていると、急に引き倒されて、同じことをし返された。いちばん敏感な場所に、シンの舌先が忍び込んでくる。軽く吸ったり、唇で柔らかく包んだり、悪戯するようにつついたり。アリスがうっとりと瞼を閉じると、シンが愛撫を止めて囁いた。こういうのを上手いって言うんだよ。どこで覚えたのさ?
「えーと」
アリスは記憶をたどる。いつからか、なんて思い出せない。口づけというのはこういうものだと思っていたし、物心ついたときから、ずっと、そうしていた。
「ものごころ、ついたときから? うそだろ」
「ほんとなの」
必死に訴えながら、アリスは思い出を掘り起こす。あれはたしか5つのとき。
その頃、アリスには好きな男の子がいた。一緒に育った近所の子で、アリスよりもひとつ年上。男の子たちには乱暴だったけれど、アリスにだけは優しかった。冒険に出るときは、必ず自分の後ろにアリスをかばい、きちんと女の子として扱ってくれた。
ある秋の日、アリスと彼はふたりだけで探検に出かけた。いつものように守られて歩きながら、アリスは幸せだけど不幸だった。彼は春になったら、先に学校へ上がってしまう。それを考えると家に帰りたくなかった。このまま遭難して、二人だけでどこかに閉じこめられてしまいたかった。
「あ、雨」
まるでアリスの祈りが空に届いたようだった。冷たい通り雨がばらばらと落ち始め、あっというまに足下の枯葉を黒く濡らした。ふたりは慌てて雑木林を走り抜け、秘密の場所にしている橋の下へ逃げ込んだ。
まっすぐ家まで走った方が早かったはずなのに、どちらもそのことは言わなかった。向かい合わせに座って、黙ったまま、ばちばちと音を立てる大粒の雨を見つめていた。
「ねえ、さむいよ」
橋の下の狭い隙間で、アリスは彼に甘えてみたくなってそう言った。少年はちらりと目を輝かせてポケットを探った。得意げに取り出したのはどこかで拾ってきたらしい、古ぼけた100円ライターだった。
「ほら」
何度か失敗してから、彼はライターに火をつけてアリスに差し出した。
「あったまれよ」
「だめだよ、あぶないよ」
目の前の炎にアリスは怖気づいた。火で遊ぶことは厳しく禁じられていたし、風にあおられて時々揺れる炎は、まるで彼の指を焼き焦がしてしまいそうにも見えたから。
「だいじょうぶ」
「だって…」
そのとき、本気で怯えていたはずなのに、アリスはなぜか不思議な歓びを感じていた。自分ひとりだけを暖めるために、危険を顧みない男がいるということ。その事実が呼び覚ます誇らしさに、胸の奥がくすぐったく騒いだ。ふだん一緒に遊ぶ女の子たちは、こんな歓びなんて、かけらも味わったことはないだろう。そのときふと、自分があらゆるものから離れて、とても遠いところまで来たような気がした。誰にも届かない、深い森の中に眠っていた湖を、たったひとりで覗き見たような。
「あち」
ふいに少年がライターを投げ出した。強い風に煽られた炎が、指先を軽く焼いたようだった。
「やけどした」
「うそ、どうしよう」
自分がやけどしたわけではないのに、アリスはうろたえて泣きそうになった。証拠を残して帰ったら、きっと彼が叱られる。
「へいきだよ、なめとけば治る」
「じゃ、あたしがなめてあげる」
それは、とっさの言葉だった。アリスは彼の手を取って、やけどをした指を自分の口に含んだ。赤く腫れた跡が痛まないように、舌でやさしく慰めながら。
そのとき何を見ていたかは、もう思い出せない。少年の顔だったか、うつむいた靴の爪先だったか、それとも、夢中になって眼を閉じていたのか。覚えているのは、自分がすすんでそうしたことだけ。やけどの治療だけじゃない。そうすることで彼を惹き付け、ふたりだけの秘密を持てると本能的に思ったから。
そして、ふいにアリスのからだの中には、今までに感じたことのない熱さが湧き出してきた。色恋に関することは何も知らなかったけれど、こんな繋がり方では到底満たされない、それだけは理解できた。声を上げて泣きたいような奇妙なもどかしさ。それが足首のあたりから這い上がってくるようで、アリスは思わずきゅっと両脚を摺り合わせた。
「もういい」
やがて、少年は素気なく手を退いた。これ以上空気が濃密になるのを断ち切るようなしぐさだった。彼にとっては、それほど印象に残る出来事じゃなかったのかもしれない。アリスは少し傷ついてうつむいた。
「なおったの?」
悲しいような、恨めしいような気持でアリスが訊ねると、少年は横を向いてうなずいた。
「帰るぞ」
アリスは頷いた。それ以上何も言うことはなく、ふたりは橋の下を出て、弱くなりはじめた雨の中を小走りに帰った。
「それ」
シンはからだを起こして、逆光を遮るようにアリスを覗き込んだ。
「覚えてる。おれだ」
「そうよ」
あのときが、アリスにとってはじめての口づけ。男の人に欲望をおぼえて、自分からしかけた最初の行為。あれに比べたら、唇と唇をはじめて触れ合わせた時のぎこちない初々しさなんて、微笑ましいくらいに子供っぽいエピソードだ。
「だから、わかる? あたしはこういうふうにしかできないの」
「へえ」
シンは感心したように呟いた。暖かな乳房を手のひらで包み、それからゆっくりと下へ這わせていく。
「その頃から、おれが欲しかったの? こんなふうに?」
「うん」
あのときは、何がしたいのかもわからなかった。何が満たされなくて、あんなに深い混乱が襲ってきたのかも。今なら知っている。あのときどうすることもできなかった欲望を、今は、同じ相手が、望むだけ満たしてくれる。こうすること以外に、欲しいものなんかないの。アリスは本気で囁き、シンをぞくりと欲情させる。
「ねえ、抱いて」
もうシンの腕の中にいるのに、アリスはそうおねだりする。シンは答える代わりにアリスにキスをして、さっきの続きを始める。陽に灼けた顔も、ゆったりと広い肩も、アリスを呼ぶ声も、いつのまにか大人の男のものになっている。ライターひとつを扱うので必死だったあの手。それが今ではいろんなことを知っている。普段は不器用なくせに、そのときだけは別人のように隠微な仕草で、アリスを快楽のきわまで追い詰める。
アリスを見下ろす冷静な顔。それがだんだん狂っていくのが好きだと思う。歯止めを失い、次第に獰猛に、言葉を忘れた動物になっていく。それが好きなの、とアリスは囁く。あなたをそうできるのはあたしだけ。そうでしょ? シンはもう応えずに、黙ってアリスの中に入ってくる。逃げられないようにアリスの脚をつかまえて、急くようなリズムを抑えながら、少しずつ深いところとつながっていく。
アリスは眼を閉じる。感じるのはシンのかたちではなくて、じかに目では見ることのできない自分自身。暖かく滑らかで、分け入ってくる存在を際限なく受け容れていく柔らかな口。シンが動く度にそこから突き上げるような揺らぎが生まれ、アリスに切ない声を上げさせる。敏感に張り詰めた皮膚の内側は、すべて滑らかな水に変わってしまったよう。指の先にまで快楽の波紋を響かせてくる。
それはあのとき覗いた暗い湖。あれほど遠いと思ったのに、こんなに近くにあったなんて。息も出来ないほど深く突かれて、アリスは喉をのけぞらせる。最後の一瞬にはもう声も出ない。全身が引きつるように震えたあと、糸の切れたマリオネットのように、すべてを失って崩れ落ちる。
後に残るのは静寂。眼を閉じたアリスの頬の上を夕日が滑り落ち、やがて窓の外には宵闇が満ちてくる。シンは一緒に眠る気にはなれなくて、アリスに贈られた銀のジッポーで煙草に火をつける。ゆっくりと苦い煙草を吸いながら、幼い日のことを思い出してみる。あの時のことは覚えているけれど、そこからずっと変わらない欲望を抱きつづけてきたなんて。想像を絶する気の長い話だとしかシンには思えなかった。
やっぱりよくわかんねえや、そう呟いて、単純明快な少年は立ち上がる。くわえ煙草のままジーンズをひっかけ、自分と、まもなく目を覚ます恋人の空腹を満たすために、冷蔵庫を開けて食べものを物色しはじめる。
アリス
これでアリスの一日はおしまい。危険なこともあったし、何か教訓めいたことを学んだような気もするのだけれど、こうしてシンに抱かれて眠りに落ちると、全部きれいに忘れてしまう。
アリスはそんな女の子。周りの人がなんと言おうと、その心は感じやすく清らかで、たった一人を愛しつづける一途さは保証つき。やがて満開になり、散りゆく花の季節を惜しむにはまだ早く、きっと明日も同じ日常を、ひらひらと、泳ぐように生きていく。
4 / 4