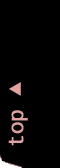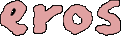白い雨/喪服
サイキカツミ
一
雨が静かに墨絵のような空から降り注いでいた。濃い緑色をした柏の枝が青煉瓦の屋根を跨ぎ、艶々とした葉の表面で雨粒を受けていた。奥には水を張ったばかりの水田が見え、波紋が無数に生成し、広がり、消滅していた。細い道が山と水田の境界線を描き、小さな小屋が稜線の中心にあった。
赤い金魚のような軽自動車が境界線を右から左に泳いでいって見えなくなり、やがて奥の交差を折れ曲がったのだろう、今度は逆に左から近付いてきた。
玲子は二階の窓から金魚が足元の庭に停止するのをぼんやりと眺めていた。そして、水槽に閉じこめられてしまったような気がした。
なぜこの場所に来てしまったのだろう。
強情を張って、街の家で執り行なえば良かったのだと後悔した。
ドアが閉まる音が聞こえた。さっきの車の側に黒い傘がぱっと開くのが見えた。テントの脇に青い傘がいた。声は聞こえないし、玲子のいる場所からははっきり誰だか分からないけれども、その青い傘はきっと敏夫さんだろうと思った。敏夫さんは晴義さんの弟だった。玲子にとって義理の弟にあたった。
物静かで秀才風の晴義とは逆に、無骨で無神経な田舎の男だったが、竹を割ったようにシャキシャキとした性格だった。
若い頃はバリバリの体育会系だったのだろう。頑丈な骨格と背丈が高く、四角い顔立ちだった。不思議と遠くからでも彼の姿は分かる気がした。傘は彼の性格のままに快活なようすで揺れていて、今日のような日になぜ笑っていられるのだろうと思った。
やってきたのはいったい誰だろう。
玲子は視線を巡らせた。あれは晴義さんの古い友人だろうか? 玲子は晴義の古い友人には一人も会ったことがないことに気が付いた。なにせもう3年も晴義には会ってはなかったし、二人だけの時間は殆どなかった。そして、あまりに性急に結婚してしまったので、なにも彼のことは分からないままになってしまった。もっとゆっくりと二人だけの時間を作ればよかったのだ。
幾分さっきより風がきつくなったようだ。雨粒が斜めにガラスに当たって砕けていた。
玲子が溜息を吐いた時、階下から舅が玲子を呼んだ。まだ通夜だというのに人が増えてきたのだった。夫の実家の田辺家は地元の名士だった。
立ち上がると白黒の垂れ幕が風に揺れているのが目に入ってきた。
年齢の割に高給取りだった玲子の夫、晴義は玲子の知らない名前も聞いたことがないアフリカの国で死んだ。
現地の部族の戦闘に巻き込まれてしまったそうで、玲子はテレビのニュースで知り、あっという間に玲子が住むマンションの前には報道人が溢れて、訳が分からなくなった。慌てて晴義の上司に連絡するとこれから現地に飛んで遺体を引き取ってくるといい、帰国するまでに準備をしておいてくれといい、現地は戦闘地区で危険なので奥様はお連れする訳にはまいりません。マスコミは相手にしないようにと機械的にいい、最期にお悔やみをいった。
突然、晴義が死んだと聞かされてもまったく実感はなかった。
呆然と佇んでいると電話が鳴って姑が出たので、いまからそっちへ行くからと慌てた様子で、晴義の上司から聞いた話を伝えているうちにどこからともなく涙が出てきた。それほど夫を愛していたわけでもなかった。情熱などではなく、ただそれまでの不倫に始まった、勢いだけであちこち広がり過ぎてしまった関係にケリをつけたかっただけだ。初めは夢中で心地よいと感じ、快楽で身も心も崩れてゆく関係は数年も過ぎると一気に腐敗して、もうどうにもならなくなっていた。律儀で堅実な夫に出会ったのはそんな時で、熱心にせがむ夫に承諾する形で結婚を決めた。
夫、晴義はまったく淡泊で、これぐらいの方がバランスが取れていいと玲子は誤魔化しているうちに、海外に赴任してしまった。
赴任に玲子がついてゆかなかったのは、以前の奔放な自分が取り戻せるかも知れないという打算もあったが、外国暮らしに恐怖感があったのも事実だった。晴義もちゃんと住居のあてが定まらないうちは、夫婦でゆくのは危険かも知れないと同意し、玲子は買ったばかりのマンションに一人残ることになった。
いざ一人になってみると、玲子は以前のように奔放に遊び回ることができない自分に気が付いた。いつの間にか意気地が冷え込んでしまっていた。不甲斐ない自分を叱咤しつつ、つつましく生活を続けているうちに、突然、夫が死んだのだ。
「申し訳ないですが、お客さんに茶でも出してやってくれませんか」
舅ではなく敏夫さんが階段の脇で玲子に話しかけた。土建屋の脂ぎった顔で煌々としていた。じっとりとした汗が雨と混じって頬から流れ落ちていた。
「ごめんなさい。こちらこそ気が回らなくて」
「いや、玲子さんには、何もさせようとは思いませんでしたが、どうにもこうにも、じさまばさまばかりで」
といって義弟は額を拭った。夫ではなくこの弟と結婚したならどれほど人生は変わったであろうかと密かに玲子は思った。
「雨がだいぶ振ってきましたね」
「ええ」と答えた。
「えれーべっぴんさんやないかァ」
座敷でてんでばらばらに会話をしていた地元の人々は玲子が座敷に入った途端、声を止め、どこからかそんな声が聞こえた。
「この度は突然の夫の葬儀にお集まり頂きまして……」と玲子が無視を決め込んで膝をつくと、近くに座っていた太った中年の女性が「テレビでさ、晴ちゃんの名前みた時には驚いたでぇ。ほんま、惜しい人を亡くしましたなぁ。これからだっていう時に」と追状を述べた。
「ええ」
玲子は茶を盆から渡しながら「この人はどこどこのだれだれ」だという話を聞き流しながら、いちいち頷いてみせた。
やがて僧侶がやってきて、場が割けて、読経が始まった。司法解剖が行なわれるということで、東京からはまだお棺の中身が届いていなかった。中身もないのに。まるで儀礼的な関係で終わってしまった私と夫みたいだと感じ、居心地が悪くなって台所に逃げた。
姑が「どうしたの? 気分でも悪いんか?」と訊いてきた。
「何かお手伝いすることでも」というと「いい。いい。玲子さんはお客さんなんだから」と慰められた。かといって今立ったばかりの読経の部屋に舞い戻る気もしなかった。
ふとみると、屋敷の裏庭にある離れの縁側で、敏夫が煙草を吸ってぼんやりとしていた。玲子は縋る気分で居間からの縁側を伝って敏夫の方に寄った。
「どうしたんや。濡れるっぜ」
離れは敏夫の部屋らしかった。あけっぴろげにガラス扉を開放しているが、中を覗くと雑誌や何かの機械が転がって、ごちゃごちゃとコード類が部屋の隅に丸まっていた。
「中、そんなに見るなよ。ま、こっちへ来て座れ」
と縁側を詰めてくれたのは助かった。玲子は敏夫の側に腰を下ろした。だが、かといって特別な用件があるわけでもなかった。
「義姉さんも大変だな。兄いが急に死んで、いきなり葬式を押しつけられた訳だから」
敏夫は半ば自嘲するような口調で言った。礼子は彼がなぜそのような話し方をするのか分からなかった。
「ほれ」
敏夫は手にした吸いさしの煙草を玲子に差し出した。玲子は手にした途端、それが何か分かった。簡素な紙で巻かれていた。煙草じゃない。
「わかるか。まだ奥にあるぜ」
玲子は、ずいぶん昔にやめたはずのハッパを深々と吸い込んだ。懐かしい香りがして、あのころの喧噪を思い出し胸が熱くなった。
「こんなところにもあるんですね」
「どこでもあるさ」と敏夫はにっこり笑って「こっち来てみ」と言った。一瞬躊躇したが、誘われるままに部屋の奥について入る。
四畳程の小さな部屋の奥に八畳ぐらいの部屋があって、万年床が敷かれたままで、その奥にパソコンとテレビとステレオが並べてあった。むっと敏夫の臭いがした。
「これこれ」
敏夫は小さな袋をかざして見せた。敏夫は腰を下ろして、玲子を呼んだ。
「手だしてみな」
両手で水を掬うように差し出したが、片手でいいと敏夫の固い手が玲子の掌を引いた。包みを破いて玲子の手の上に僅かに載せた。
「キメ方は知ってるんだろ?」と訊かれたので、玲子は頷いた。鼻を近付けて吸うと、ぴりぴりと粘液を刺激して、かあっと身体が熱くなる気がした。
やった、やった。散々やった。一時は中毒になってしまうかと思うほどやった。クラブでキメてそのまま男とトイレでやって、またダンスホールに戻ると、また別の手が玲子の身体に差し伸べられて、キスをする。懐かしさと、次第に沸き上がってくる高揚感に玲子は腰をぺったりと畳につけて、茫漠と意識が舞う気がした。
「わたしね。昔やってたのよ。ほんと、若いころ──」と言いかけた途端に、身体が強引に捩られた。玲子の唇に敏夫がしゃぶり付いてきた。
「あ、いけない」と思った瞬間に胸を鷲掴みにされた。玲子は慌てて身を引こうとした。だがあまりの力に身動きさえできない。
「だめですわ」ようやく顔を背けてそう言うに留まった。
「そうかい」
敏夫は答えるが早く、玲子の喪服の下に手を滑り込ませた。慌てて足を閉じようとしたが、間に合わなかった。太い指がショーツ越しに感じられ、指先が玲子の敏感な部分を探しているのが分かった。
「やめてください。人を呼びますよ」
「呼んだとしてどうする。亭主が留守のまま死んで、それでも薬でキメて男を欲しがってる淫乱と皆に宣伝するのかい? いっそのことお前を坊主連中の前に連れていって、やつらにはめられたいのか。いいよ。オレが連れてってやるから」
玲子は身体を捩った。
突然人が変わった敏夫に恐怖を感じたからだった。傲慢な薄笑いを浮かべて、別人のようだった。もしかすると薬のせいかも知れない。でも、本気かも知れなかった。硬直した身体を敏夫の腕は放さなかった。
「よしてください」
ようよう言葉を吐き出すと両手で敏夫を押し返そうと肘に力を入れた。
「こんなに濡れているじゅあないか」
「いや」
ショーツの脇から指が入り込んできた。玲子の外唇をまさぐり、入り口を這って陰核に指が触れた。三年。三年の間に何度自慰をして過ごしてきただろう。溜まらなくなって、買い物途中にデパートのトイレで触ったこともある。夜な夜な、毎夜どうして以前のような勇気が失われてしまったかと嘆きながら、その部分に触れていた。だが、ずっと他人の指に触れられることを拒否してきた。だからこそその禁忌が破られたことが衝撃的だった。
指が第一間接程入って来て、逃げつつ唇部分をくちゃくちゃと弄り始めた。内壁をじわじわと探り、奥へ奥へと指が入って行き、また逃げた。前後に動きだしてやがて一定のリズムで動かし始める。感情などお構いなしに玲子の中の声は知らずと溢れてしまう。
「お前、本当に溜まっていたんだな。夫の留守に男でも連れ込むのが普通だろうに。本当はそんなに貞淑な妻ではないだろう?」
敏夫は舌で玲子の歯茎をなめ回し舌を差し込んできた。その時、玲子の中で理性が立ちふさがった。
「やめて」
読経が終わることを示したように木魚の音が聞こえてきた。敏夫を押し戻して、ようやく身体から開放された。
「これ以上はだめなの。ごめんなさい」といい、慌てて立ち去ろうとすると、敏夫の腕が玲子を引き留めて、「待てよ。これを」といってさっきの袋を喪服の袂に突っ込んだ。
「ごめんなさい」
玲子は足早に敏夫の部屋を離れた。
乱れた喪服の裾を慌てて整えて台所に戻ると、「どこ行ってたの? 玲子さん」と姑の恵子が問いただした。玲子は赤くなり青くなりしてるうちに涙が溢れてくるのが分かった。「あれあれ」恵子がまるで実の子のように玲子の頭を撫でる。
「義姉さんに兄貴の写真を見せてた」と背後から声がした。敏夫だった。
「まあ。そんなこと、後で見せてあげればいいじゃないか。さあさ、涙をお拭き」
玲子は白いハンカチを渡されて涙を抑えた。
「ごめんなさい」
「いいえいいえ」
その時、玄関が騒がしくなり、座敷からざわざわと人が動くのが分かった。誰かが台所に呼びに来たのがわかった。
晴義の遺体が東京から届いたのだった。
1 / 3