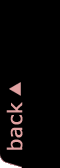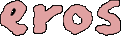二
がやがやと音をたてて物事が進行するのに巻き込まれているうちは気が楽だった。ふと我に返ると、三年振りに見た晴義の冷たくなった顔が浮かんで、よりによって夫の弟に言い寄られたのだということが、溜まらなく罪深いことだと感じられた。玲子は袂で何か固いものがかちゃかちゃと音を立てるのは大分前に気が付いていた。人前で、それを取り出してしまわなかったことを幸運に感じる。卵の三分の一ぐらいの大きさのピンク色をしたプラスチックのボールと、そこから伸びたコードだった。それが何か分からぬ訳はなかった。ローターとコントローラーだった。なぜそのようなものが袂に入っていたのかと問うまでもなく敏夫に違いなかった。コカインの袋と入れる際にこっそり忍び込まれていたのだろう。突っ返そうと思ったが、敏夫は一段落した後、車でどこかへ出ていってしまっていた。
舅、姑とテーブルで気の弾まぬ話のあと、与えられた二階の部屋に戻って、玲子はぼんやりとしていた。
そろそろ深夜を回る時間だった。喪服の帯を解くことも面倒な程、玲子は疲労していた。
卓袱台にローターとコカインの袋を置いたままじっと見つめていると、また涙が溢れてきた。理由などなかった。もちろん変わり果てた晴義の姿は心を掻き乱す要因であったかも知れない。だが、それだけではなかった。色々な記憶と、三年の月日と、夕方の敏夫との出来事が一緒くたに襲ってきて、玲子の中で暴れ出していた。
自分のことだけを見ていて、晴義に対してなにかしてあげれたことがあったのだろうか。それ以上に自分自身がこの数年の間、幸福で居れたのだろうか。晴義はどういう想いで私を見ていたのだろう。結局晴義には以前の行状を話せないまま終わってしまった。この数年の私を知って貰うことなく居なくなってしまったのだ、と玲子は卓袱台に突っ伏して涙した。
スイッチを入れてみると、振動器はトカッタトトッカカッと音を立て、蛙の玩具のように飛び跳ね卓袱台の上をあちこちと移動した。深刻な気分の中に奇態な動作をする器具があること自体が何かの冗談のようだった。
常に紳士的な態度を崩さなかった晴義に比べてあの弟の敏夫はどうだ。
一瞬でもあんな男を良さそうだと感じた自分を殴り付けたくなるほど、時間が経つにつれ腹が立ってくるのだった。
玲子は一旦、スイッチを切って、また付けた。手の中でその振動を味わってから、ショーツの表面を滑らしてみた。
軽い振動が伝わり、自宅で愛用してるのよりは幾分荒っぽいなと考えながら、こんなものか、これではいけないなと思ってスイッチを切った。
しばらくして、再びスイッチを入れた。今度はクリトリスの側で振動するようにショーツで挟んで、パックを開いた。
少量を卓袱台上に白い線を引くようにして盛って、顔を近付け鼻から吸引した。熱い刺激が顔の中で広がった。その感覚の中で、再びショーツの上を振動で撫で回すと、徐々に気が乗るかも知れないと思った。敏夫はまだ帰宅していないようだった。車が帰宅する音はついぞ聞こえなかった。
玲子は安心して、意識をチューニングしてその一点に集中してゆく。振動が皮膚を揺らし、腰部の内側を反響させて腹腔に満ちてくる。
じわじわと温かいものが玲子の陰部を中心にして広がってゆき、濡れ始めた秘部が更なる刺激を求めていた。
ショーツを完全に下ろして股を開いた。ローターを押し当てながら沼に指を押し込んだ。夕方に触られた太い指を思い出し、この今弄っている指が自分の指ではなく、あの指が掻き回してくれたらもっと、と思い、むっと匂った男の肌に包まれて、ああ。あの。敏夫のペニスはいったいどういうものかと想像し、あの身体に似合った、太くて固い逸物であったら、私をこの場所から連れ出して欲しいと望み、身体のなかに大きく太い感情が駆けめぐった瞬間に玲子は階下から呼ばれる声を聞いた。
はっとして、居を正して器具を荷物の脇に片した。
姑が風呂に入れということらしい。返事をして、気が紛れた瞬間に玲子は恥ずかしさに身が竦む思いがした。
シャワーを浴びながら、先程までの情欲の炎が一緒に流されて行くようで、玲子は安堵した。なぜそのような感情が沸き上がってしまったのだろうかと悲しくなってきて、変わり果てた姿の夫の装束姿を思い出した。なぜ自分だけがこのような目に遭ってしまうのだろう。ほんのちょっとのバランスが崩れてしまうとこんなことになってしまうのだ、と玲子は考えた。ほんのちょっとの運命のボタンの掛け違いで、一人になってしまった。
私の何が悪かったのか。晴義が帰国するのをずっと待ってたはずだった。長い間、夫のことだけを考えて暮らしてたはずだった。なのになぜ。
玲子はシャワーを浴びながら胸を軽く押し上げるようにして洗った。Eカップの胸をずっと誰にも触らせずに、二〇台後半をずっと晴義のために生きてきたので、これからどうすればいいのか分からなかった。
学生の頃には男たちからもてた。私は有頂天だった。でも、そんな若さはもうない。私はなんのために生きてきたのだろう。気を付けてはいたが徐々に肌は衰えてくる。醜悪で惨めなおばさんになってゆくのが、悲しい。私は――
いや。そんなの嫌。
私はもっと前向きに生きていかねばならないのだ、と玲子は考えを改めた。不運にも死んでしまった晴義のためにも、私自身のためにも前向きになろうと決心をした。あのローターも薬も突っ返してやろう。卑野で粗暴な敏夫という義弟に突っ返してやろう。もしまた暴力を振るうようなことがあったら、鉄パイプででも殴ってやろう。武器を探さねば、と思いながら家からもって来た部屋着に着替えた。
だが、部屋に戻った瞬間に玲子は異様な雰囲気に身体を硬直させた。
瞬時に口元を何かで抑えられ身体も羽交い締めにされた。むっとするあの匂いに目が眩んだ。
「うぐぅっ!」
「(敏夫さん、なにを!)」
口を押さえられ、声にならなかった。
「なあ、義姉さん。オナニーしただろう」
残酷な目が玲子の顔面に迫ってきた。玲子は首を振った。
「嘘をつけ。オレがやったローターを使っただろう? と訊いているんだ」
もう一度玲子は首を振って拒否した。
「このむっつりスケベが」
口を押さえる布の圧力が強くなる。玲子は息がほとんどできずに噎せた。
「この匂いを嗅げばわかるさ。義姉さんのマン汁の匂いだね」
玲子はその時はじめて口を押さえている布にレースの模様が付いていることに気が付いた。白く細い布の部分が少ないレース地の布。さっきまで履いていたショーツだった。
「(いやああ)」
「声をあげるな」
噎せかける玲子の頭を叩いて敏夫は耳元で言った。
「こいつと嗅ぎ比べてみるか」
敏夫が玲子の顔の横にローターを持ち出したのだった。
「オレが見つけた時もぐっしょり濡れてたぜ」
そんなことはないと思いつつ、玲子は顔が紅潮するのがわかった。悔しさで胸が一杯になって、両手で敏夫が羽交い締める腕を引っ掻いた。
「んのアマ」
「待てよ」と別の声が背後すぐに聞こえた。
玲子は心臓が飛び出すかと思うほど驚き、男の腕が背後から伸びてきて、引っ掻く手を力強く握って引き離した。ぐっと背後に引き寄せられて、冷たいものが手に掛けられた。はっとして身を戻そうとしてももう無理だった。反対側の腕も背中に引っ張られて冷たいものが掛けられた。手錠だった。
「いやああ」
玲子は口をショーツで縛られて、ようやく男たちの腕から開放されたが、床に転がされた。
もう一人の男をみて、玲子は驚いた。以前、学生の頃にクラブでよく踊っていた吉田という男だった。薬の回し合いもしたし、トイレでちょっとしたお遊びもしたはずだった。
「なんでオレがここにいるのか知ってるか?」
吉田は未だホスト風の金色に染めた髪型で、黒いスーツを着ていた。
礼子は首を振った。
「オレとトシはガキの頃からの友達でな。お前がトシの兄と結婚したときには驚いたぜ」
「義姉さん。オレは兄貴が死んで嬉しい。ずっとこの時を待っていたんだ。義姉さんが結婚した時からあんたを犯したくて犯したくて溜まらなかった」
敏夫は目をぎらぎらさせて玲子を見た。
「お前、オレが迫っても歯牙にもかけなかったな。なぜだ」
吉田がそう言った。玲子はあんたがおかしいからよ、と心の中で呟いたが、状況はそんなに悠長ではなかった。自由な足を使って背後に逃げる。二人が好色そうな笑いを見せて追ってくる。
背後が壁になったところで玲子は絶望した。
「なあ。義姉さん。あんた溜まってるんだろう? オレ達が抜いてやるぜ」
もうどうしようもないと観念するしかないのか。玲子の目に涙が滲んで世界がぼんやりしてきた。彼らはナイフを取り出して玲子の胸に押しつけた。
「妙な真似をしたら、あんたも棺桶に入ることになるぜ」
胸の谷間にナイフの先が迫って、T-シャツが破かれていった。白くむっちりとした肌がその下から現われて男たちは驚喜した。ピンク色のフロントホックのブラジャーが太い指によって割られ、中からたわわな柔らかそうな稜線を描いた果実がぷるんと弾けて飛び出した。玲子の胸は豊かであっても垂れることのない張りがあった。中央のピンク色した乳首は恐怖におののいている。
「良い身体だな」
「だろ。乳首、立ってるんじゃないか」
敏夫が果実にむしゃぶりついた。
なまあたたかい唇と舌の感触が玲子をぞっとさせた。
「いやあ」と玲子は身を捩ったが、再び叩かれて「騒ぐと殺す」と脅された。ジーンズがずり下ろされて、ショーツが現われた。黒のレースだった。嫌。嫌。嫌。と玲子の中の声が玲子の身体を硬直させた。
「おまえ。こんなイヤらしい下着着て、亭主の葬式に出ようっていう腹だったのか」
吉田が言った。
思い出した。吉田は粘着質の性質で、クラブで踊ってた女友達中では非常に嫌われていた。粘着して、相手を疲労させていた奴で、係わり合いになるのは誰もが避けていたのだった。
ショーツが一気に下ろされた。
黒々としたデルタは白く見事な玲子の身体のなかで、あでやかなコントラストを描いた。すかさず敏夫の手が茂みを覆い、指が触れてきた。
「へへへ」
敏夫は口を歪めた。
「やっぱりお前はこんな風に犯されたがってるんじゃないのか」
敏夫が玲子の顔に近付けた指はしっとりと濡れているのだった。どうしてという声が玲子の中で上がって、その声に励まされて顔を背けた。
「これ」
敏夫の背後で吉田が袋を差し出した。敏夫は起きあがって手の中に袋の中身をぶち開けて玲子の股間に差し込んだ。
「粘膜は粘膜だよな。義姉さん」
「いやぁぁあ」
ぐちょぐちょと手の平を押しつけられて擦り込まれてゆくのが分かる。玲子はもう駄目だと思った。クラブの後、パーティーでそうした記憶が蘇ってきて、あのとき私はどうしたのだろうと思う。
薬と玲子の徐々に溢れてきた愛液が混じった手を敏夫はじっとりと嘗めた。
「義姉さん。乳首が立ってるぜ」
腰の辺りから徐々に温かいものが身体の中に浸透して行く感覚を、礼子は悲しさと共に感じた。その悲しさは雌としての本能だった。
分かっていたのだ。玲子は、一旦タガが外れてしまうと、もう止まらない自分の性格を知っていたのだ。だから貞節に貞節に過ごしてしまおうとしていたのだった。
性急に敏夫が玲子の中に入って来た時に玲子はゆっくりと観念した。
2 / 3