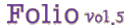犯人を名指しし、犯人が使ったトリックを解き明かし、犯行動機を指摘する。
そこで大抵の犯人は、(時には聞かれてもいないことについて)衆人の前で洗いざらいブチまけだす。
書き手も、自らの仕掛けたトリックの種明かしをする快感があるのだろう、ネタ晴らしは、それまで焦らしてきた分、性急かつ饒舌であることが多い。というより、ほぼ間違いなく饒舌である。無口な探偵という触れ込みであっても良く喋る。もしくは助手に喋らせる。
だが。
だが、である。ここで逆説が入る。
探偵役が誰であれ、果たして、彼ないし彼女がつきとめた犯行動機は、行動を起こさせるに足る理由であったのか?
探偵の推理など自己満足だ。犯人の長ったらしい告白も、読者を満足させるためのものでしかない。
そして結局、作者の想定した「疑問」の範囲内での答えでしかない。
僕らは、すべての謎が解けたつもりになって、ずっと探偵に騙されて来たのではないだろうか。
その饒舌な喋りに納得して本を閉じたあと、何年も経ってから、フト思い出してもう一度、その本を捲った時――、真犯人もトリックも、ネタのすべてを分かった上で、もう一度、物語を最初から追った時、何がしかの小さな疑問を見つけなかっただろうか?
たとえは、トリックを「謎」の本質に据えては、決して解くことの出来ない本当の「謎」、登場人物たち自身すら気づいていない、犯罪の動機、物語の真の始まりである、「切っ掛け」。
探偵が推理し、犯人が自白したとしよう。犯人は自分の動機を語る。…が、それが本当に動機なのかどうか、誰に分かるだろう?
継母にいびられていても、必ず継母を殺したいほど憎むわけではないし、相思相愛の恋人をハズミで殺してしまった女が、恋人の死体を切り刻むことだってある。
確固たる証拠があったとしても、それは「犯罪行為」を立証するもの、あるいは「トリックの仕掛け人と、そのトリックの再現可能性」を指摘したに過ぎない。
探偵役は秘密を暴くのが仕事であって、見ず知らずの他人を理解する義務は無い。
いかにも納得したような顔をして、さわやかに物語の舞台に幕を下ろす探偵と観衆に、犯人はほくそ笑むだろう。彼ないし彼女にとって最も重大な秘密、「真の動機」というべきものは、決して誰にも見つからない。
つまりそれが、「スケルトン・イン・ザ・クローゼット」。
古びた小さな骨は、本人が扉を開けて中身を洗いざらい整理しようと思わない限り、決して誰にも見つからない、…永遠に。
<ミステリーを文学として愉しむならば。技巧に囚われず、ストーリーを追うならば。登場人物の心情に同意でき、かつリアリティが無ければ、決して面白いとは思えないだろう。>
2/2