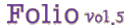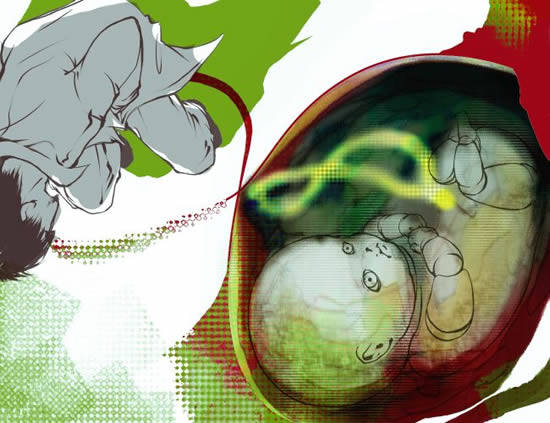〈瓦谷探偵公司〉
事務所のドアにはそう書かれたプレートが掛かっていたが、それにはこの部屋が空き部屋ではないことを示すほどの効果しかなかった。私はコートのポケットから鍵を取り出して鍵穴に鍵を差し込んだ。しかし、奇妙なことに鍵は掛かっていなかった。
「探偵さんにしては無用心なことだ」
事務所に入った私をそんな台詞が出迎えてくれた。
来客用の椅子に腰掛けたその台詞の主は着崩れたコートをはおり、濃過ぎる口髭にサングラスまでかけたあからさまに怪しい男で、なにか楽しいのか私の顔を見据えニヤニヤと笑っていた。
私は事務所の中に入ると、ひとまず男を無視してデスクの後ろにあるブラインドを開けた。差し込む光は春の日差しというには程遠いものだったが、光も差し込まぬ薄暗い部屋で見知らぬ怪しい男と向かい合うよりはまだましというものだった。
窓の外を意味なく一瞥してからデスクの椅子に腰を掛け、引き出しからホープを取り出し、火を点けた。紫煙が弱々しい陽光に照らされた埃の粒子の中、登り漂っていく。
一本まるまる吸い終わってからようやく闖入者を見据えた。男は口髭を僅かに揺らして微笑んでみせた。怪しい男の怪しい微笑みに、私は何故かこの部屋における主客が転倒しているかのような感覚を覚えた。
「あなたが瓦谷さんですね」
男は質問というより確認するようにそう訊ねた。しかしその問いは間違っていた。瓦谷というのはかつての私のパートナーでいつの間にかいなくなったしまった男の名前であって私の名前ではなかった。私は訂正しなかった。
「不法侵入だ」
「ああ、まぁ、そうかもしれんが鍵は開いていたし、外は寒かったからねぇ。春ももうすぐだと思っていたが寒の戻りとかいうやつさ。この時期だというのにこう寒いと春なんて永遠にやって来ないんじゃないか、とそんなことを思わないか?」
男はどこか楽しそうにそう言った。来客用の椅子はわざとスプリングの具合をおかしくしており、客を落ち着かせないようにしてあるのだが、この男は落ち着いていた。あるいは落ち着いているふりをしていた。
探偵事務所にわざわざやって来る客は普通落ち着いてなどいない。一見落ち着いて見える場合も内心に大きな不安を抱えているものだ。探偵という見知らぬ人間に自らの秘密を晒す不安よりも、抱えた不安の方が大きい人間だけが探偵の事務所にやって来る。探偵の仕事は真実を知ることでなく、客の不安を解消することだ。そのため客に最後のひと押しをするためスプリングの具合をおかしくしておくのだ。だから、探偵の前で必要以上に落ち着いていられるような客にろくな客はいない。目の前の男は文句なしに、ろくでもない客のトップクラスだった。
「講釈なら他所でやってもらおう。知らないのなら教えてやるがここは探偵事務所だ」
「勿論知っているさ。講釈がしたいなら大学の教壇にでも立ってるよ。依頼したいことがあってね」
男はそういうとコートのポケットを探った。しかしどうやら目当てのものは見付からなかったようだ。
私は自分のホープを一本放ってやった。男は礼のつもりか片頬を僅かに上げてからタバコに火を点けた。
「探偵さん、あんたに一人の人を捜して欲しいんだ」
「行方不明人ならまず警察に届けるべきだ。日本の警察は探偵小説の警察より若干優秀だ」
男は器用に肩を竦めて言った。
「ちょいと訳ありでね。警察の手に負えるもんじゃないんだ。これを見て欲しい」
男はポケットから乱雑に折られたメモの切れ端を取り出しデスクに広げてみせた。
そこには〈野上あきら〉という名前とこの事務所からそう遠くない住所が書かれていた。
「〈のがみ〉ではなく〈のうえ〉と読むんだがね」
男はそのことがさも重要であるかのように言った。
「行方不明人の住所ほど無意味なものはない」
「そうとも言えないさ。本人がいなくなった以上、手がかりが残されているとしたら、かつて本人が生活していた場所以外にない。違うか?」
男の言うことはもっともだった。
「そこまで解っているなら自分でやったらどうだ」
男は再び肩を竦めてみせた
「おかしなことをいう探偵だ。自分で出来ないからこそわざわざやってきたんだぜ。心配しなくても金はあるよ」
男はコートのポケットから膨れた茶封筒を取り出して、先程のメモの横に置くと、まるで今まで入っていた茶封筒の代わりのように手をポケットに突っ込んだ。大金は入っていても一本のタバコも入っていない奇妙なポケットだった。
私は一応茶封筒の中身を確かめて見た。今までこの事務所でお目にかかったことのないような大金が入っていた。
「お宅の連絡先は?」
癖なのかまた肩を竦めてから男は答えた。
「生憎とタバコと連絡先は切らしていてね。こちらからまた連絡する。それでいいだろう?」
男がまともな人間でないことは解り切っていたから私はただ黙って頷いた。
「早速今日から頼んだぜ、探偵さん」
そう言って立ち上がり、怪しい微笑みを私に寄越して部屋を立ち去ろうとする男を私は呼び止めた。
「ところでお宅の名前は?」
男はどんなぼんくらな警官でも思わず逮捕したくなるような、とびっきり怪しい微笑みを浮かべると言った。
「野上あきら、と言ったら?」
私の表情の変化をじっくり見てから、男はさして面白くなかったというようにまた肩を竦めてみせた。
「探して欲しいのは野上あきらであって、俺じゃないさ。じゃな、よろしく頼んだぜ。瓦谷探偵」
男はおどけて一礼してから部屋のドアを閉めた。
部屋には私と僅かな紫煙だけが残された。
1/3