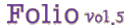入り口にならんだ郵便受けには九号室のところに真新しいマジックで〈野上〉と記されている以外どこにも何も書かれていておらず、老朽化した廊下は、一歩足を踏み入れれば、濛々と埃が舞い起こるのではないだろうかと思わせた。
私の事務所のビルよりも遥かに薄暗いその廊下を私はゆっくりと進んだ。やはりどの部屋も人が住んでいる様子はなく、一番奥の九号室からだけ、僅かに明かりが漏れていた。
私が歩を進める度に廊下はギシギシと軋み、廊下に吊るされた明かりはチカチカと不安げに瞬いていた。一歩進むごとに私まで周りに合わせて年をとっていくかのような錯覚を覚えた。
九号室の前に辿り着くと中から話し声のようなものが聞こえてきたが、耳をそばださせてみれば、それはテレビの音に相違なかった。
私の脳裏に無人の薄暗い部屋でただテレビだけがともっている光景が浮かんだ。私はその不気味な光景を追い払うようにして扉に手をかけた。
扉はなんの抵抗もなく開いた。部屋は畳張りの六畳ほど
の部屋でともされたテレビとそれを見詰めていた一人の少女以外は見事なまでに何もなかった。
少女はゆっくりと振り返りると、間抜けに立ち尽くす私を訝しげに見詰め小首を傾げてから言った。
「誰?」
私はその少女の問いには答えずに部屋に上がりこむと少女の隣に腰をおろした。テレビの中ではすっかり昼の顔になったコメディアンがゲストにサイコロをころがさせていた。薄暗い部屋とテレビの男の一種やる気がないようにも思われるテンションの高さが奇妙に入り混じっていて、なんともいえない妙な空気が充満していた。
少女は白い清潔そうなシャツに赤いスカートを穿きふわふわとした白い襟をつけた赤いコートを着ていて、さしずめサンタクロースの孫といった風情だった。そして腕の中には赤ん坊の人形を抱えていた。
私は少女の目をまっすぐ見詰め、尋ねた。
「ここは君の部屋か?」
少女は私の問いにふるふると首を振り答えた。
「解らないわ」
「いつからここにいる?」
少女は私を見詰め返し、呟くように答えた。
「解らないわ」
私はいったん質問を止め部屋の中をゆっくりと見渡した。
部屋には押入れさえなく他には勿論のこと誰もおらず、何もなかった。私はそのことを確認すると再び少女に問うた。
「君の名は?」
少女は当然のように答えた。
「解らないわ」
少女もいったん私を見詰めるのを止め人形の頭をひとしきり撫でてから私に尋ねた。
「あなたは誰?」
何故かその質問は私をドキリとさせた。私は慌てて答えた。
「私は探偵で、この部屋にいたはずの野上あきらという男のことを調べに来たんだ。野上あきらという名前を聞いたことがあるかい? もしかしたら君のお父さんかな?」
「解らないわ」
私はそう少女に問うてからいくつかのことに気がついた。
あきらという名前は女性にも用いられることがあるのだ。
あの怪しい依頼者も野上あきらという人物が男であるとは一度も言わなかった。また私は野上あきらの性別を知らないだけでなく年齢も知らなかった。何故そのことに今まで気がつかなかったのか全く不思議なくらいだった。
「君は野上あきらなのか?」
少女は首を傾げいくらか考えてから答えた。
「多分違うよ」
私はその答えに多少面食らいながら冗談のつもりで一つの質問を付け加えた。
「その君の抱いている赤ん坊が野上あきらなのかい?」
そう尋ねられた少女は私の顔をしばらく不思議そうに見詰めてから何故かはにかんで答えた。
「そうかもしれない」
私はその答えに再びドキリとした。少女の様子にふざけている様子は全くなかった。私はその〈野上あきら〉かもしれない人形をじっと見詰めた。どこからどう見てもそれはセルロイドの人形だった。頬は赤く塗られ、僅かに生えている髪の毛も明らかに毛糸の類だった。
私はこの奇妙な依頼を受けてしまったことを後悔し始めていた。いや始めから乗り気でなかったのだが、依頼人のでたらめの態度に屈して追い返すのが癪だったから引き受けてしまったのだ。
しばらく脳裏に様々な思いを巡らさしていると、少女は少女なりに気まずさを感じ取ったのか、懐から一本の赤いヒモを取り出すと私に話し掛けてきた。
「探偵さん、一本のヒモで作れる迷路の話知ってる? えっとね。このヒモのはじっこをスタートとゴールにするのね。このままじゃ一本道で全然迷子にならないけどこうやってバツがあるワッカにすると途端に迷路になるの」
少女はそう言って人形を抱えながら、畳の上に円を作ってみせた。ただの円ではなく少女の言うスタートとゴールがそれぞれ少しずつ円からはみ出していた。
「これのどこが迷路なんだい?」
「もう、解らないの? スタートしてしばらくすると道が三本になるの。一つはゴールへの近道。一つはぐるっと回る回り道、もう一つもぐるっと回って元にもどってくる戻り道。近道以外はまたこの分かれ道に戻ってしまうの。ゴールに辿り着ける人は運のいい人ね」
まるで人生の比喩のようだと答えようと思ったが比喩という言葉をどう説明したらよいか思いつかなかったので私は別のことを言った。
「私は野上あきらを探しに行かなくてはならないけど君はどうする?」
少女は私を見詰め、人形を見詰め、そして次に首を傾げてから言った。
「あたしも行く」
2/3