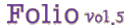みことが響の家をはじめて訪ねたのは、新学期になって間もなくのことだから、おおよそ一ヶ月前のことだ。それ以来、みことは頻繁に響の家を訪ねるようになった。中学三年の響には両親の他に年の離れた大学生の兄がいたが、妹には異常に優しい彼は、妹が友達を家に招くことに文句の一つもなかった。
みことと響は三年生のクラス替えで同じクラスになったことを縁に、友人づきあいを始めた。そのせいか、響はまだみことのことをよく分かっていない。二週間前に彼女が誕生日を迎えたことくらいは知っていたが、たとえば、こんなに仲良くなったというのに、今でも響の家に上がるときは驚くほどおしとやかになってしまい、ひどく緊張している素振りを見せることの理由とかが、未だに響には分からないのだ。
みことは雑誌を持ってきていたので、夕食後に響が入浴しているときにはそれを読んでいた。入浴を終えた響が何を読んでいるのかと聞くと、あまり聞きなれない雑誌名を伝えられた。「一ヶ月くらい前から読み始めたの」と言ったみことの顔は、どこかしら赤い。ふーんと頷いた響が紙面を覗き込むと、開いていたページには眼病についての記事が載っていて、その隣には星座占いがぶっきらぼうに書いてあった。つまらない雑誌を読んでいるのだなと響が思うと、風でペラリとページがめくれた。
載っていたのは中高生に大人気の俳優の女性スキャンダルで、響もファンであったために残念に思った。と、みこともどこか浮かない顔をしていたので「残念だね」と二人でお互いを慰めあったりもした。だが、みことと違って響には最近になって付き合い始めた、初めての恋人がいるせいか、どこか楽しむような口調になり、最後にはのろけ話に変わってしまっていた。夏休みからは受験勉強を本格的に始めなければならないので、こうしてのんびりしていられるような時間は貴重だった。
二人とも、夜はリビングルームで過ごしたが、暑かったので入り口のドアは開けておいた。ここを開けておくと、家の廊下の先までが一目で見渡せる。左側の手前に響の部屋があり、その向かいが兄の部屋、さらに奥にあるのが両親の寝室と父親の書斎である。
ところで、二人はともに近視だが、普段から眼鏡をつけてはいない。中学生とはいえ女子であるから、身だしなみには気を使う。どうやらメガネをかけた自分の顔が嫌いらしい。特にみことはその傾向が顕著で、彼女の眼鏡姿は滅多に見られない。
その夜も、みことは外すのが億劫になったのかどうか、コンタクトをつけたままリビングのソファでうたた寝してしまっていた。響は床に毛布を敷いて眠っている。こちらはメガネを枕元に置いてあるから、コンタクトは外してあるのだろう。
夜中に物音を聞きつけて目を覚ましたのは、二人ともほぼ同時であった。響がふと廊下を見ると、自分の部屋の扉から誰かが出てくるようなシーンが見えたのだが、寝起きの上に裸眼のため、よく見えない。だが、その影が向かいの兄の部屋に帰って行ったらしいことは辛うじて分かった。
響は怒った。確証もなく疑うのは申し訳ないが、今の影はまず間違いなく兄のものだろうと思った。兄の過保護は最近になってひどく気になっていたが、まさか部屋に忍び込むような真似をされるとは思ってもいなかったのだ。おそらく、付き合い始めた恋人の影が、響の生活のどこかから感じられたために不安になったのだろう。
鼻息を荒くした響が横を見ると、どうやらみこともその光景を見ていたらしかった。みことはコンタクトをしたままだったから、響が見れなかった部屋から出てくる兄の姿をしっかり見たはずである。証人がいるならば兄を問い詰めやすいと考えた響は、みことに「私はメガネなくてよく見えなかったけど、みことは今の、見たよね?」と確認した。
だが、みことは「何のこと?」と首を傾げて見せた。響は座りなおし「今、私の部屋からお兄ちゃんが出てくるの、見たよね?」とくどいくらいの確認をしたが、みことは首を横に振るばかりである。だが、響は納得がいかない。だって、顔こそ確認できなかったものの、誰かが自分の部屋から出てきたところはしっかり見たのだ。
じゃあ、どうしてみことは見ていないなどと嘘を吐いたのか。それが響には分からない。
「という話なわけだ」僕は体を起こして、雨に膝枕をしてやりつつ言った。なるべく簡潔に話したつもりだったが、外はもう夕暮れが迫っていた。「何か分かったかい?」
「もちろん」雨は目を瞑ったまま、頷いた。膝枕をしている僕の足を触って楽しそうに唇を枉げている。「わたしが正しかったことが分かった」
「つまり?」予想はついていたが、確認のために促してみる。
「つまり」雨は目を開けて、悪戯っぽく微笑んだ。「カーくんの話はつまらない」
「そんなことだと思ったよ」僕はひらひらと遊ぶカーテンを腕に巻きつけた。「何で成瀬みことが嘘を吐いたかが分からないんだ」
「響さんは」雨が視線を逸らして言う。「カーくんのクラスメイト?」
「ああ」僕は正直に頷いた。「柿本も成瀬もクラスメイトだ」
「それで、相談されたんだ」寂しそうに言う雨の顔は、色の白さだけがやけに目立った。
「たぶんね」頷くと、雨はやれやれと首を振った。「なんだよ」
「別に」雨が僕の膝から起き上がる。「シェイクスピアは偉大だと思っただけ」
「それは、今回の話と何か関係があるのか?」
「関係っていうか、答えになってると思う」黒髪を指で梳かしながら、雨は言った。「知らないだろう。『恋は盲目である』って、シェイクスピアの台詞なんだ」フフンと鼻を鳴らしそうな表情で威張る雨。
「それが答え?」僕は自虐的に半笑いの表情を作った。「ちっとも分からない」
「だろうね」雨はつまらなそうに言って、机の上に放り出しておいた雑誌を僕の方に投げた。「カーくんには、まだ情報が足りてない」
「なるほど」僕は額で受け止めた雑誌を拾い上げて、「これがその足りない情報なわけだ」
「そうなると思う」雨は酷くつまらなそうに机に向かって腰掛けた。こういうときの雨が煙草を吸うと、きっと絵になると思うんだけど、本人は健康に悪いという理由で喫煙しない。法律の年齢制限の話がちっとも出て来ないのが雨らしい。「それが、たぶん三日目に成瀬みことが読んでいた雑誌と同じもの。偶然わたしも購読してた」
僕は額をさすりながら、雑誌の表紙に目を落した。確かに聞いていた雑誌の名前と同じ字面がそこには並んでいた。
「前の方のページに、人気俳優のスキャンダルが載ってる。もっとも」暗くなってきたので、雨がリモコン操作で電気をつけた。「大事なのは、その前のページだけどね」
探すまでもなく、見るべきページは一発で見つかった。「この眼病の記事が重要なわけか」
「恋は盲目である」雨はまた言った。「コンタクトをしたまま寝ると、目の中の毛細血管が酸素を求めて肥大化し、黒目を侵食することがある」
どうやら雨は記事の内容を覚えていて、要約して解説してくれているらしい。「そうすると」面倒なので、雑誌から目を上げて雨の説明だけを聞くことにする。「どうなる?」
「最悪、失明」雨は眩しそうに天井を見上げて、もう一度電気を消した。部屋の中はさっきより暗くなった気がした。雨の白い頬が余計に目立つ。「血管の入り込んだ黒目の部分の視力は、当然ゼロになる。治癒の望みはない」
「絶望だね」僕は腕を組んで頷いた。「成瀬が、そうだったって言いたいのか?」
「恋は盲目って、シェイクスピアは言ったんだ」
「つまり、成瀬は嘘なんかついていない。コンタクトをつけたまま眠ってしまったから、この眼病にかかって、視力がゼロになってしまって見えなくなった? 前からそういう兆候があったから、気になってこの記事の載っている雑誌を買った? そういうことか?」僕は息を吐いた。「でも、本当にそうだったら怖くて、いくらなんでもコンタクトをつけたまま寝たりはしないだろう?」
「だから」雨は初めて僕を正面から見据えた。暗闇の中で、雨の黒い目が光っているように見えた。「シェイクスピアは偉大なんだ」
「恋は盲目なら飽きたよ。……ああ、そっか。成瀬は柿本の兄貴に恋してたってことかい? そうか、それならメガネ姿の自分を見られたくないから無理にでもコンタクトをし続けたって解釈ができるね。柿本の家に頻繁に訪れた理由も、そのくせ訪れるたびに緊張していた理由も説明はつく」僕は笑った。「でも、納得は出来ない」
「世の中に、納得できる事柄なんて滅多にないよ」
「それは真理だけど、それとこれとは話が別だ」ベッドの上に座ったまま、身じろぎした。
「別にできる話なんて世の中にはない」雨はポンと椅子から飛んで、僕の隣にダイブしてきた。「世の中は連続なんだ。別になる話はどこにもないと思う」
「それも真理だけど」いいかけて、やめた。「整理しよう」
「ご自由に」
2/3