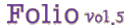「それもご自由に」雨がもぞもぞ動きながら、うつぶせのまま声を出す。「でも、やめた方がいいと思う」
「なんで?」
「意味がないから」
「なんで?」
「決まってる」仰向けになった雨の睫は、すごく長い。「間違ったことを整理しても、意味がない」
「なるほど」僕は頷いた。
「分かった?」
「よく分かった」雨を睨む。「今日の雨の機嫌が良くないことが良く分かった」
「なんで?」上体を起こして、雨が不思議そうに目を丸くする。「わたし、機嫌悪くないけどな」
「今日の雨は嘘ばっかりだ」
「それは仕方ない」雨は少し申し訳なさそうに目を伏せた。「今日はそういう日なんだ」
「なんだよ、そういう日って」雨があまりにも雨らしくないので、少しだけ腹が立ってきた。「そんな日があるのか」
「ていうかね」くるくる髪の毛を弄る雨。「わたしは牡牛座だから」
「全く完全に驚くくらいパーフェクトに意味不明だ」世界中の嘆きを体現するように、僕は神に祈るくらいの気持ちで額に手を当てた。
「完全とパーフェクトは重複だ」雨はクールというか、バカ正直な面がある。「それはカーくんらしくない」
「それで、だ」強引に話を元に戻す。「さすがに成瀬失明説は却下でいいんだろう?」
「当たり前だね」ポンポンと自分の隣を叩きながら雨が言う。「そんなに簡単に失明なんてしないし、本当に失明してたらもっと大事になってるはずだ」
「それはそうだ」僕は頷いた。「それはそうだけど、そうなるとどうなる?」
「どうもならない」雨が自分の隣を強く叩きながら答える。「ただ、成瀬さんは失明していないという事実が分かる」
「それじゃあ駄目だ」僕が諦めて催促通り雨の隣に座ると、雨が嬉しそうに目を細めた。「それだと、何の進展もない」
「だから、さっきから言ってる」雨の黒髪が頬に触れた。小さな頭が僕の肩に寄りかかってきたのだ。「恋は盲目なんだ」
「雨」名前を呼んだ。「いい加減に、全部説明してくれないか」
「おっと珍しい」雨がおどけた声を出して僕から離れた。「カーくんが怒るなんて」
「怒ってない」手を伸ばして、遠ざかりそうになった細い肩を捕まえて、自分の方に引き寄せる。「ただ、教えて欲しいだけだ」
「交換条件、等価交換」雨は大人しくまた僕に寄りかかる姿勢に戻って、呟いた。「教えたら、カーくんはわたしに何をくれる?」
「キスしよう」僕は頷いた。「特別大サービスだ。ほっぺにチュウ」
「嬉しくない」雨が首を振る。「そんなの、全然嬉しくない」
「また雨らしくない嘘だ」額を小突くと、痛いと雨が言った。「口元が笑ってるぞ」
「悪いことは出来ない」雨が微笑んで抱きついてくる。「それは魅力的な条件だけど、ところで、前払いはできる?」
「駄目に決まってる」首を振った。「ただでさえ、等価より高いんだ」
「贅沢は言えない」なんてことだと言わんばかりに溜息を吐いた雨は、もう一度あの雑誌を拾い上げた。「最後の情報。この雑誌の星占いは、よく当たることで有名なんだ」
「なるほど」僕はその雑誌を手に取った。「では戯れに、雨の運勢、牡牛座を見てみよう」
「金運、健康運は最高値。だけど恋愛運は最低値。ワンポイントアドバイス、大切な人に対してや大切な人に関しては嘘を吐こう」雨が天井を見上げながら言った。「だったかな」
「正解」僕は今日一番に盛大な溜息を吐いた。「嘘だろ?」
「何が?」雨が頬を差し出しながら言う。「何が嘘であって欲しい?」
「この占いが正解だなんていう馬鹿げた物語は」その頬をつねって、自嘲した。「頼むから嘘であってくれ」
「まったくカーくんは」つねられた頬をさすりながら、雨が眉を寄せる。「乙女心が少しも分かってない」
「確かに、成瀬は三日前である五月七日の時点で、二週間前に誕生日を迎えたらしい。となると、必然的に彼女も牡牛座だ」僕はとんがった雨の唇に指を当てる。濡れていた。「雨と同じ、ね」
「見ていたページは俳優のスキャンダルでも、まして眼病なんかでもなく、この星座占い。彼女がこんな雑誌を買う理由なんて、このよく当たる星座占いくらいしか可能性がない。ちなみに、成瀬さんが雑誌を読み始めたのは一ヶ月くらい前からで、初めて柿本さんの家を訪れた時期、つまり初めて柿本さんのお兄さんを見た時期と合致する」雨が僕の指を舐める。もっと濡れた。「何か質問は?」
「なんで「こんな雑誌」を雨が購読してるんだろう」
「忘れてると思うけど、わたしだって中学三年生の女の子だ」雑誌を僕の手から奪い取る。「よく当たる星座占いくらいには興味がある」
「それは初耳」大げさに驚いた振りをする。「だからさっき、そのページがやけに開きやすかったんだ」
「それにしても」雨は白いカーテンをくるくる回して遊んでいる。「柿本さんのお兄さんには頭が下がる」
「下げるなよ」僕はそのカーテンを雨から取り上げて、言った。「妹に彼氏ができて心配になったからって真夜中に妹の部屋に侵入して家捜しだぞ。ちょっと異常なんじゃないのか。気持ち悪いぞ、その兄貴」
「そうかもね。――でも」雨は不満そうに頷いて、もう一度頬を差し出してきた。「カーくんは本当に女心がわからない」
「雨のことなら」僕はその白い白い頬に、唇を優しく落した。「誰よりも知ってるけどね」
「当たり前だ」嬉しそうに頬を撫でても、口調は相変わらずぶっきらぼうな雨。「兄が誰よりも妹を知らないでどうするんだ」
「どうもしない」僕は外を見た。そろそろ夕暮れさえ終わろうとしている。「親とかもいる」
「カーくんは」雨も外を見た。寂しそうな横顔だった。「双子の兄妹を引き裂くような離婚をした両親が、わたしをどれだけ分かっていると思う?」
「このくらい」僕は小指の爪の先っぽを指差した。「多くて、このくらいかな」続いて、親指の先を指差した。
「違う」憮然と呟いた雨が人差し指で示した先には、ゴミと化した『授業参観のお知らせ』プリントが転がっていた。「あのくらいだ」
僕はベッドに仰向けに倒れこんだ。雨を抱きしめたいと思った。「あのくらいか」
雨が僕の上にまた覆い被さってきた。「あのくらいだ」
「僕は」僕は雨の顔を両手で押さえ込んで、唇にキスをした。雨は目を閉じていた。「これくらいだ」
雨が真っ赤になって俯いたので額を撫でてやると、なぜか涙目になりそうな雨が上目遣いで僕を睨んだ。「会話になってない」
「なってる」僕は薄く笑って、さらさらの髪を指の間に通した。「雨の理解力と努力が足りないだけだ」
「それは盲点だった」雨は僕の胸に顔をうずめた。泣いているのかもしれないと思った。「でも、キスは頬の約束だった」
「忘れてるみたいだから確認するけど」僕は笑った。「僕も牡牛座なんだ」
今週、牡牛座は大切な人に嘘つかなければ恋愛運が最低らしい。
「しかしね、カーくん」胸の中で雨が呟く。
「ん?」
「柿本さんのお兄さんは確かに異常だし気持ち悪いだろうけど」雨が僕の体をよじ登ってきて、目の前で無邪気に笑った。「わたしたちほどじゃないと思う」
「うん、まあ」僕はその雨を抱きしめて、(ああ、ヤバイなあ、僕)と心の中で呟いた。「それはそうだろうね」
「やっぱり、こういうのって不味いんだろうな」僕に抱きしめられて、嬉しそうに目を細めながら、でも雨は暗いトーンで言った。「きっと、良くないんだろうな」
「でも、仕方ない」半ば投げやりになった僕は、外を見た。もう世界は藍色になっていた。でもまだ、白いカーテンは揺れていた。「雨も、さっき言ってただろ」
「何が?」雨が笑う。もう、言わなくても気付いてるだろうけど、カーテンが白いから、僕は真っ暗な部屋で言葉を続けることにした。
「シェイクスピアは偉大なんだ」僕は、雨の口調を真似て言った。「恋は盲目である」
雨が、笑った。
3/3