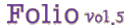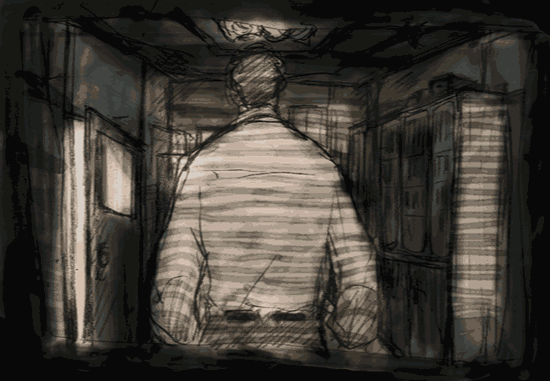1.
「榎本君」
隣の部屋から物憂げな声が聞こえ、私は書き物をやめて顔を上げた。いつのまにか日は傾き、埃っぽいブラインドの間から鋭い光が条を成して差し込んでいる。私は少し眼を細めて立ち上がり、黒い影の横縞が刻まれた壁の前を通り抜けて隣室へ向かう。終日自室に閉じこもっていながらドアは締め切らないのが彼の癖だ。
「どうした、錦織」
覗き込むと、ミステリー探偵・錦織慎一郎は古いオークの机に足を投げ出し、大きな肘掛け椅子にもたれかかって煙草を吹かしていた。がらんとした机の上には三角柱の形をしたプリズムが転がっている。ペーパーウェイトの代わりに使っている、錦織の気に入りの品。それは窓から入る西陽を集め、虹色に分解して扇状に拡散させる。
「光というのは、普段は一つの像を結ぶためにしか存在しないように見える。けれどこうして分解すると、実は七つの波長を持っているのさ」
「そんなことを言うために呼んだのか?」
そうだと認めるのはさすがに憚られたのか、革靴の踵の横に転がるプリズムに視線を逃がして錦織は肩をすくめた。応接セットと書棚、仮眠用のソファ。高価なアンティークのように見えなくもないこの部屋の調度品は、実は、近所の会計事務所が廃業した際に粗大ゴミ置場から掠め取って来たものだ。私がぜえぜえ言いながら机を運搬している間、錦織は手伝おうともせず、にやにや笑いながら3階の窓から私の作業を見下ろしていた。
「あの…な…錦織…お前も…手伝え!」
「部屋を選んだのも、その家具が欲しいと言ったのも君自身だよ。僕は家具なんかなくても構わない」
確かに、不動産屋を何軒も歩き回ったのは私だし、この部屋の淡灰色の壁にはオークが合うと言ったのも私だ。しかし私が一人で不動産屋巡りをしたのは錦織の無精のせいだし、書棚が要るのも、錦織が溜め込む大量のファイルや蔵書を収めるためではないのか。言いたいことは山程あったが、ミステリー探偵の我儘に逆らえないのが助手の悲しさよ。私はそのあと一時間あまりも掛けて、重厚感たっぷりのオーク家具を担いで路上と事務所を何度も往復した。私の悲劇的状況は、まるで十字架の重さに喘ぎながらゴルゴタの丘へとまろび歩くイエス・キリストのそれだった。
あまり知られていないことだが、世の中にはミステリー探偵という職業がある。スポーツ選手と一口に言ってもサッカーや野球、テニスやゴルフとバリエーションがあるように、探偵にもやはり専門分野というものがあるのだ(と、錦織が言っていた)。
ミステリー探偵の中には、世を忍ぶ仮の姿を持つものもいる。つまり、彼等の表向きの身分は探偵ではない。家政婦、小学生、温泉女将、スチュワーデス、古書店主などの一般市民として平穏な日常を暮らしているのだが、いざ事件となると我が物顔でしゃしゃり出てくる。彼等に対しても私はある種の苦々しさを感じているのだが、それを細々と論うのは本意ではない。今はそれよりも、もっと探偵然とした探偵に関する話をするべきだろう。
ミステリー探偵。彼等は事件性の高い仕事を極端に好み、浮気や空き巣の調査、ペット探しといった平凡な依頼はまず受けない。収入の多少や衣食住は決してステイタスではなく、誇るべきものはその推理と知性のみ。およそ住居向きとは言えない、繁華街の谷間にあるビルの一室などに事務所を構えて棲んでいる。食べることには執着しないが(確かに、探偵が犯人よりも先にカツ丼を欲しがるようでは格好がつかない)、珈琲や煙草などの嗜好品にはうるさい者もいる。
またミステリー探偵は数カ国語に堪能で、歴史や哲学、文学や芸術にも造詣が深い。「名探偵は机で推理する」などと嘯きながら終日座っているので虚弱な文系人間かと思いきや、犯人追跡などの捕り物となると、周囲が驚くほどの運動神経を披露する。着るものは「いつも同じ」か「まいど奇抜」かのどちらかで、自分の外見を良く見せようと心を砕くことはあまりない。ときに女性に恋心を寄せられることがあるが、本人は無関心であることが多い。あれほど勘の冴えた推理を見せることがありながら、その方面にだけ鈍感なんてことがあるわけもないのだから、恐らく面倒を避けてしらを切っているのだろう。
ミステリー探偵の行くところ、必ずと言っていいほど事件が巻き起こる。多くの場合は殺人、時には宝飾品や美術品、現金や金塊などの盗難事件。たいがい警察とは折り合いがよくないものだが(しかし中に1人くらいは話のわかる奴がいる)、あの手この手で謎を解きほぐし、犯人を追い詰める。
それから、ミステリー探偵には、もうひとつ忘れてはならない必須事項がある。
助手だ。
優秀なミステリー探偵に助手の存在は欠かせない。助手は公私ともに探偵に最も近しい存在であり、大抵のところ常識をわきまえ、知的で物腰も穏やかだ。常識では理解しえない探偵の奇癖に翻弄され、つまらない凡人扱いされながらも愛想を尽かすことはなく、探偵への献身的なまでの敬意は尽きない泉の如く湧き出してくる。探偵の鮮やかな謎解きを手助けするためであれば、周囲の誤解や非難からも身を以て擁護する役目を買って出るし、瑣末な調査や留守番、あるいは影武者などの雑用の類を一手に引き受ける。また、助手の一部はものを書く職業に就いており、ミステリー探偵が事件解決にもたらした知られざる功績を精力的に記録し、出版という形を通して世に広めることとなる。
まったく損な役回り。面倒ばかりで気苦労の耐えない人種。それがミステリー探偵の助手、つまり榎本卓司という私自身なのだ。
2.
灰色の部屋。
私は中央にぼんやりと立っている。錦織はドアの傍にいて、警部や鑑識、ふてぶてしくそっぽを向いた容疑者などのギャラリーを前にして滔々と演説を続けている。殺害現場を再現しての謎解きが彼の独壇場だ。
「謎の核心はいかに殺したかでもなく、いかにここから脱出したかでもない。いかにその両方を同時に成し遂げたかです。そのからくりを今から御覧に入れます。さて、まずこの錠前に糸をひっかける。そしてあの梁を通して固定する。こうしてバランスを保っておいて、いいですか、ナイフでここを結んだ糸を切るのです」
得意満面で錦織はいい、懐からナイフを取り出す。糸一本で保たれていたバランスは一瞬で失われ、私の後頭部を鈍い衝撃が襲った。ぐはっ、と声を上げ、私は思わず頭を押さえて床にうずくまる。
「今のは錘入りのテディ・ベアだからよかったが、これが本当の凶器だったら、今頃榎本君は即死です。ともかく犯人はこうして被害者を殺害し、この糸を手繰って凶器を回収した。糸が引き抜かれると部屋の錠前もかかってしまう。あとに残るのは密室と死体だけ、というわけです」
おお、とどよめきが上がる。ぱらぱらと起こる拍手の中から恰幅のいい警部が足を踏み出し、錦織に握手を求める。さすがですな錦織さん、鮮やかな推理でした。周りがうんうんと頷く中、私は痛む頭を抱えたまま、その騒めきを半ば遠くに聴いている。
ミステリー探偵の助手である自分に疲れを感じたとき、私は文壇バーに立ち寄ることにしていた。文壇バーといっても作家の溜まり場ではない。ここは文壇を彩る登場人物たちの溜まり場だ。あらゆる種類の文芸作品の登場人物が同じ空間を共有できる貴重な場所だ。
私はここに行き交う人達を眺め、時間を潰すのが好きだった。彼等はごく平凡な存在に見えながら、実際には、それぞれに特別な物語を生きている。
たとえば、カウンターでウォッカを飲んでいる黒い服の若者はファンタジー小説の魔導師だ。グラスを持つ手は骨張って青白い。指先に薄い爪が張り付いて、温度のない燐光を放つようだ。彼はゆるく目を閉じ、まるで失われた王国の記憶を惜しむような表情で、銀の指輪とグラス、そして氷が触れ合う音に耳を澄ませている。
一方、何の価値もないネズミのように背を丸めてテーブル席でウィスキーを飲んでいるあの男。彼は実はスパイものの悪役で、最先端の研究所で生物兵器を造っている科学者だ。彼が年齢よりも老け込んで見えるのは、家族にも本当の仕事を悟られないよういつも神経を張り詰めていて、気の休まる間もないせいなのだ。そして、私の目の前を横切って行った若い女は、ポルノ小説の主人公。電車の中だろうがトイレットだろうが映画館だろうが男の言うなりで、出かける先々でやられまくっている彼女が、男に襲われずにいられる唯一の場所がここなのだ。私は見るともなしに彼女を見送る。身体にぴたりと沿うような象牙色のタイトスーツが艶めかしい。
もちろん、ここに集うのは主役級の人物だけではない。たとえば、奥のテーブルでビリヤードに興じているのは、宇宙船「スターシップ・クルセイダーズ」のメカニック・チームだ。本編ではエイリアンと死闘を繰り広げる討伐隊員の活躍ばかりが描かれるが、彼等が乗り回すスペース・モービルは、このメカニックの努力がなければ動かない。しかし、この中で名前を与えられているのはチーム・リーダーのホーソーンだけ。それ以外のメンバーは、「いかつい作業員」「眼鏡をかけた神経質そうなエンジニア」以上の描写を与えられる機会はない。それから、テーブル席で気まずく沈黙を持て余している男女4人組は、私にも親しいミステリー探偵ものの「連続殺人事件の被害者同盟」だ。一見合コンの席に見えなくもないのだが、実際は彼らの間には、「同じ犯人に殺された」という以外の接点はひとつもない。一人など1ページ目の4行目で、すでに死体で発見されることになっている。その後の展開を知らないのだから話題も弾むまい。気の毒なことだ。
まるでドラマのごった煮だが、彼等を見ているのが私は好きだ。私だけじゃない、そう思うことで気持ちが僅かに慰められる。誰もが自分だけの舞台設定を背負い、理不尽なほどデフォルメされた世界観の中に生きている。問題が起こるたびに魔法で解決する人生、出歩くたびに見知らぬ男の手に触られまくる人生、あるいは誰に名前を呼ばれることもなく惨殺される人生。そんなものが本当はあるわけもないのだが、その世界の住人である以上は抗いようがない。ファンタジーには魔法、ポルノにはセックス、そしてミステリー探偵ものには事件がつきものなのだから。
酔ってくると私は朦朧となる。バーテンダーが何やら私に話掛けているが、何の話をしていたのか思い出せない。壁紙の継目に広がる染みのように、自分の生きている世界にヒビが入り、そこから流状化した私自身が流れ出していくような錯覚がする。不安定に腰を乗せたスツールが軋み、私は急激に喉の渇きを覚える。飲物をくれ、そう言ってもバーテンダーは穏やかに微笑して首を振るばかり。その前に質問に応えてください。この模様は何に見えますか?
私は目を凝らす。ああそうだ、私と彼は視覚ゲームを楽しんでいたのだ。杯の影絵の白黒を逆転すると向かい合った二人の人間の顔になるという騙し絵の話から始まり、灰皿や万年筆、独特のシェイプを描くグラッパのボトルに至るまで「見方を変えればそれは何に見えるか」というクイズを出し合っては笑っていた。
目の前にはスコッチを注いだグラスが掲げられている。くるりと回転させたグラスの内側を、とろみのある琥珀の酒が条を成して流れ落ちる。
「降参ですか?英国の蒸留職人は、この条を女の脚に喩えたそうですよ。滑らかで艶があって、僅かにうねっている…」
「成る程ね」
私は平静を装って薄笑いを浮かべる。だが、目の前にあるこれは違う。それは私が垂れ流した自我の残滓。かたちを整えきれなかった歪なままの影法師。背中に滲んだ汗のように生ぬるく不快な感触を振り払おうと、私は声を上げる。
「返してくれ……それは」
「それは?」
私は首を振る。なんでもない、それは俺の酒だ。倒れたグラスからこぼれ出し、滑らかなカウンターを汚していく。力尽きてカウンターに伏した私は目の高さに水面を見る。エッジは表面張力のせいで美しく丸い。やがて流れはカウンターの縁に届き、そこで均衡を崩して床に滴り落ちる。ぼたぼたぼた、という音が小刻みに連続して聞こえ、革靴を履いた爪先が飛沫に濡れる。こぼれ落ちた液体は、もうグラスには戻らない。
1/4