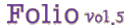3.
やはり灰色の部屋。
私は今度は椅子に座っている。公園にあるような硬い木のベンチ。背中に張りつく不快感は消えないが、錦織はそんなことはかまいやしない。今日も得意満面で演説だ。
「さて、そこにいる容疑者の日下部さんは、事件前夜に被害者の真瀬さんと酒を飲み、彼が抑鬱状態で自殺を仄めかすのを聞いたと言っている。散りゆく夜桜を見たいから公園で毒を飲んで死ぬのだと。それが本当なら、哀しいほどセンチメンタルで美しい散り際だ」
錦織は私を振り返る。私を哀れむように一瞥して物静かに続けた。
「だが、真瀬さんが息を引き取った現場は公園じゃない。容疑者が別の場所で薬殺して、後からここへ運んできたんだ。市の緑化委員会に問い合わせて調べたのだが、事件の前日、公園は改修工事をしていた。つまりあのベンチは”ペンキぬりたて”だったのさ。容疑者の言う通り、本当に前夜からそこに彼が座っていたとしたら、被害者の尻と背中にはべったりとペンキが付着しているはずだ」
私は厭な予感がする。背中から立ち去らない湿気を含んだ不快感。私は立ち上がり、身体をねじって自分の背を覗き込む。案の定そこには、許し難いほど爽やかなミントグリーンのペンキが、ロールシャッハ・テストのごとくグロテスクなシミを描いていた。
「ほらご覧なさい、ひどいものでしょう。しかし被害者の背中にはペンキなんか付着していなかった。それは何を意味するか?日下部さん、あなたが嘘をついているということだ」
「くそお」
日下部が悔しげな呻きを上げるが、錦織は構いもしない。ギャラリーに向けて軽く肩をすくめて見せると、いつも通りのどよめきと拍手がはじまった。私は眼を閉じ、頭を振る。何がめでたいのかさっぱり解らない。背中を指先で探るとぬるりとした液体に触れた。眼を閉じていると、感触だけはまるで血糊のようだった。
わかっている。私の役目はミステリー探偵・錦織慎一郎の活躍ぶりを書き留め、彼の真実への功績を書物にして残すことだ。自分の外面を取り繕い、うわべの名誉を守ることなどに固執してはいけないのだ。
殺人、誘拐、強盗、詐欺。彼が好む類の陰惨な事件をただ書き連ねたとて、世の人々は一瞥をくれもせずに立ち去ってしまうだろう。自分でものを考えようとしない人たちのために、私はまず、錦織慎一郎が鮮やかな謎解きをする場面を自著の山場として設定した。彼の滔々たる演説は物語の名物となり、また同時に、そこだけを拾い読みすれば事件の決着が理解できるという「ずる」をするためのアンカーポイントとしても機能した。
さらに、そこに若干の娯楽性を付け加えるため、私は(今となってはそれを激しく後悔しているのだが)ある要素を付け加えた。錦織慎一郎の助手である榎本卓司…私自身を、道化として扱ったのだ。
自らが身体を張って実験台となり、錦織が立てた仮説に基づいて事件の模様を再現する。時折トリックを仕掛ける犯人の役を仰せつかることもあるが、ほとんどの場合は被害者だ。頭を殴られたり(鈍器ではなくぬいぐるみで、ではあるが)、背中をペンキまみれにされるのなんかは序の口だ。ビルの壁から宙吊りにされて「消えた死体」を演じたこともあるし、増水中の川の中州に置き去りにされたこともある。危機的な状況に追い込まれた助手・榎本卓司がうろたえ、助けを求めて騒ぐシーンは、陰惨な事件の中での数少ないお楽しみだった。切れ者の錦織とぶざまな榎本、その対比は今や、「探偵・錦織慎一郎」シリーズにおいて、決して外せない「お約束」となっていた。
「でも、わかるだろう?もうこんなことには疲れたんだ。殺人事件にも華麗な謎解きにも心底うんざりだ」
気がつくと私は文壇バーにいた。かなり酩酊しているらしく、頭の芯が螺旋状に揺れる心地がする。私は誰に向かって話しているのだろう、ふと疑問が湧いて顔を上げた。目の前には美しい女がいた。滑らかな長い髪と翳りを帯びた瞳。何度もここで見かけていたポルノ・ヒロインだった。
「自分で自分の物語に酔うことができないんだ。君ならわかるだろう、男に抱かれていても、自分の中に全く欲望が沸き上がってこない時のあの薄ら寒さが。シナリオの通りに乱れ狂い、際限なく男を呑み込んで見せながら、冷いまま取り残されている心の空虚さが。僕にはその冷たさがわかる。僕も同じだから」
彼女は何も応えない。けれど全身の気配から、まるで氷像にヒビが入るように、相手の警戒が解け始めているのを感じ取ることができる。私は言葉を絶たず、さらに畳みかけた。
「こんなことを君に頼むのは筋違いだってわかってる。でももう駄目だ。今だけでも自分の役割を忘れたいんだ。誰かがいてくれないと頭がおかしくなってしまう。頼むから僕を助けてくれ」
今夜の彼女は象牙色のスーツではなく、銀鼠色に光るカシュクールを着ていた。斜めに重なった襟元には深いドレープが寄り、その襞の内側は暗く陰って視線を曖昧に遮っている。その柔らかな襞を乱暴に掻き広げたい欲求に駆られた。
「…うちへ来て」
彼女は、長い時間私を黙って見つめたのち、それだけを短く告げた。私はスツールから立ち上がり、まるで縋りつくように、彼女の肩に手を添える。
彼女の住居はマンションの最上階にある吹き抜けのロフトで、真暗な中に天窓から朧月の光が寝台の上に落ちていた。壁は淡い灰色で、家具はひどく少ない。女らしさを意識してそぎ落としたような無機質さに、かえって彼女の日常の過酷さがかいま見える気がして切なかった。
私たちは月光に引き寄せられる羽虫のように、服も脱がないままベッドに向かった。冷えたシーツに肘をついて彼女を見下ろすと、背中の上に広がる空間の高さを皮膚で感じることができた。まるで深海の底にいるような、安らかな孤独感。
「ここ、落ち着くでしょ」
私の思いを感じ取ったかのように彼女は呟いた。私は曖昧に頷き、銀鼠色のカシュクールの胸元に手を差し入れた。先刻から眼を引きつけてやまなかった場所、その内側には温かく滑らかな肌が息づいている。一秒でも早く唇を這わせたいと思いながら、私はわずかに醒めた脳の一部で彼女の言葉を聞いていた。
「いつもは一人で、ここで小さくなって眠るの。何もない部屋、高い天井、暗い天窓。私以外には誰もいない、そのことにほっとする。どんな欲望もここには届かない。だから安心して眠れるの」
「そんな場所に、どうして僕を入れてくれたんだ?」
「あなたにも、私と同じ時間が必要だと思ったから。そんなふうに見えたから……」
私は黙って頭を垂れた。彼女の深い許容に感謝した。私たちはぎこちなくことを始めた。暗い孤独の底で手探りするように彼女を愛撫し、見栄も虚勢もなく、欲望のまま性急に挿入した。技巧は足らずとも、熱を帯びた肌どうしを擦れ合わせていると、それだけで情欲の甘い香が立ち上ってくる。私たちは息を喘がせ、もがくように手足を絡ませて頂点を求めた。
それは、背中から追い立てられるような、ひどく切羽詰まったセックスだった。彼女の柔らかな暗闇に包まれながら、自分を逃げ惑う爬虫類のようだと思った。暖かな洞穴の匂いに惹きつけられながら、外気に触れた肌はひりつき、決して安らぐことを許されない。なんてちっぽけで惨めな生き物。私は知らぬうちに嗚咽していた。
「許してくれ。何もできない僕を許して」
何もできないどころか、こうして彼女を犯している。この部屋は、こんなふうに女を貪る、男達の汚れた欲望を遮断出来る場所のはずだったのに。私は自分を慰めるためだけに彼女の聖域を壊したのだ。
「それでいいの。私も同じ。楽になって、私の上で」
悲しみと愛おしさに突き上げられて、私は自分を抑えることができなくなった。頬に触れようとした彼女の手首を掴み、強くシーツに押しつけた。胸に焼けつくような痛みを感じながらも、むしろリズムは高まり、小刻みな息は次第に熱を帯びていく。自分のペースを緩めないまま私はエクスタシーに達し、全てが終わってしまってから、ようやく、ゆっくりと理性を取り戻し始めた。
こんなふうに我を忘れたセックスは、遠い昔、初めてのとき以来だった。彼女の肉体はこの部屋と同じ昏い海のようで、深く身を沈めるほど、興奮と裏腹の懐かしい揺らぎに慰められる心地がした。全ての男に同じ感情を与えることができるなら、それこそが彼女の、ポルノ・ヒロインとしての最高の資質なのかもしれなかった。
「ありがとう」
髪を撫でて囁くと、彼女はこちらを向き、ゆるく瞼を閉じたまま、口元だけで軽く微笑んだように見えた。彼女にとってもこの一刻は、自分の役割から解放され、暖かな暗闇に安らぎを覚える時間だったのかもしれない。
自分の顔に手をやると、指先に涙の筋が触れた。本能のままに動くことしかできなかった自分が気恥ずかしくなり、私はシャワーを借りることにした。
シャワーを出ると、彼女はさっきの姿勢のままで眠っていた。私は彼女に毛布を掛けてやり、穏やかな寝顔を黙って少し眺めた。しなやかな身体に寄り添って自分も眠りたい誘惑に駆られたが、いきなり泊まり込んであからさまな朝の空気を共有するのは図々しすぎる気がした。私は取材用の手帳を一枚引きちぎって短いメッセージを書いた。
「君のお陰で救われた。もしよければまた会いたい。今夜、文壇バーで待っている」
まだ暗い街をタクシーで抜け、自分の部屋に帰り着いたのは夜明け前だった。誰もいない部屋は静まり返って、電気製品の唸りだけが低く響いている。
疲れていたが感情は穏やかだった。錦織の事務所にはひと眠りしてから向かえばいい。普段さんざん迷惑を被っているのだ、多少遅刻したところでかまうものか。開き直りに近い気分で私は薄く笑い、そのままベッドにばたりと倒れ込んで眠った。
2/4