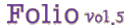「馬鹿な」
「言っただろう、光というのはただ一つの像を結ぶために存在するように見える。しかし角度を変えれば、そこには幾つもの色彩の層が現れる」
錦織は懐から愛用の三角プリズムを取り出した。手の中で光を弄びながら語りつづける。
「ここに居るのは榎本卓司という一人のミステリー作家だ。9年前に新人賞を獲ってデビュー、その後も堅実に書き続け、3年後に出したシリーズがヒットした」
ミステリー探偵・錦織慎一郎シリーズ。それは榎本にとって初めてのヒット作だった。ただでさえ我の強い錦織慎一郎のキャラクター性は、作者の榎本自身が作中で頼りない探偵助手を演じることでさらに際立ち、人気を呼んだ。
「この部屋は君が借りた実験工房だ。物理的なカラクリ、五感に訴える心理的な錯覚、時間の経過を操作することで相手の目を欺く方法…君はこの部屋で色々なことを試した」
私は茫然として錦織の説明を聞いていた。まるで他人事のような話し方をする。その実験台にさんざん私を使い回したのは錦織自身ではないか。
「確かに、時には実験に相手役が必要になることもある。しかし、君は一人で幾つもの役をこなした。狂言回しの榎本卓司でありながら、探偵・錦織慎一郎や石頭の警察官、忌まわしい犯人や物言わぬ死体すら演じた。やがて君の中で錦織慎一郎は、君自身を凌ぐほどのリアリティを持った存在になっていった」
「…そうだ…」
私は急速に全ての事実を受け入れ始めていた。確かに私はこの部屋を実験に使った。執筆用の事務所という名目で手に入れたこの場所で、私は終日奇妙な一人遊びに興じていたのだ。
「そのロールプレイが部屋の中だけで済んでいれば、まだ害がなかったのかもしれない。しかしそこで止めることはできなかった。倒れたグラスからこぼれる酒と同じで、一度流れ出したものは決して元には戻らない。君の想像の翼は、外界で起こる物事にまで影を落とした」
「どういうことだ」
「文壇バーさ」
一瞬の間も置かずに錦織は指摘した。
「君が通っていたのはどこにでもあるホテルのバーだ。確かに色々な種類の人間が出入りしていたが、彼等は決して虚構の存在ではない。しかし君は人間観察をするうちに、得意のロールプレイを始めた。まったく鮮やかなものだったね、まさに一つの像から七色の物語を引き出すプリズムの眼差しだ。売れないサックス・プレイヤーは黒衣の魔導師に、自動車の部品工場の面々は宇宙船の修理屋に。そして、ごく真面目な女教員の今泉エリカは…」
私は首を振った。一言も抗弁することはできず、ただその続きを聞きたくないと頑なに願う意外になかった。
「君のファンタジーを受け容れてくれるポルノ・ヒロインだったというわけさ」
「でも…でも、彼女は私の苦しみを理解してくれた」
「ああ、あの繰り言か。男に抱かれながら、そこに一片の演技もない女がいると思うかい?彼女はとても優しい女だ。時には自分の演技に酔えないまま、男に抱かれてやることもあっただろう。だから君の物語に共感して、部屋にまで招き入れてくれたのさ」
しかしあの夜の私は彼女の部屋を訪れてもなお、現実の世界に戻ることはできなかった。それどころかより深く、空想の中に沈み込んでしまったのだ。海底で喘ぐごとく彼女を抱き、そしてあの光が私を狂わせた。ブラインドに遮られ、細い横縞の模様を描く無彩の光。見慣れたそのヴィジョンが、私を灰色の実験室に引き戻した。
「彼女を絞め殺したのは君自身だよ、榎本君。君は彼女を実験用のマネキンに使ったのだ」
「なんてことだ…」
私は呻いた。なんということをしてしまったのだ。しかしそれは事実だった。私が長い髪を撫でてありがとうと囁いたとき、既に彼女は息をしていなかったのだ。手の中にまだ微かに残る記憶を、私は冷ややかな汗と共に握り締めた。
彼女の部屋は私にとって最高の実験室だった。家具らしい家具もなく、逃げ道といえば玄関か高い天窓しかない密室。そこで犯人は被害者を情事のあとで絞め殺して逃走するのだ。まるで他の誰にも触れさせまいとするように、ドアノブの内側にハンカチを結びつけた密室状態を残して。
その小細工は、構想中の新作で使うはずの……まだ誰にも話していない、私だけのアイディアだった。
エピローグ
「なんて…ことだ」
私は絶望に乾いた唇でもう一度呟いた。身を支えるものを探したが、古めかしいソファは沈み行く泥船のようだった。錦織はいつの間にか立ち上がり、あの哀れむような穏やかな眼で私を見つめていた。
「認めるか?」
私は力無く頷いた。私は榎本であり、同時に錦織だった。今なら理解できた。探偵の立ち居振る舞いが何ゆえそこまで極端に華々しく、助手は地味で損な役回りばかりを引き受けなければならないのか。華麗な謎解きで喝采を浴びる探偵と、全ての名誉を諦め、探偵の活躍を書き留める助手。光と影、太陽と月。私たちは磁石の両極であり、二人で一人だったのだ。
錦織は奇妙な優しさを滲ませた声で呟いた。
「榎本君、君は自分だけが貧乏クジを引いたと思っているかもしれない。君が僕を疎ましく思っていたことも知っている」
私は首を振ったが、近年自分の書く作品に嫌悪を覚えていたのは事実だった。そこに現れるのは、人間の生よりもアリバイやトリックばかりが優先される歪んだ世界。することといえば、自ら謎を仕掛けてはもっともらしく解いてみせ、ケレン味たっぷりの演説をぶち上げることの繰り返し。その中で、私は少しずつ虚構の分身、錦織慎一郎に主導権を奪われていった(厳密に言えば、自ら奪わせていたのだが)。私が存在するために残された道は、自分を貶めて笑い物にすることだけ。自己嫌悪に深く陥るほどに、自らの鏡像である錦織への嫌悪も強まっていった。
「しかし榎本君、実際には、僕こそが虚構の影法師でしかないんだよ。その中で僕も苦しんだことだけは解ってほしい。それでお互い様ということにしないか」
「お互い様だって?」
私は首を振る。妄想の罠に嵌まって今泉エリカを絞め殺したのは私であり、錦織にはなんの咎もないではないか。
「僕も間接的には有罪だ。君が彼女を殺すのを止めなかった。何が起こるか予見できていたのに見殺しにした。…君がこの部屋の外で誰かと関係を結ぼうとしていることが許せなかったのかもしれない」
私は改めて錦織の孤独を思った。終日この部屋から出ることはなく、他人の秘密を暴き、罪状を並べ立て裁くことでしか関係を結べない。彼にとって私の行為は、到底許せない裏切りだったのだろう。
「榎本君、それでも僕は君に感謝しているよ。僕が短い間だけでも存在できたのは君のお陰だ」
「そんな…私の方こそ」
不覚にも声が震えた。錦織がいなければ、私はここまで「私」として生きることはできなかっただろう。錦織の活躍を多くの読者が待ち望み、喝采を浴びせる。その度に私は、自分が選ばれた人間になったような気がしていた。錦織慎一郎というミステリー探偵、その物語に選ばれた存在。それこそが私自身の存在理由であり、同時に存在を危うくする理由でもあったのだ。全てが急速に終わりつつあるこの期に及んで、私は自分がいかにこの探偵に愛着を感じていたかを改めて思い知った。
「しかし、僕の役割はここまでだ。他人ならいくらでも糾弾できるが、君を告発するのだけは御免だよ。僕はここを立ち去り、同時に消え失せる。二度と現れることはないだろう」
「待て、錦織!私は…」
強い不安が胸を掠め、私は叫んだ。しかし錦織は、私が泣こうが縋ろうが立ち止まる性格ではない。いつもの癖で少し肩をすくめると、踵を返し、すたすたと部屋を横切ってそのまま出ていった。ドアを出ていくときの後ろ姿が私に似ていたか、いなかったか。そんなことを確かめる間もないほどに呆気なく。
どれほどの時間が経っただろう。私の手の中には冷たい三角プリズムだけが残された。陽の落ちた部屋にもはや光はなく、手の中でうつろに回転させてみても、なんの像も結びはしない。
そこには色も光もなく、物語からも切り離された、ただ無表情な灰色の部屋だけがあった。錦織慎一郎は立ち去り、永遠に戻ってこない。私は半身を失った奇妙な浮遊感の中で、静かな絶望に浸されて、いつまでも茫然としていた。
了
4/4