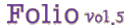4.
電話のベルで目を覚ました。不自然な姿勢で眠っていたせいか、首や腕の節々が痛む。相手をかなり待たせてから、私はようやく受話器を取った。
「榎本君、大丈夫か」
電話の主は錦織だった。ちらりと時計に目をやると、既に午後の3時を過ぎている。ずいぶん長く眠り込んでいたらしいが、その失態さえ今は微笑を運んできた。こんなに深く、何者にも妨げられずに眠れたのは何ヶ月ぶりだろう。
どうせ暇な事務所だ、一日さぼったくらいで大騒ぎすることもなかろうにと思いながら、私はそれでも快活に応えた。
「ああ、おはよう錦織。悪いな、ちょっと寝坊してしまって」
錦織はすぐには応えなかった。必要以上に勿体ぶって、長い間を置いた後に切り出した。
「榎本君、昨夜のことだが…」
「なんだい?」
どきりとしながらも、平然を装って私は問い返す。昨夜私がどこにいたか、確かに錦織なら調べ出すのはお手の物だろう。だが私は、自分が恥ずべきことをしたとは思えなかった。
「榎本君、君が一緒にいた彼女のことだが」
「珍しいな錦織、そんな歯切れの悪い物言いは。いいか、彼女のことを悪く言うのは許さないよ。確かに彼女は官能小説の主人公だが、本当は物語に書かれているような淫乱じゃない。僕は彼女とまた会うつもりだ。反対しても無駄だよ」
「反対はしないよ。確かに無駄だからな」
錦織は電話の向こうで溜息をついた。
「何も知らないんだな、君は。TVをつけてみろ」
「なんだって」
その一言に悪い予感がした。私と彼女の一晩の出来事は、決してマス・メディアが騒ぎたてるようなものではないはずだ。片手で受話器を握ったまま、片手でリモコンを掴む。次々にチャンネルを替えても、流れてくるのは眠くなるほど生温い平日の昼間の番組ばかりだ。何もないだろう、そう言い返そうとした瞬間、昼のワイドショーの画面が切り替わった。私はリモコンを握ったまま凍り付く。画素の粗い無表情の顔写真。殺人事件の被害者と報道されている女は、私が昨夜抱いた彼女だった。
「な…」
私は錦織と会話するのも忘れ、TVコメンテーターの言葉を茫然として聞いた。被害者の氏名は今泉エリカ、年齢27歳。学校教員だったが定時になっても出勤しないため、不審に思った同僚が自宅を訪れて死体を発見したという。死因は絞殺による窒息死、素裸で、ベッドの中で死んでいた。死亡推定時刻は午前3時半頃。
3時半といえば、私が立ち去って間もなくのはずだ。私が出ていくのを見すまして、誰かが彼女の部屋に忍び入ったのか?しかし、彼女の部屋には戸締まりがされていたはずだ。立ち去るときに、開けっ放しでは不用心だろうと思って、私は確かあの時…
「それなのに、これは一体どういうことなんだ?」
“どういうことなんでしょうねえ”
私はぎくりとして振り返る。まるで耳元で囁かれたかのように聞こえたその声音は、TVのコメンテーターが発したものだった。TVの中では男女のコメンテーターが部屋の見取り図を見ながら言葉を交わしている。
“この事件には奇妙なことがありましてね”
“ほほう“
“死体が発見されたとき、部屋は戸締まりがされていたんです。この玄関ドアがですね、外からは開けられない状態になっていたんです”
“しかし、合鍵を使って侵入すれば…”
“それがですねぇ、戸締まりをしていたのは鍵じゃないんですよ。室内側のドアノブには男物のハンカチが結ばれていたそうなんです。部屋を立ち去るときに、隙間から手を入れてハンカチを結ぶことは不可能でしょう”
“それでは、この事件はつまり…密室殺人事件というわけですか”
その瞬間、背筋にぞっと悪寒が走った。
私は彼女を巻き込んでしまった!殺人犯が世を嘲笑い、ミステリー探偵が闊歩する血なまぐさい世界に、最も忌まわしい形で、彼女を引きずりこんでしまったのだ。私はきつく瞼を閉じる。彼女を守ろうと思っただけなのに、どうしてこんなことになったのだろう?
「理由を知りたいか、榎本君?」
今度こそ耳元で声が聞こえ、私は悲鳴を上げそうになった。声の主は電話の向こうの錦織だった。
「君が知りたければ説明してあげよう。事務所で待っているから来たまえ」
電話は唐突に切れ、私は一人で取り残された。本当は事務所へなど行きたくなかったが、部屋の空気は息苦しいほどに蒸し暑く、これ以上留まることは耐えられそうになかった。私は仕方なく汗に濡れたシャツを着替え、追い立てられるように部屋を後にした。
事務所に着く頃にはすっかり日は傾いていた。埃っぽいブラインドの間から斜めに差し込む光の条が、淡灰色の壁の上に黒い影の横縞を刻んでいる。その前を足早に通り抜けながら、この映像には見覚えがあると全身で感じた。こんな時にデジャ・ヴに捕らわれるなんて。出口のない幻覚の中に足を踏み入れるような不快さで私は隣室へ踏み込んだ。
「錦織」
声をかけると、ミステリー探偵・錦織慎一郎は古いオークの机に足を投げ出し、大きな肘掛け椅子にもたれかかって煙草を吹かしていた。がらんとした机の上には三角柱の形をしたプリズムが転がっている。ペーパーウェイトの代わりに使っている、錦織の気に入りの品。それは窓から入る西陽を集め、虹色に分解して扇状に拡散させる。
「光というのは、普段は一つの像を結ぶためにしか存在しないように見える。けれどこうして分解すると、実は七つの波長を持っているのさ」
「そんなことを言うために呼んだのか?」
苛立ちはもはやピークに達しており、私は掴みかからんばかりの剣幕で錦織を問いつめた。
「一体どういうことなんだ!どうしてこんなことになる!?」
錦織は目を伏せた。いつもの傲慢不遜な態度は影もなく、苦しげに呟いた。
「君が一番わかっているはずだ。ミステリー探偵は事件がなければ存在意義を失うのだと」
「ふざけるな!」
私の叫び声は悲鳴のようだった。怒りで自分を支えていなければ、その場に泣き崩れてしまいそうだった。
「冗談じゃない、何がミステリーだ、どうして彼女を巻き込んだ!だいたいこの世界の住人は、どうして自分の苦しみを殺人なんて短絡的な手段で解決しようとするんだ?愛が醒めたから、遺産を欲しいだけ取るには兄弟が多すぎるから、出世の邪魔だから、遠い昔に虐められたから、秘密を握られたから、人前で侮辱されたから、裏切られたから、飽きたから、自分の強さや知性や芸術的感性を誇示したいから、嫌いだから、好きだから、だからって殺す?そんな理由で人を殺していたら人生が幾つあっても足りやしない」
「しかし、そんな笑えるほど稚拙な理屈が、我々の世界ではまかり通っている。僕は探偵で君は助手だ。対岸には事件を起こす犯人がいて、周囲には被害者がいて協力者がいて妨害者がいる。登場人物は限定された文脈のみを背負った盤上の駒に過ぎない。その駒が卓上で織りなすプロセスこそが意味を持つのであって、駒そのもののパーソナリティなんて大した問題じゃない。SFだろうがポルノだろうが、そこで事件さえ起これば役割を割り当てる事はできる、そして全てはミステリーとして動き出すのさ」
「誰がそんなことを決めた!お前のためか、錦織?お前が偉そうにふんぞり返って謎の解決を演説するために?そんなことのために彼女は死んだのか!?単なる駒の一つとして!」
私が言葉を切ると、錦織は机から脚を降ろして立ち上がり、私を見つめた。怖いほど鋭く透通った眼差しだった。
「全ての出来事が、僕のためだと思うのか」
「他に何がある!何があるって言うんだ、なぜならあのトリックは、あの密室は」
私は最後まで言い終えることはできなかった。錦織が私の襟首を捕まえ、力任せに部屋の隅まで引きずっていったからだ。古いソファに私の身体を投げ出すと、有無を言わさず上に圧しかかった。
「何をする」
「謎解きをしてやろうと言うのさ。昨夜何が起こったかを再現してやる」
錦織は私を押さえつける手に力を込めた。恐ろしい力で、振り解こうとしてもびくともしない。
「君は行きつけのバーで今泉エリカと出会った。何度か姿を見かけていたが話をしたのは初めてだ。ともかく君は彼女のマンションの一室を訪れ、そうしてベッドで情事に及んだ。こんなふうに」
錦織はぞくりとする声で囁き、男が女を犯すような強引さで、脚の間に膝を割り込ませてくる。それだけで、身体の中の何かがじわりと濡れた。恐怖と裏腹の、足首のあたりから痺れのように這い上がってくるような興奮。一瞬で私は女になった。男に組み敷かれ、動悸を悟られないように息を殺して、与えられる官能を待ち受ける敏感な生き物に。
「昨夜…こうして彼女を見下ろす君の上に、天窓からの光が落ちかかっていた」
今や錦織は私自身であり、私は哀れな今泉エリカだった。圧倒的な力でねじ伏せられたまま、自分の上にいる男を見上げる。呼気から煙草の残り香がした。
「雲はあったが月光は明るく、天窓に掛かったブラインドの影がシーツの上にくっきりと刻まれていた。この灰色の部屋の壁のような横縞が、見えはしないだろうが君の背中の上にも刻まれていた」
酔わせるような錦織の囁きに誘われて、不意に意識のスクリーンに昨夜の映像が蘇った。深海の部屋、銀鼠色のカシュクール、天窓の朧月、夜目に白い胸元と温かな彼女の内側。そして私自身は?理性を失って昂ぶり狂った揚句、嗚咽しながら許しを求めた。そう、許しを……何の罪に対して?
私は力任せに錦織を突き飛ばした。ソファのアームレストに背を打ちつけた錦織が顔をしかめる。
奇妙な胸騒ぎと息苦しさに目眩がした。私は初めて見るもののように目を見開き、正面にいる錦織をまじまじと見つめる。
なぜ今まで一度も気づかなかったのだろう? その顔も、仕種も声も指先も。全てはただ一つの現実を目の前に突きつけていた。
錦織は私自身だった。
3/4