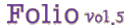●五月二十五日
岸和田さんの新作のラストが思い浮かぶまで、日記もお預けにしてそれに集中しようと思っていたら、こんなにも間が空いてしまった。それで、思いついたのかといえばまったくそうではない。あれから何度も読み返してはいるのだが、犯人とトリックが閃くどころか、ますます謎が深まっていくばかりだった。
誰かもう岸和田さんに送った人間はいるのだろうか?
古今東西のミステリーを読み漁ったぼくがこれだけ梃子摺っているのだから、そんじょそこらの奴にそう簡単にできるわけはない。例え既に送った人間がいたとしても、それは恐ろしく幼稚で思わず失笑してしまうような代物ばかりに違いない。ここは焦らず、じっくり考えていくのが得策だ。
謎が解けていないぼくが、どうして今日日記を書こうと思ったかというと、自分の中に留めておくのが我慢できない、腹の立つ事件があったからだ。
朝(といっても、夜更かししているぼくにとってはそうだが、世間的には既に昼といわれる時刻だった)、ぼくが階下に降りていくと、居間の方から父親の上機嫌な笑い声が聞こえてきた。珍しく土曜日に父がいる理由など深く考えもせずに、新しいプリンターを買うための小遣いをねだろうと思っていたぼくは、機嫌の良いチャンスを逃してなるものかと寝起きの三点セット(パジャマ、寝ぐせ、目やに)の状態で居間に飛び込んだ。
居間にいたのは、父親、母親、妹の三人……ではなかった。見たことのない上品そうな顔立ちをした若い男が妹の横で微笑んでいた。後で聞いたところによると、その男は、つい最近妹とコンパで知り合った超一流大学の法学部に通っている、いかにも父親を上機嫌にさせるにはじゅうぶんの経歴の持ち主だった。そんなVIP客の前に、すべてがむさ苦しいぼくが現れたものだから、父親の顔は一瞬にして天国から地獄へと移り変わった。そして、その閻魔から怒りの一鉄槌が下されようとした瞬間、妹の口から思わぬ言葉が発せられた。
「あら××さん(あまりの衝撃で今でもどう呼ばれたのか覚えてない。ぼくの名前でないことは確かだ)、おはようございます。昨夜も遅くまでお勉強ですか? 大変ですね」
妹は、目を丸くしている一同をよそに男に向かって説明する。
「こちら受験勉強のためにうちに居候している私の従兄弟です」
その妹の言葉に、男は納得し、安堵したような表情を浮かべた。
「そうですか。私はお兄さんがいると聞いていたので、そのお兄さんなのかと思いましたよ」
と、父親を確認するかのように見る。
「そ、そうなんだよ。こっちでバイトしながら予備校に通いたいというので、うちで預かってるんだ」
父親も妹の作り話にぎこちなく合わせる。ぼくはすがるような思いで母親を見るが、彼女も父親に合わせて引きつった微笑を顔に浮かべているだけで、ぼくとはまったく目を合わせようとしなかった。
「お兄さんはどちらへ?」
「兄はいまですね……」
男の質問に対する答えを聞かぬまま、ぼくはその場を後にした。これ以上自分が惨めになる言葉を聞いていたら、自分すらまだ見たことのない何かのスイッチが入りそうで怖かったのだ。
どいつもこいつも、ぼくを馬鹿にしやがって!
でも、それも今のうちだけだ。近いうちにきっとあんたたちは、ぼくを尊敬の眼差しで見ることになるだろう。だが可哀相なことにそのときはもう遅いんだ。ベストセラー作家になったぼくに家族の縁を切られるんだからな。
そのためには、あの作品のラストを書き上げて著作権を手に入れなければ。
もうのんびりしていられない。
2/3